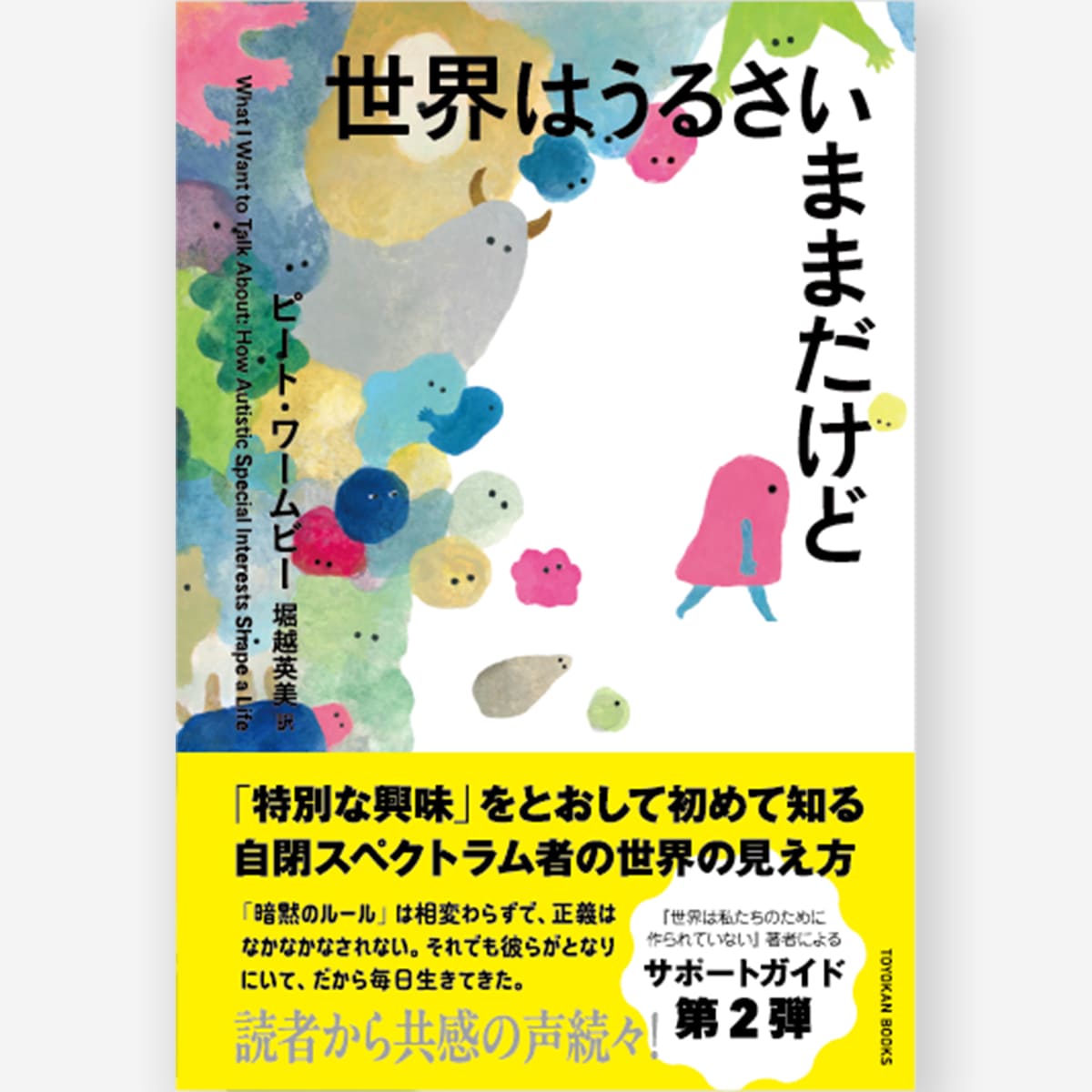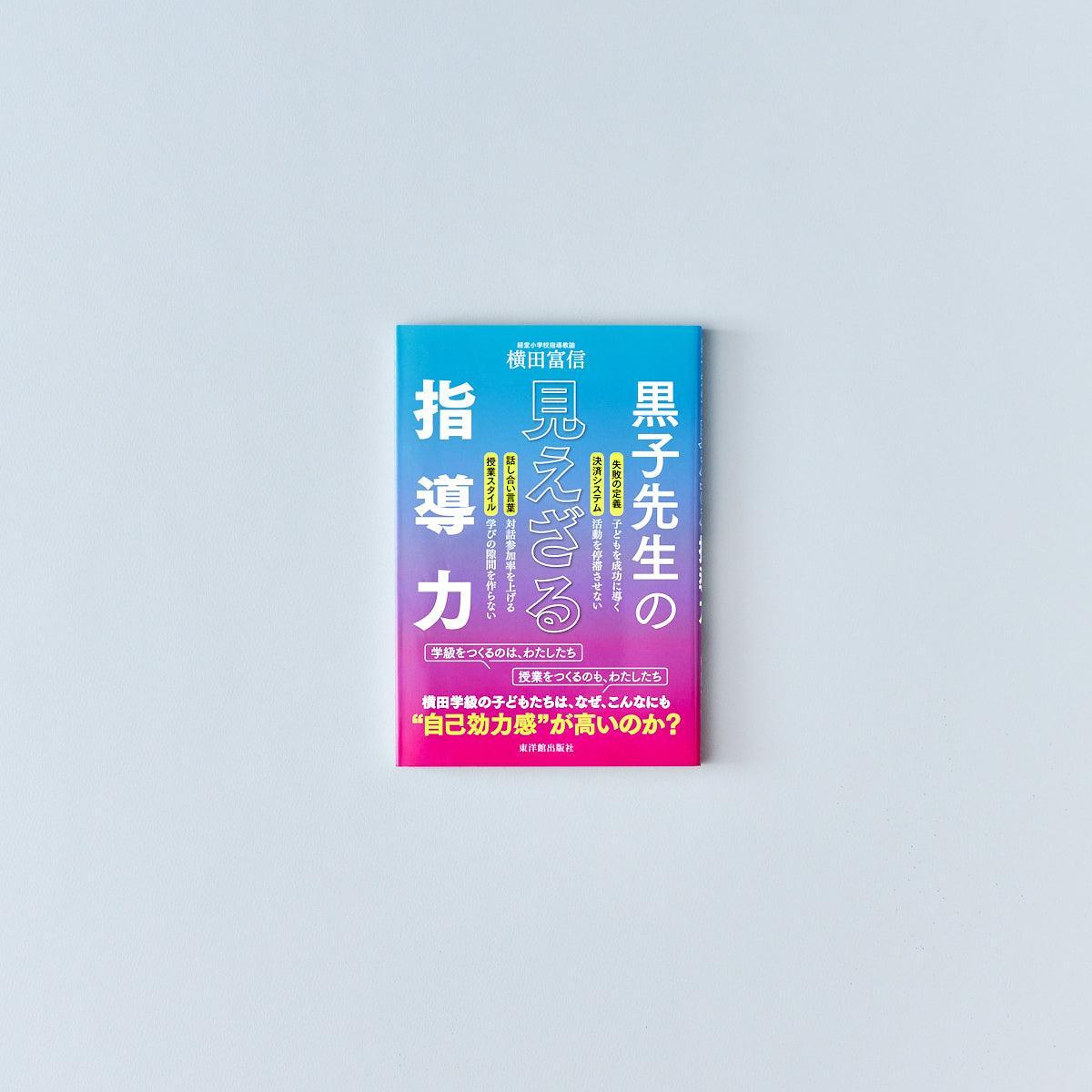
黒子先生の見えざる指導力
付与予定ポイントpt
今
6
人がこの商品を閲覧しています
レビューを書くと100ポイントプレゼント
商品説明
[失敗の定義]子どもを成功に導く!
[決済システム]子どもの活動を停滞させない!
[話し合い言葉]対話参加率を飛躍的に上げる!
[授業スタイル]学びの隙間をつくらない!
「学級をつくるのは、わたしたち」
「授業をつくるのも、わたしたち」
横田学級の子どもたちは、なぜ、こんなにも“自己効力感”が高いのか?
--------------------------------------
「A先生だと、クラスがまとまらないんだよな~」
以前、ある学級の子どもが、こんなことをつぶやいているのを耳にしたことがあります。それを聞いた私は、“この子は「学級は教師がつくるもの」と思っているんだな”と感じました。
「学級をどうつくっていけばよいか…」教師であればだれもが悩む問いであり、さまざまなとらえがあると思います。目の前の子どもたちの状況によっても、「何をもってよしとするのか」も変わるでしょう。
たとえば、(前の学年で荒れてしまった、あるいは、いじめが原因でお互いに疑心暗鬼になっている、などの)むずかしい状況を抱えている子どもたちであれば、「学級は教師がつくるもの」でよいのかもしれません。四の五の言わせずに引っ張っていくリーダーシップが求められるときだって、教師にはあるからです。
しかし、(どんな学級にも課題はありますが)学級全体にまで波及してしまうレベルの負の課題でもない限り、学級をよりよくする主体は子どもたちであるはずです。さらに踏み込んで言うと、「学級は自分たちがつくってるんだ」という子どもの意識を、教師としていかに醸成するかが重要だと私は考えています。
学級をよくしようというとき、さまざまな場面で褒めたり叱ったりすることが教師には求められます。しかし、教師の側が一方的にやりすぎると、子どもは「学級は教師がつくるもの」という意識を強めてしまうでしょう。
では、どうするか。
どんな学級をつくっていけばよいかを、子ども同士が学び合える場をつくればよいと思います。(黒子としてリーダーシップの意図のもとに)教師からの一方向を子ども同士の双方向に変えるのです。
本書は、「学級づくり」「授業づくり」の両面から、子どもたちの“自己効力感”を最大限に高める「考え方」と「方法」を紹介します。
[決済システム]子どもの活動を停滞させない!
[話し合い言葉]対話参加率を飛躍的に上げる!
[授業スタイル]学びの隙間をつくらない!
「学級をつくるのは、わたしたち」
「授業をつくるのも、わたしたち」
横田学級の子どもたちは、なぜ、こんなにも“自己効力感”が高いのか?
--------------------------------------
「A先生だと、クラスがまとまらないんだよな~」
以前、ある学級の子どもが、こんなことをつぶやいているのを耳にしたことがあります。それを聞いた私は、“この子は「学級は教師がつくるもの」と思っているんだな”と感じました。
「学級をどうつくっていけばよいか…」教師であればだれもが悩む問いであり、さまざまなとらえがあると思います。目の前の子どもたちの状況によっても、「何をもってよしとするのか」も変わるでしょう。
たとえば、(前の学年で荒れてしまった、あるいは、いじめが原因でお互いに疑心暗鬼になっている、などの)むずかしい状況を抱えている子どもたちであれば、「学級は教師がつくるもの」でよいのかもしれません。四の五の言わせずに引っ張っていくリーダーシップが求められるときだって、教師にはあるからです。
しかし、(どんな学級にも課題はありますが)学級全体にまで波及してしまうレベルの負の課題でもない限り、学級をよりよくする主体は子どもたちであるはずです。さらに踏み込んで言うと、「学級は自分たちがつくってるんだ」という子どもの意識を、教師としていかに醸成するかが重要だと私は考えています。
学級をよくしようというとき、さまざまな場面で褒めたり叱ったりすることが教師には求められます。しかし、教師の側が一方的にやりすぎると、子どもは「学級は教師がつくるもの」という意識を強めてしまうでしょう。
では、どうするか。
どんな学級をつくっていけばよいかを、子ども同士が学び合える場をつくればよいと思います。(黒子としてリーダーシップの意図のもとに)教師からの一方向を子ども同士の双方向に変えるのです。
本書は、「学級づくり」「授業づくり」の両面から、子どもたちの“自己効力感”を最大限に高める「考え方」と「方法」を紹介します。