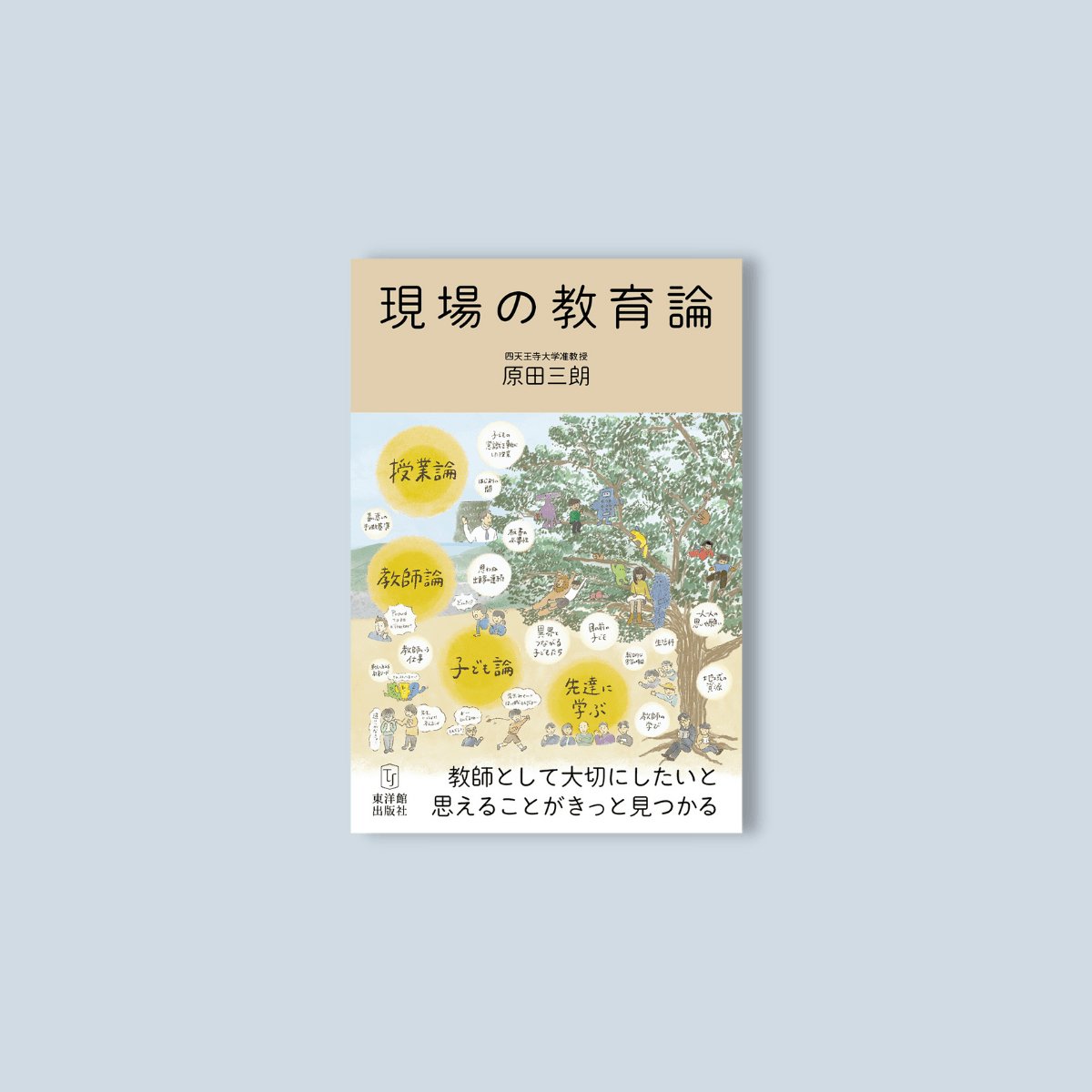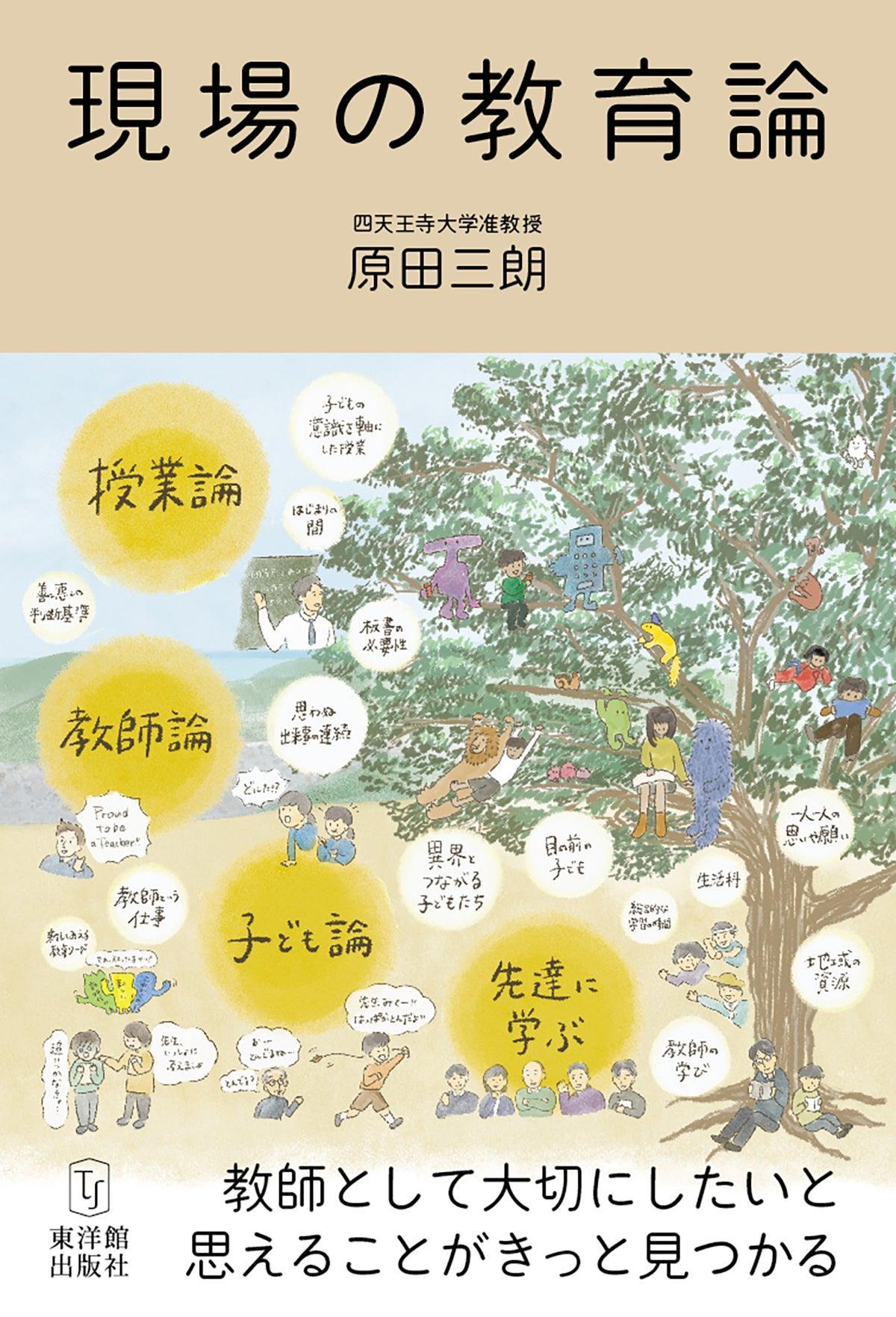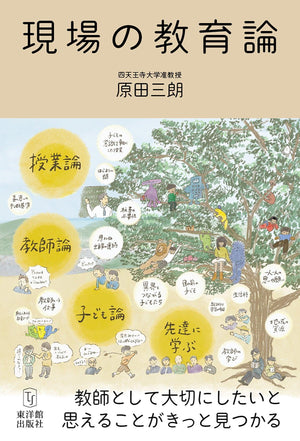現場の教育論
レビューを書くと100ポイントプレゼント
商品説明
教師として大切にしたいと思えることがきっと見つかる!
本書の概要
GIGAスクール、STEAM教育、個別最適な学びと協働的な学びなど、時代の要請に応じて次々と「新しい言葉」が生まれる教育界。新しい潮流に乗り遅れまいとして、忙しい日々の合間を縫って学ぶ教師たち。そのような姿に感銘を受けながらも、「本当にそうであってよいのか」と著者は疑問を呈します。
いつの時代も新しいチャレンジは大切です。その際、教育者としての自分自身の歩みを考察できてこそ、そのチャレンジは子どもたちの教育に資するものとなります。
教育とは、本当に迂遠なものです。曲がりくねっていて、回りくどく、どこにたどり着くかわからないその先で、自分自身とつながり直すのです。そうしたルーツをつくるのが、10代の体験なのであり、本書はそうした学びをつくるヒントがたくさん詰まっています。
本書からわかること
「一回性」と「固有性」に満ちた学習を子どもたちとともに紡ぐ
教育とは、目の前にいるその子を育てることです。仮に、その子が町の学校に通う4年生だとするならば、山の学校に通う4年生とは違う4年生のはずです。隣の学校に通う4年生とも、隣の席に座っている4年生とも、やっぱり違うはずです。
その子はその子であってほかのだれでもない、その子の前に立つ教師としての私は、私であってほかのだれでもない。そこには、再現性があるようでなく、共通性があるようでない、「一回性」と「固有性」に満ちています。
本書では、そんな子どもたちの学ぶ姿を明らかにします。
■本書集録:「教室の事実」「学びを生み出す『間』」「長い道のり」など
教師が学ぶって、どういうことなのだろう
研修というと、かしこまった場所で一堂に会し、司会進行役がいて、タイムスケジュールどおりに段取りよく進めていく情景が思い浮かぶのではないでしょうか。それとともに、意見交流が活発にならない情景も浮かんでしまうこともしばしば。
形式を重んじる研修だけが教師の学びではないはず。むしろ、日常に溶け込むような学びこそ、私たち教師本来の学びなのではないか。もし、心理的安全性に包まれて語り合うことができれば、議論はおのずと闊達になります。
そこで本書では、ラウンド・スタディ方式の研修を提案しています。お互い思う存分語り合い、自分にとって本当に必要な「問い」を獲得できる手法です。
■本書集録:「学びの文化の苗床」「喫茶店での研修会」「教師たちの町探検」など
こちらの岸に先生がいて、川の向こう岸に子どもたちがいる
「子どもとはどんな存在ですか?」などと問われたら、答えに窮してしまうと著者は言います。子どもは難解で、日々、変化を遂げるからです。しかし、子どもと同じ景色を見ることはできます。
黒板を背に一方向からだけ見るのではなく、全体を俯瞰して見る、子どもの側から見る。このように多様な「見る」という行為によって、子ども側の岸辺に立つことができます。
本書では、教師をはじめとする大人をハッとさせるような「子どもの内面」を浮き彫りにする方法を紹介します。
■本書集録:「ふるさと写真展」「不揃いのソロイ」「異質な他者」など