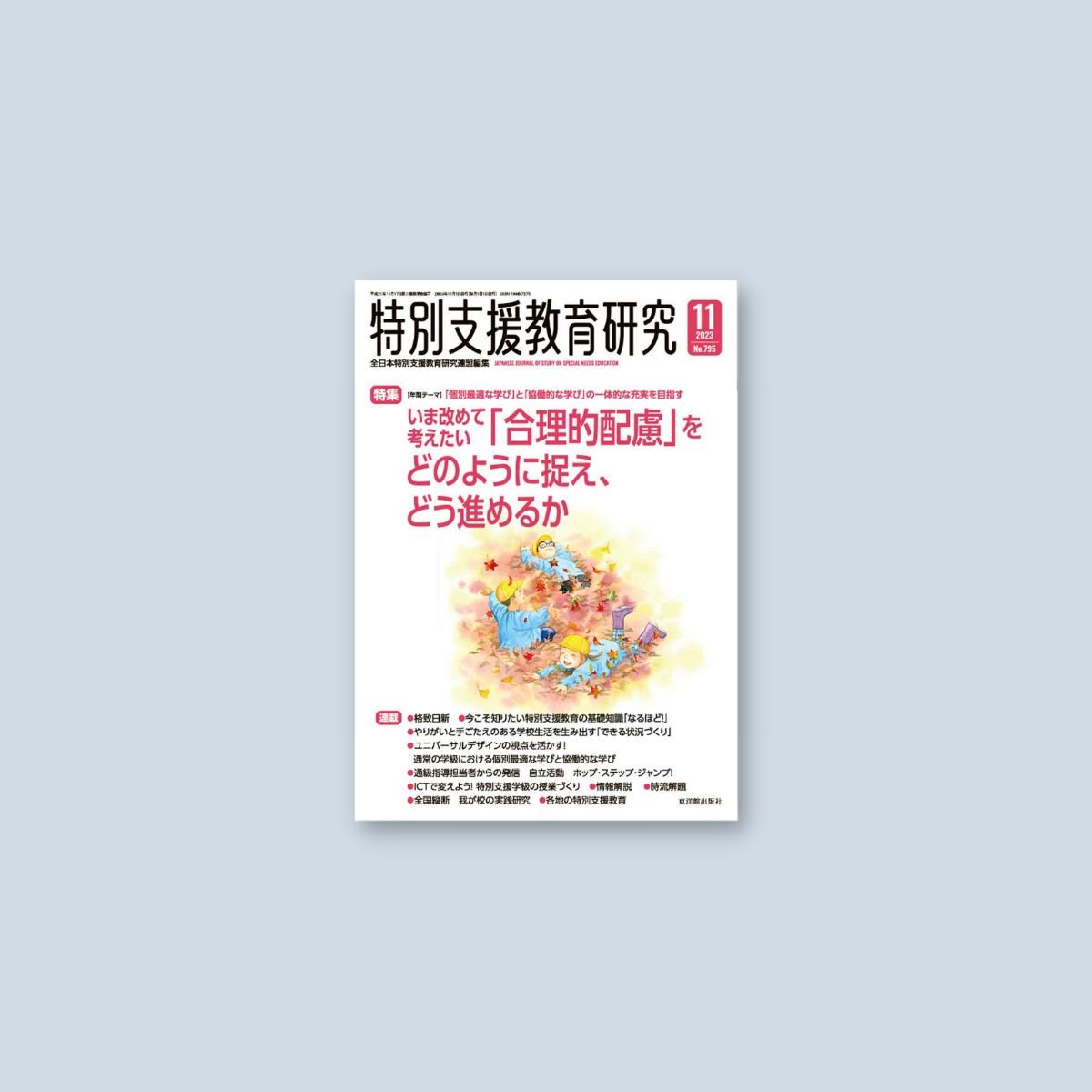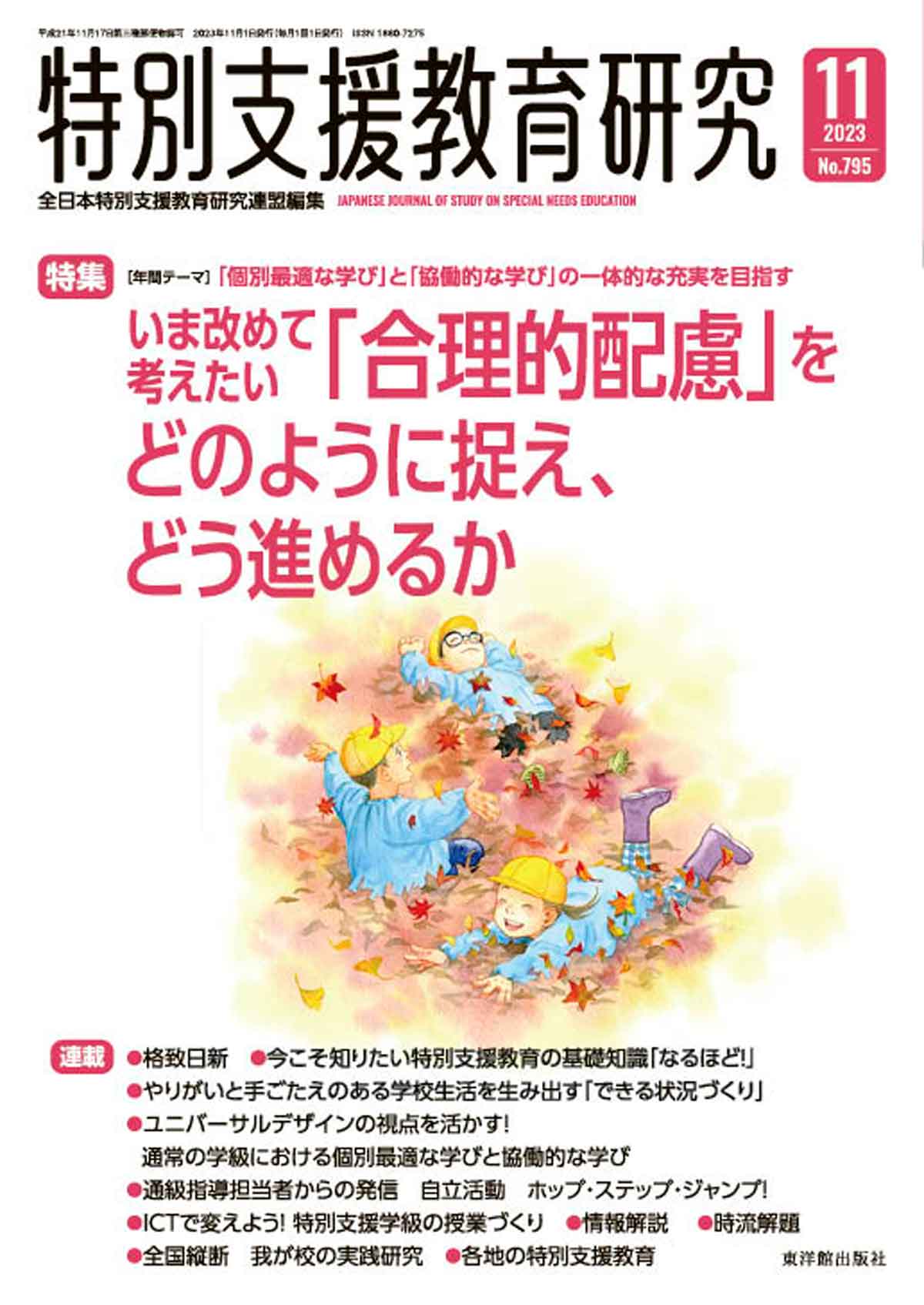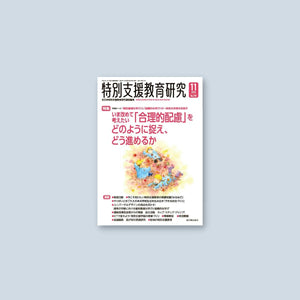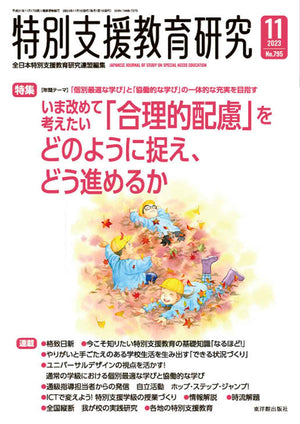月刊 特別支援教育研究2023年11月号
レビューを書くと100ポイントプレゼント
商品説明
中教審答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~」を踏まえ、「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」報告(令和3年1月)が提示されました。
その報告の「特別支援教育を巡る状況と基本的な考え方」には、「共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念が重要であり、その構築のために特別支援教育の取組を着実に進めていくことが必要」であると記載されています。この報告された方策の実現を目指して令和4年度に設置された「特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議」では、特別支援教育を担う教員の専門性の向上策として、全ての教員に特別支援学級等の経験を求めることが示されました。
また、令和4年12月には10年ぶりとなる「通常の学級に在籍する特別な教育的配慮を必要とする児童生徒に関する調査」の結果が公表されました。調査結果は、小・中・義務教育学校の段階においては、学習面又は行動面で著しい困難を示さすとされた児童生徒が8.8%(推定値)の割合で通常の学級に在籍しているとされています。
また、高等学校においても2.2%の割合でした。この結果を受けて設置された「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議」報告(令和5年3月)には、今後、校内委員会の機能強化、自校通級や巡回指導による通級による指導の充実、特別支援学校のセンター的機能のさらなる充実等が提言されています。
学校現場においては、これまで以上に特別支援教育に係る管理職及び教員の専門性が求められています。さらには、学習又は生活上の困難さの解消や軽減に必要な配慮の充実も必要となっています。そこで本特集では、個々の困難さから生じる学びにくさを解消・軽減するために必要な合理的配慮の在り方について示すとともに、各学校における具体的な取組などを紹介します。合理的な配慮等によって当該児童生徒の学びがどのように保障され、成果に結びつくためのポイントは何であったかを解説することで各校の参考となる一冊となることを願っています。