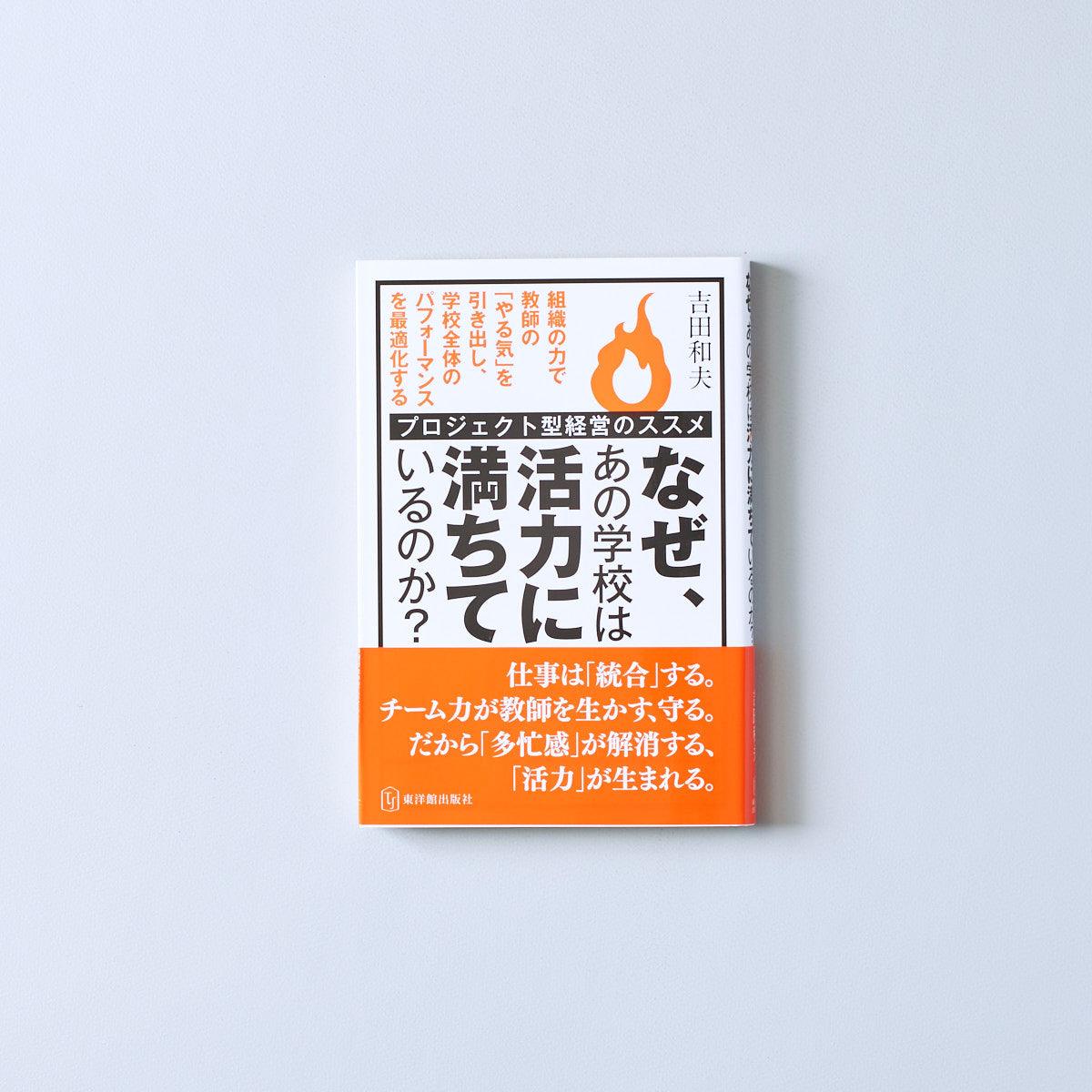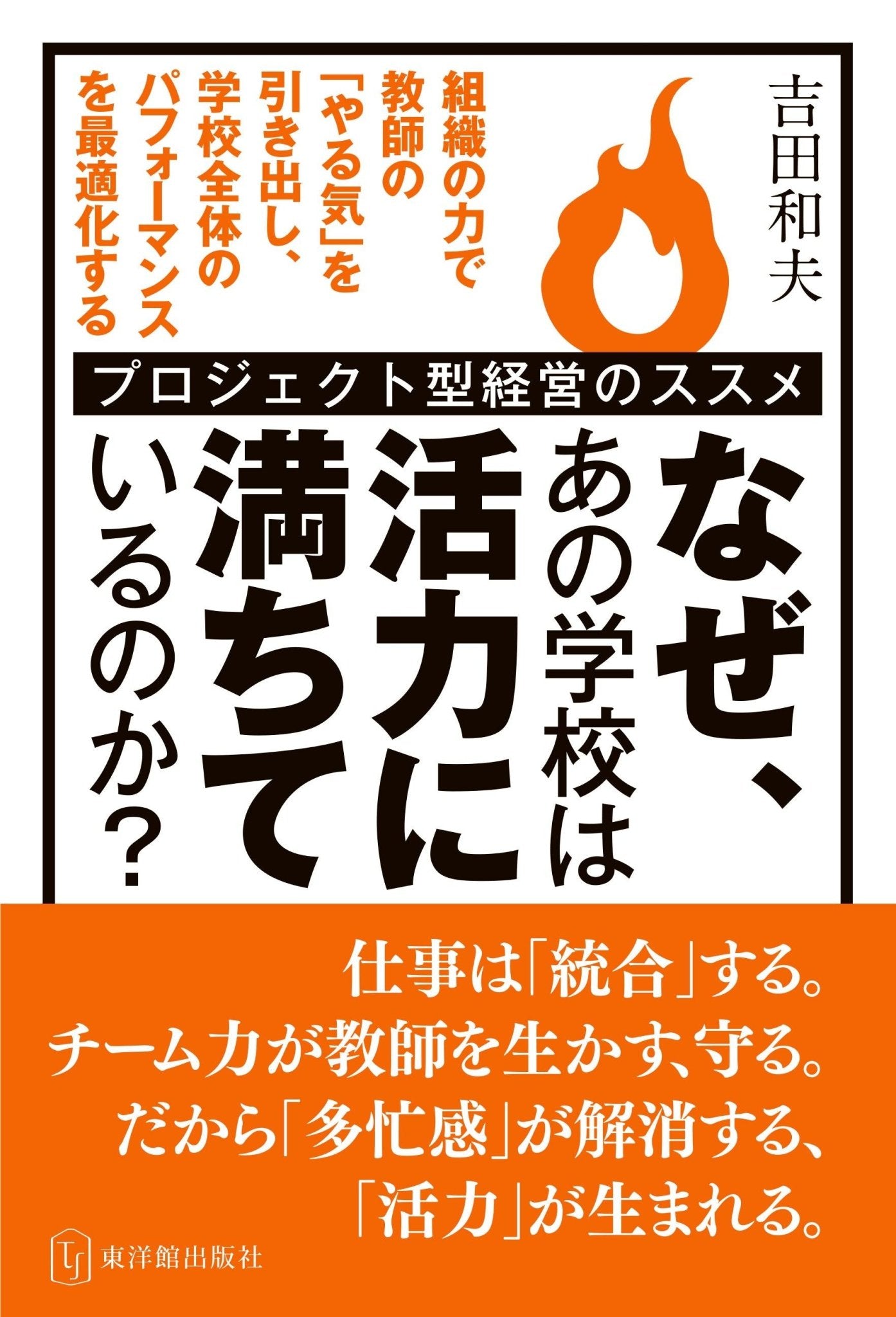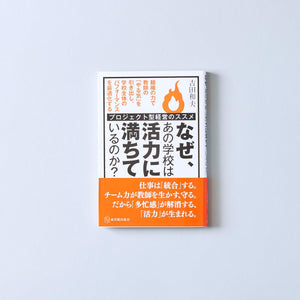なぜ、あの学校は活力に満ちているのか?
付与予定ポイントpt
今
6
人がこの商品を閲覧しています
レビューを書くと100ポイントプレゼント
商品説明
現在の学校では、精神性疾患に罹る先生、志半ばで教職を去る先生が増えるなど、学校という職場にかつてないストレスがかかっています。このストレスの最大の原因は「多忙感」。しかし、これはいったいどこからやってくるのでしょう。
仕事量が多いだけでは説明がつきません。なぜなら、子どもの教育に忙しいのは、教員のやりがいでもあるからです。
実は、必要感のない仕事への「負担感」、自分のやりたい仕事ができない「不満感」、職場での人間関係への「不安感」こそ、教員の「多忙感」の正体。
そこで、本書では、教員の「多忙感」を解消する学校経営、すなわちプロジェクト型経営を提案します。教員が仕事しやすい組織、教員のやる気を引き出すコーチングを通して、学校全体のパフォーマンスを高めます。そのプロセスで、教員間の「人間関係」をスムーズにし、教員の「多忙感」を解消します。
校長や副校長、教頭をはじめ、主幹教諭や主任も含め、学校の経営層は、このような組織をどのように構築し、運営していけばよいかを詳細に提案します。