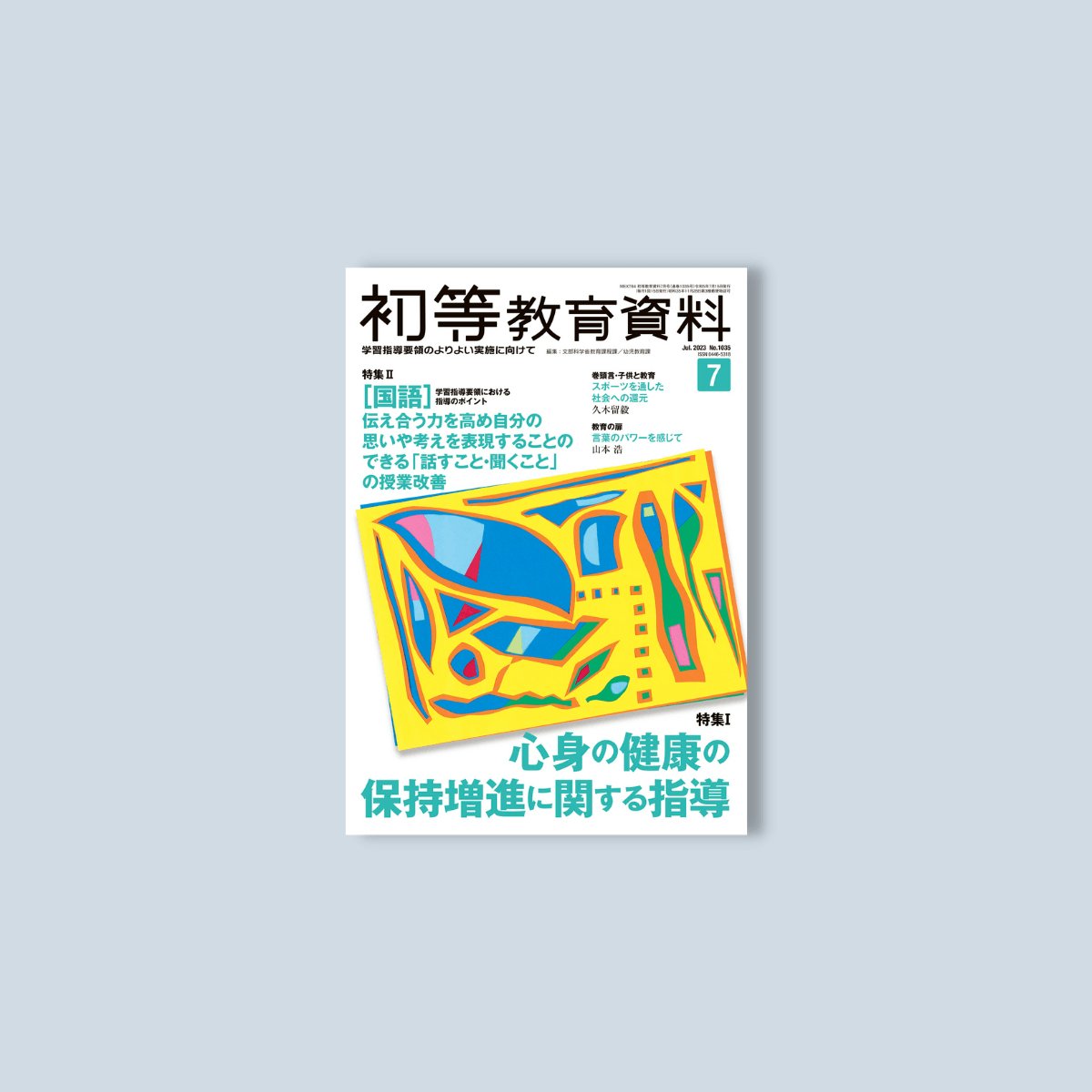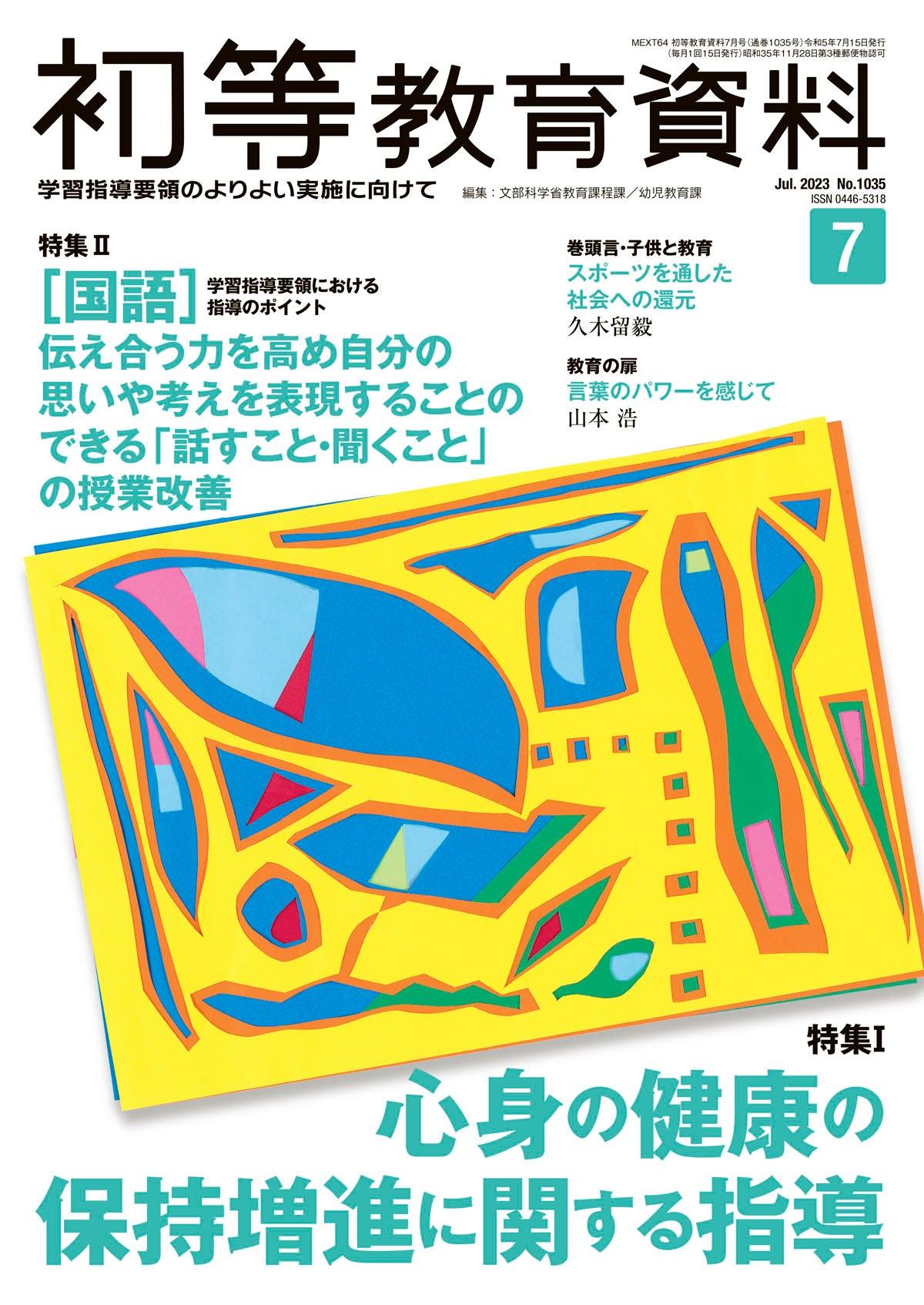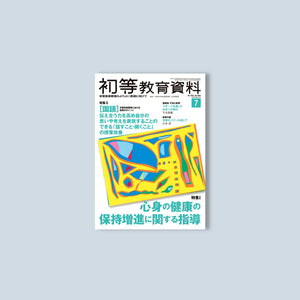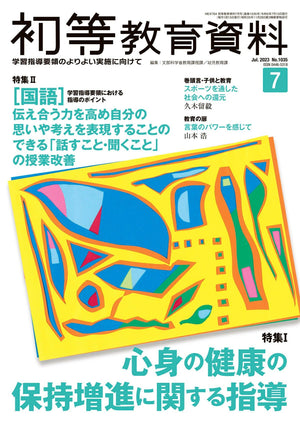レビューを書くと100ポイントプレゼント
商品説明
本書の概要
文部科学省の最新の教育施策や学習指導要領の要点を分かりやすく解説し、具体的な授業実践と併せて紹介。各教科等に係る内容は、全て教科調査官が責任編集。新学習指導要領に基づき、最新の教育情報をいち早く、正確に得るために、全教員・教育委員会必読の月刊誌。毎年12月には増刊号として「幼稚園教育年鑑」を刊行。
特集Ⅰ
心身の健康の保持増進に関する指導
教育基本法では、教育の目的として「健やかな身体を養う」ことを規定しており、また、『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総則編』では、健やかな体について「学校における体育・健康に関する指導を、児童の発達の段階を考慮して、学校の教育活動全体を通じて適切に行うことにより、健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を目指した教育の充実に努めること」と述べられています。また、心身の健康の保持増進に関する指導においては、情報化社会の進展により、様々な健康情報や性・薬物等に関する情報の入手が容易になっていることなどから、子供が適切に行動できるようにする指導を一層重視する必要があります。
心身の健康のうち、ユニセフが令和2年9月に公表した「子どもの幸福度」に関する調査結果では、日本の子供たちは、身体的健康は1位だったのに対し、精神的健康は37位(38か国中)という結果でした。このことからも心の健康について指導の充実を図ることが喫緊の課題であると言えます。
そこで、本特集では、カリキュラム・マネジメントの考え方を踏まえ、心身の健康の保持増進に関する指導がより効果的に行われるよう、特に心の健康に重点を置きつつ、解説、論説、座談会、実践事例を通して理解を深めていきます。
特集Ⅱ
学習指導要領における指導のポイント[国語]
伝え合う力を高め自分の思いや考えを表現することのできる「話すこと・聞くこと」の授業改善
「話すこと・聞くこと」領域の学習活動に関する現状として、令和4年度全国学力・学習状況調査結果によると、「互いの立場や意図を明確にしながら計画的に話し合い、自分の考えをまとめることに引き続き課題がある」との指摘があります。また、国語科の授業に限った項目ではないが、質問紙調査において、5割を超える子供がほぼ毎日、あるいは週3日以上、何らかの形でICT端末を学習に活用すると回答しています。しかし、その中身を詳しく見ていくと、「話すこと・聞くこと」領域に関わりが深い「学級の友達と意見を交換する場面」「自分の考えをまとめ、発表する場面」に限ると、2割を少し超える結果でした。ICT端末をよりよく使う時期を迎えているからこそ、改めて、伝え合う力を高め自分の思いや考えを表現することのできる「話すこと・聞くこと」の授業について考える必要があります。
そこで、資質・能力の育成に向けて、効果的なICT端末の活用を含め、様々に工夫され授業改善が行われてきていますが、より一層、国語科で身に付けた「話すこと・聞くこと」の資質・能力を育成していくため、『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 国語編』に言語活動の種類ごとにまとめた形で示している言語活動例に沿って実践事例を示しながら、伝え合う力を高め自分の思いや考えを表現することのできる授業改善のポイントを示していきます。