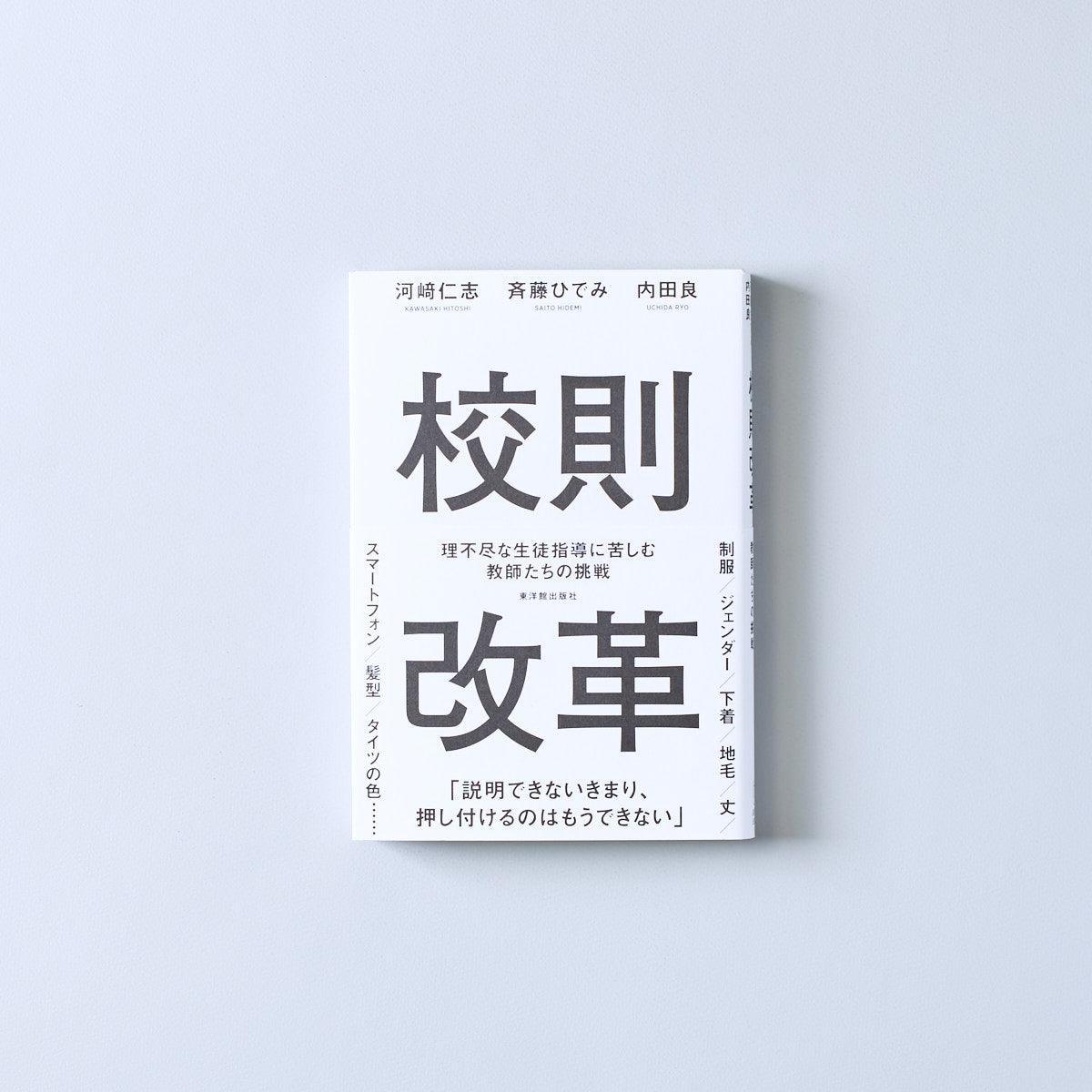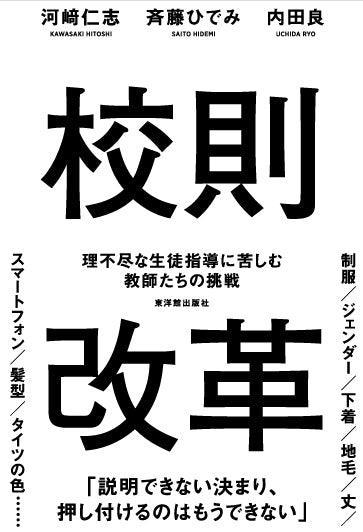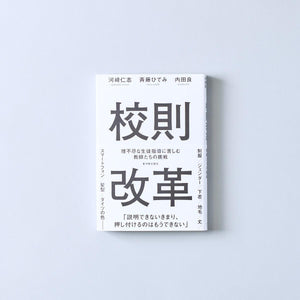校則改革 理不尽な生徒指導に苦しむ教師たちの挑戦
レビューを書くと100ポイントプレゼント
商品説明
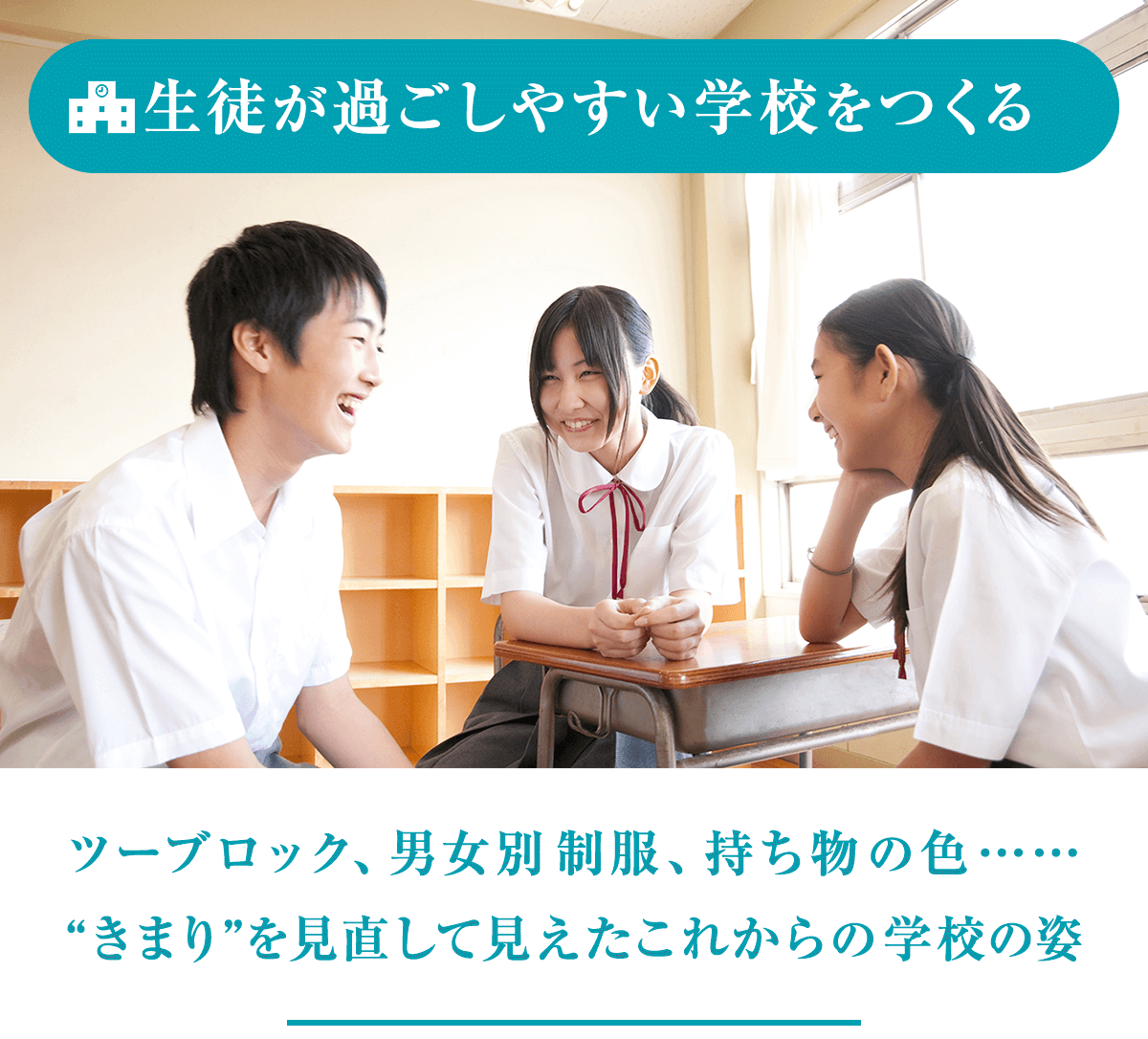
校則見直しはいま、「生徒自身による見直し」「生徒会が主体的に取り組んだ成果」として語られている。生徒が自分たちのルールを自分たちで取り決める。とても意義深い活動だ。だが一方で、生徒会が黒色のタイツを認めてほしい動いたところで、それが生徒会の総会や生徒指導部の教師によって却下されるような事態も起きている。
本書は、学校は大人=教師がつくっているのだという自覚と責任感をもって編まれている。校則見直しの必要性が叫ばれる今日、教師自身が時代の流れや生徒の思いを受け止めながら、どのようにそのあり方を考え、また変革してきたのかの具体例が記された。
―はじめに(内田良)より
3751人――
これは、学校のきまりが原因で不登校に陥っている児童生徒の数です。(令和2年10月公表「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」、文部科学省)
地毛矯正や下着の色の検査、髪型の厳格な規定など、明確に指摘される項目以外にも、
・寒暖の変化が激しい年なのに冬服の解禁日が決められている
・男子はスラックス、女子はスカート
など、登校が苦しくなる校則がまだ多く存在しています。
2018年に弊社刊行の『ブラック校則』から3年。本書では、校則を変革した教師の実践や、有識者らのコラムなどによって校則の未来の姿を提案します。
1. 校則は時代に合わせて見直しを
校則には根拠法令はありません。「生徒指導提要」(2010年3月、文部科学省)では、「学校教育において、社会規範の遵守について適切な指導を行うことは極めて重要なことであり、校則は教育的意義を有しています」と記されています。一方で「学校を取り巻く社会環境や児童生徒の状況は変化するため、校則の内容は、児童生徒の実情、保護者の考え方、地域の状況、社会の常識、時代の進展などを踏まえたものになっているか、絶えず積極的に見直さなければなりません」とあります。
校則そのものが非合理というわけではなく、「教員がいたずらに規則にとらわれて、規則を守らせることのみの指導になっていないか注意を払う必要があります」ともあるように、学校の現状や地域の実態などに合わせて見直していく必要があります。
2. 校則を変えて教師の働き方改革に!――兵庫県明石市立朝霧中学校の改正例
朝霧中学校の生徒指導担当の河﨑仁志先生は、同僚の間で「どこからがツーブロックなのか」という定義が共有されておらず、疑わしい髪型の生徒が現れるたびに、各学年の生徒指導担当らが集まり、協議をすることに疑問に思っていました。生徒や保護者への説明も、「そういうルールなんで……」と苦しい説明に終止していました。
教師の間でも、「しっかりと根拠を説明できない校則はやめるべきだ」という機運が高まり、変更することになりました。河﨑先生は、以下の順序で全方位的に意見をくみ上げながら校則を改正していきました。
- 市内の中学校、高校に校則の現状をヒアリング。併せて小学校の教諭からも意見を聞く。
- 校則についてのアンケートを、生徒、保護者、教師に配布。
- 生徒、保護者の希望制の参加とした「校則を考える会」(計3回)でアンケート結果などを踏まえて校則改正のたたき台を作成。
- 職員会議で承認
12月に開始し、2月には改正案を決定し、新年度から運用し始めました。以下が校則改正の一例です。


朝霧中学校では、「問題行動が起きる前に先手を打つ」ことや「人と違う外見によって発生するトラブルを回避する」ことを目的として校則が運用されていました。校則を変更した後、そうした問題は確認されておらず、「個性の尊重」と「安全・健康面の改善」という新たなベネフィットが得られたとのことです。なにより、「自分たちがつくった校則」という認識が子どもたちに芽生え、快適そうに過ごしながらも、前向きにきまりに向き合う姿が見られました。
また、上述した「ツーブロック協議」などの生徒指導や保護者対応が減ることで教師の働き方改革につながりました。教師の中では服装を厳しく統一することで「見栄え」を重視するのではなく、むしろ服装などに現れることのある「心の乱れ」をしっかり見取り、向き合うことが大事だという生徒指導の本質を再認識し、生徒理解が増進されました。
最後に、「校則を考える会」に参加した保護者の事後アンケートから抜粋します。
先生各位が、子供たちの視点を大切に検討する立場を取られ、主体性を大切にしながら、TPOに応じた振る舞いや規則を遵守することとのバランスを取った校則へのシフトを目指しておられることが感じられ、より快適な学校生活を送ることへ向けた有意義な会でした。また、毎日の生徒指導の大変さ、難しさに触れることができ、普段から細やかに子供たちに接していただいていることへの感謝の気持ちを新たにしました。
本書では、朝霧中学校の校則の新旧比較や、変更における詳細の時系列表など校則変更を考える際の参考にしていただける作りを心掛けました。
3. 学校の姿勢がいま問われている
こうした改革例だけではなく、中学校と高校の教師が匿名で本音を話す「覆面座談会」も実施しました。「『自分は頑張っている』とアピールしたい、教師的な“いい子”が自発的に校則を強化する」ことや「きまりがないとわが子が浮いてしまうから、靴の色などきまりを設けてほしい」などの、校則の強化を望む人がいることも見えました。「自分の嫌いな顔だから化粧をしてきているのに、泣いている生徒の化粧を落とさせる」指導が辛く、校則改革を提言するも会議にすら上げることができず教師を辞めたくなった体験など、水面下の教師側の葛藤も露になりました。改革の際には、アンケート等を実施し、学校に集う関係者の意見をしっかりと調整することが求められるでしょう。
そこで本書では、教師の改革例だけでなく、LGBTの当事者、教育学者、法曹、メディア記者ら有識者から寄稿をいただきました。厳しい校則に内在する問題点を指摘しつつ、改革の際に押さえるポイントを提案いただいています。
- 「先生もまた、生徒とともに、『自分たちのコミュニティ(職場)は自分たちでつくる』仲間です」
- ―苫野一徳(哲学者・教育学者)
- 「多様性を尊重するとは、これまでのルールを変えたり、新しくルールを作るための知恵や技術を指すのだ」
- ――遠藤まめた(一般社団法人にじーず代表)
- 「学校や教師の姿勢がいま、問われている」
- ――氏岡真弓(朝日新聞社編集委員)
「学校教育の主役である子どもたちが生き生きと生活できるような学校づくり」に向け、いま、学校の姿勢が問われています。なにより、先生方が学習指導と生徒指導に専念するための学校の環境整備の参考にしていただければ幸いです。
主なコラム執筆者
- 大津尚志(教育学者)
- 後藤富和(弁護士)
- 西郷孝彦(元世田谷区立桜丘中学校長)
- 真下麻里子(弁護士)
- 室橋祐貴(日本若者協議会代表理事)
- 吉川裕基(NHK記者)
関連書籍『ブラック校則』 編・荻上チキ、内田良 (2018年8月刊行)⇒ 詳細はコチラ