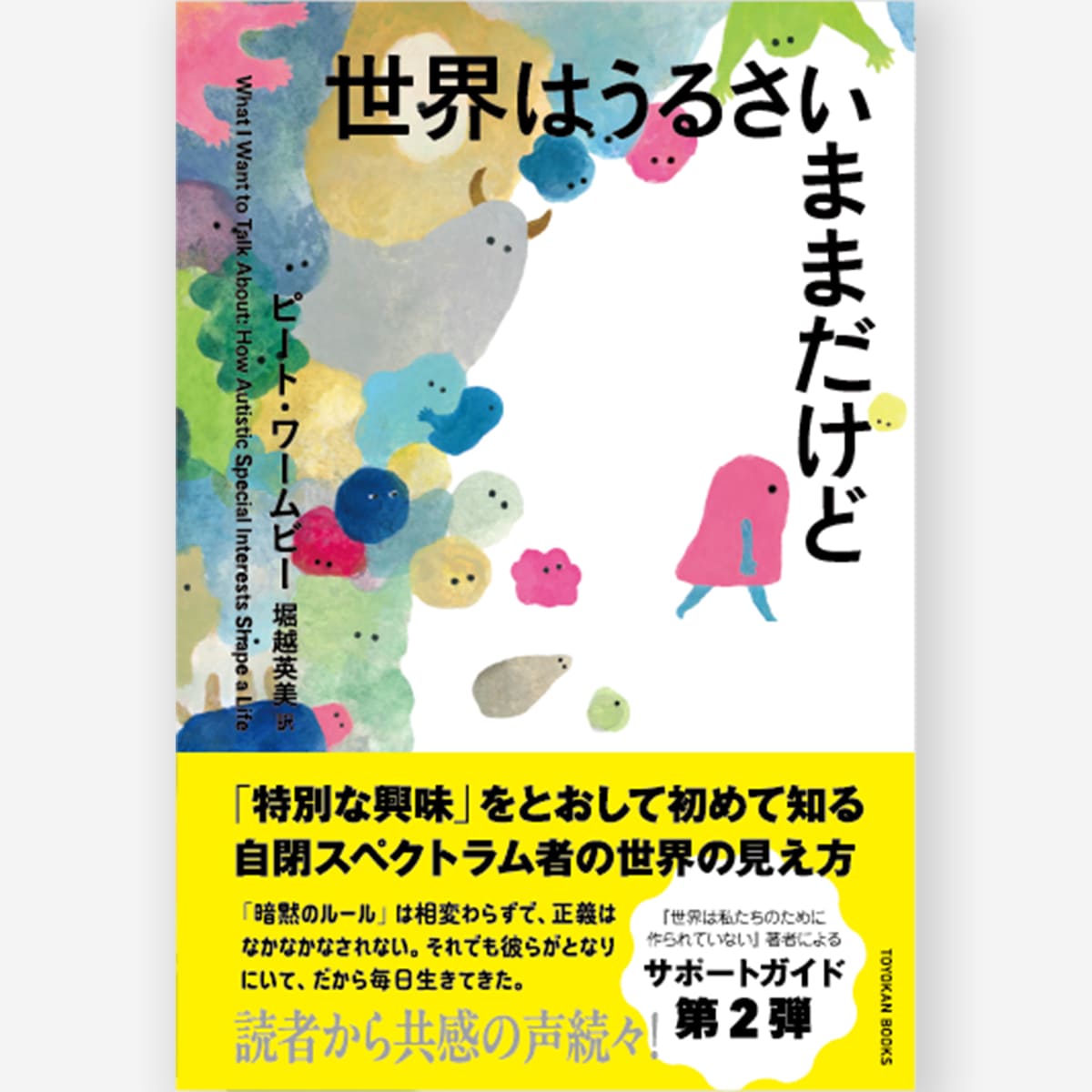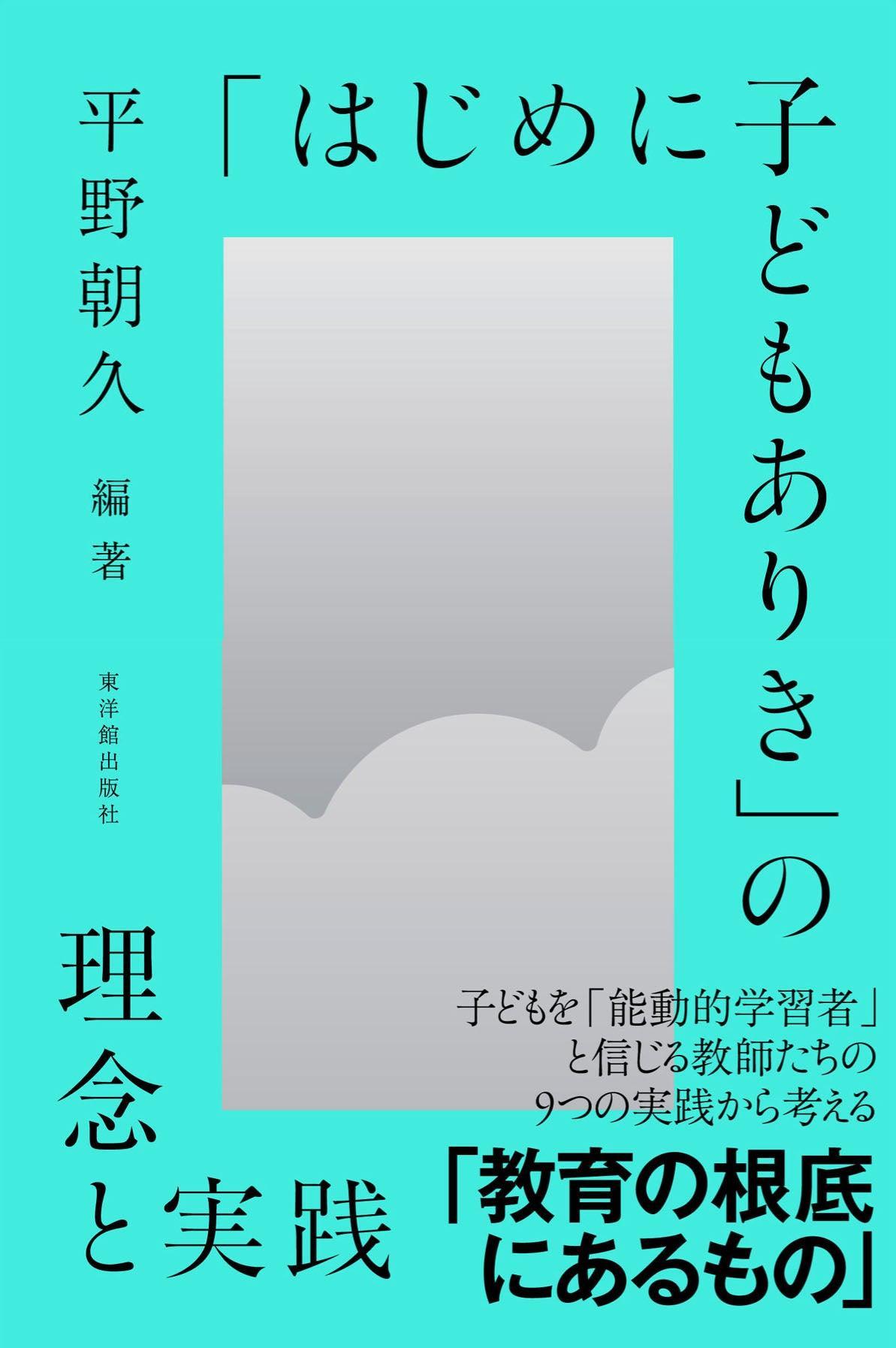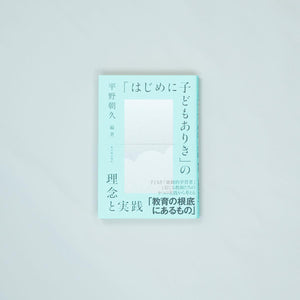「はじめに子どもありき」の理念と実践
レビューを書くと100ポイントプレゼント
商品説明

ベストセラー教育書『はじめに子どもありき』の考えに基づく最新の実践集!真の意味で子どもが「主体的に学ぶ」授業の実現へ
「自ら伸びようとする」子どもたちと授業を共につくる
学校教育では、多くの教師が、子どもが主体的に追究し、学ぶことを願い、そのような授業の実現に努力してきました。
一方で、教える対象である子どもが、どのような子どもであるか分かる前から、目標や内容はもちろんのこと、学習する場所や時間、教材等々も細かくことごとく決めてしまい、子どもがそれに合わせる「はじめに教師(の都合)ありき」の授業も、たびたび指摘されてきました。
本書では、1994年に刊行された『はじめに子どもありき』(学芸図書)の考えをアップデートして再掲し、それに基づく9人の教師の最新実践を紹介します。子どもは「自ら伸びようとする」と信じる先生の授業づくり、学級/学校づくりが分かります。
「はじめに子どもありき」とは――教師は何もしないわけでは全くない
「はじめに子どもありき」とは、ただ子どもに全てを任せて、教師は指導や支援する必要がないという考えではありません。教師をはじめとして子どもの育ちにかかわる人たちの果たす役割を見直し、改めて、子どもの主体的な追究と学びの実現への支援をすることが求められます。
そこで重要なのは子どもの事実を「価値判断をせず、共感して、ありのまま、わかろうとする」ことです。
もちろん、教師、特に授業者であるが故にわかることやそうでなければわからないこともあろう。それは大切にしながらも、子どもを共感的に見取るためには、見取る時には、そのような教師性(教師であること)から脱却することが必要である。
教師は、子どもの行動を見て、子どもが言ったことを聴いて、子どもを理解しようとする。しかし、その時にどのような立場で見、聴き、理解しようとしているであろうか。子どもを指導する教師として「こうあるべし」ということに照らして見てはいないであろうか。授業場面だけでなく、子どもを見る時に、あるべき子ども像を傍らに置いて、それに照らして一人ひとりを見てはいないであろうか。授業者であれば、本時でねらいとすることに照らして見てはいないであろうか。そして、それに照らして「そうでないこと」を直ちに「そうであること」へと変えようと指導してはいないであろうか。
授業者であれば、子どもを見取る際には、子どもに寄り添い、子どもと共に追究し、学ぶ一人として、また子どもと共に生き、成長していく一人として見取るようにしたい。それは、担任教師であればこそできることでもある。
(本文より抜粋)
また、学ぶ者の論理とすでに学んでいる教師の論理は異なっています。

図のように子どもの自然な学びの道筋は、しばしば不合理であり、紆余曲折することになります。こうした試行錯誤をとばすように、すでに学んだ者が最短経路で教えていくことは、その子の学びになりません。
このように、子どもが学ぶということを見つめ直し、子どもの真の主体的な学びを提唱したのが「はじめに子どもありき」です。そして、このこうした子どもを信じきって行う教育論は、「指導事項を満たすことができるのか」「理想論ではないか」など批判を受けたことも事実です。
本書には、それでも「自ら伸びようとする」子どもたちの思いを最大に引き出しながら、授業をつくった実践があります。ここでは、物語文を読んでその世界を実際に体験したいと思った子どもたちとともに校庭に出て学びを深めた国語科の実践を紹介します。
授業後に物語の続きを書き始める子どもたちにとっての「本物」の体験と学び
一年生 国語科 物語文『くじらぐも』の授業
本文を一読した後、子どもたちは「本物のくじらぐもに会ってみたい。」「くじらぐものお話みたいにやってみたい。」と願っていた。
そこで、『くじらぐも』の内容と同じように、次の時間に校庭へ出てみることにした。子どもたちは、校庭に出ると体操を始めた。すると、本当に空に大きなくじらが現れた。
「見て!くじらぐもだぁ~!」
「本当だ。すごい、すごい!」
「ねぇ、みんなで『くじらぐも』のお話を読もうよ。」
Aさんが提案すると、子どもたちは、
「うん。いいね。楽しそう。」
と、提案を受け止めて音読をし始めた。教室での音読とは違って、本当に生き生きとした音読だった。私も一緒に読みながら、くじらぐものセリフのところは、私が声色を変えて読んでみた。子どもたちは微笑みながら、音読を続けていった。そして、この『くじらぐも』の話の一番楽しい場面に入った。子どもたちがくじらぐもに飛び乗る場面である。
「みんな、手をつないで丸くなるよ!」
Bさんが、みんなに呼びかけた。子どもたちは、呼応するように手をつないで大きな輪をつくった。
「天まで届け、一、二、三!」
子どもたちがジャンプする度に、くじらぐもの声も大きくしていった。そして、とうとう雲のくじらに乗ることができた。実際に乗っていないが、子どもたちは、十分乗っている気分になっていた。
「くじらぐもは、ジャングルジムの上に、みんなを降ろしました。」
と読み終わると、誰ということもなく一斉にジャングルジムがある方へ走り出した。そして、子どもたちはジャングルジムの上に乗ると、「さようなら。」と言って、雲のくじらに手を振った。ちょうどその時に、本当に四時間目の終わりのチャイムが鳴った。

――
授業を振り返って
その日の昼休み、校庭にくじらぐもを探しに行く子どもたちも多く見られた。また、このことをきっかけに、「『くじらぐも』のお話の続きを考えたい。」と願って、自ら自由帳に物語の続きを書く姿も見られた。
教科学習においても、子どもの思いや願いを大切にすることは、その子どもなりの主体的な学びを大切にすることにもなり、その子どもの学びをより豊かにすることにつながるのであろう。
子どもの学びを考え直す、「能動的学習者」たちと歩んだ9人の実践集です!