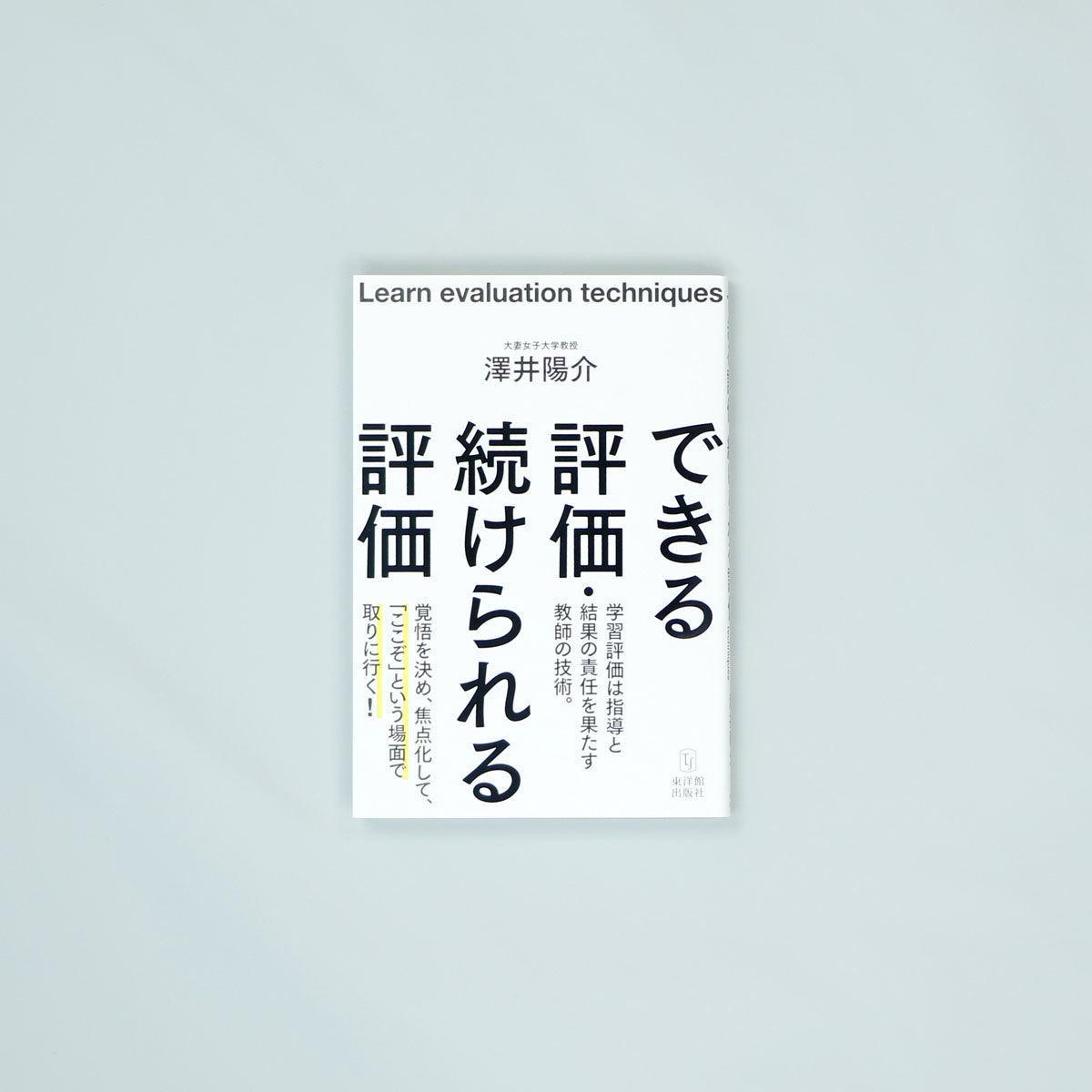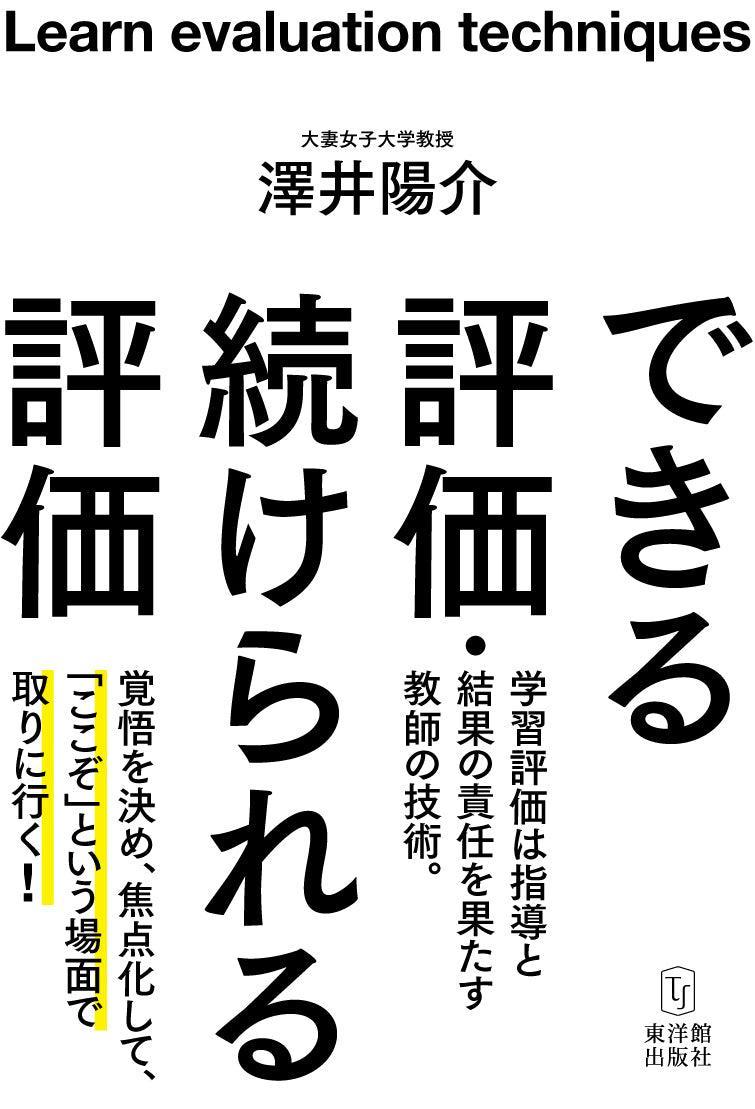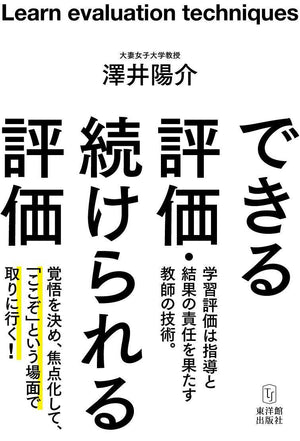レビューを書くと100ポイントプレゼント
商品説明
「学習評価は難しい、大変だ」と感じている先生方の悩みを解決!
学習評価は、指導と結果の責任を果たす教師の技術
- 確かな理解と方法を身に付けることで、無理なく評価できるようになる
- 資質・能力を評価する着眼点が分かる
- 評価を「指導に生かす」ことと「記録に残す」ことの関係を含め「指導と評価の一体化」の真の意味がよく分かる
- 年間を通じた評価マネジメントの方法が分かる など
社会科をはじめとする現場の実践例を交えながら、学校段階を問わず、どの教科等にも通用する学習評価の考え方・方法を分かりやすく解説するとともに、見落としやすいポイントなどを1冊にまとめています。
無理なく、できる範囲で妥当性・信頼性のある学習評価を行うために押さえておくべきは「指導と評価の一体化」です。古くからある言葉ですが、「適切な評価を行うために指導と一体化させるものだ」と理解されている先生方は少なくないようです。つまり、指導よりも評価のほうに軸足があるという受け止めです。
しかし、そうではなく、「軸足は指導の充実のほうにこそあり、そのために評価と一体化させる」と受け止めるのが賢明です。もし「評価のための指導」という意識が強すぎれば、いつまで経っても「評価は難しく、大変なもの」であり続けます。
ここで、改めて目を向けてほしいのが、学習評価は何に準拠するかです。そう「目標」です。つまり、「ちゃんと目標に準拠して評価していますよ」ということがきちんと説明できればOKなのが原理・原則です。端的に言うと、次の説明となります。
「指導と評価の一体化」の考え方に基づき、目標に沿って「評価」と指導を重ねてきた結果を最終的に「評価」したものである。
この説明には、「評価」という言葉が2回登場します。
[前段]目標に沿って評価と指導を重ね
[後段]結果を最終的に評価した
少々分かりにくい表現かもしれませんが、たいへん重要なポイントです。「指導と評価の一体化」の基本的な考え方を明確に示すものだからです。(図にすると「資料」のとおりです)
1 評価したことを「指導に生かす」
この「指導に生かす」方法には、次の二つの側面があります。
①授業における目標を実現して子供の資質・能力の育成を目指す、すなわち学力を高めるために生かすという側面
②その前提として、子供の学習状況を把握したら教師の指導改善に生かすという側面
①は、その場で子供に「助言する」「褒める」など、子供に直接働きかける例が挙げられます。
②は、「多くの子供の理解が不十分だと感じられたら次の時間で補充的な指導をする」「学習を通じて育成が不十分だったと感じられた資質・能力(例えば「思考力、判断力、表現力等」)があれば次の単元で補う」などといった、教師自身の授業改善、指導改善につなげる例が挙げられます。
この「指導に生かす」段階では、評価規準を細かく考えて授業に臨む必要はありません。そもそも評価規準をいつも頭のなかで反芻しながら授業を行っている先生はほぼいないでしょうし、「指導に生かす」段階では「ABC」を付けないからです。言い換えれば、評価規準の数だけ「ABC」を付けるわけではないということです(国研の参考資料の例では、ほぼ毎時間どの観点の評価規準と対応するか指導計画に記されていることもあって、思い違いしやすいことの一つ)。
2 評価したこと(の評価)を「記録に残す」
次は、授業を通じて評価と指導を重ねてきた結果を「記録に残す」評価です。「ABC」を付けるのはこの段階です。
端的に言えば、前述の「指導に生かす」とは教師自身が「指導する責任を果たす」 ことだとするならば、「記録に残す」とは教師自身が「指導した責任を取る(明らかにする)」ことだと言えるでしょう。
このように、評価には2つの段階があるのです。
「いかなるときでも『ABC』を付けることが評価だ」と思い込んでしまうと、単元の端々で「ABC」をたくさん付けたくなります。その結果、[前段]の場面でも「『ABC』を付けておこう」と考えてしまうのです。それでは、評価のための指導となってしまい、指導と評価は一体化しません。
それでもなお「ABC」を付けたい衝動に駆られるのであれば、心のなかで「自分は現在『指導する責任』を十分に果たしているだろうか」と自問してみるとよいでしょう。教師は自分が指導したことを記録に残すのであって、指導していないことまで記録に残す責任を負う必要はないからです。
ここまで「指導に生かす」「記録に残す」とを分けて個別に説明していますが、評価そのものが2種類あるわけではありません。評価したことを指導に生かすか、それとも記録に残すかと、いわば「使い道の違い」を説明しているのです。
子供の学習状況に関わるたくさんの情報のなかから「何をどう選択・判断するか」といった指針となるものが評価規準や評価材料であり、根幹になるのが目標だという構造で考えるとよいと思います。
だから(評価を気にするよりもまず先に)教師としての自分の意図を明確にして指導し、指導した結果どのような変容が子供に見られたのかを見取るようにすればよいのです。
本書では次の具体策を掲載しています。
できる評価・続けられる評価の具体策
[具体策①] 資質・能力が見える単元をつくる
[具体策②] 目標をよく考える
[具体策③] 「A」は後回しにして「B」を探す
[具体策④] 教科セクトでカリキュラムをマネジメントする
[具体策⑤] 評価材料はねらってとりにいく
[具体策⑥] 「指導」のほうを強く意識する
[具体策⑦] 教材会社のワーク・テスト活用の仕方
[具体策⑧] 日ごろから評価材料を集めておく習慣を付ける
[具体策⑨] 学期末に子供に「振り返り」を書かせる
[具体策⑩] 評価のための演習(研修)