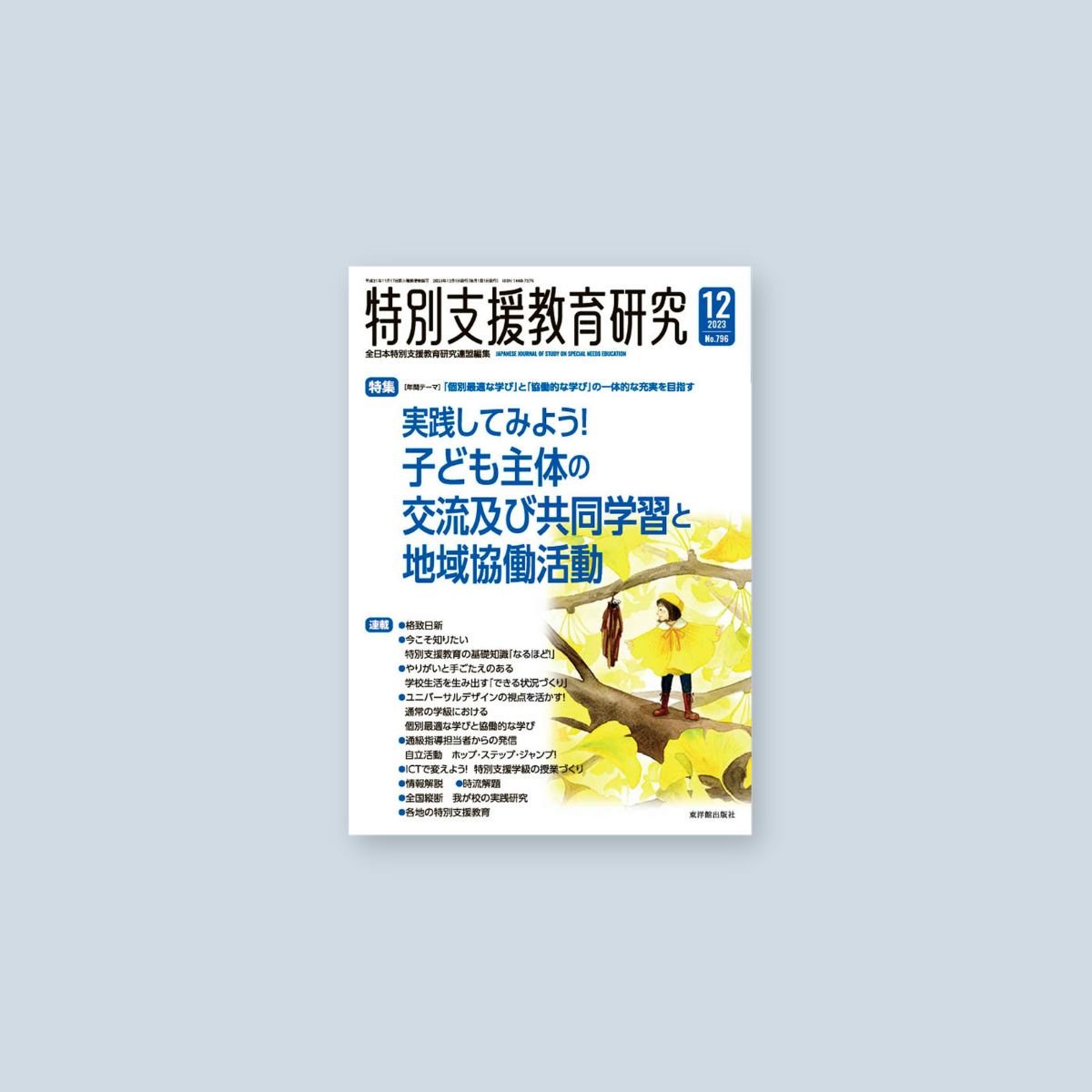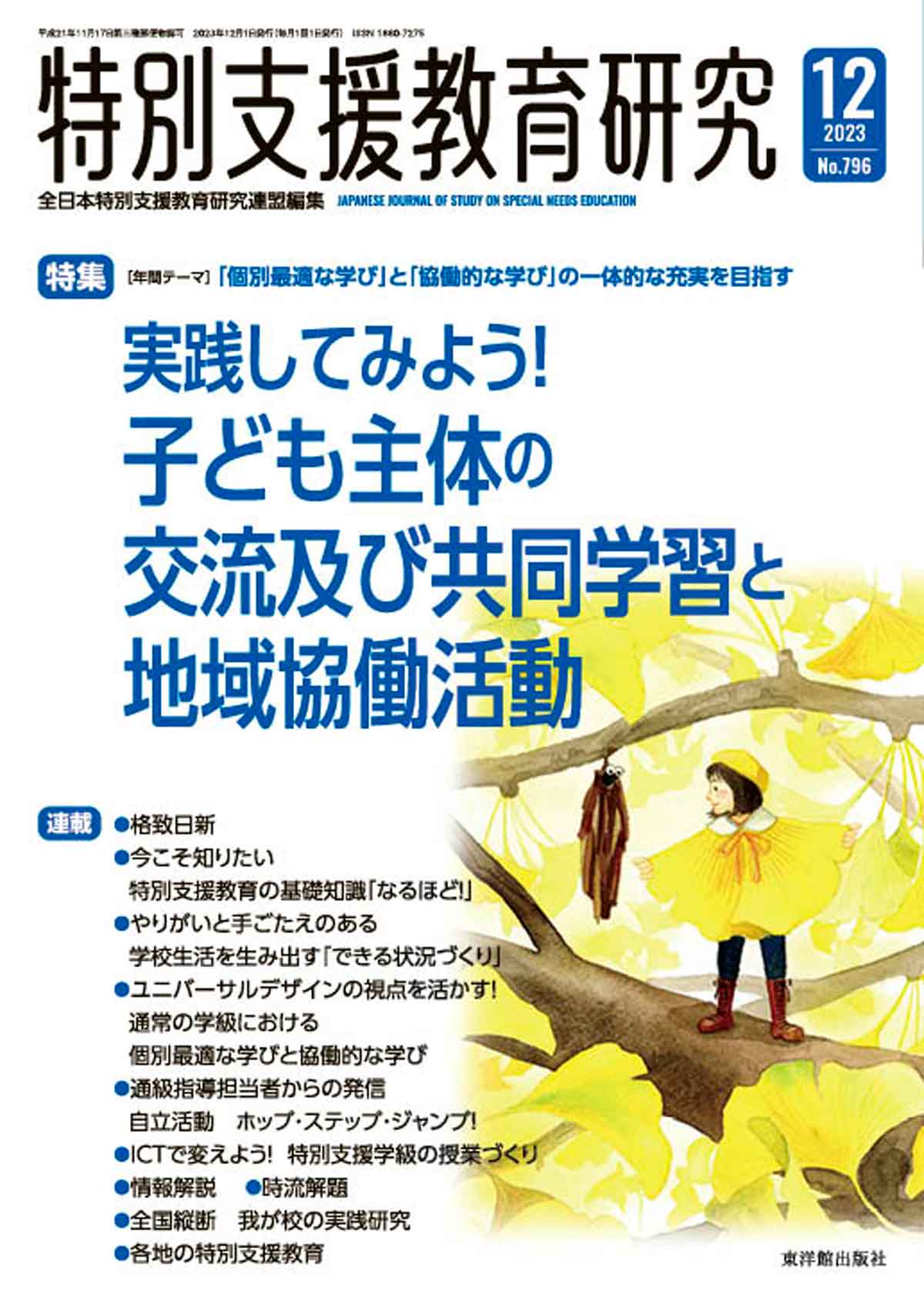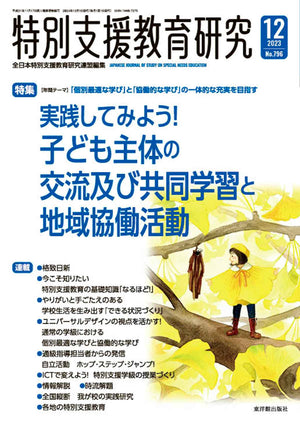レビューを書くと100ポイントプレゼント
商品説明
学習指導要領においては小学校、中学校、高等学校、更に幼稚園教育要領、そして特別支援学校学習指導要領と、全てにおいて交流及び共同学習の推進が位置付けられています。すなわち交流及び共同学習は、特別支援教育の課題に留まらず、多様性が重視されている令和の時代の現代的な重要な教育課題と認識すべき事項となっています。
また、インクルーシブ教育システムの構築が、同じく特別支援教育に留まらず令和の時代の喫緊の重要な課題であることは言うまでもありません。国連の障害者の権利に関する条約に基づいて我が国は国内法を整備して様々な施策等を実行してきましたが、日本の特別支援教育が大切にしてきた特別支援学校、特別支援学級等の学びの場を位置付けたインクルーシブ教育システムを発信するためにも、交流及び共同学習の実践は重要になっています。
そこで本特集では、小・中学校等、そして特別支援学校における交流及び共同学習を中心に、地域との連携・協働の促進により共生社会の形成に資する地域協働活動を取り上げることとしました。交流及び共同学習の実践では、担当する学校現場の教職員が事前の協議や実践の準備の大変さを訴えることが少なくありません。研究委嘱やモデル地域・モデル校に指定されると、様々な取組がなされていますが、それが継続できないことも少なくありません。そこで、通常の学級においても、特別支援学校や特別支援学級においても、更に地域においても、持続できる実践が求められています。交流及び共同学習とは、「やらされる実践」であってはなりません。言うまでもなく、子供たちが主体的に取り組んでいく実践を目指す必要があります。そういう実践の価値を評価し、意義のある活動が将来に向けて持続可能な教育活動となるよう、丁寧に取り組まれている実践を取り上げて発信したいと考えます。
交流及び共同学習を推進し、その充実を図るためには、学校経営の柱に据えた取組が必要です。そういう学校経営に取り組んでいる校長から、これからの交流及び共同学習に向けた提言を取り上げたいと考えます。また保護者の立場からの提言も取り上げ、今後の展望を提案していくものとします。本特集が、交流及び共同学習に負担感を覚えている学校現場に一石を投じ、子供主体の交流及び共同学習の実践が広がっていくことを目指していきたいと考えます。