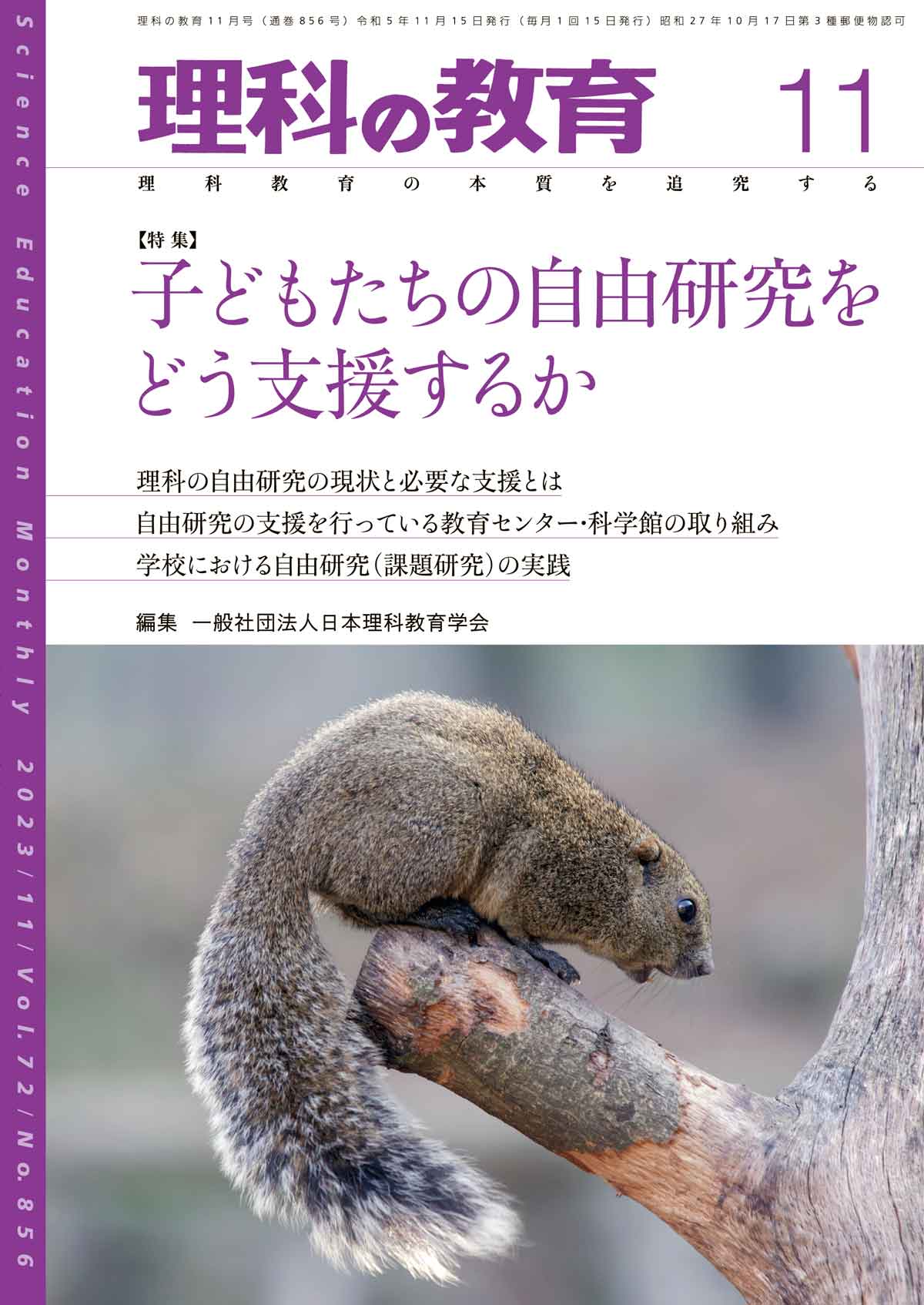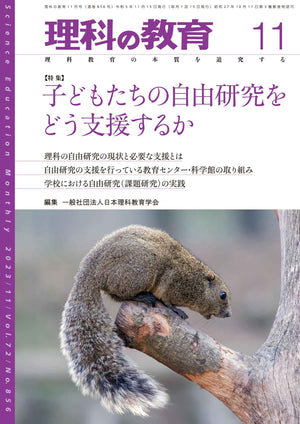令和5年11月号
通巻856号
2023/Vol.72
【特集】子どもたちの自由研究をどう支援するか
■理科の自由研究の現状と必要な支援とは
●理科における自由研究を支援する上で考えたいこと 人見 久城5
■自由研究の支援を行っている教育センター・科学館の取り組み
●堺サイエンスクラブの自由研究に関する取り組み 川田 健次9
●児童の探究力を育む自由研究相談会
-対話を通した問診と探究を阻害しない処方の追究- 遠藤 晃13
●主体的に科学する子どもの育成を願って-静岡県牧之原市における地域の公益財団法人による小学生の理科自由研究支援- 渡邉 聡17
●自由研究の発展につながる多角的なアプローチ-研究発表ボードを活用した事業展開- 古野 峻也・貞國 真穂・伊藤 和俊21
●自由研究を支える「学ぶ力」を育てることを支援する教育委員会の取り組み
―川崎市の理科自由研究の取り組みを例に― 鈴木 克彦25
■学校における自由研究(課題研究)の実践
●子どもの探究心を育てる自由研究
-自由研究に主体的に取り組むための指導・支援- 花澤 利圭29
●理科研究及び標本づくりに取り組む価値や方法を親子が捉えることができるようにするための支援についての実践報告-教師や保護者,講師との連携を通して-
先間 裕哉32
●通常授業における科学的探究力の育成 大川 創史35
●大阪教育大学附属天王寺中学校の自由研究支援
日髙 翼・篠崎 文哉・田中 真理子38
●授業や部活動における課題研究支援と支援ツールの開発 中村 元紀41
●課題研究の着実な推進と内容の洗練に向けて
仲野 純章・松浦 哲郎・米田 敬司44
連載講座
●『理科教育学研究』を授業に生かす
評価に関する知識を整理して活用しよう-アセスメント・リテラシーのモデルからの整理- 渡辺 理文・杉野 さち子・森本 信也48
●生徒をひきつける観察・実験
ユスリカの唾腺染色体の観察 新井 直志50
●教材研究一直線
ヨウ素の昇華を観察する 田中 千尋52
●教材の隠し味
シャープペンシルの芯の抵抗について調べる学習 森 泰一54
●Let’s Try!理科授業のDX
撮影した実験動画を編集しよう! 福嵜 将樹56
●先生はサイエンスマジシャンNEXT
月の表面はいつも同じ? 辻本 昭彦57
学会通信59
次号予告64
〈今月の表紙〉
タイワンリス
学名:Callosciurus erythraeus thaiwanensis
ネズミ目リス科。
かつては中国南部・台湾に生息していたが,飼育個体が逃げ出したことをきっかけに,日本各地に定着している。耳の大きさや腹部の色などで,ニホンリスと見分けがつく。
表紙写真:片平久央
表紙・本文デザイン:辻井 知
(SOMEHOW)
Society of Japan Science Teaching
SCIENCE EDUCATION MONTHLY
2023/Vol.72/No.856
How Should We Support Children’s Independent Research During the Summer Vacation?
5 What We’d Like to Contemplate When Supporting Independent Research Projects in Science
HITOMI Hisaki, Utsunomiya University, Tochigi
9 Efforts of Helping Children With Summer Homework Project in Sakai Science Club
KAWATA Kenji, Sakai Board of Education, Osaka
13 Holding a Consultation About Summer Homework Project, Which Helps Children Develop the Ability to Explore
ENDO Akira, Minami Kyushu University, Miyazaki
17 Hoping for the Development of Children Who Are Willing to Do Science : Support for Children to Do Science Research Projects Sponsored by Nonprofit Foundation in the Community (Makinohara City)
WATANABE Satoshi, Yamazaki Foundation for Promoting Children's Education, Shizuoka
21 Multilateral Approach Leading to Promote Student Independent Research Project : Using the Presentation Board for Research Project
FURUNO Junya, SADAKUNI Maho, ITO Kazutoshi, Kushiro Children's Museum, Hokkaido
25 Our Efforts to Help Children Improve the “Ability to Learn,” Hosted by Board of Education : As an Example of Efforts for Summer Science Projects in Kawasaki City
SUZUKI Katsuhiko, Kawasaki Comprehensive Education Center, Kanagawa
29 Summer Research Projects to Develop Children’s Inquiring Minds : Teaching and Support for Children to Actively Engage in Individual Projects
HANAZAWA Rika, Midorimachi Elementary School, Chiba
32 Practical Report on the Support of Parent and Child, Who Learn to Understand the Value and Method of Conducting Science Studies and Preparing Samples : Through the Cooperation Among Teacher, Guardian, and Lecturer
SAKIMA Yuya, Elementary School Attached to Kagoshima University, Kagoshima
35 To Promote the Scientific Ability to Explore in Ordinary Lessons
OOKAWA Soshi, Atami Lower Secondary School, Shizuoka
38 Efforts of Summer Research Project at Tennoji Lower Secondary School Attached to Osaka Kyoiku University
HIDAKA Tsubasa; SHINOZAKI Fumiya, Osaka Kyoiku University, TANAKA Mariko, Tennoji Lower Secondary School Attached to Osaka Kyoiku University, Osaka
41 Development of Instructional Support Tool and Support for Research Project in Class and Club Activities
NAKAMURA Motoki, Kyuyo Upper Secondary School, Okinawa
44 To Make Steady Progress in Research Project, and to Refine Its Contents
NAKANO Sumiaki, Nara Upper Secondary School, Nara; MATSUURA Tetsuo, Ryukoku University, Kyoto; KOMEDA Takashi, Nara Upper Secondary School, Nara
48 Bringing “Journal of Research in Science Education” into the Classroom
50 Demonstrations to Attract Students
52 Hot Pursuit of Science Material Development
54 Tips to Spice up Instructional Materials
56 Let's Try! DX in Science Lesson
57 My Teacher Is a Science Magician <NEXT>
目次英訳:柿原聖治
A table of contents is translated into English by KAKIHARA Seiji