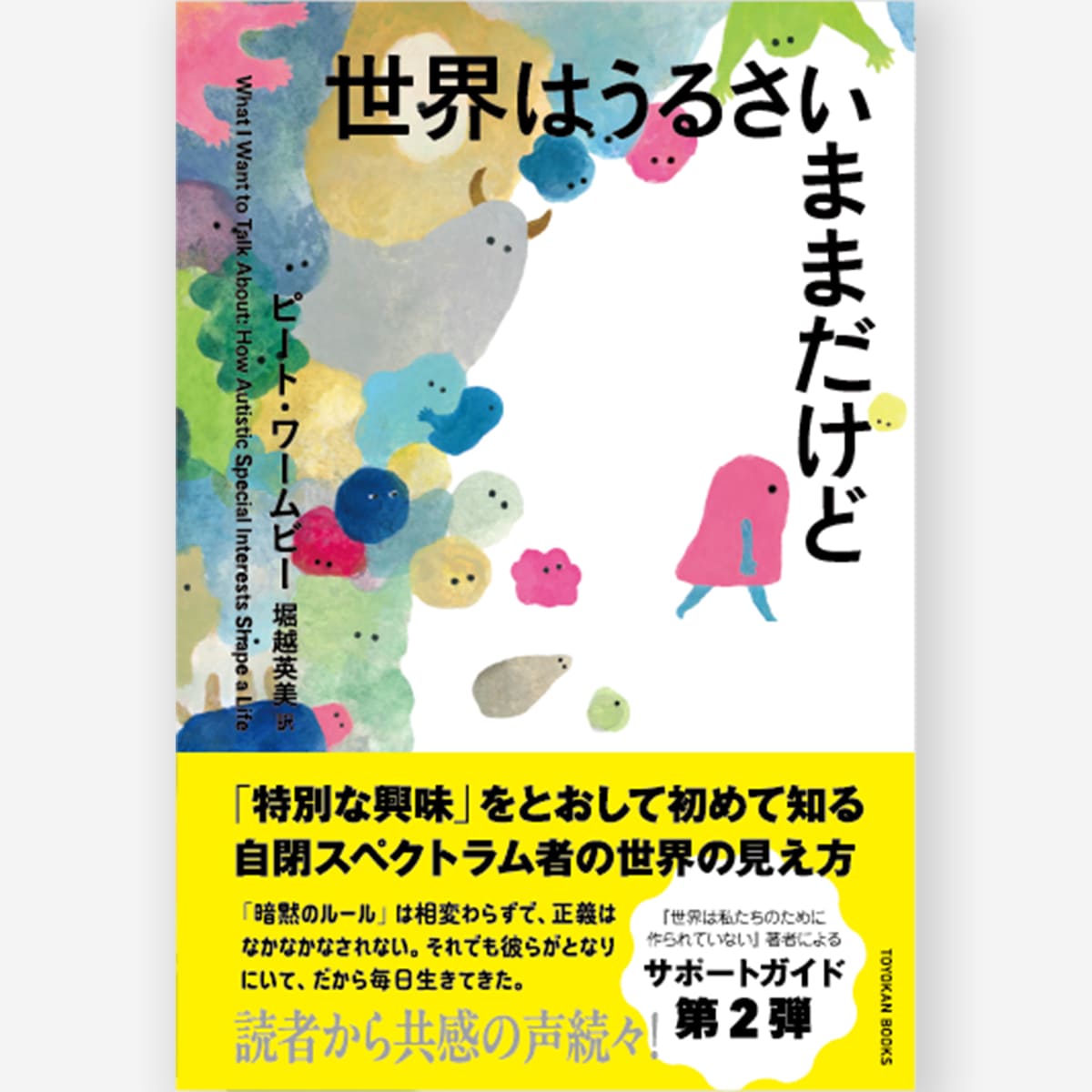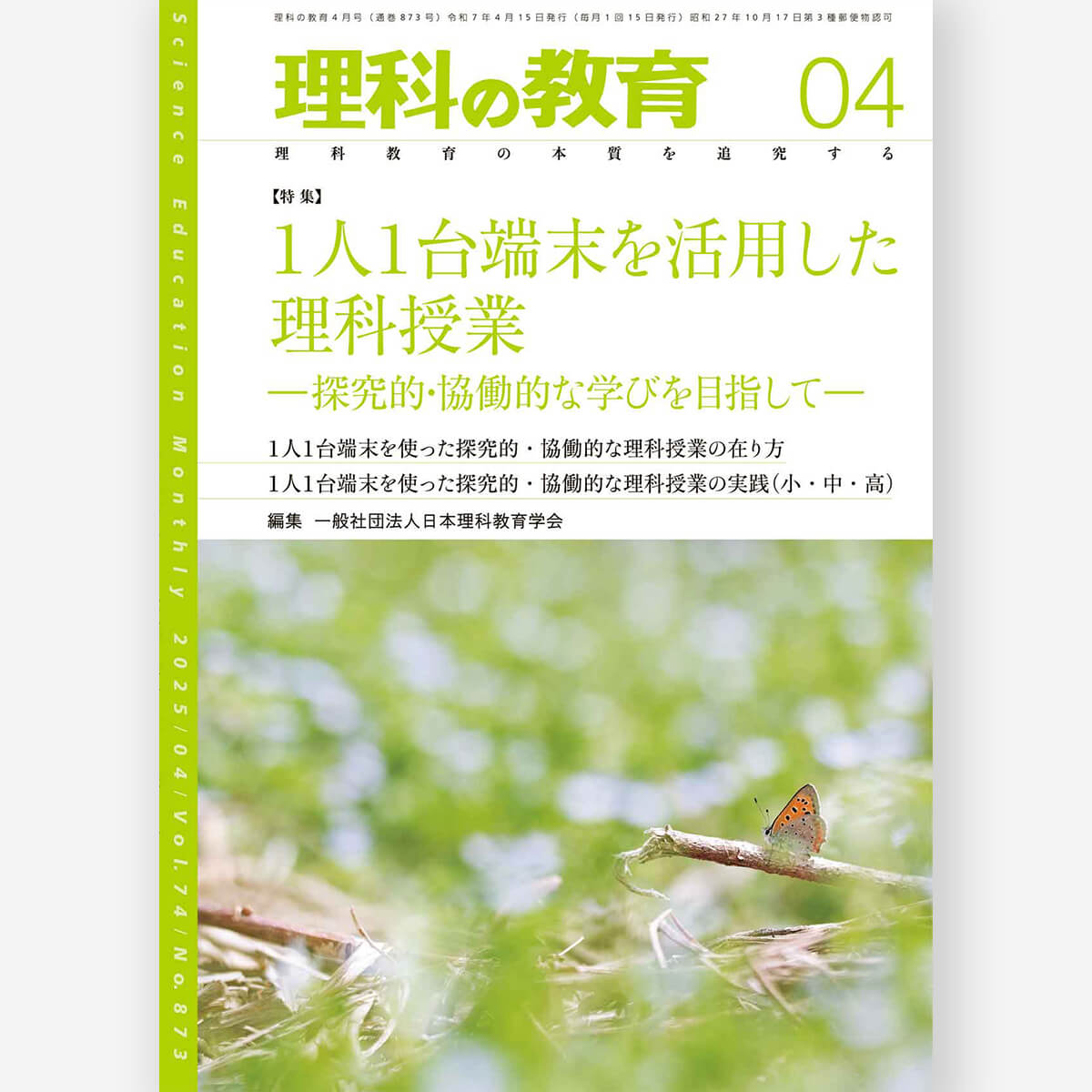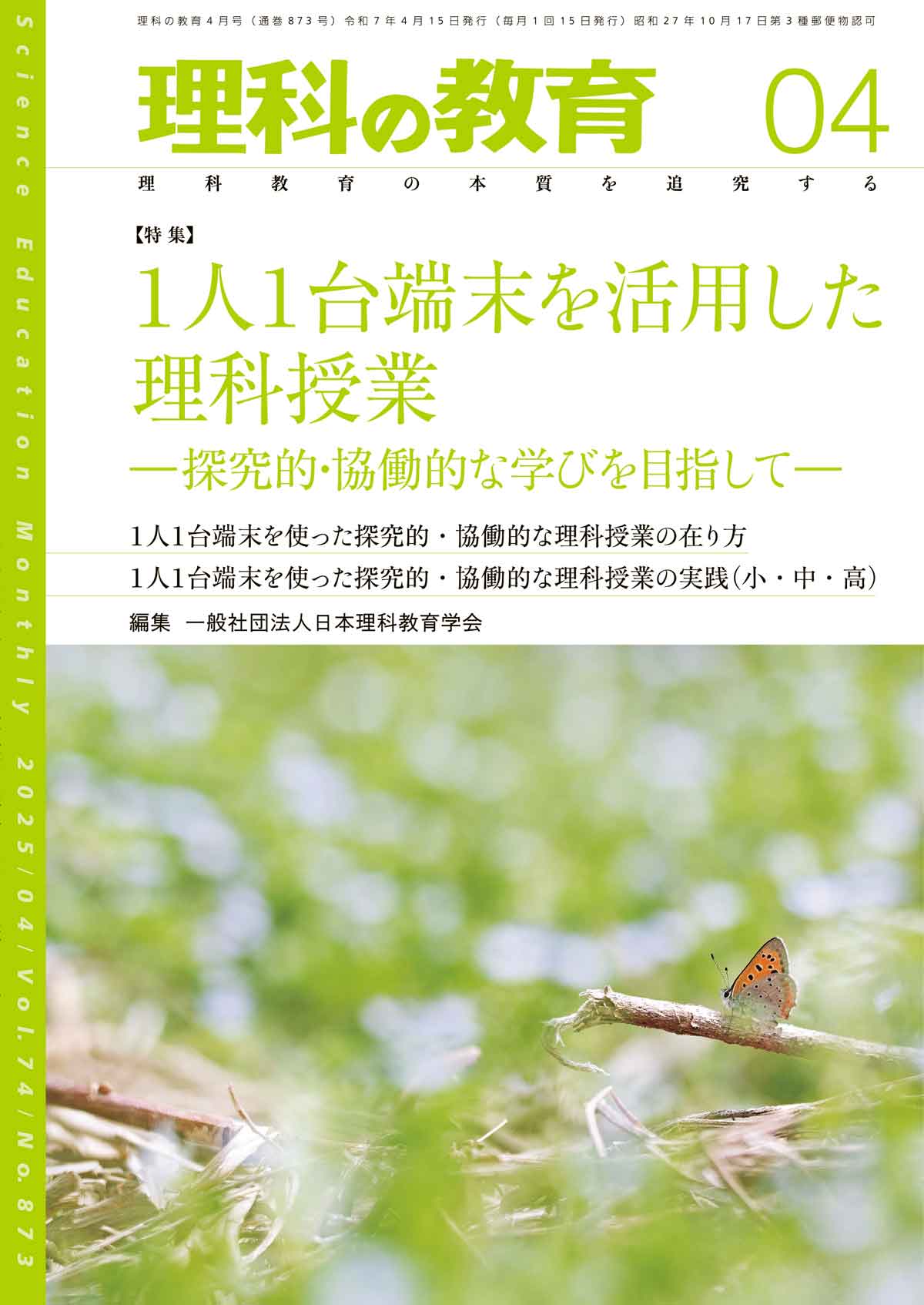令和7年4月号
通巻873号
2025/Vol.74
【特集】
1人1台端末を活用した理科授業-探究的・協働的な学びを目指して-
■1人1台端末を使った探究的・協働的な理科授業の在り方
●1人1台端末を使った個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実
-「他者参照」と「共同編集」から- 久保田 善彦5
●1人1台端末の活用による理科教育の変革
-ICT・生成AIの可能性と課題- 中村 大輝9
■1人1台端末を使った探究的・協働的な理科授業の実践(小学校)
●小学校理科教育でのICTの効果的な活用
-物質・エネルギー分野での活用の可能性を探る- 上敷領 静香13
●探究的・協働的な学びを通して発見する理科の魅力
-理科×1人1台端末で広がる可能性- 縄 祐輔16
●1人1台端末を活用した理科授業の実践
-科学的な学習を目指して- 秋葉 翔20
●児童一人一人の考えを取り入れた理科授業の改善を目指して-小学校第5学年
「流れる水のはたらき」における授業実践を通して- 中島 潤一23
■1人1台端末を使った探究的・協働的な理科授業の実践(中学校)
●1人1台端末を活用した探究的なSTEAM学習-中学校第1学年「状態変化 物質の融点と沸点」における授業実践- 上原 孝枝26
●生成AIを協働パートナーにした探究的な理科授業モデルの提案
真木 大輔29
●「探究の過程」をサポートするタブレット端末の活用
-理科授業での実践紹介と実践を支える校内での取り組み- 斉藤 剛志32
●短時間コツコツ型PBLでのデジタル図鑑の制作
-非認知能力(ソフトスキル)の育成を目指して- 矢野 充博35
●授業におけるタブレット端末によるデータの共有について
成川 玲也38
■1人1台端末を使った探究的・協働的な理科授業の実践(高等学校)
●表計算ソフトを用いた物理シミュレーションを課題解決ツールへとつなげる授業実践-個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実及び情報科との連携を目指して-
稲垣 貴也41
●端末が拓く探究型理科授業の可能性-「観察・実験×ICT活用」で共創する教室を創造する- 中村 英幸44
連載講座
●『理科教育学研究』を授業に生かす
評価判断力を働かせ,自己調整的に学ぶ―小学校第3学年「明かりをつけよう」の単元を事例に― 齊藤 徳明・和田 一郎 48
●生徒をひきつける観察・実験
雲を作ろう 山口 晃弘 50
●教材研究一直線
魅力的な鉱物の実験① 田中 千尋 52
●教材の隠し味
自然災害・環境問題を多面的・総合的に考察する能力や態度を育成する教材
-山火事の事例を用いて- 池野 康太 54
●概念構築を目指した探究型授業
~流れにくさの概念形成を目指した授業~
理解に課題があるとされたΩの法則へ 荒尾 真一 56
●理科とわたしの仕事
理科の魅力は「会話」に宿る 研究者レン 58
●先生はサイエンスマジシャンNEXT
「ねるねるねるね」で化学変化を! 辻本 昭彦 59
第2回『理科の教育』
大賞の決定 60
学会通信 63
入会案内 64
次号予告 68
〈今月の表紙〉
ベニシジミ
学名:Lycaena phlaeas
チョウ目シジミチョウ科。
春から秋にかけて成虫が見られる小型の蝶。鮮やかな橙色と黒い斑点が特徴。
表紙写真:片平久央
表紙・本文デザイン:辻井 知
(SOMEHOW)
Society of Japan Science Teaching
SCIENCE EDUCATION MONTHLY
2025/Vol.74/No.873
Science Lessons by Using PC/Tablets for Each Student: Aiming for the Inquiry-based and Cooperative Learning
5 Promotion of Combining Individually Optimal Learning and Cooperative Learning, by Using PC/Tablets for Each Student
KUBOTA Yoshihiko, Tamagawa University, Tokyo
9 Revolutionary Change in Science Education by Using PC/Tablets for Each Student: Possibility of ICT & Generative AI, and their Challenges
NAKAMURA Daiki, University of Miyazaki, Miyazaki
13 Efficient Use of ICT in the Elementary School Science Lessons: To Explore the Possibility of Using ICT at the Field of Physical Science
KAMISHIKIRYO Shizuka, Gamou Elementary School, Saitama
16 Attractiveness of Science to Discover Through the Inquiry-based and Cooperative Learning: Potential for Further Development of Science by Using PC/Tablets for Each Student
NAWA Yusuke, Himeji Board of Education, Hyogo
20 Practice of Science Lessons, Using PC/Tablets for Each Student: Aiming for Scientific Learning
AKIBA Sho, Itabashi Dai-6 Elementary School, Tokyo
23 Aiming to Improve Science Lessons in Which Each Student's Ideas Are well Incorporated: Educational Practice of “Functions of Flowing Water” in Fifth Grade
NAKAJIMA Junichi, Hokota-minami Lower Secondary School, Ibaraki
26 Inquiry-based Learning of STEAM by Using PC/Tablets for Each Student: Practice of “Changes of State, Melting and Boiling Points of Substances” in 7th Grade
UEHARA Takae, Tokyo Metropolitan School Personnel In-Service Professional Development Center, Tokyo
29 Proposal of Inquiry-based Science Lessons Model, With Generative AI Serving As a Cooperative Partner
MAKI Daisuke, Lower Secondary School Attached to Ehime University, Ehime
32 Use of PC/Tablets to Support “Discovery Processes”: Practical Examples of Science Lesson, and School Activities to Support Educational Practice
SAITO Tsuyoshi, Lower Secondary School Attached to Gunma University, Gunma
35 Making a Digital Pictorial Book at PBL (Project Based Learning), That is a Short-time & Steady-Style: Aiming to Develop Non-Cognitive Ability (Soft Skill)
YANO Mitsuhiro, Lower Secondary School Attached to Wakayama University, Wakayama
38 Data Sharing by Using PC/Tablets in Lessons
NARIKAWA Reiya, Goshomi Lower Secondary School, Kanagawa
41 Instructional Practice of How Physics Simulations Using a Spreadsheet App Become a Powerful Tools of Problem Solving: Trying to Integrate Individually Optimal Learning with Cooperative Learning, and to Collaborate with Informatics
INAGAKI Takaya, Lower & Upper Secondary School Attached to Hiroshima University, Hiroshima
44 Possibility of Inquiry-based Science Instruction by Using PC/Tablets: To Create Classroom With the Help of “Observation & Experiment×ICT Use”
NAKAMURA Hideyuki, Tomioka-nishi Upper Secondary School, Tokushima
48 Bringing “Journal of Research in Science Education” into the Classroom
50 Demonstrations to Attract Students
52 Hot Pursuit of Science Material Development
54 Tips to Spice up Instructional Materials
56 Inquiry-based Lessons Aimed at Constructing Conceptions
58 Science and My Job
59 My Teacher Is a Science Magician <NEXT>
目次英訳:柿原聖治
A table of contents is translated into English by KAKIHARA Seiji