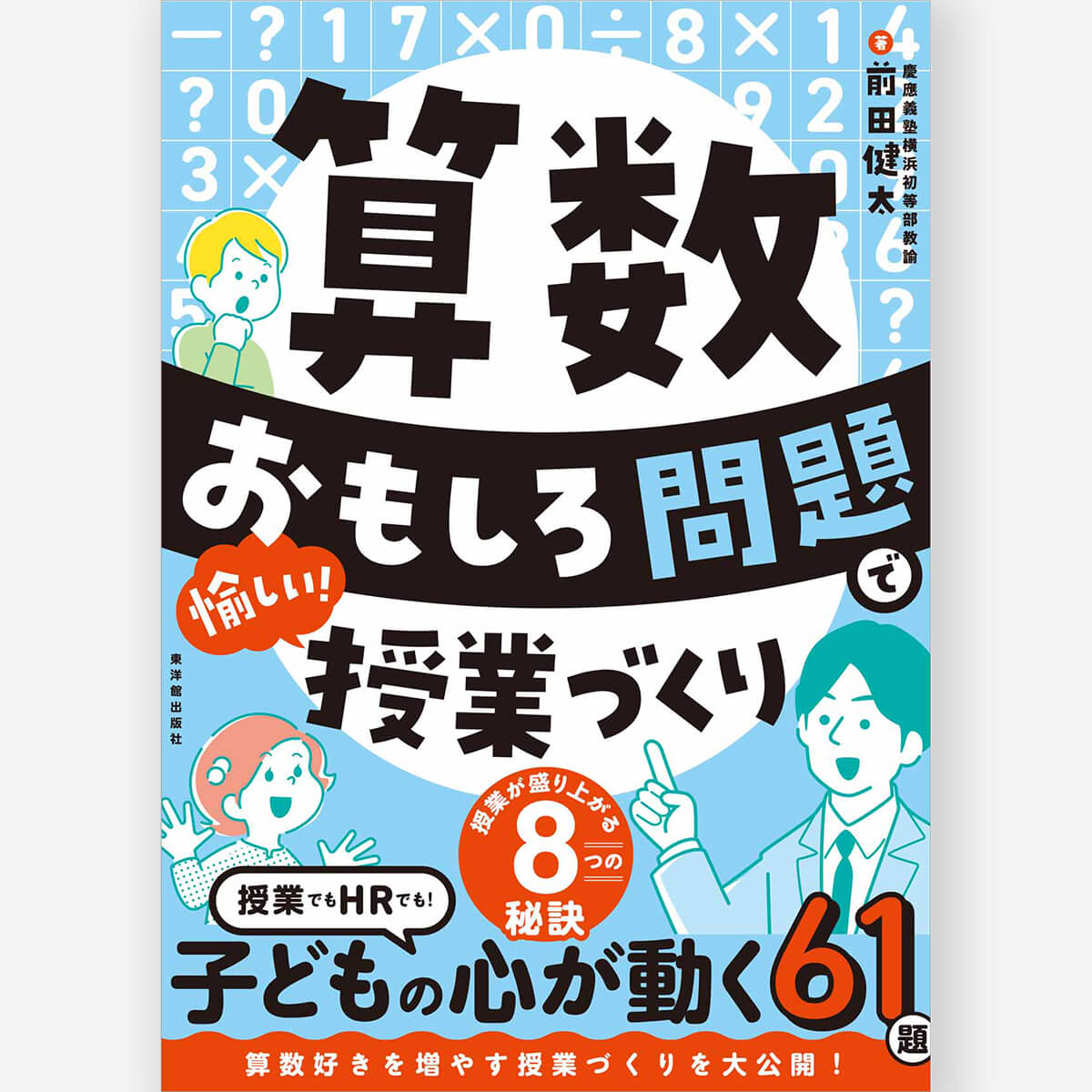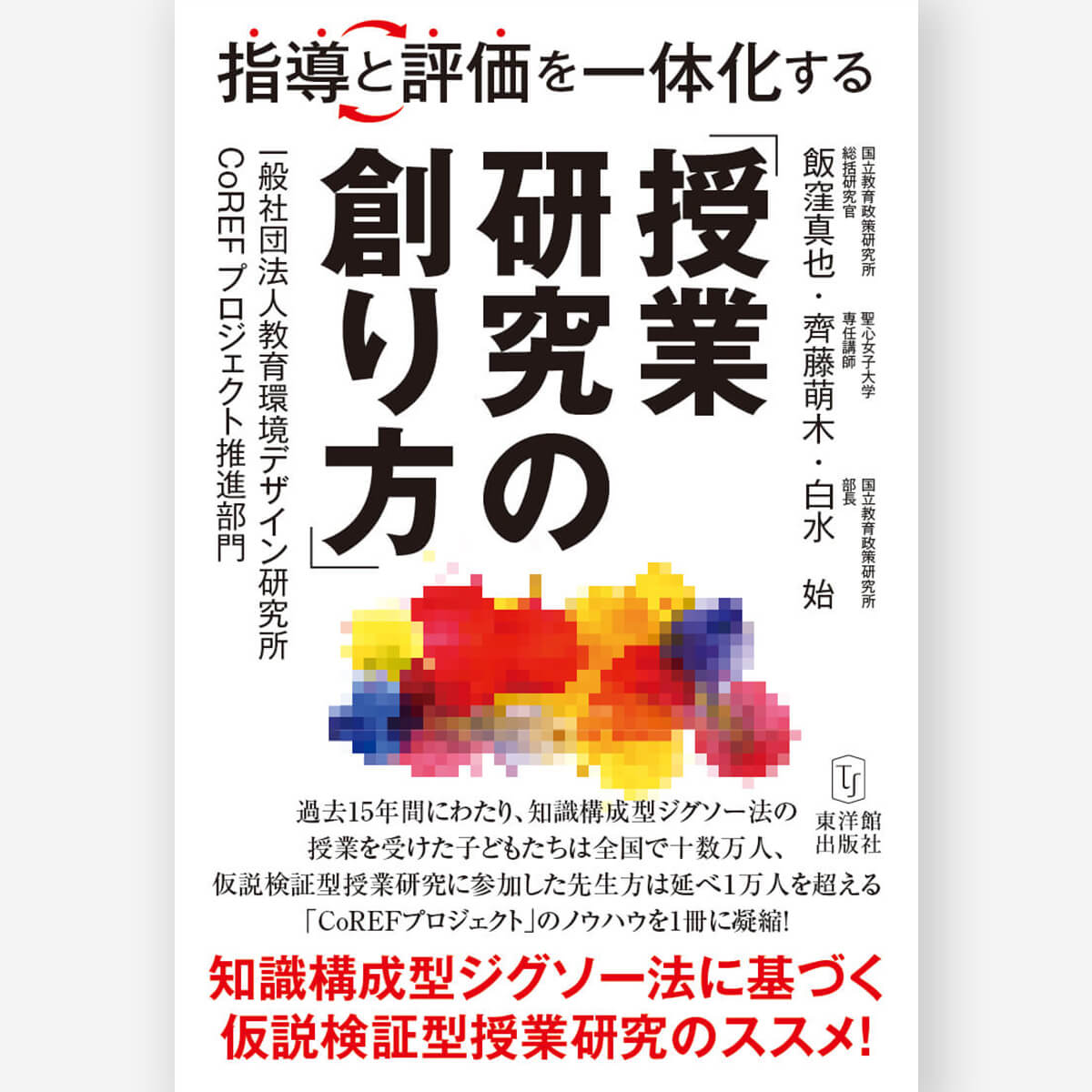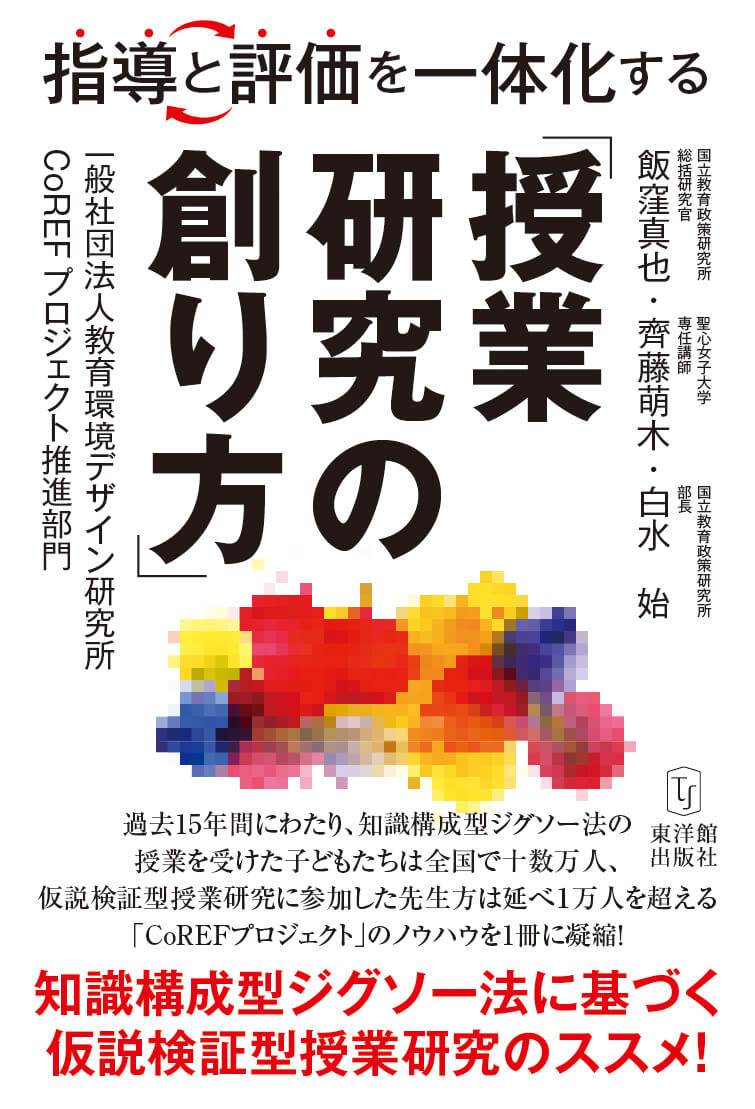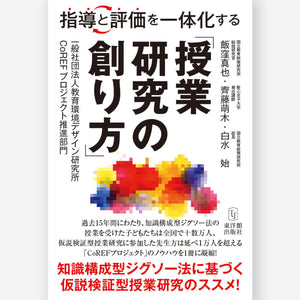指導と評価を一体化する「授業研究の創り方」―知識構成型ジグソー法に基づく仮説検証型授業研究のススメ!
レビューを書くと100ポイントプレゼント
商品説明
先生方が深く学べる「対話」を全力でサポートする至高のバイブル
知識構成型ジグソー法に基づく仮説検証型授業研究のススメ!
過去15年間にわたり、知識構成型ジグソー法の授業を受けた子どもたちは全国で十数万人、仮説検証型授業研究に参加した先生方は延べ1万人を超える「CoREFプロジェクト」のノウハウを1冊に凝縮!
本書の概要
授業研究は、子どもの「学びの過程」を軸にして学び合えてこそ先生方は真に成長し、子どもたちもまたいっそう深く学べるようになる―それが実は、指導と一体化する学習評価の核心です。
そして、そんな先生方の学びを、働き方改革が叫ばれる今日にあっても無理なく効果的に行おうとする試みが、本書で紹介する知識構成型ジグソー法を用いた仮説検証型の授業研究なのです。
本書では、「前向きの評価観」に基づき、どのようにして子どもの「学びの過程」を軸足に据えた授業研究を実現すればよいのか、そのノウハウのすべてを1冊にまとめています。
知識構成型ジグソー法そのものに興味がある方も、主体的・対話的で深い学びの実現に向けて授業研究をどう創っていけばよいかに興味がある方も、ぜひお手に取っていただければ幸いです。
本書からわかること
これからの授業研究において、なぜ「前向きの評価観」をもつことが欠かせないのかがわかる
「前向きの評価観」は、子どもを能動的で有能な学び手と信じ、その子どもたちが学ぶ学習環境として授業を捉え、授業のデザイン次第で子どもはその学ぶ力を発揮できるという学習者観・学習観です。
この「前向き」ということを、もう少し詳しく見てみると、当初予想していたとおりに子どもたちが学ばなかったときにすら、それを「なぜ、そんな学び方/つまずき方をしたのだろう」と掘り下げて考え、「では明日はこういう風に授業を変えよう」という形で、各時点の「学びのゴール」を柔軟に変えていくことまでを含みます。だからこそ、日々の学びを見とって伸ばす形成的評価が、子どもの昨日から今日へ、今日から明日へと学びをつなげていくことを支えるのです。 ではなぜ、こうした評価観をより重視する必要が生じているのでしょうか。それは、現代における「学びのゴール」そのものが変化しているからです。そこで本書では、「前向きな評価」に軸足を置いた授業研究の考え方と方法を紹介します。
「知識構成型ジグソー法」を例に、「学びの事実」と「学びの過程」を軸にした授業研究の具体的な進め方がわかる
授業にしても、授業研究にしても、正しい一つの手法というのはあり得ません。しかし、正しい一つの解はなくても、物事を前に進めていくためには、理論に基づいた仮説をもって(その負の側面も意識しながら)、リスクをとってアクションを仕掛けていくことが必要です。学習科学の世界では、こうしたアプローチをデザイン研究(Design Based Research)と呼んでいます。本書で紹介する「知識構成型ジグソー法」を活用した授業研究はその一例です。その具体的な特長は、次が挙げられます。
●活動の型がはっきりしているので、それぞれの学習場面でどのような子どもの姿(「学びの過程」)が生まれそうなのか、具体的な「想定」をもちやすい。
●この手法には子どもの力を引き出す仕掛けがあるので、初めて取り組む学校や先生方においても、授業の流れや子どもの学び方、つまずき方を見とりやすい。
●共通の前提に立っているため、個別・具体の子どもの「学びの過程」について先生同士で対話しやすい。
この「知識構成型ジグソー法」を活用した授業研究を具体的にどのように進めていくかを切り口に、「学びの過程」を軸にした「授業研究の創り方」を考えていきます。
先端技術を活用することで、働き方改革が叫ばれる今日であっても無理なく効果的に授業研究を創るヒントがわかる
若年化、多忙化、孤立化が進む学校で授業研究を質高く、効率的に進めるためには、授業づくりの負担や学びの見とりの難しさなど、多くのハードルが存在します。授業研究を支える先端技術にはどのような可能性があり、学校現場はそれをどのように使いこなしていけばよいでしょうか。本書で紹介する「知識構成型ジグソー法」を活用した授業研究では、文部科学省「次世代の学校・教育現場を見据えた先端技術・教育データの利活用推進(最先端技術及び教育データ利活用に関する実証事業)」等を通じて次のシステムを開発し、授業研究のサポートを行っています。
●「学譜システム」(授業研究のデータベース・システム)
●「学瞰レコーダー」(子どもの発言やつぶやきを拾う記録装置)
●「学瞰システム」(子どもたちの学びの可視化システム)
それぞれの現場でも何らかの先端技術が活用できるようになっているのではないでしょうか。本書では、どのような先端技術を活用するかよりも、先端技術をどのように活用すれば、効率的・効果的に教材研究や授業準備を行えるようになるのかに焦点を当てて解説します。