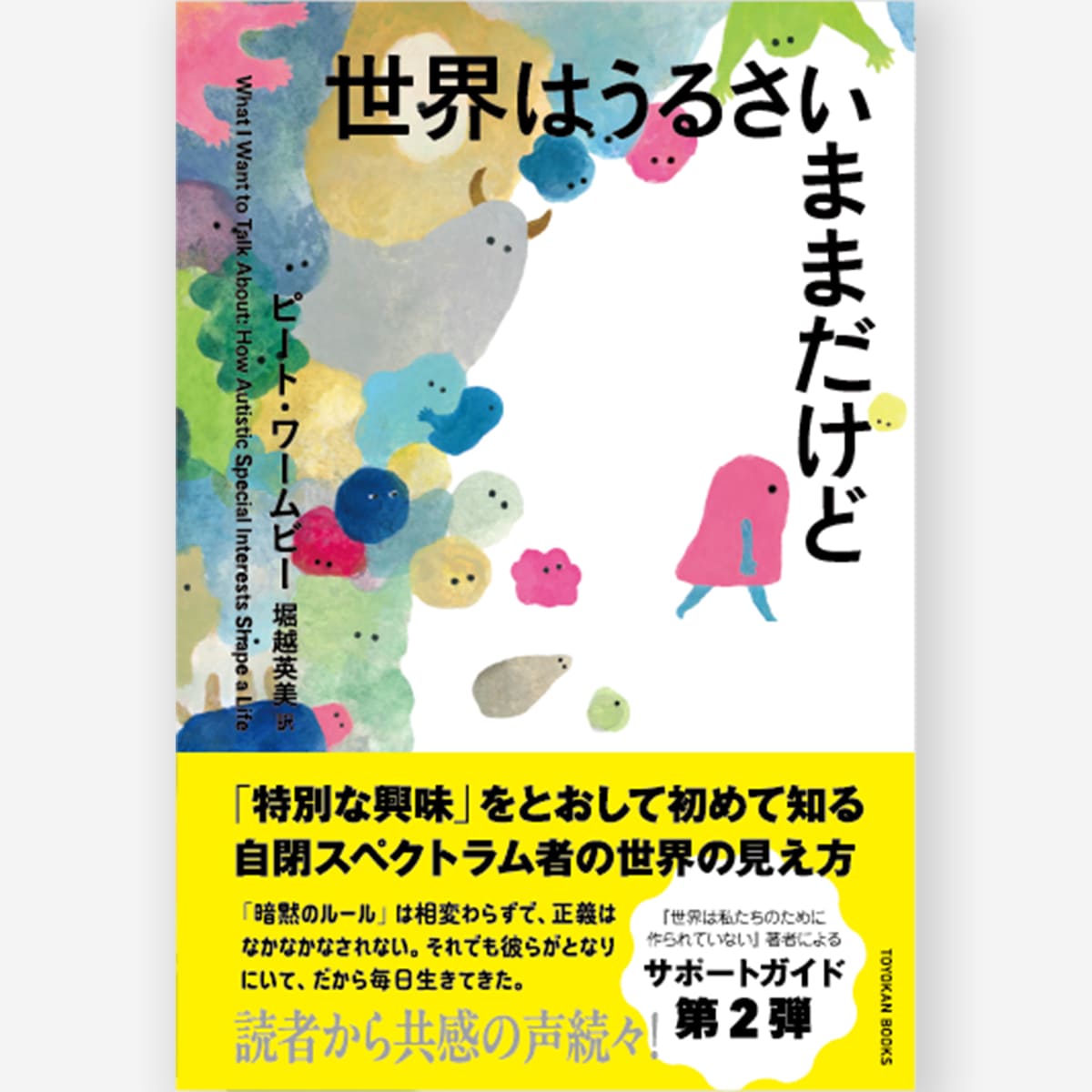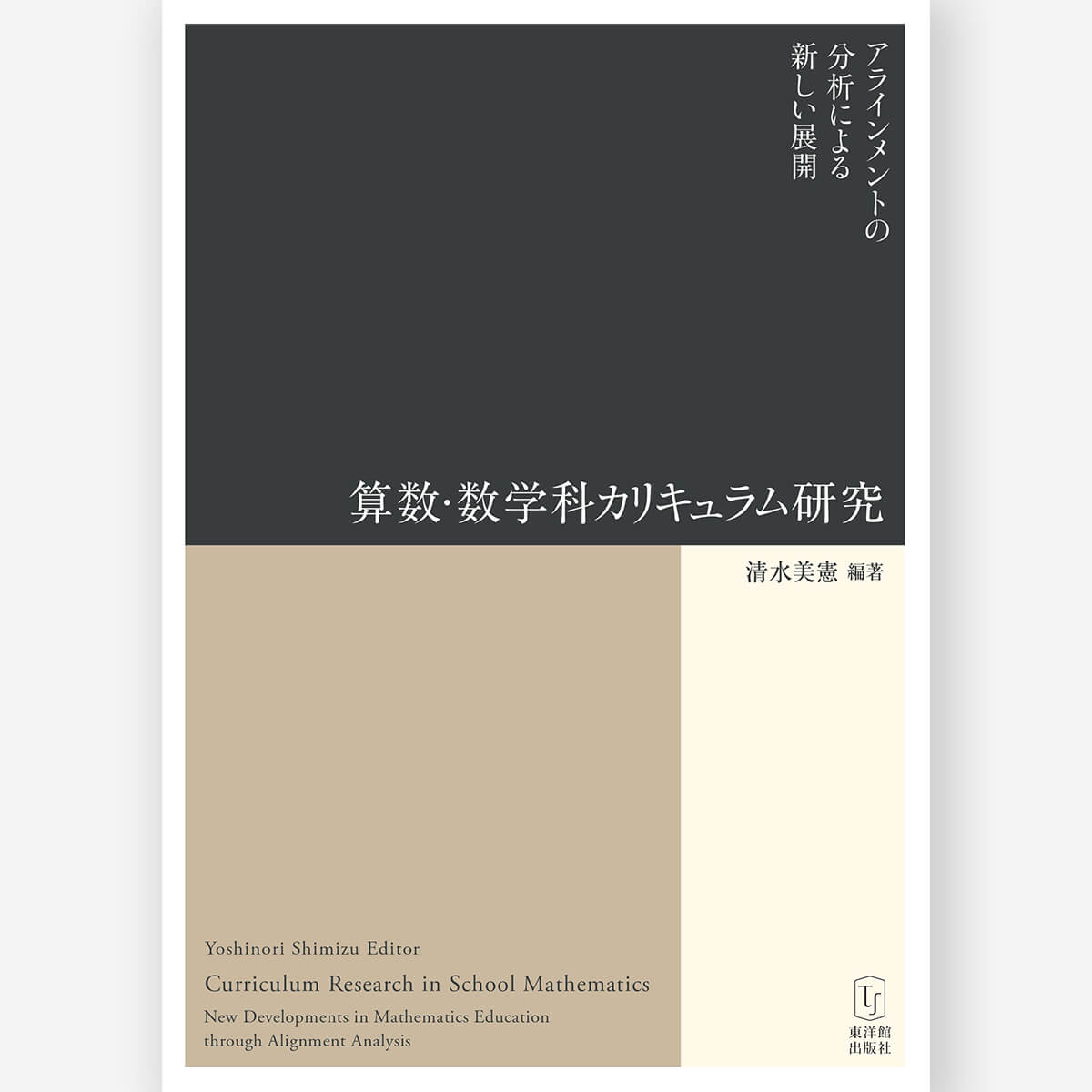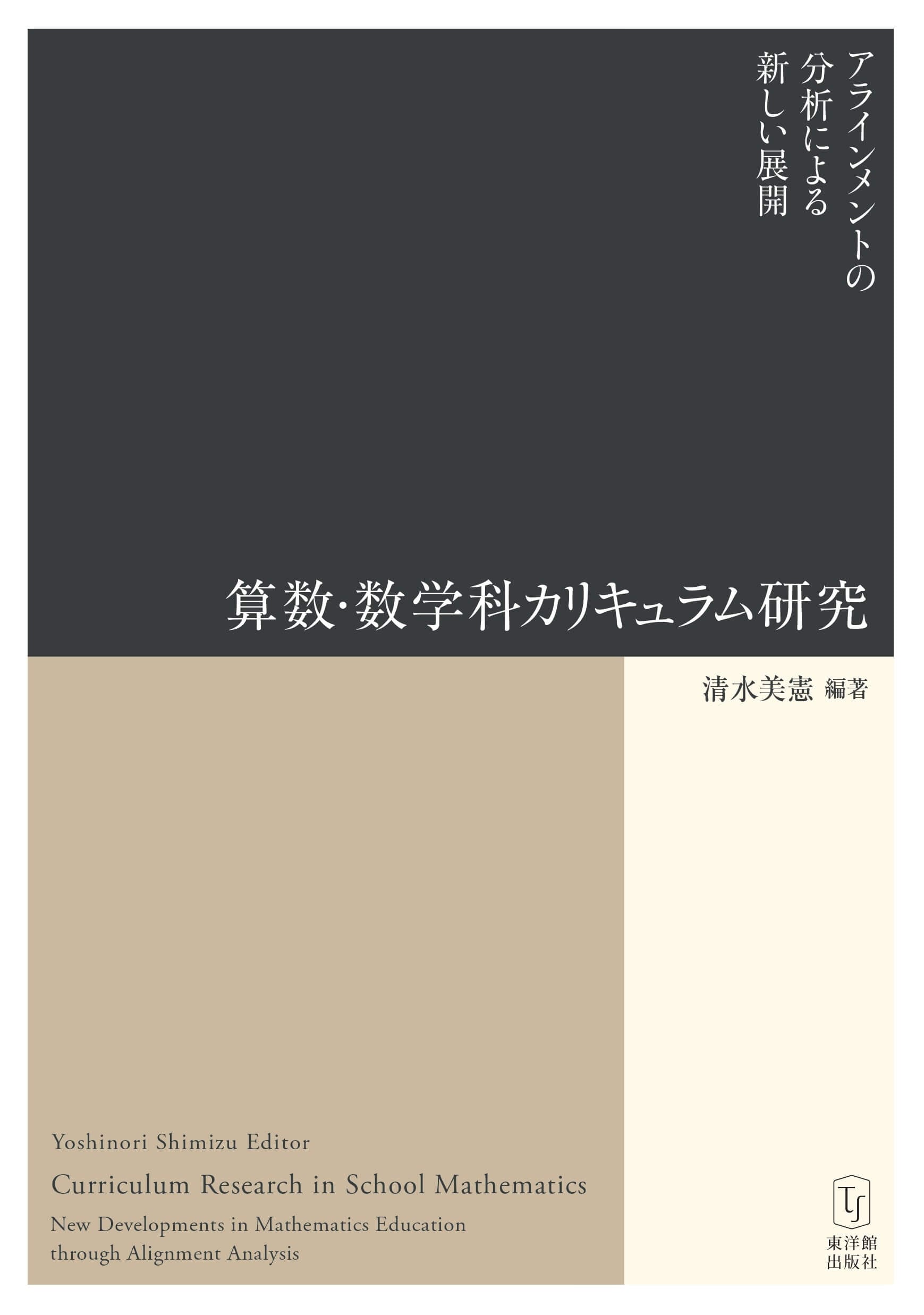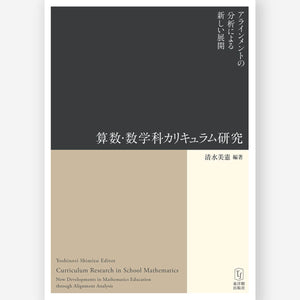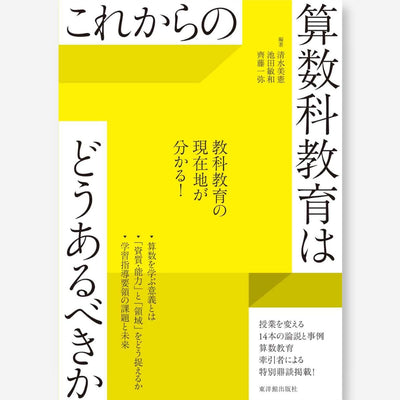算数・数学科カリキュラム研究 -アラインメントの分析による新しい展開-
レビューを書くと100ポイントプレゼント
商品説明
資質・能力の育成を確実にするため、学校数学カリキュラムを構築!
アラインメントを通した最新の数学カリキュラム論。
本書の概要
本書では、資質・能力ベースの学校数学カリキュラムの構築をめざして、その方法論について述べます。国際数学・理科教育動向調査(TIMSS)等で示される「意図されたカリキュラム」「実施されたカリキュラム」「達成されたカリキュラム」を観点に、これら三層を跨ぎ動的なものとして整合させる、アラインメント(Alignment)の実態を把握することが、本書の研究目的となります。
本書からわかること
カリキュラムのアライメントとは何か
アラインメント(Alignment)とは「整列」や「調整」を意味し、本書では特に、教育における「意図されたカリキュラム」(目標)、「実施されたカリキュラム」(指導)、「達成されたカリキュラム」(評価)が整合的かつ機能的に整列している状態を指す単語として用いられます。
「意図されたカリキュラム」:教育の設計段階で意図される層。文部科学省の学習指導要領や学校の教育課程編成、教師の授業計画など。
「実施されたカリキュラム」:実際に授業や教育活動として展開される層。教師が授業でどう取り扱ったのか、どんな教材を使ったのか、授業の進め方など、現場で行われた教育実践を指す。
「達成されたカリキュラム」:学習者が実際に習得した知識・技能・態度など、教育の結果として生徒の側に生じた学習成果をみる層
生徒の学習到達度調査(OECD/PISA)やTIMSSでは、上記の、教育施策の意図と実践、評価のカリキュラムの層を相互連関させることで、資質・能力の確かな育成を行うことが検討されています。そこで本書の研究は、一体として組織化されたこのカリキュラム構築に必要となる、アラインメントの解明が目的となります。
各章では、学習指導要領記載の意図を学習指導案へどのように落とし込まれたのかというアラインメント(「意図」 → 「実施」の整合)など、層間のアラインメントの実態について分析されます。また、「達成」という意味では、国(全国学力・学習状況調査等)や地域自治体(入学試験・学力調査等)といった、縦断するアラインメントもあります。
研究者はもちろん、学校現場で日々授業を担う教師にとっても、これからの数学教育を考えるうえで必読のカリキュラム論となるでしょう。
以下に、本書に収録された諸研究の一部を抜粋し、紹介します。
「意図」と「実践」を媒介する、「潜在的に実施されたカリキュラム」としての教科用図書
教科書とは、学習指導要領とその解説の「意図」の解釈、教室で教師と児童生徒が使用する「実施」、この両方を媒介するアラインメントの機能を果たすものと見なすことができます。本書では、学習指導要領と解説における数学的な見方・考え方の記述が、教科書のどの記述に当たるのか、コードとして抜き出し、教科書を用いた実践内でどのようにそれが発現されたのかまで分析する研究があります。そうすることで、アラインメントの手段としての教科書の役割が明らかにされます。
なぜ指導案と実践のズレは生じるのか。そして不整合をどのように調整するのか
授業の理念(「意図」)のレベルで想定される活動が、教科書では必ずしも網羅されておらず、「実施」へ向けた指導案への落とし込みと実際の授業実践とで、ズレが生じることはままあります。本書では、このような数学科の「意図されたカリキュラム」と「実施されたカリキュラム」との整合の実態を明らかにするとともに、不整合がある場合、研究協議会を経ることによって、数学的な見方・考え方とその働かせ方に関して、「意図」と「実施」の調整が行われた実態を捉える研究があります。
こんな先生におすすめ
・算数・数学教育学のカリキュラム論に関心のある教師・研究者
・児童生徒の資質・能力の確かな育成をめざす教師
・学習指導要領から指導案の作成、学習評価まで組織化されたカリキュラム構築の方法を知りたい教師