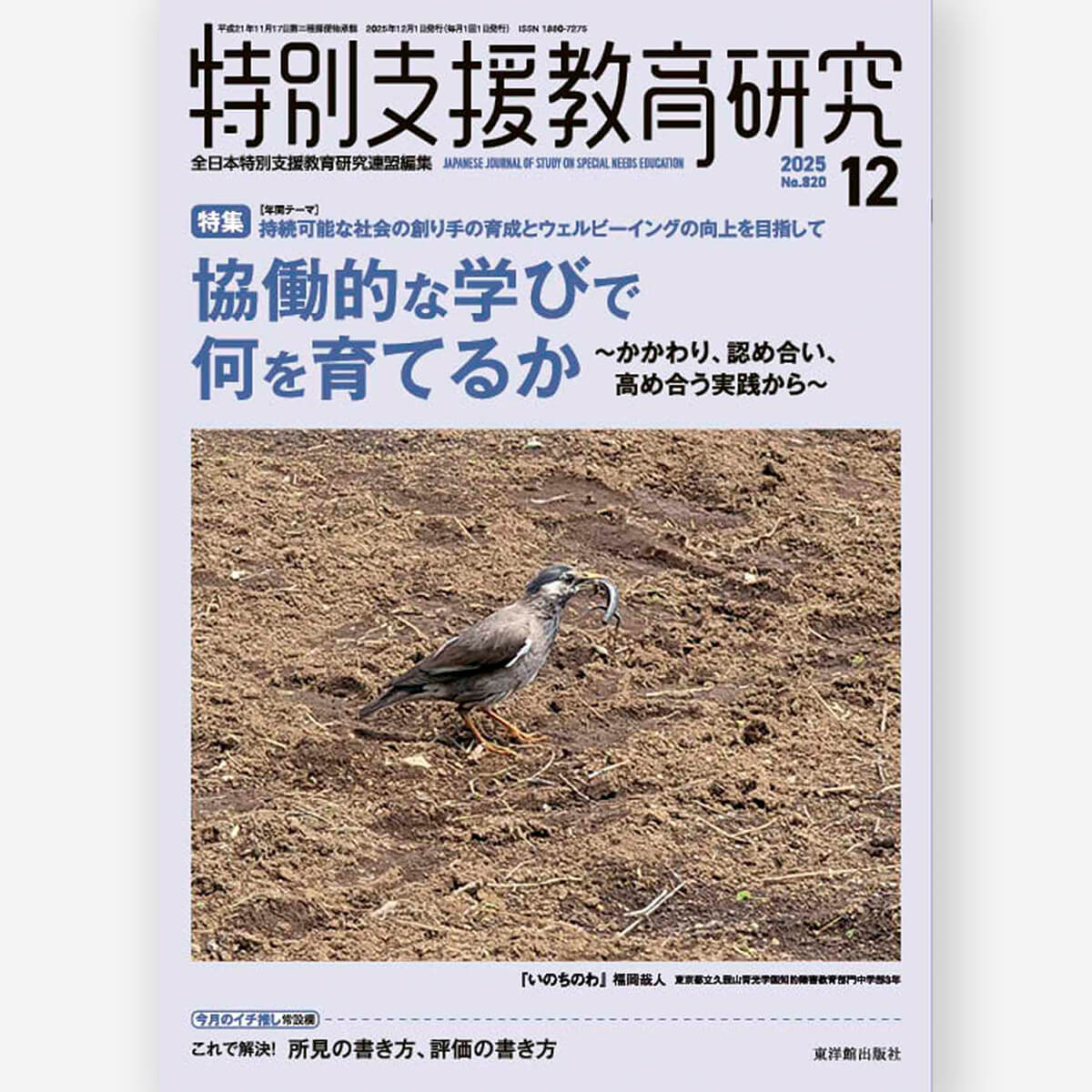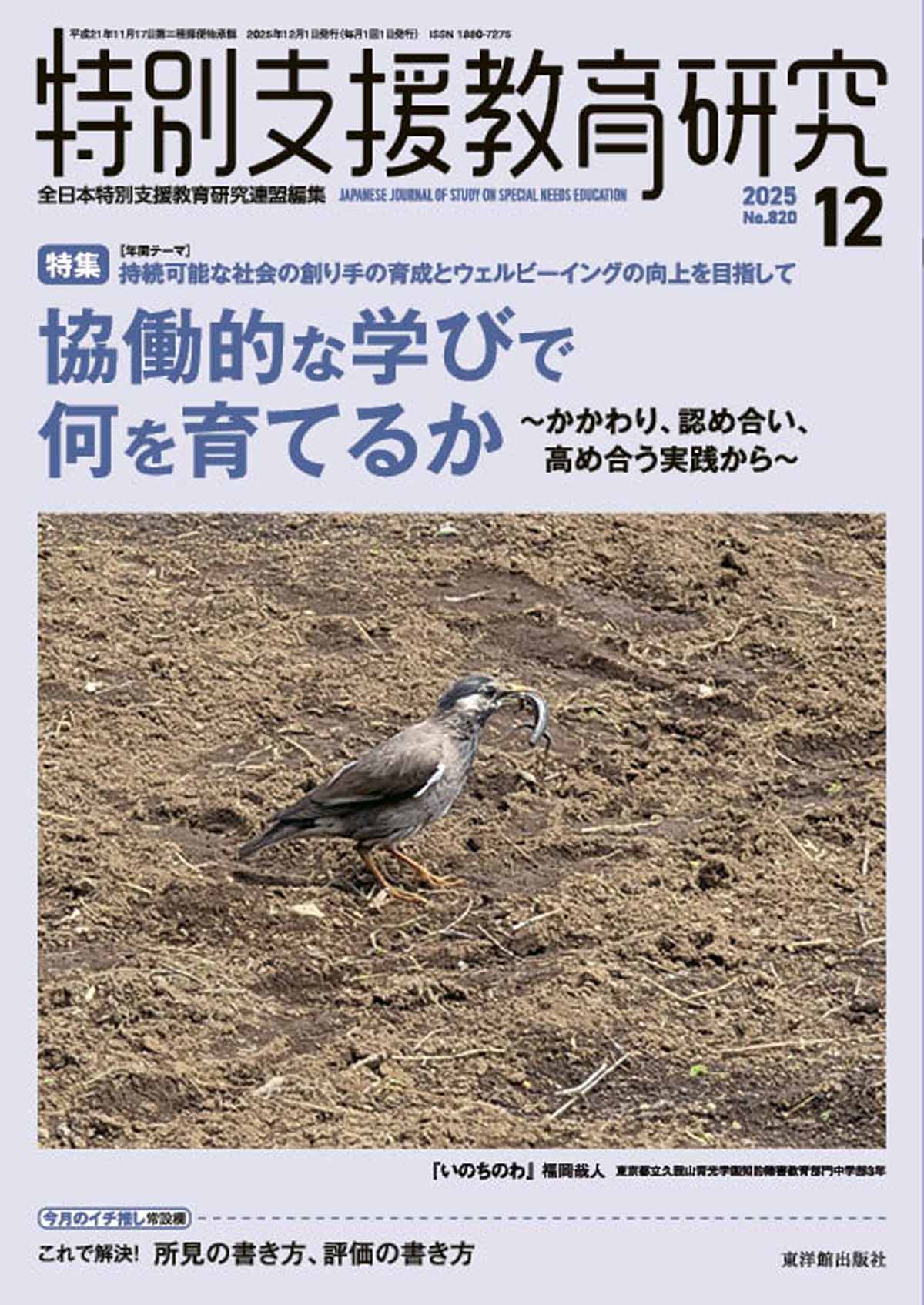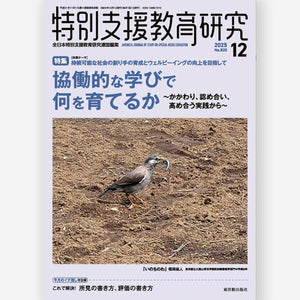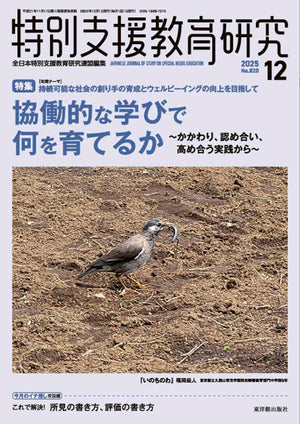レビューを書くと100ポイントプレゼント
商品説明
特集
協働的な学びで何を育てるか
~かかわり、認め合い、高め合う実践から~
「個別最適な学び」と「協働的な学び」という言葉は、教育現場で知らない教員はいないくらいに認知されているのではないでしょうか。しかし、学校教育現場、特に特別支援教育の現場での「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実は、どれくらい具現化されてきているでしょうか。
特別支援教育の現場において、アセスメントを丁寧に行い、個々の障害に応じた指導に力を入れた実践は多く目にします。「個別最適な学び」は充実していると言えそうです。しかし、一方で、個に応じた指導・支援に重点を置くあまり、関わりを通して学び合う機会が十分ではない状況がないでしょうか。
中央教育審議会においても、「個別最適な学び」が「孤立した学び」に陥らないよう、子供同士で、あるいは地域の方々をはじめ、多様な他者と協働しながら学んでいく「協働的な学び」の充実についても重要であるとして、次のように述べています。「子供一人一人のよい点や可能性を生かすことで、異なる考え方が組み合わさり、よりよい学びを生み出していくようにすることが大切である」「『協働的な学び』において、同じ空間で時間を共にすることで、お互いの感性や考え方等に触れ刺激し合うことの重要性について改めて認識する必要がある」(中央教育審議会答申、令和3年1月26日より抜粋)。
特別支援教育に関わる子供たちが、関わりを通して、互いの「よさ」に気付き、それぞれの強みを生かして共に助け合う態度・行動を培い、共生社会の担い手として生きる力を育んでいきたいものです。
そこで、本特集では、特別支援学校や特別支援学級、通級指導教室等において、関わりを大切にして学び合う機会を充実させている実践を紹介いたします。また、教師と子供、子供同士、地域の方々や家族など多様な関わりに着目して、障害の程度が中度・重度の子供や、重い自閉症のある子供が共に学ぶためには、どのような方法が適切なのかについて考察していきます。認め合い、高め合う実践を紹介しながら、「協働的な学び」を通して、何を育てていくのかを追究していく特集にしたいと考えています。