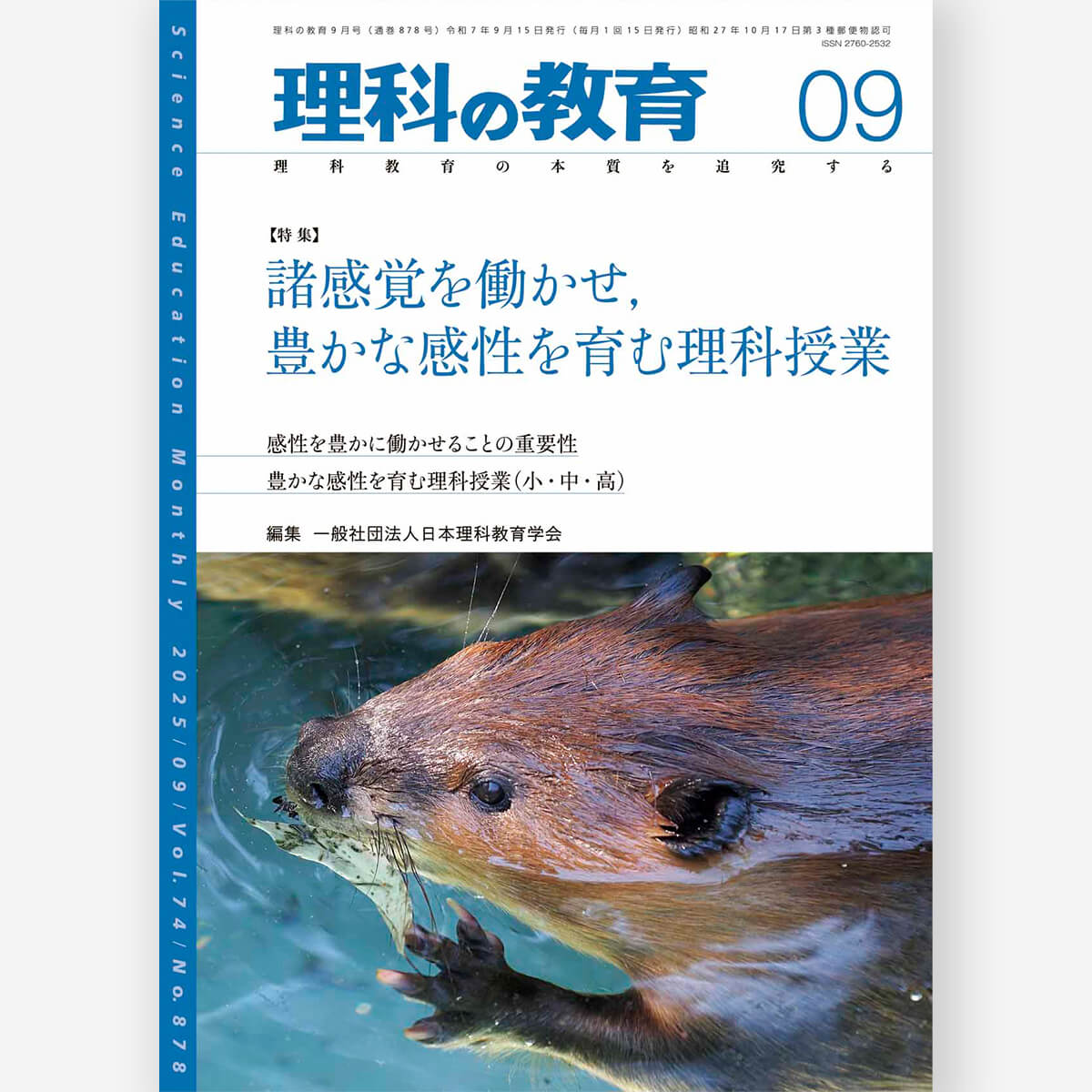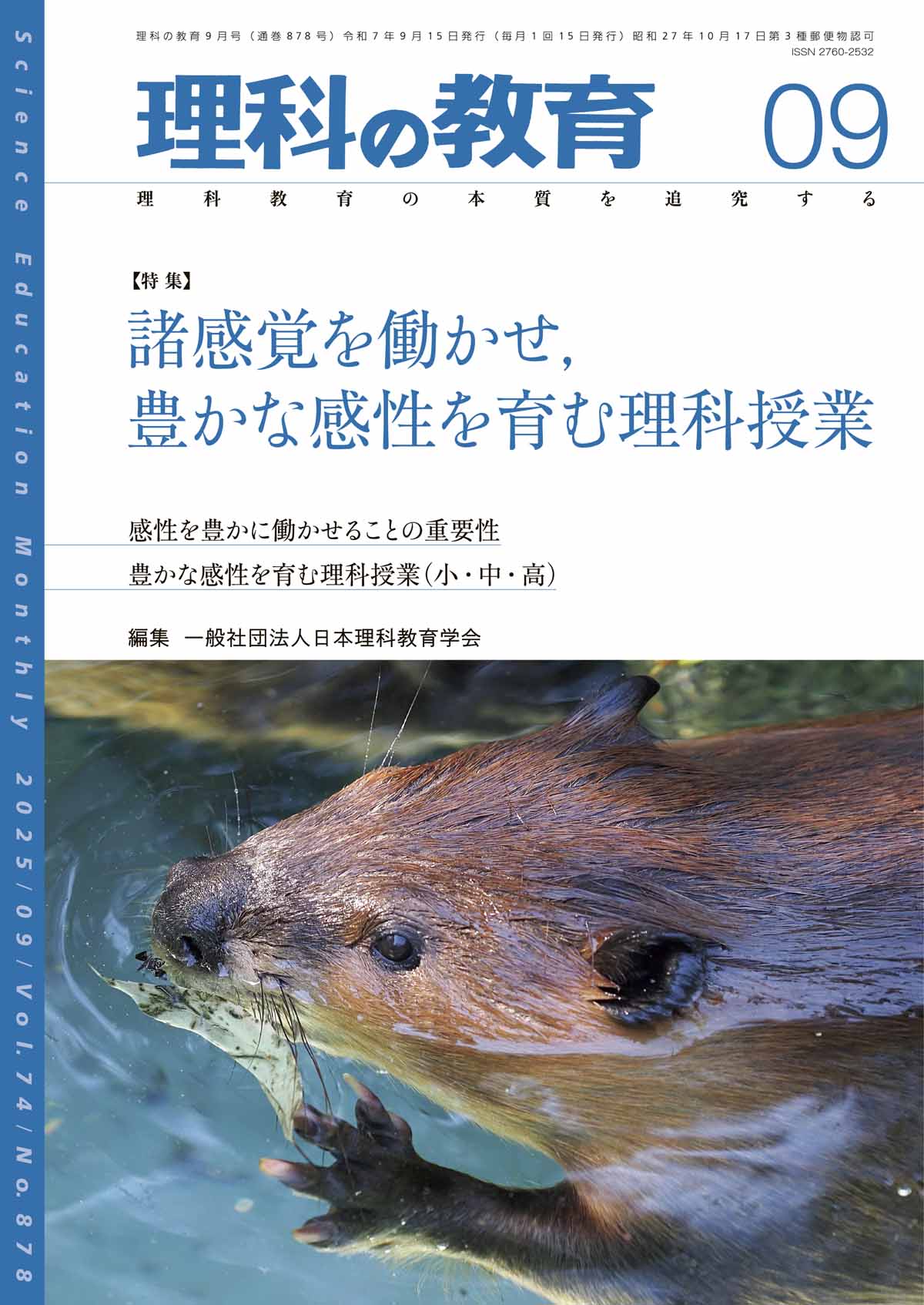理科の教育
令和7年9月号
通巻878号
2025/Vol.74
【特集】
諸感覚を働かせ,
豊かな感性を育む理科授業
■感性を豊かに働かせることの重要性
●センス・オブ・ワンダーが生きる理科の授業 露木 和男5
●持続可能な社会の創り手の育成に向けて
-理科教育が担うべき大きな役割- 鳴川 哲也9
■豊かな感性を育む理科授業(小学校)
●生活とつなぐ単元導入と単元終末の工夫
-小学5年生の実践- 丸山 哲也13
●五感を関連付けて考える理科授業
-学校での共通体験を生かして- 津村 純16
●児童の好奇心に寄り添い,共に探究する中で育まれる感性
-小学校第1学年・生活科の実践事例を通して- 梅原 恭平19
●自分と比べながら植物の生きる巧みさを知る
-植物の水の通り道について調べる学習を通して- 江口 活22
●感覚主導学習(Sensory-driven Learning:SeDL)-第3学年「音の性質」,第4学年「水のすがた(水の三態変化)」の実践- 岩本 哲也25
■豊かな感性を育む理科授業(中学校)
●自己決定の基本的欲求理論を活用した授業の推進 松本 浩幸28
●子どもの感性をひらく理科の学び-野尻湖ナウマンゾウ博物館と実現する本物に触れる地層学習- 佐久間 直也31
●発問に対し,実物に触れながら考える活動
-中学校第2学年「電流とその利用」単元において- 髙橋 拓寛34
●生徒の可能性は無限大
-OPPA が可能にする生徒と教師の感動の共有- 山口 真一37
■豊かな感性を育む理科授業(高等学校)
●科学的な法則の直接体験で豊かな感性を育む-気体の状態方程式と静水圧平衡
から算出する建物の高さの測定- 竹田 大樹40
連載講座
●『理科教育学研究』を授業に生かす
合意形成能力の育成を目指した理科授業―合意点を見つける力に焦点を当てて―
古石 卓也・山中 真悟・中山 貴司・木下 博義 44
●生徒をひきつける観察・実験
ネギの葉の観察 新井 直志 46
●教材研究一直線
原生動物を驚かそう 田中 千尋 48
●教材の隠し味
年周運動と公転「太陽と地球の位置関係から季節を推測しよう」
~モデルの作成とICT を活用した主体的な課題解決活動~ 遠藤 大輔 50
●概念構築を目指した探究型授業
~月と太陽の特徴を見いだす知識・技能を惑星に適用~
惑星モデルが再現できる限界を逆に利用して 荒尾 真一 52
●図書紹介
内ノ倉 真吾〔著〕『理科教育におけるアナロジーに基づく教授学習ストラテジー研究』 中山 迅 54
●先生はサイエンスマジシャンNEXT
いけるぜKahoot !授業でクイズ大会 辻本 昭彦 55
オンライン全国大会
(一次案内) 56
学会通信 58
次号予告 68
Society of Japan Science Teaching
SCIENCE EDUCATION MONTHLY
2025/Vol.74/No.878
Science Lessons Designed to Be More Sensitive Through the Senses
5 “Sense of Wonder” Brings Science Lessons to Life
TSUYUKI Kazuo, Waseda University (formerly), Tokyo
9 To Develop Young Children Who Will Go on to Become the Pillars of Sustainable Society: Major Role That Science Education Should Play
NARUKAWA Tetsuya, Fukushima University, Fukushima
13 Improvement of Introduction Unit and End of Unit, Connected with Daily Life: Practice in 5th Grade
MARUYAMA Tetsuya, Nagaoka Elementary School Attached to Niigata University, Niigata
16 Science Lessons to Be Considered in Connection with the Five Senses: Sharing Common Experiences at School
TSUMURA Jun, Elementary School Attached to Utsunomiya University, Tochigi
19 The Sensibility That Is Cultivated by Exploring Nature Together with Teacher, While Satisfying Children’s Curiosity
UMEHARA Kyouhei, Wakkanai-Chuuou Elementary School, Hokkaido
22 Get to Know the Tenacity of Plants, Compared with Our Species: Learning About Examining the Pathway of Water in Plants
EGUCHI Ikuru, Koyanose Elementary School, Fukuoka
25 Sensory-driven Learning (SeDL): Practice of “Properties of Sound” in 3rd Grade, and “Changes of State (Three Forms of Water)” in 4th Grade
IWAMOTO Tetsuya, Ajihara Elementary School, Osaka
28 The Pursuit of the Lessons by Using Theory of Basic Needs of Self-determination
MATSUMOTO Hiroyuki, Midori Lower Secondary School, Hokkaido
31 Science Learning to Develop Children’s Sensibility: Learning about Stratum Through Direct Contact with Real Things, Using Nojiriko Nauman Elephant Museum
SAKUMA Naoya, Junior High School at Otsuka, University of Tsukuba, Tokyo
34 Activity to Have Students Think About Teacher’s Questioning While Being Contact with Real Things: “Electricity and Its Uses” in 8th Grade
TAKAHASHI Takuhiro, Takashou Lower Secondary School, Hyogo
37 The Sky Is the Limit for Students: OPPA Enables Us to Share Excitements with Students and Teacher
YAMAGUCHI Shin-ichi, Kasukabe Lower Secondary School, Saitama
40 Development of Rich Sensibility Gained Through First-hand Experience of Scientific Laws: The Height of a Building Is Measured Using the Ideal Gas Equation and Hydrostatic Equilibrium
TAKEDA Hiroki, Keio Shonan Fujisawa Junior & Senior High School, Kanagawa
44 Bringing “Journal of Research in Science Education” into the Classroom
46 Demonstrations to Attract Students
48 Hot Pursuit of Science Material Development
50 Tips to Spice up Instructional Materials
52 Inquiry-based Lessons Aimed at Constructing Conception
54 Book Review
55 My Teacher Is a Science Magician <NEXT>
目次英訳:柿原聖治
A table of contents is translated into English by KAKIHARA Seiji
〈今月の表紙〉
アメリカビーバー
学名:Castor canadensis
齧歯目ビーバー科。
強い切歯をもち,木をかじり倒す。木の枝,石や泥などで水をせき止め,ダムや巣をつくる。
表紙写真:片平久央
表紙・本文デザイン:辻井 知
(SOMEHOW)