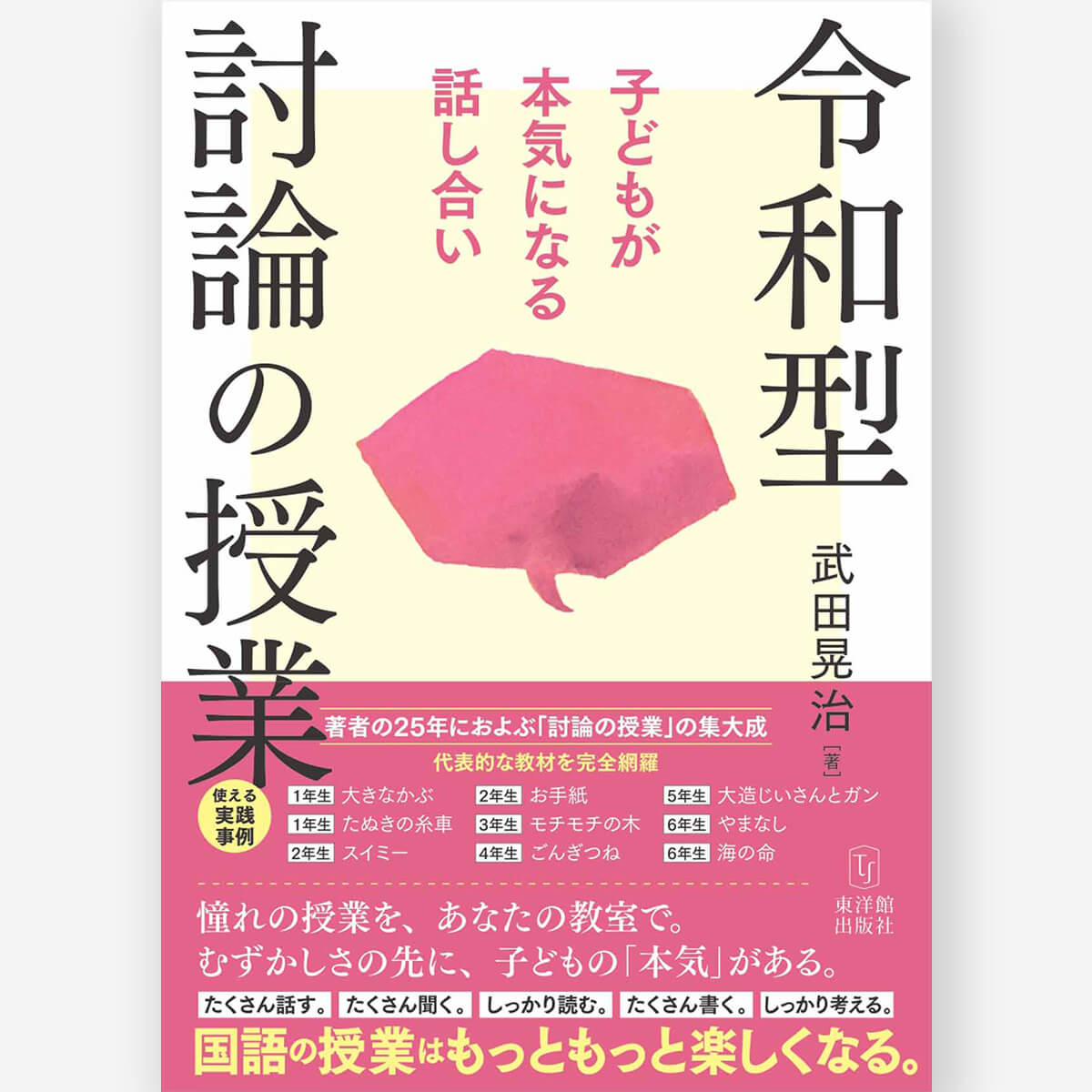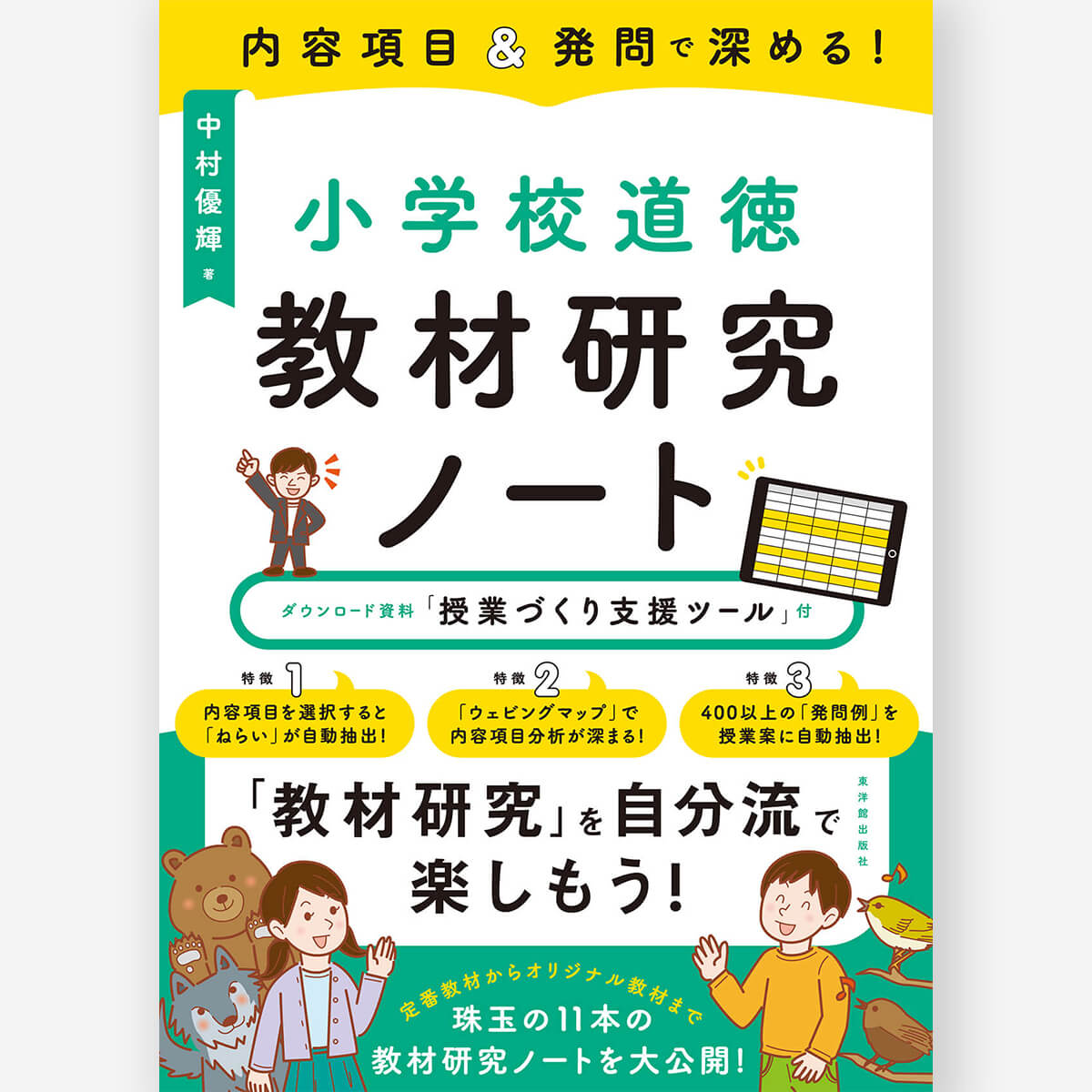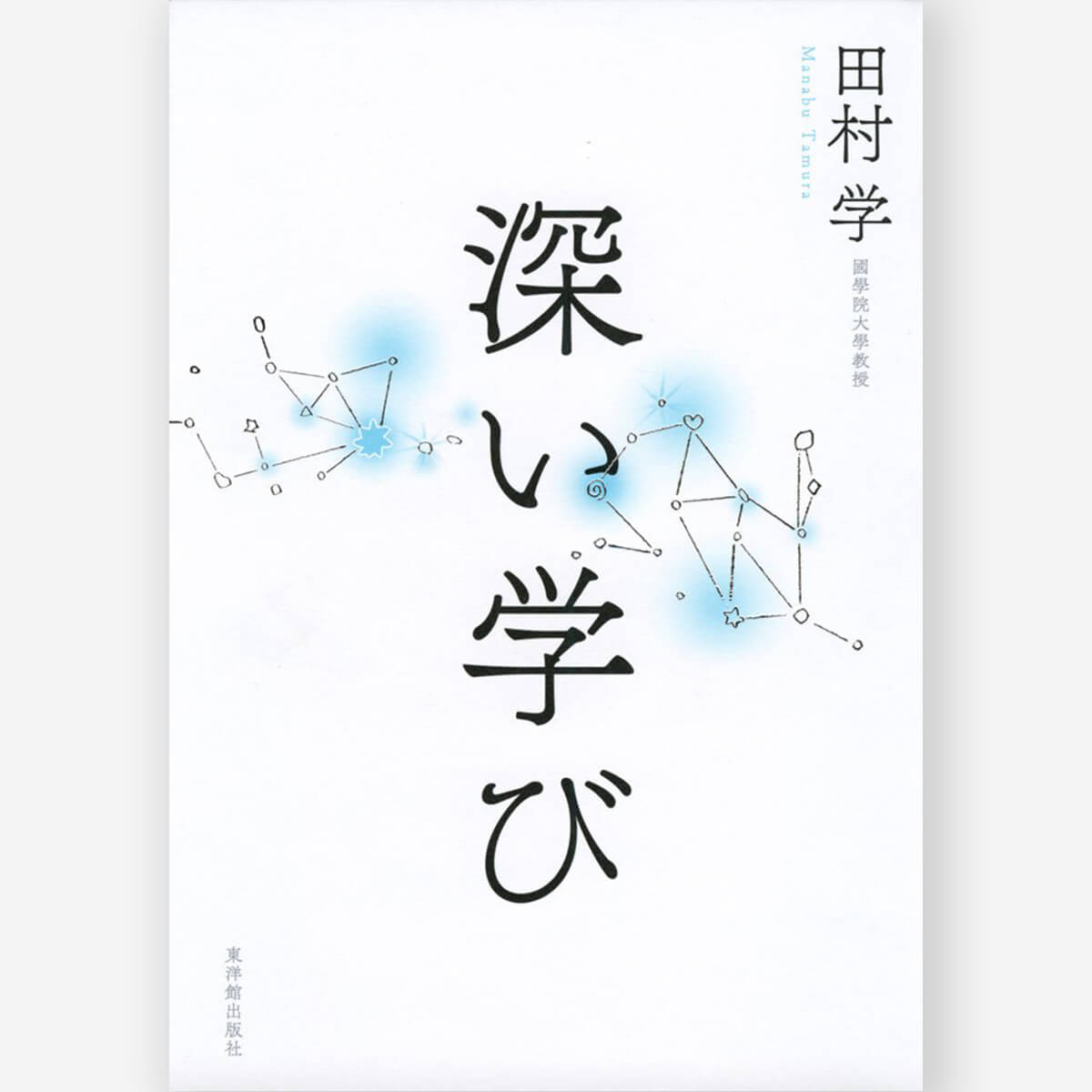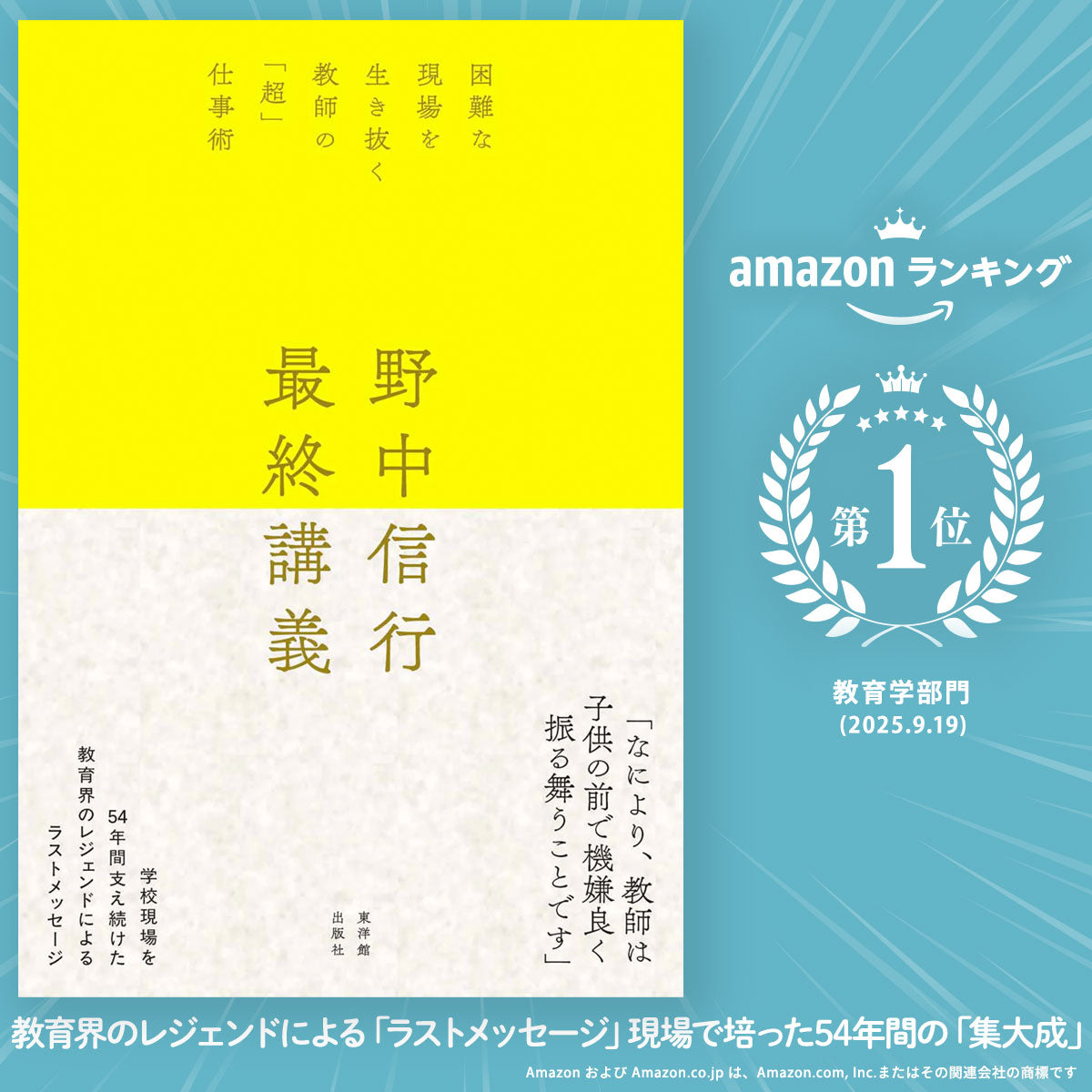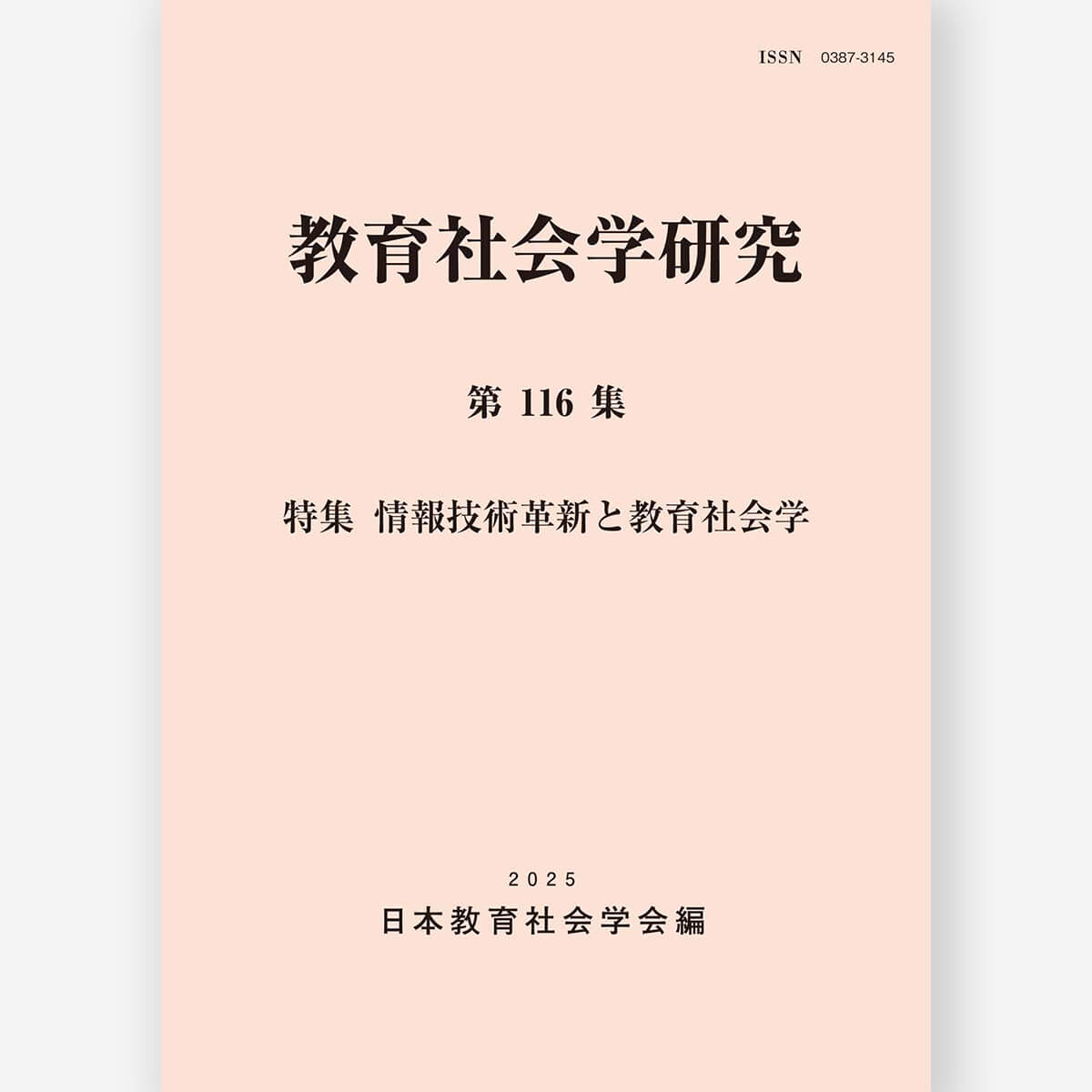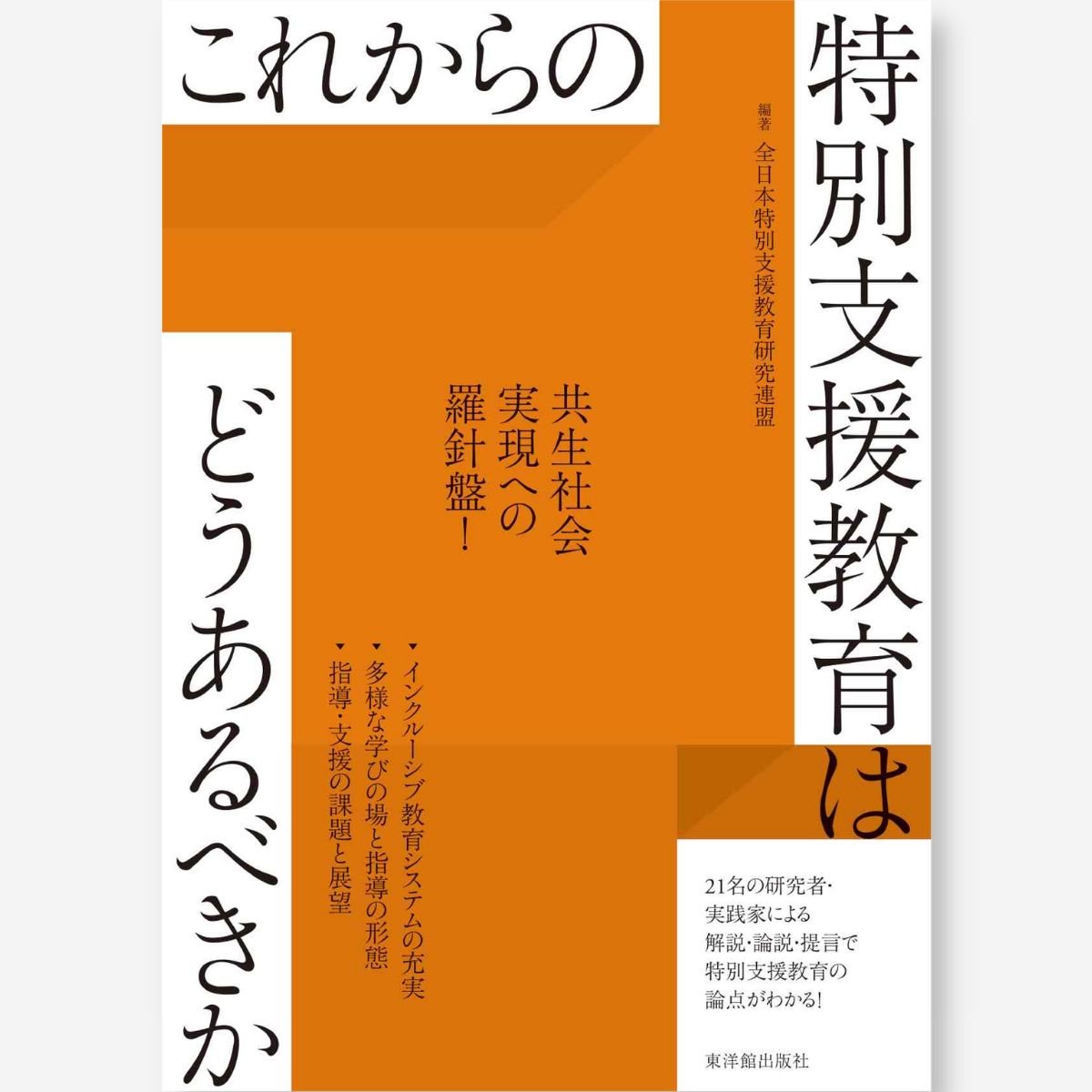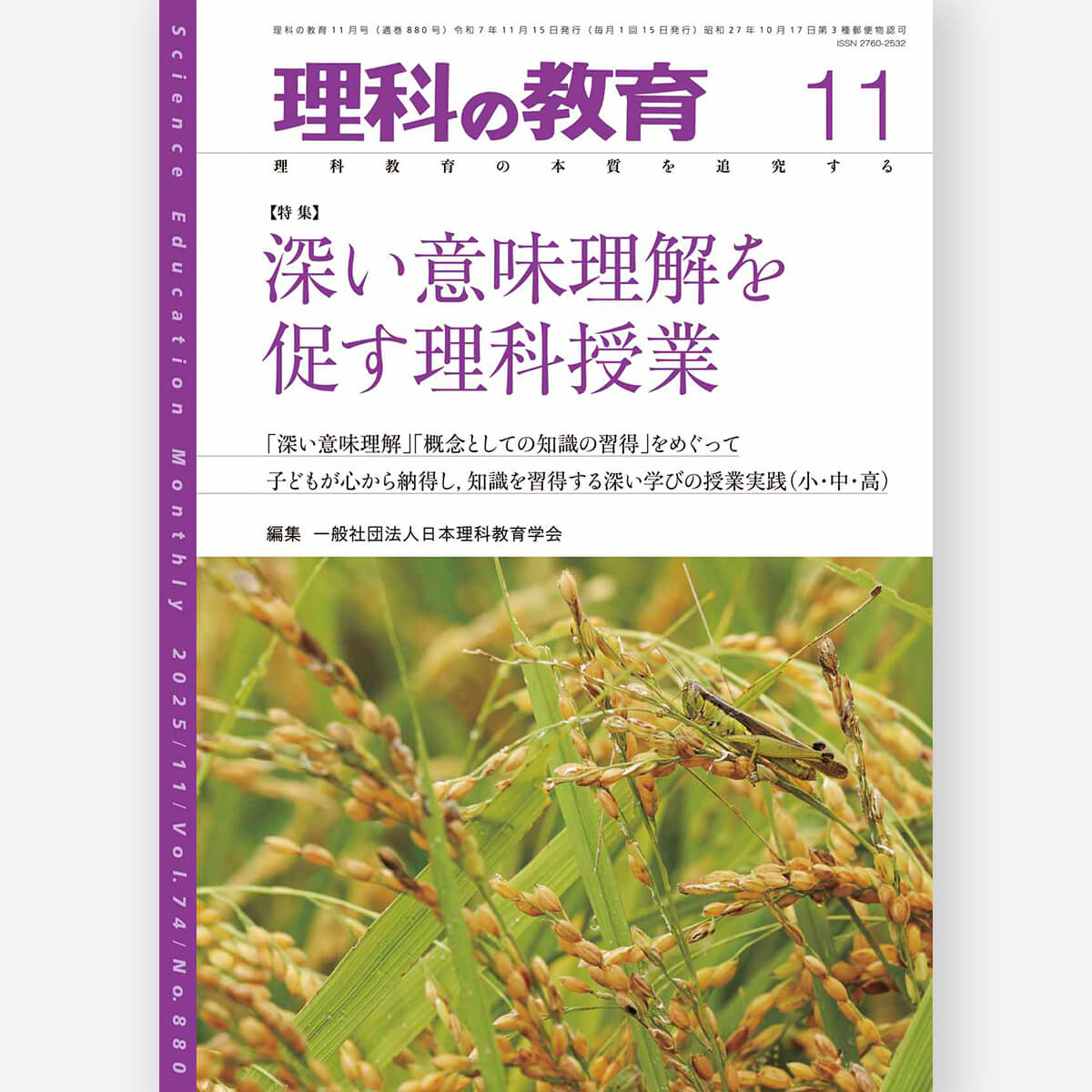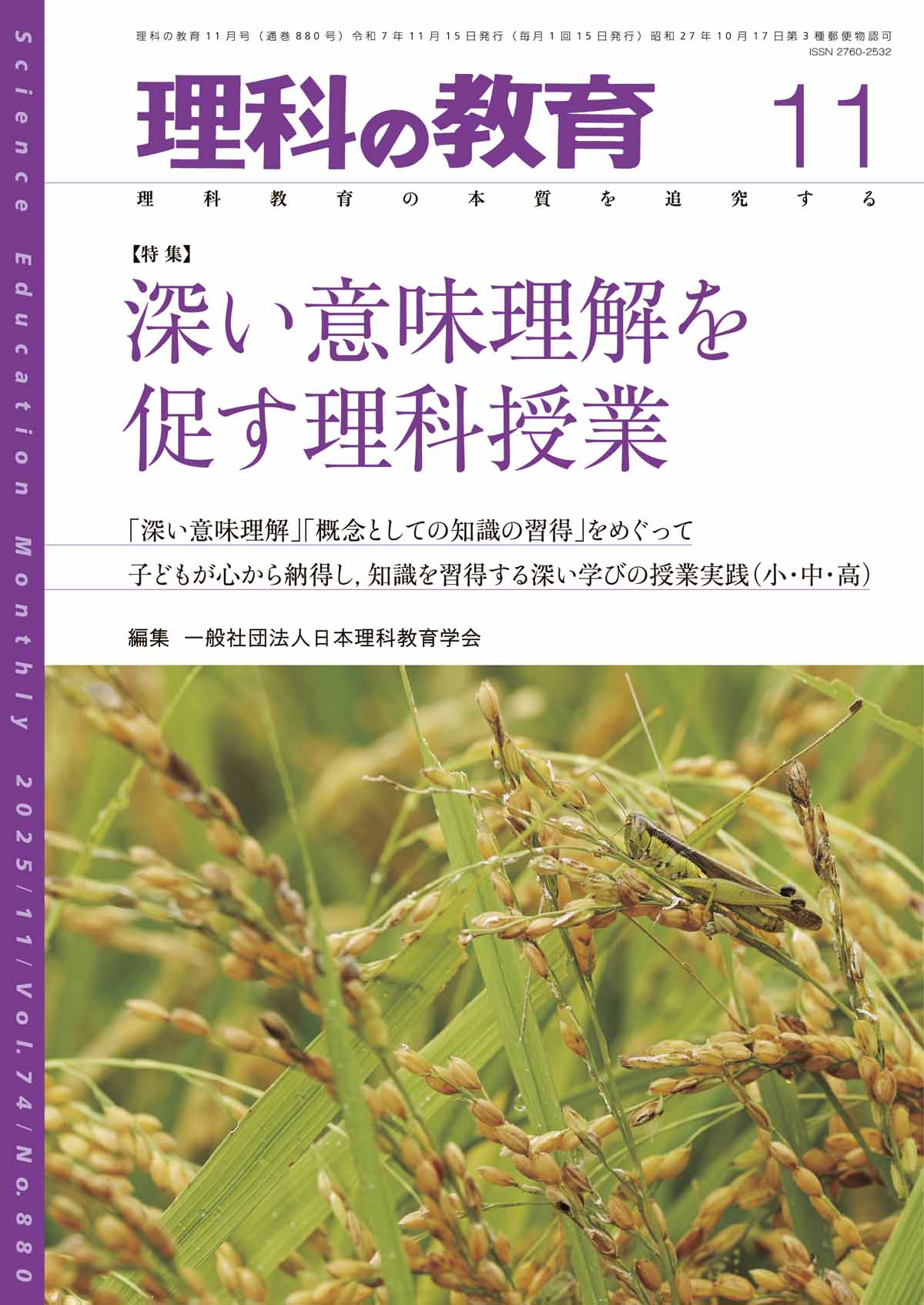理科の教育
令和7年11月号
通巻880号
2025/Vol.74
【特集】
深い意味理解を促す理科授業
■「深い意味理解」「概念としての知識の習得」をめぐって
●理解に納得と活用が加わるとき
-概念生態系から考える深い意味理解- 渡辺 理文・葛貫 裕介5
●モデルベース学習による科学概念の形成 雲財 寛9
■子どもが心から納得し,知識を習得する深い学びの授業実践(小学校)
●子どもの多様な興味や疑問に基づく学習による意味理解の促進-「もっと知りたい,わかりたい」という思いから広がる意味理解の世界- 松尾 健一13
●シミュレーションを用いた児童が主体的に探究する授業の実践-シーソーを題材とした小学校第6学年「てこ」の単元を通して- 内野 皓輝16
●子どもが納得し,知識を関連付けていく授業実践
-第4学年の事例を通して- 水野 花恋19
●体験から言葉を紡ぎ,子どもに「納得」をもたらす授業デザイン
-第3学年「太陽と地面の様子」から- 前田 昌志22
■子どもが心から納得し,知識を習得する深い学びの授業実践(小・中学校)
●生活の「なぜ」から始まる深い学びの理科授業
-在外教育施設ジョホール日本人学校での実践- 宮下 健太25
■子どもが心から納得し,知識を習得する深い学びの授業実践(中学校)
●「科学のミライを担う私たち」 教科横断的な理科授業での深い学び-中学校理科と技術・家庭科を組み合わせて「生活に役立つ科学」が実感できる授業-
結解 武宏28
●問いの焦点化が生む納得感のある学び-「静岡県の地形はどのようにできたのか」を追究する授業実践- 大久保 正樹31
■子どもが心から納得し,知識を習得する深い学びの授業実践(中等教育学校)
●舌から肛門までつながっているブタの内臓一式を用いた学習-生徒による教材作成と授業運営を組み込んだ授業実践- 佐野 寛子34
■子どもが心から納得し,知識を習得する深い学びの授業実践(高等学校)
●課題の発見・追究を通して生徒が実験を企画する授業展開
-生徒たちの「腑に落ちた」を引き出す授業の工夫- 古賀 康裕37
●理科の授業で演劇を!?-演劇的手法を用いて深い理解へ導く高校化学の授業- 渡辺 亮真・日髙 翼40
●深い意味理解を促すためのエネルギー概念の習得に向けて-エネルギー概念の確立の歴史と新しい考え方の実践事例を通して- 原口 博之43
連載講座
●『理科教育学研究』を授業に生かす
科学的概念の理解を促す対話活動―酸・アルカリ概念を事例に―
木内 裕佑 46
●生徒をひきつける観察・実験
非接触型IC カードを利用した電磁誘導の学習 吉田 勝彦 48
●教材研究一直線
白衣のメルトダウン 田中 千尋 50
●教材の隠し味
映画『となりのトトロ』を用いた月の学習 髙橋 政宏 52
●概念構築を目指した探究型授業
~太陽系に関する知識をクイズ形式で定着を図る~
PISA 型の読解力のレベルを意識した問いで 荒尾 真一 54
●先生はサイエンスマジシャンNEXT
鳥の言葉がわかる 辻本 昭彦 56
学会通信 57
オンライン全国大会
(一次案内) 60
次号予告 68
Society of Japan Science Teaching
SCIENCE EDUCATION MONTHLY
2025/Vol.74/No.880
Science Lessons to Promote a Deeper Semantic Understanding
5 In Case of Adding Satisfaction and Utilization To Understanding: A Deeper Semantic Understanding, Considered from Ecosystem of Conception
WATANABE Masafumi, Tokyo Gakugei University; KUZUNUKI Yusuke, Fuchu Dai-3 Elementary School, Tokyo
9 To Form a Scientific Conception, Through a Model-based Learning
UNZAI Hiroshi, Hiroshima University, Hiroshima
13 To Promote a Deeper Understanding Through the Lessons Based on Children’s Diversified Interests and Questions: World of a Semantic Understanding That Expands from the Desire “I Want to Know More and Understand Well”
MATSUO Ken-ichi, Masaki Elementary School, Nagasaki
16 Instructional Practice for Children to Explore Actively by Using Simulation: “Lever” in 6th Grade, Using a Seesaw As a Teaching Material
UCHINO Kouki, Fukiage Elementary School, Saitama
19 Instructional Practice in Which Children Try to Relate Each Knowledge Satisfactorily: Through Examples of 4th Grade
MIZUNO Karen, Tateno Elementary School, Kanagawa
22 Instructional Design for Children to Get a “Satisfaction” from Deriving Words from Experiences: “The Sun and the Ground” in 3rd Grade
MAEDA Masashi, Yonenosho Elementary School, Mie
25 Deep Learning of Science Instruction, Starting From “Why?” in Everyday Life: Practice at the Japanese School of Johor (Overseas Educational Institution)
MIYASHITA Kenta, Japanese School of Johor, Malaysia
28 “We, the Supporter of Future of Science” Deep Learning Through an Interdisciplinary Approach to Science Instruction: The Lesson “Science Useful in our Daily Life” in Which Students Can Realize the Benefits by Combining Middle School Science With “Technology and Home Economics”
YUGE Takehiro, Kohoku Lower Secondary School, Nagano
31 To Help Students Get a Sense of Satisfaction by Focusing on the Questions: Practice of Inquiry-based Lesson of “How the Land of Shizuoka Is Formed ?”
OKUBO Masaki, Shimada Lower Secondary School Attached to Shizuoka University, Shizuoka
34 Learning by Using Internal Organs of a Pig, Which are Connected From Tongue to Anus: Instructional Practice for Students to Make a Teaching Material and Class Management
SANO Hiroko, Koishikawa Secondary School, Tokyo
37 Instructional Development for Students to Work Out Plans of their Experiments, Through the Discovery and Inquiry of the Assignment: Instructional Improvement to Help Students “Fully Understood”
KOGA Yasuhiro, Kamimura Gakuen, Kagoshima
40 Drama Activity in Science Class!?: To Promote a Deeper Understanding of High School Chemistry Class by Using Dramatic Method
WATANABE Ryouma, HIDAKA Tsubasa, Osaka Kyoiku University, Osaka
43 Toward Mastering Energy Conception to Promote a Deeper Understanding: Practical Examples of History of Establishing Energy Concept and a New Way of Thinking
HARAGUCHI Hiroyuki, Totomi-Sogo Upper Secondary School, Shizuoka
46 Bringing “Journal of Research in Science Education” into the Classroom
48 Demonstrations to Attract Students
50 Hot Pursuit of Science Material Development
52 Tips to Spice up Instructional Materials
54 Inquiry-based Lessons Aimed at Constructing Conception
56 My Teacher Is a Science Magician <NEXT>
目次英訳:柿原聖治
A table of contents is translated into English by KAKIHARA Seiji
〈今月の表紙〉
ハネナガイナゴ
学名:Oxya japonica japonica
バッタ目バッタ科。
水稲の害虫としてよく知られている。水田ではコバネイナゴとハネナガイナゴの2種類がよく見られる。主に翅の長さが違うが,正確には腹部の裏側を見ないと見分けられない。
表紙写真:片平久央
表紙・本文デザイン:辻井 知
(SOMEHOW)