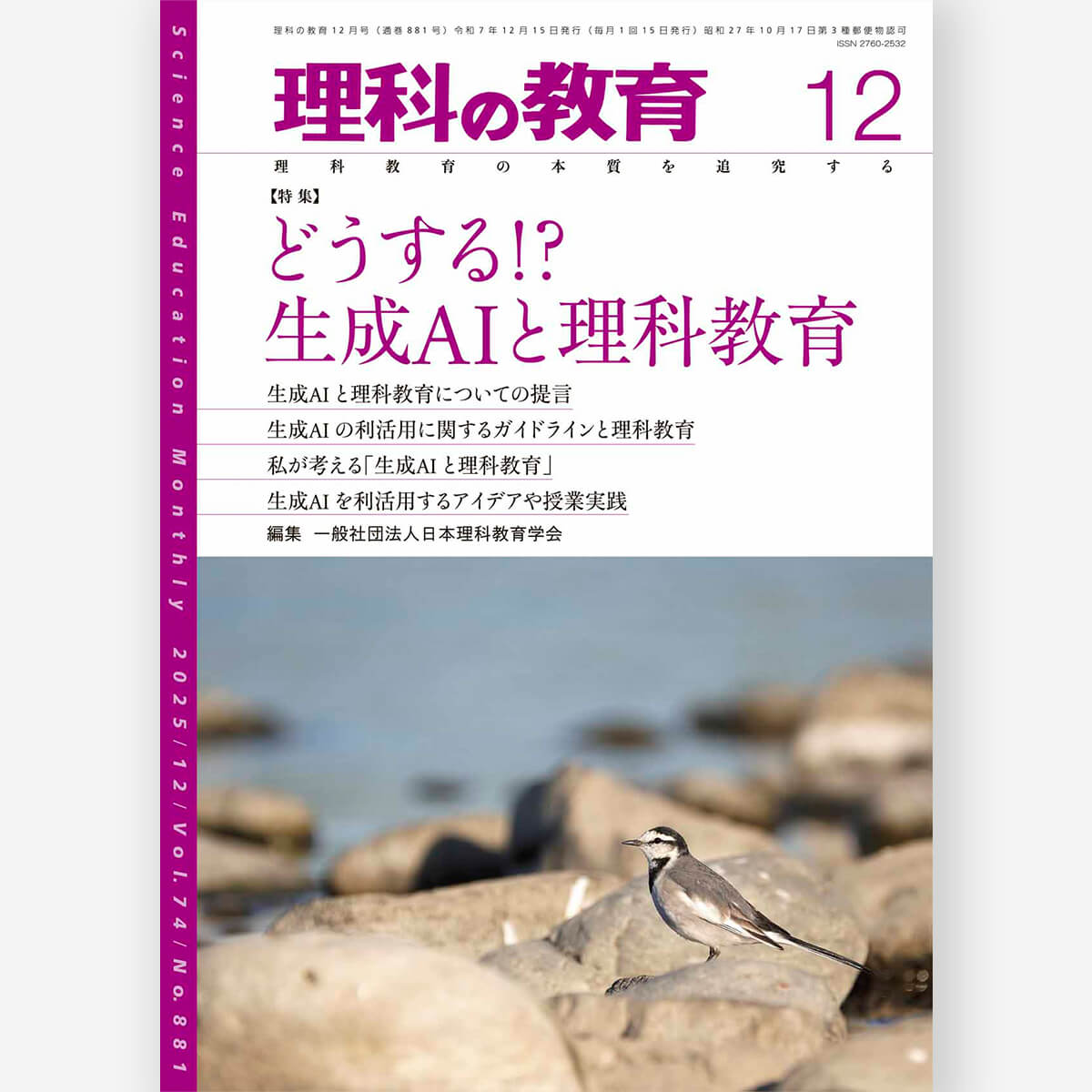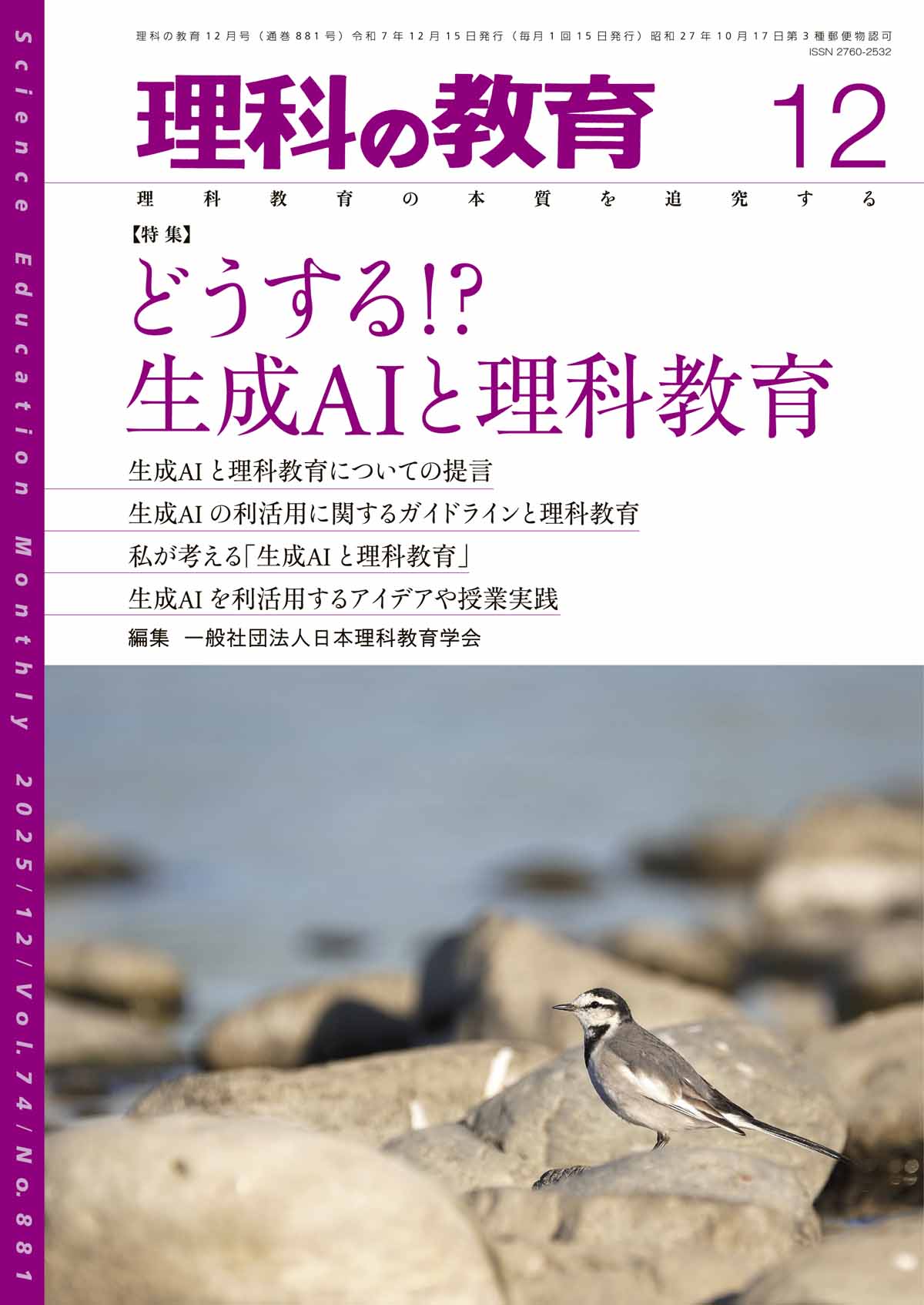理科の教育
令和7年12月号
通巻881号
2025/Vol.74
【特集】
どうする!?
生成AIと理科教育
■生成AIと理科教育についての提言
●理科教育における生成AI活用の可能性と課題 中村 大輝5
●生成AIによる理科教育実践の新展開-VUCA社会の「あいまいさ」が導く新たな教育の可能性- 辻 義人9
●SSH高校生が生成AIの「中身」に迫る!-言語系生成AIの仕組みを体験・観察・記述で学ぶ理科授業の実践- 中野 良一13
■生成AIの利活用に関するガイドラインと理科教育
●生成AIを「出発点」とする理科授業の可能性-防災を題材とした理科授業における生成AI活用の試み- 近野 洋平16
■私が考える「生成AIと理科教育」
●生成AIを活用した理科における活用場面の提案-生成AIを利活用することで,より深い学びへ- 金川 弘希19
■生成AIを利活用するアイデアや授業実践
●学習内容を関連付けた対話的な学びを促進する生成AIの活用-SAMRモデルに基づくより高次の活用段階を目指して- 森川 大地22
●画像生成AIで思考力を育む理科の授業づくり-第5学年「流れる水の働きと土地の変化」の授業実践を通して- 赤塚 広大25
●生成AIと理科教育の現在地
-可能性と課題を捉え,未来の学びを拓く- 野田 佳吾28
●中学校理科への生成AI導入の実際とその検討 諸岡 史哉32
●生成AIを活用した探究的な活動
-中学校1・2年地球領域での実践を通して- 森野 宅麻35
●生成AIを取り入れた光合成の探究的な学び -探究的な実験活動の中で有効な生成AIの使い方とは何か- 齋藤 太嗣38
●生成AIを活用した理科教員業務支援の実践報告
-教材作成から授業改善まで- 石神 克海41
●生成AIを活用した授業改善
-「文字起こし」を分析し,指導力改善を図る- 橋爪 慶太45
連載講座
●『理科教育学研究』を授業に生かす
授業目標と評価方法を一致させる-「評価の三角形」を基にした授業の計画と実践-
渡辺 理文・杉野 さち子 48
●生徒をひきつける観察・実験
水の合成 山口 晃弘 50
●教材研究一直線
ムラサキキャベツの教材性 田中 千尋 52
●教材の隠し味
転がるジャム瓶コンテスト 藤原 僚 54
●概念構築を目指した探究型授業
~北極星側から見て地球の自転方向はどっち?~
小学校3年生の太陽の動きと棒の影の学習から 荒尾 真一 56
●先生はサイエンスマジシャンNEXT
どうする生成AIと理科教育① 辻本 昭彦 58
学会通信 59
全国大会報告 60
オンライン全国大会
(二次案内) .63
総目次 68
次号予告 76
Society of Japan Science Teaching
SCIENCE EDUCATION MONTHLY
2025/Vol.74/No.881
How Should We Deal With Generative
AI and Science Education?
5 Possibility of Generative AI in Science Education and the Challenges We Face
NAKAMURA Daiki, University of Miyazaki, Miyazaki
9 New Development of Practices in Science Education by Generative AI: Possibility of New Education Led by “Vagueness” in VUCA Society
TSUJI Yoshihito, Future University Hakodate, Hokkaido
13 SSH Students Try to Work Out “What Lies Behind” a Generative AI!: Practice of Science Lessons in Which the Mechanism of Linguistic Generative AI Is Studied Through Experience, Observation and Description
NAKANO Ryoichi, Kantan AI Education Labo
16 Possibility of Taking Generative AI As a “Starting Point” for Science Lessons: Attempt to Use Generative AI in Science Lessons, Based on Disaster Preparedness
KONNO Yohei, Wada Elementary School, Yamagata
19 Proposal of Creating a Situation in Which Generative AI Can Be Used in Science: Making Science Lessons Deeper by Using Generative AI
KANAGAWA Hiroki, Osaka Aoyama University, Osaka
22 Making Use of Generative AI to Promote Interactive Learning That Is Linked with Learning Contents: Aiming for the Higher Level of AI Usage, Based on SAMR Model
MORIKAWA Daichi, Nishi-tokyo Municipal Sakae Elementary School, Tokyo
25 Lesson Planning in Science to Develop Thinking Power by Using Image Generative IA: Practice of “Action of Running Water, and Change of Land” in 5th Grade
AKATSUKA Kodai, Satogaoka Elementary School, Fukushima
28 Current Situation of Generative AI and Science Education: To Develop Future Learning, With Possibility and Challenge in Mind
NODA Keigo, Elementary School Attached to Nagasaki University, Nagasaki
32 Practical Method of Introducing Generative AI Into Middle School Science, and Its Review
MOROOKA Fumiya, Lower Secondary School Attached to Ibaraki University, Ibaraki
35 Inquiry-based Activity by Using Generative AI: Through the Practice of Earth Science in Grades 7th and 8th
MORINO Takuma, Hibarigaoka Lower Secondary School, Hyogo
38 Inquiry-based Learning of Photosynthesis Incorporating Generative AI: How to Use Generative AI Effectively During Inquiry-based Lab Activity
SAITO Taishi, Gakuyou Lower Secondary School, Shizuoka
41 Practical Report of Supporting the Workloads of Science Teachers by Using Generative AI: Ranging From Material Development To Instructional Improvement
ISHIGAMI Katsumi, Shimizu-minami Upper Secondary School, Shizuoka
45 Improvement of Lessons By Using Generative AI: To Analyze “Transcribe to Text,” and Improve the Teaching Skills
HASHIZUME Keita, Misato Lower Secondary School, Saitama
48 Bringing “Journal of Research in Science Education” into the Classroom
50 Demonstrations to Attract Students
52 Hot Pursuit of Science Material Development
54 Tips to Spice up Instructional Materials
56 Inquiry-based Lessons Aimed at Constructing Conception
58 My Teacher Is a Science Magician <NEXT>
目次英訳:柿原聖治
A table of contents is translated into English by KAKIHARA Seiji
〈今月の表紙〉
ハクセキレイ
学名:Motacilla alba lugens
スズメ目セキレイ科。
かつては水辺の鳥というイメージだったが,近年は生息域が広がり,都市部の公園などでも見かけるようになった。
表紙写真:片平久央
表紙・本文デザイン:辻井 知
(SOMEHOW)