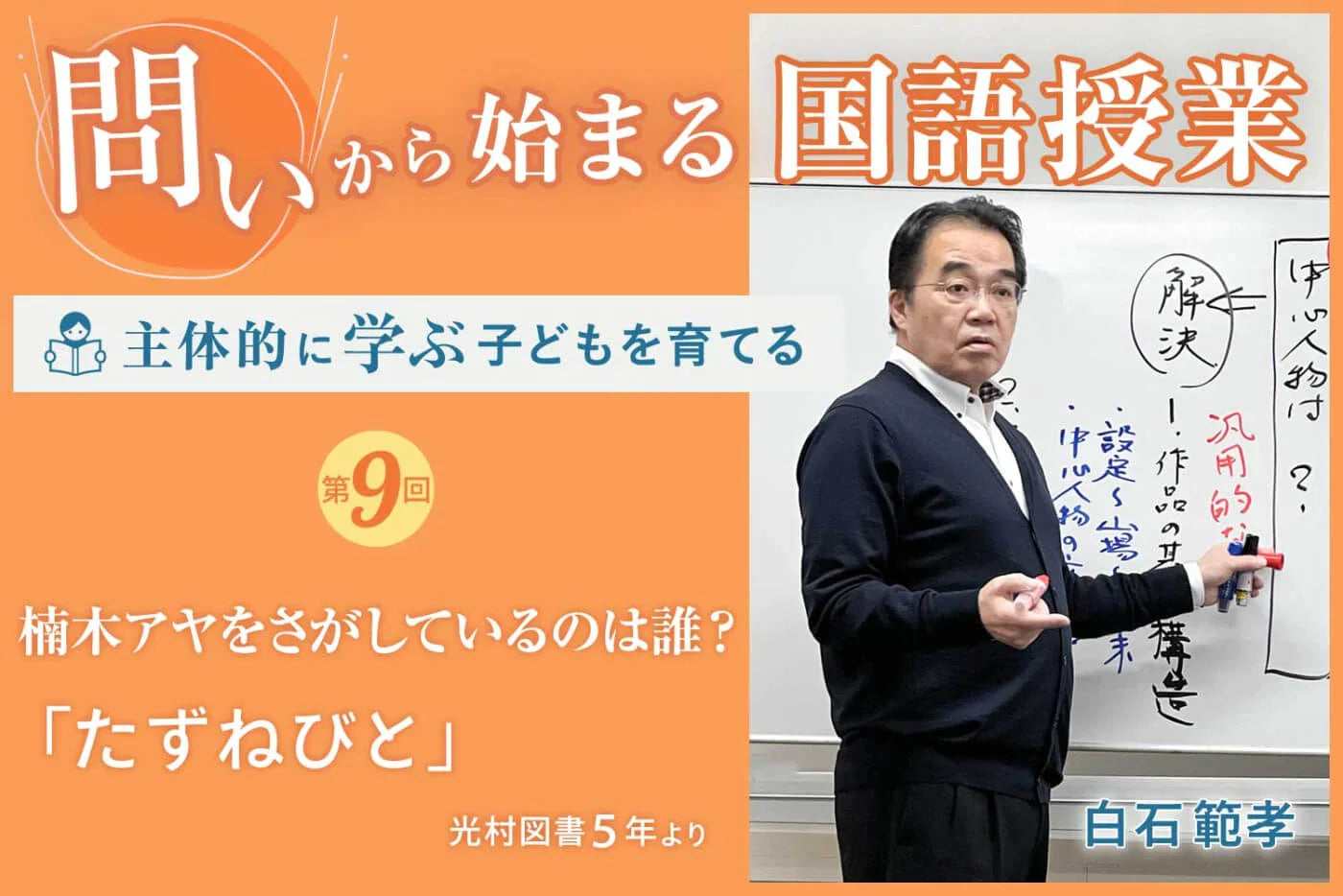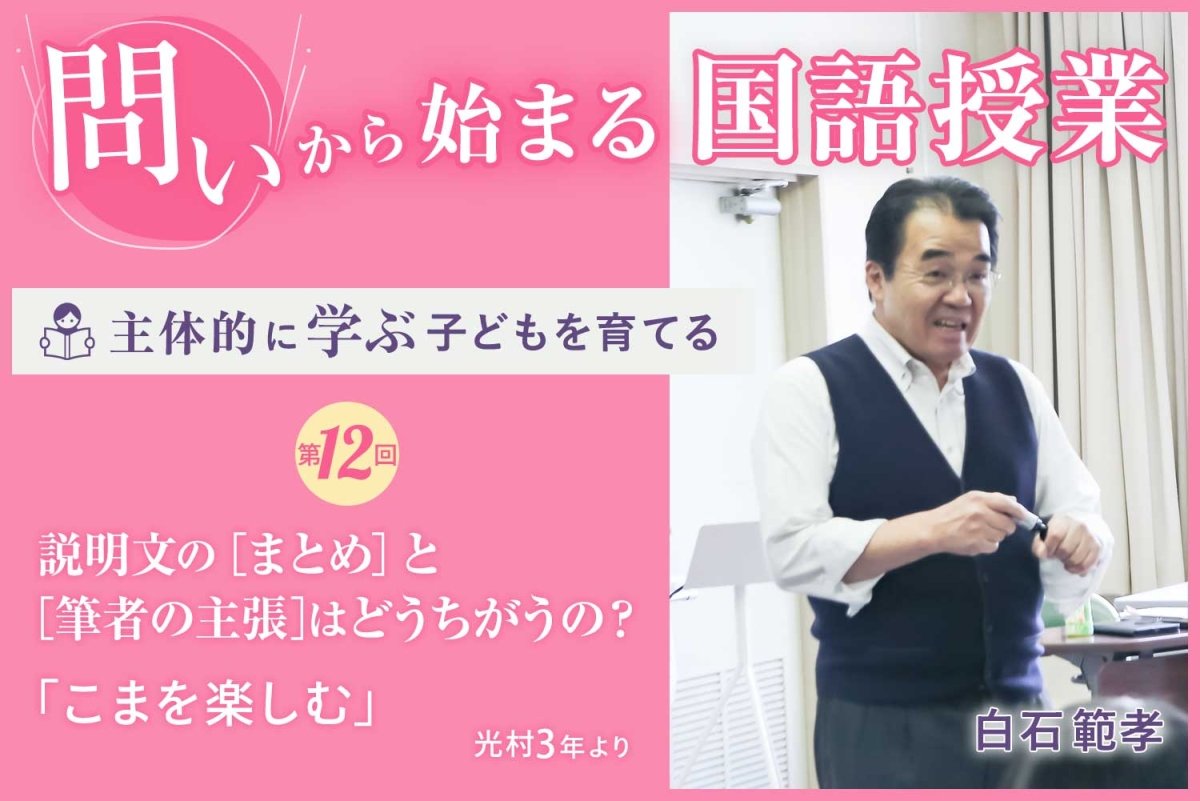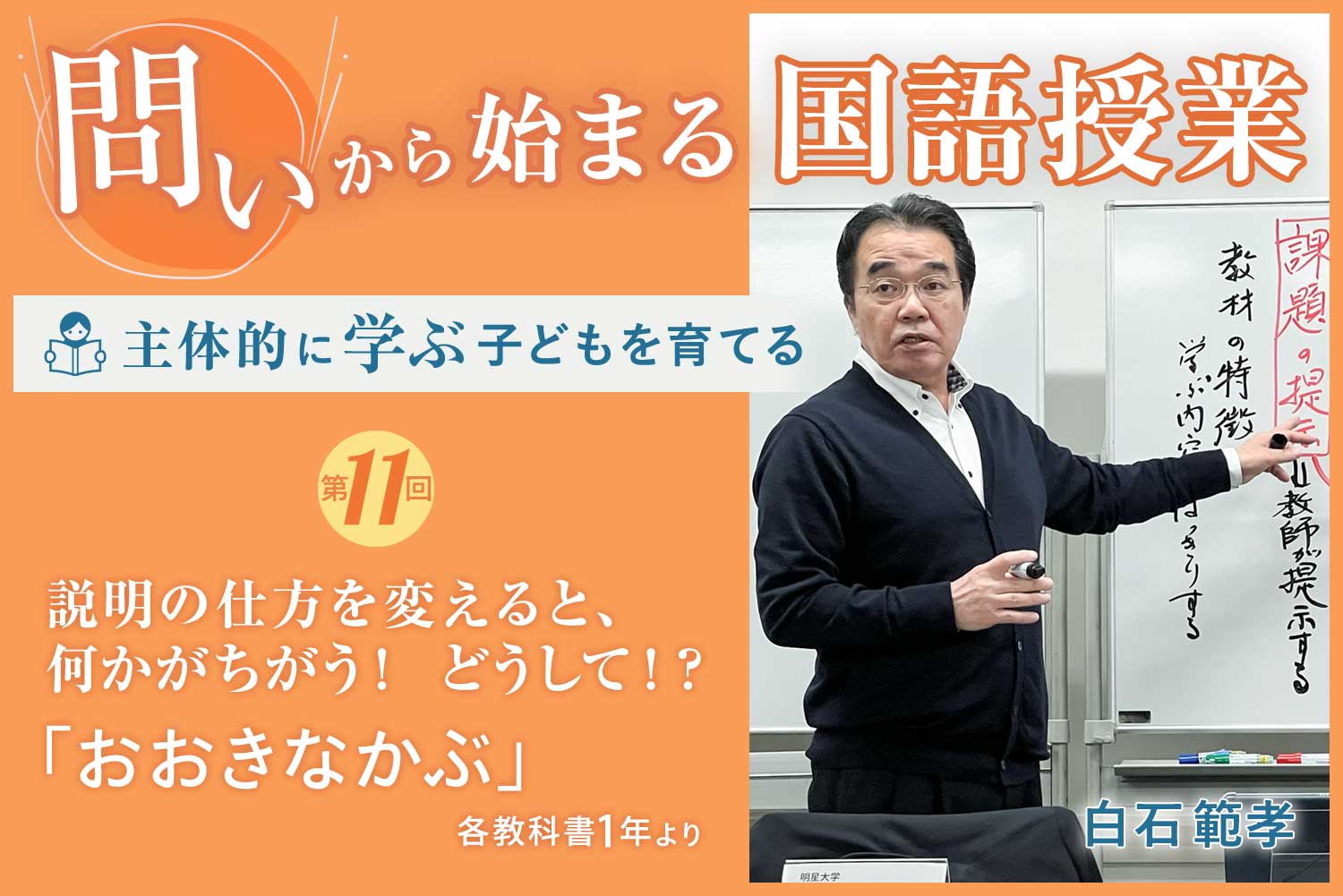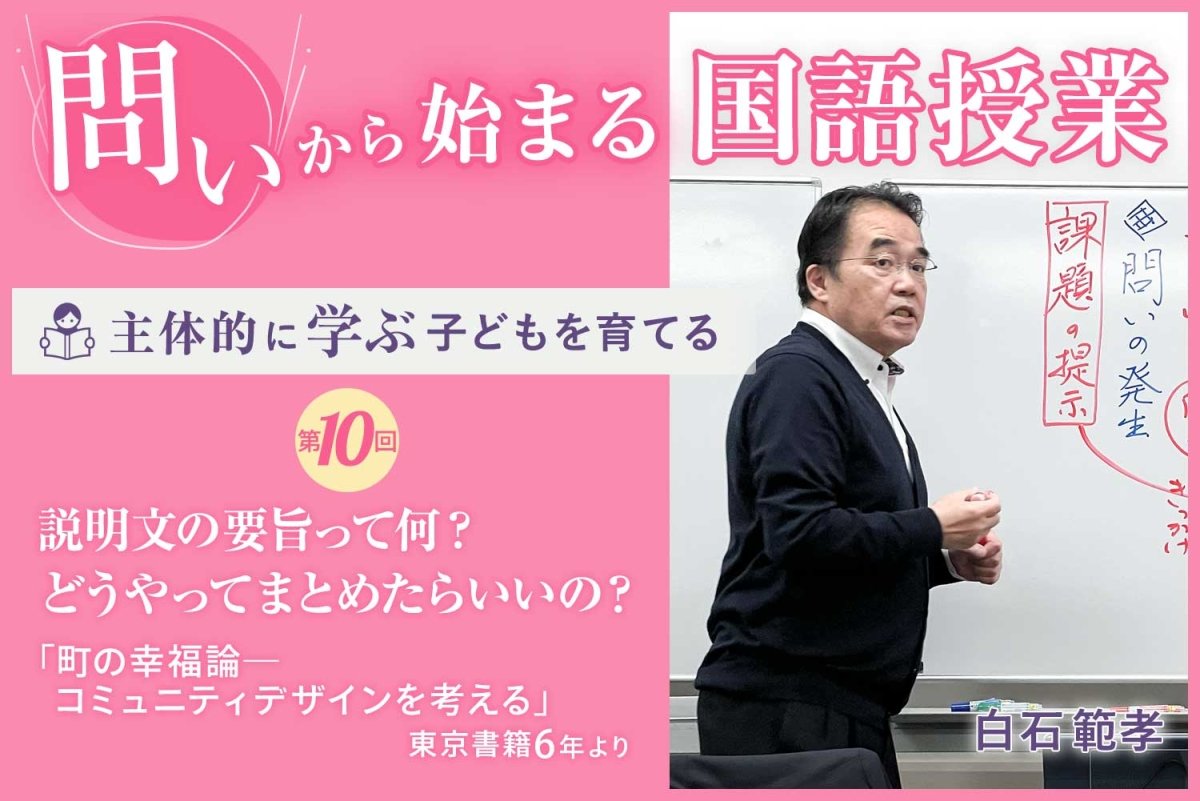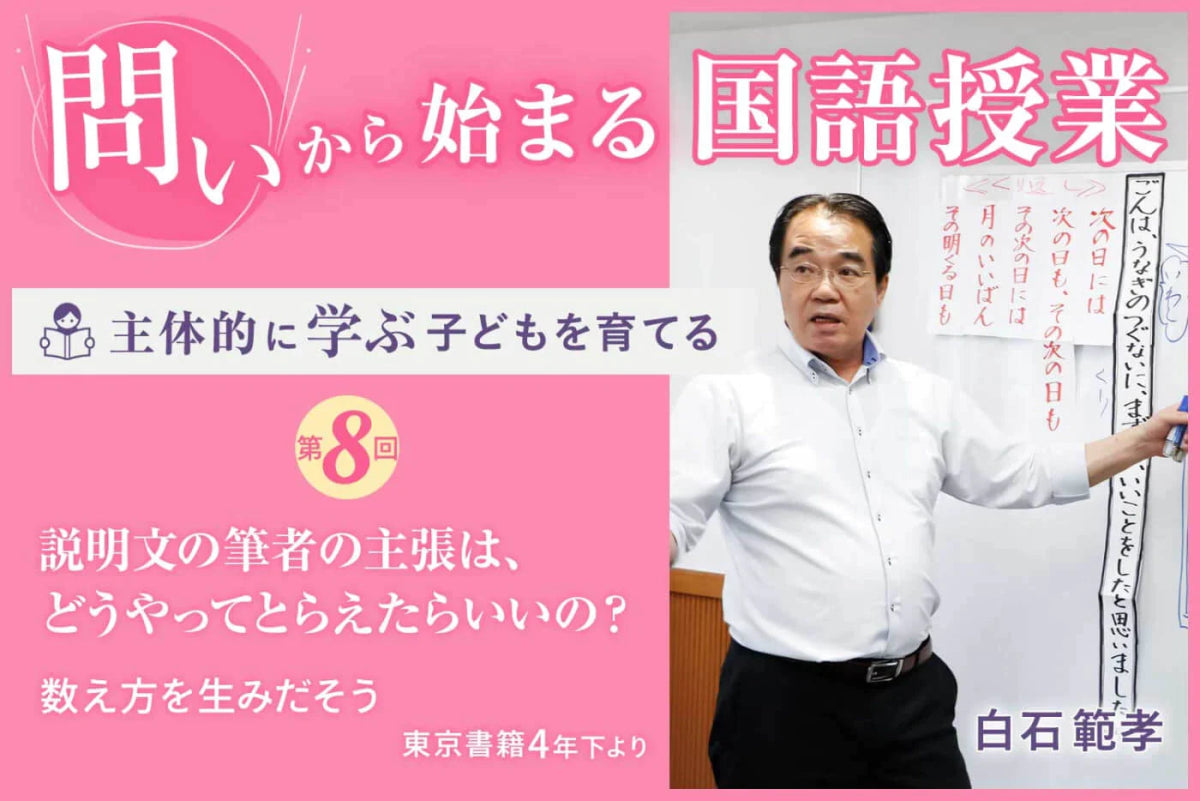ともすると平和教育で終わってしまいがちな戦争を扱った物語。しかし、作者が描こうとしたことを丁寧に読み取ることによって、「国語の教材」として学びを深めることができるのです。
【今回の「問い」】
楠木アヤをさがしているのは誰?
【習得を目指す力】
物語の題名や設定の場面の叙述も丁寧に読み、物語の主題に迫る力
【問い】の解決による汎用的な力の習得とは
授業においては、子どもたち自身が【問い】をもち、自発的に解決しようとすることが大切だと言われます。
そのためにも、授業づくりにおいては、教師が【課題】【活動指示】【ズレ】【問い】【技】の関係を理解し組み立てていくことが必要です。
※「【問い】の解決による汎用的な力の習得」の詳細については本連載の第2回を参照

それでは、「たずねびと」の、実際の授業を見ていきましょう。
1.教材研究によって教材の特徴をとらえ、 どんな「技」を習得させるのかを明らかにする
「たずねびと」には、次のような特徴があります。
特徴1 題名が意味深い。
技 →題名を、物語の主題をとらえる手がかりとすることができる。
一般に「尋ね人」とは、「居場所がわからなくなった人」のことです。
この物語を読む多くの読者は、捜されているのはポスターの中に名前が書かれていた「楠木アヤ」のことだろうと思って読み進めるでしょう。
しかし、物語の終盤で、捜されているのは「楠木アヤ」ではなく、「楠木アヤを知っている人」であることが、次第に明らかになってきます。
このことが、物語の主題とも深く関わっています。
何気ない題名ですが、実は深い意味をもった題名だと言うことができます。
特徴2 設定部分の中心人物のこだわりをしっかりとらえることが、物語の主題に結びつく。
技 →設定をしっかりとらえることで、読みを深めることができる。
物語の中心人物は様々な「こだわり」をもっています。
この「たずねびと」の中心人物「楠木綾」の設定場面でのこだわりは、「どうして誰も『楠木アヤ』のことを覚えていないのか。『楠木アヤ』をさがしたい」というものでした。
クライマックス後に「戦争の犠牲になった人々を忘れないでいることが、悲劇を繰り返さないことにつながる」という思いを強くします。
設定場面での中心人物の思い・こだわりをしっかりとらえておくことで、この中心人物の変容を、より明確にとらえることができるのです。
2.教材の特徴から、 子どもたちにどんな【問い】をもたせるのかを明らかにする
今回は特徴1として挙げた「題名が意味深い」に着目し、中心人物である楠木綾の変容に目を向けさせます。
【問い】
楠木アヤをさがしているのは誰?
3.子どもたちに【問い】をもたせるための【課題】を設定し、 【活動指示】を行う
子どもたち「中心人物」と「中心人物の心の変容」に関心をもたせるため、次のような【課題】を示しました。
【課題】
題名の「たずねびと」とは、誰が誰をさがしているのでしょうか。
4.子ども同士に思考の【ズレ】を感じさせ、 子ども自身に【問い】をもたせる
「題名の「たずねびと」とは、誰が誰をさがしているのでしょうか。」という課題に対し、「誰を」の部分はほとんどの子どもが「楠木アヤ」と答えます。一方、「誰が」の部分に、次のような【ズレ】が生じます
【ズレ】
楠木綾が、楠木アヤをさがしている。
親や家族が、楠木アヤをさがしている。
ポスターを書いた人が、楠木アヤをさがしている。
ポスターを書いた人が、楠木アヤを知っている人をさがしている。
ここから、次のような【問い】が生まれます。
【問い】
楠木アヤをさがしているのは誰?
実は、この問いは、【課題】「題名の「たずねびと」とは、誰が誰をさがしているのでしょうか。」の答えには結びつきません。
なぜなら、前述の通り、この物語の「たずねびと」とは、「楠木アヤ」をはじめとする、広島の原爆で亡くなったひとびとのうち、名前しかわかっていない人の、身寄りや知り合いの人たちのことだからです。
この物語は、「楠木アヤ」という11歳の少女が原爆で亡くなったのに、その少女をさがす人がだれも現れないというところに、戦争の悲惨さを描いているのです。
子供たちは「楠木アヤをさがしているのは誰?」という【問い】からアプローチし、この物語の主題に迫っていくことになります。
5.【問い】の解決
物語の多くの事柄は、「設定」の部分に描かれています。
この物語でも、中心人物・楠木綾の「楠木アヤをさがしたい」という気持ちが表現されています。
と同時に、「どうして誰も『楠木アヤ』のことを覚えていないのか。」という疑問ももっています。この疑問が物語の終盤、「原爆供養塔の近くにいる被爆者のおばあさん」と話すことによって解消していくのと同時に、新たな思いへもつながっていきます。
設定の場面を丁寧に読んでみましょう。
ポスターを見た綾は、
――死んだ人をさがしているんだ――
ととらえますが、その数行前に、ポスターに書かれていた文章として、
「ご遺族の方や名前にお心当たりのある方は、お知らせください」
という文章が紹介されています。
つまり、このポスターは、「死んだ人」をさがしているのではなく、「死んだ人を知っている人」をさがしているのだということが、すでにここで述べられているのです。
しかし、多くの子どもは綾と同じように、この設定を深くとらえることなく、先へと進んでいきがちです。
さがしているのは「死んだ人を知っている人」であることは、綾と共に物語の終盤で理解することになりますが、実は設定の場面ですでに述べられているのだということに気づかせ、設定の場面をしっかりとらえることの大切さを気づかせたいものです。
設定の場面の、この「ご遺族の方や名前にお心当たりのある方は、お知らせください。」の一文は、実はクライマックスに向けての伏線にもなっています。
原爆供養塔で会ったおばあさんは、綾が「名前と年齢が同じ」というだけの理由でそこにやって来たことを知り、アヤに「よかったね」と語りかけ、綾には「アヤちゃんのことを、ずっと忘れんでおってね。」と言います。
これがきっかけで綾は、さがされていたのは「死んだ人」ではなく、「その人を知っている人」であることに気づきます。
自分のことを思い出してくれる人さえいなくなってしまった原爆の犠牲者の悲しみを改めて深く感じるのです。
今月号のまとめ
題名や設定の場面もしっかりとらえましょう。
物語の学習というと、出来事の展開や場面、クライマックスに力点を置きがちですが、題名や設定の場面もしっかりとらえることの大切さをご理解いただけたでしょうか。
この物語が戦争の悲惨さを描いていることは、多くの子どもは読み取ることができるでしょう。
しかし、前述の【問い】を読みの柱とすることによって、作者は、「一人の人間が生きていたことを知る人さえいなくなってしまう悲劇」を描こうとしたのだということが、より鮮明に浮かび上がります。
戦争を題材とする物語の学習では、ともすると平和教育に軸足が置かれてしまいやすいものです。
しかし、国語の学習として扱う以上、作者が描こうとしたことを叙述をもとにとらえ、論理的に読み解いていくことが大切だと考えます。