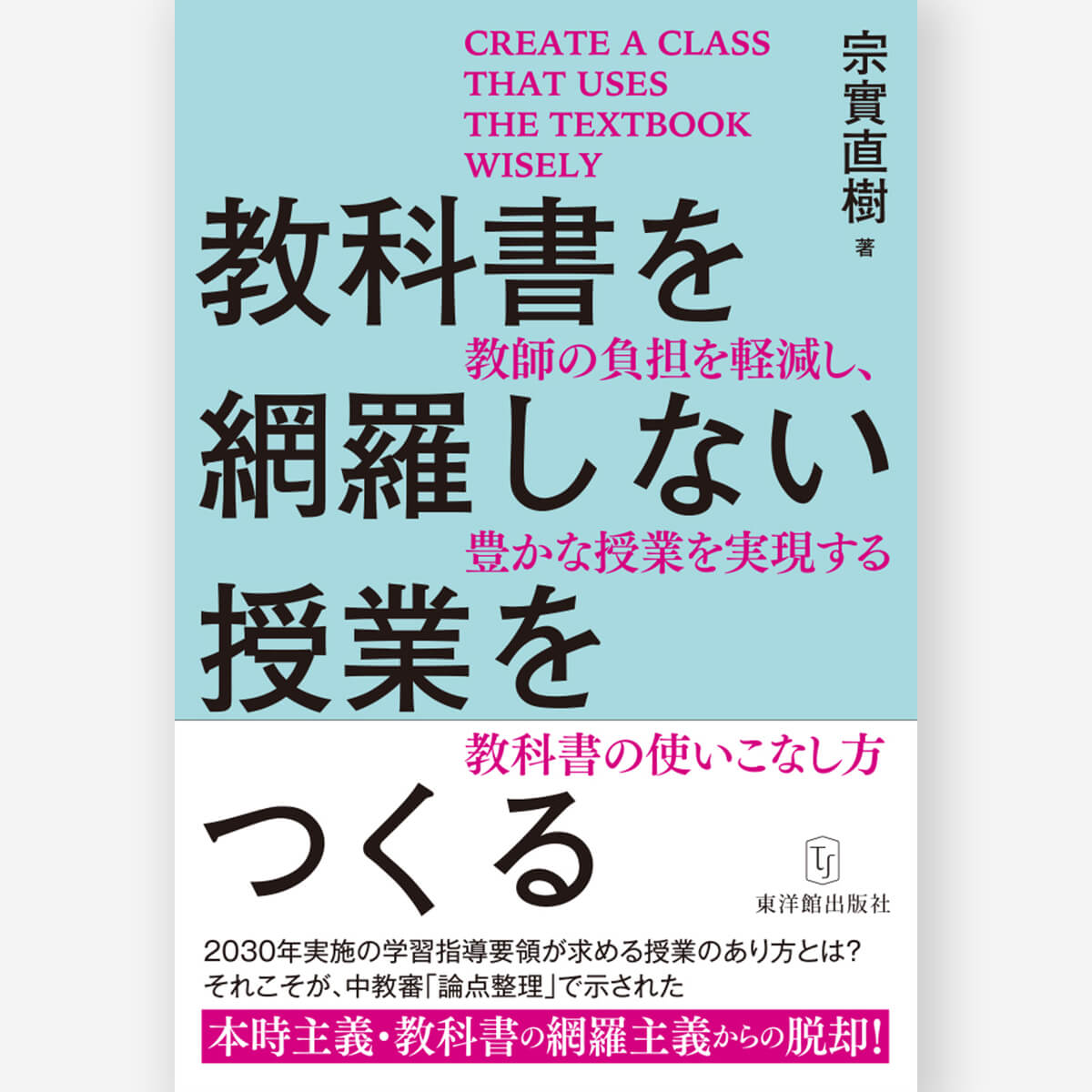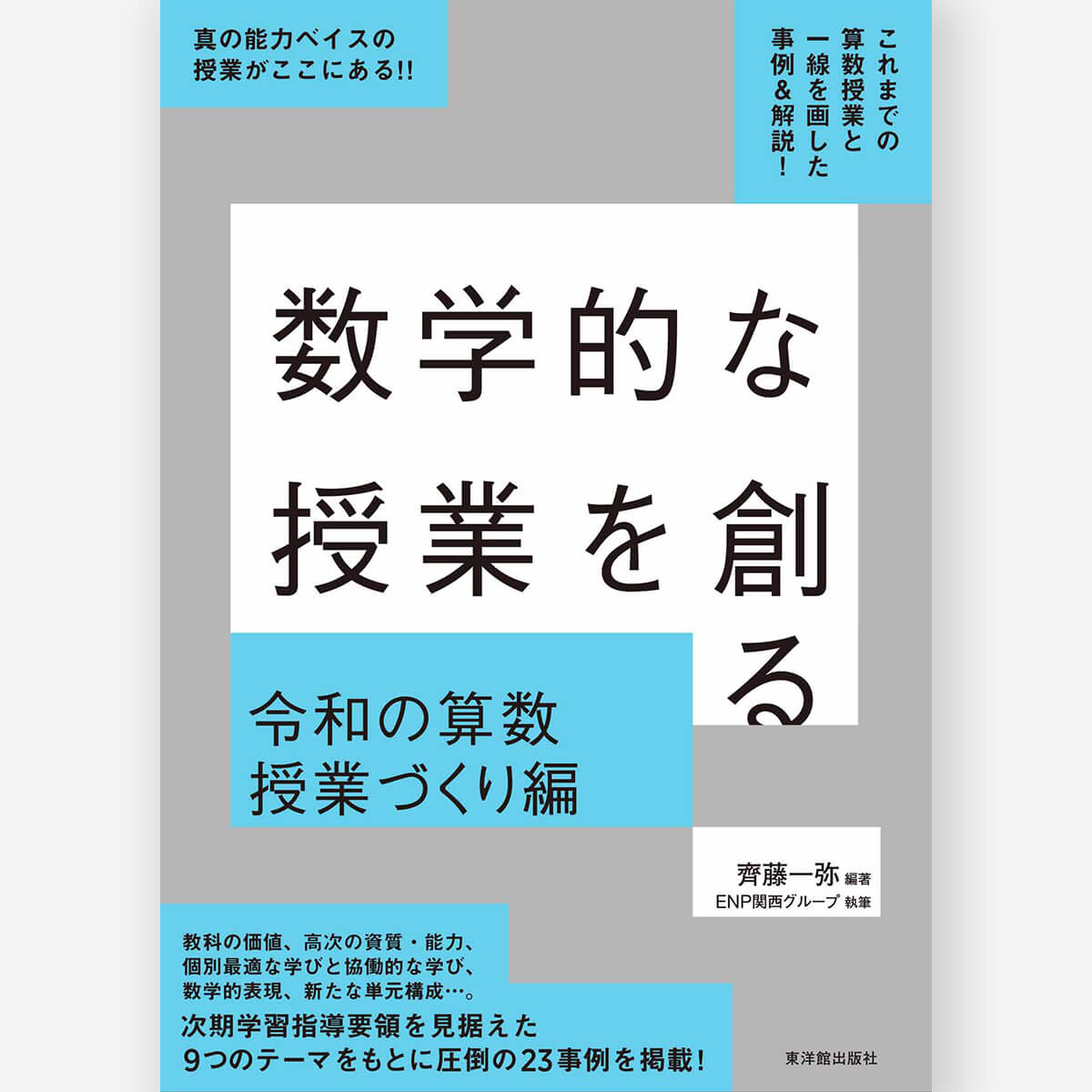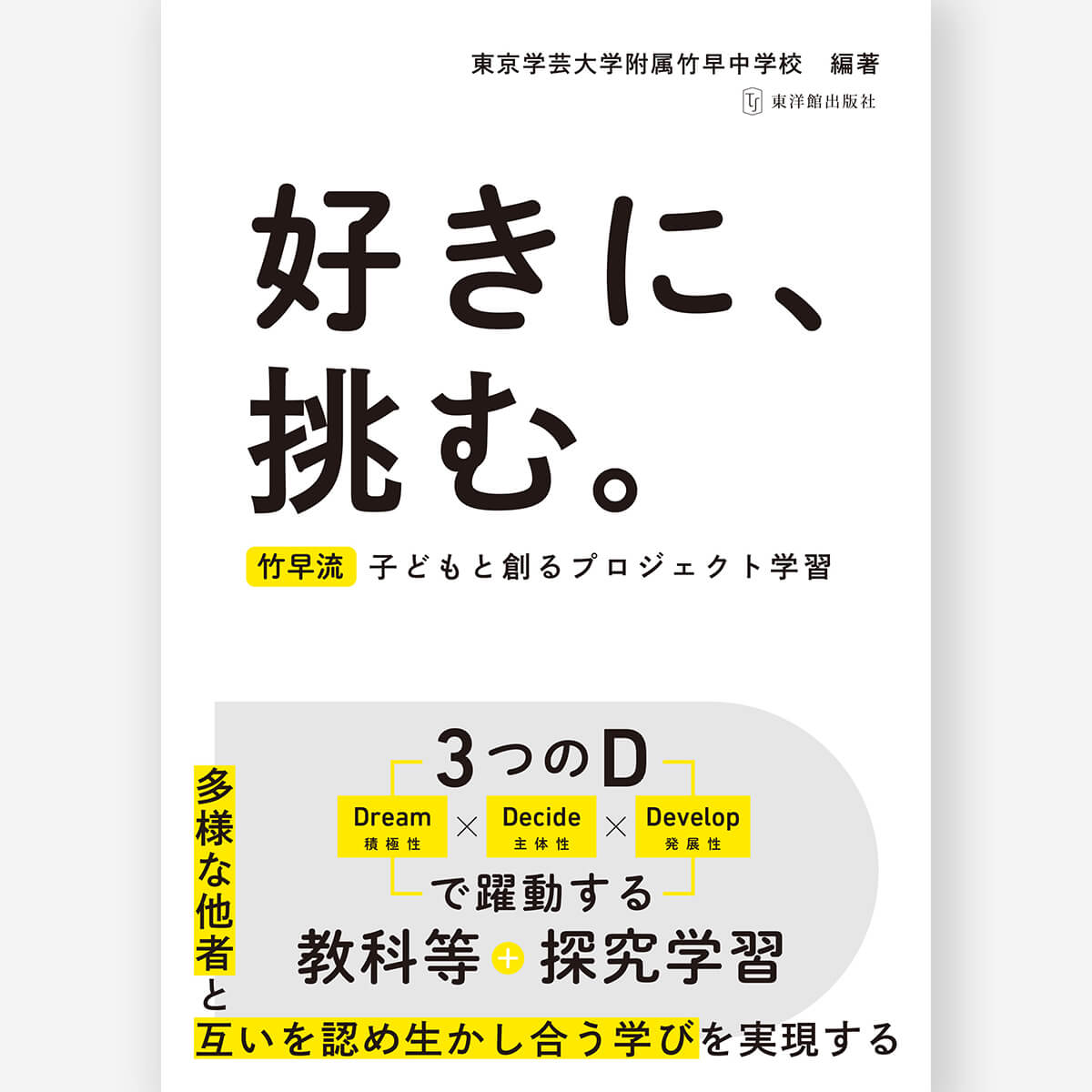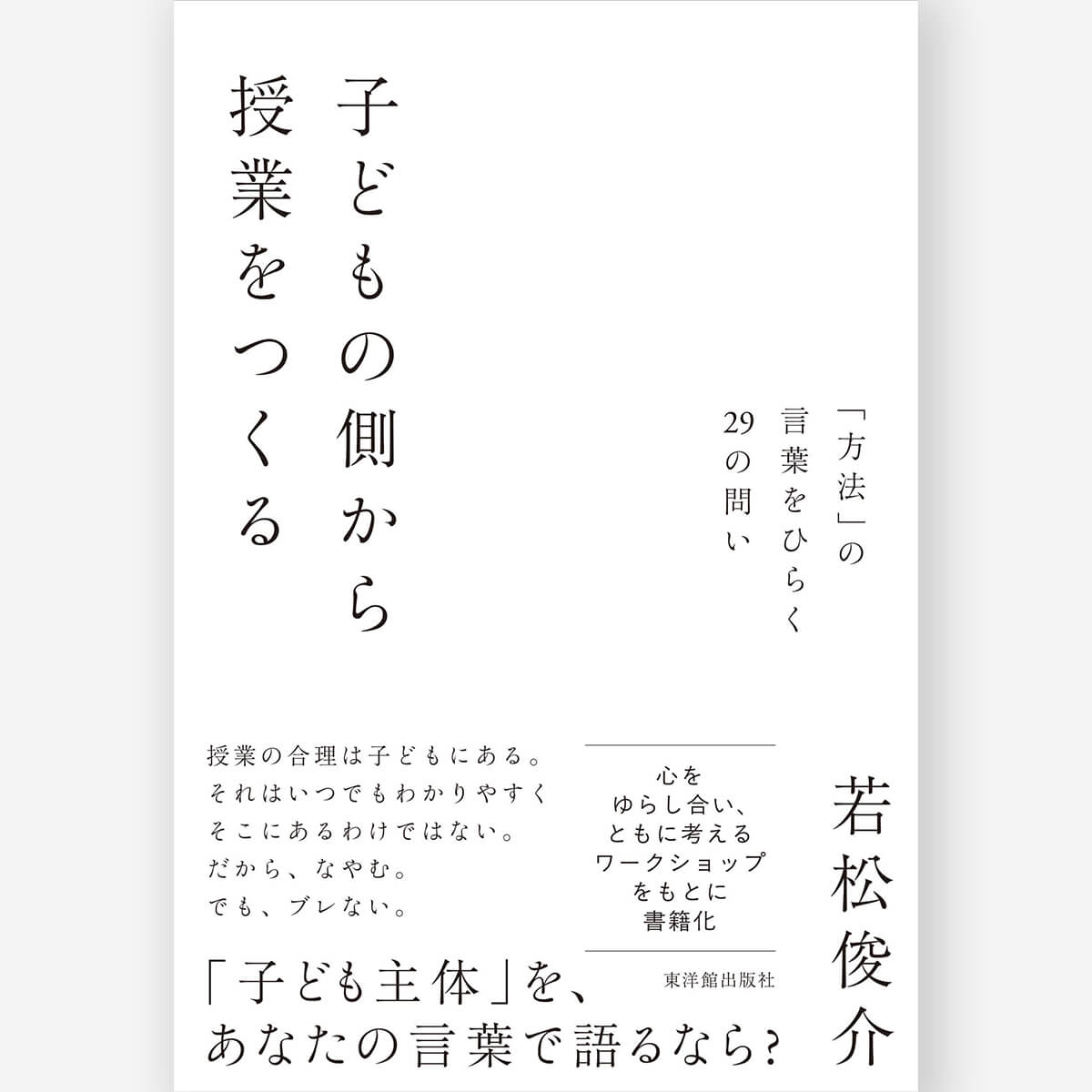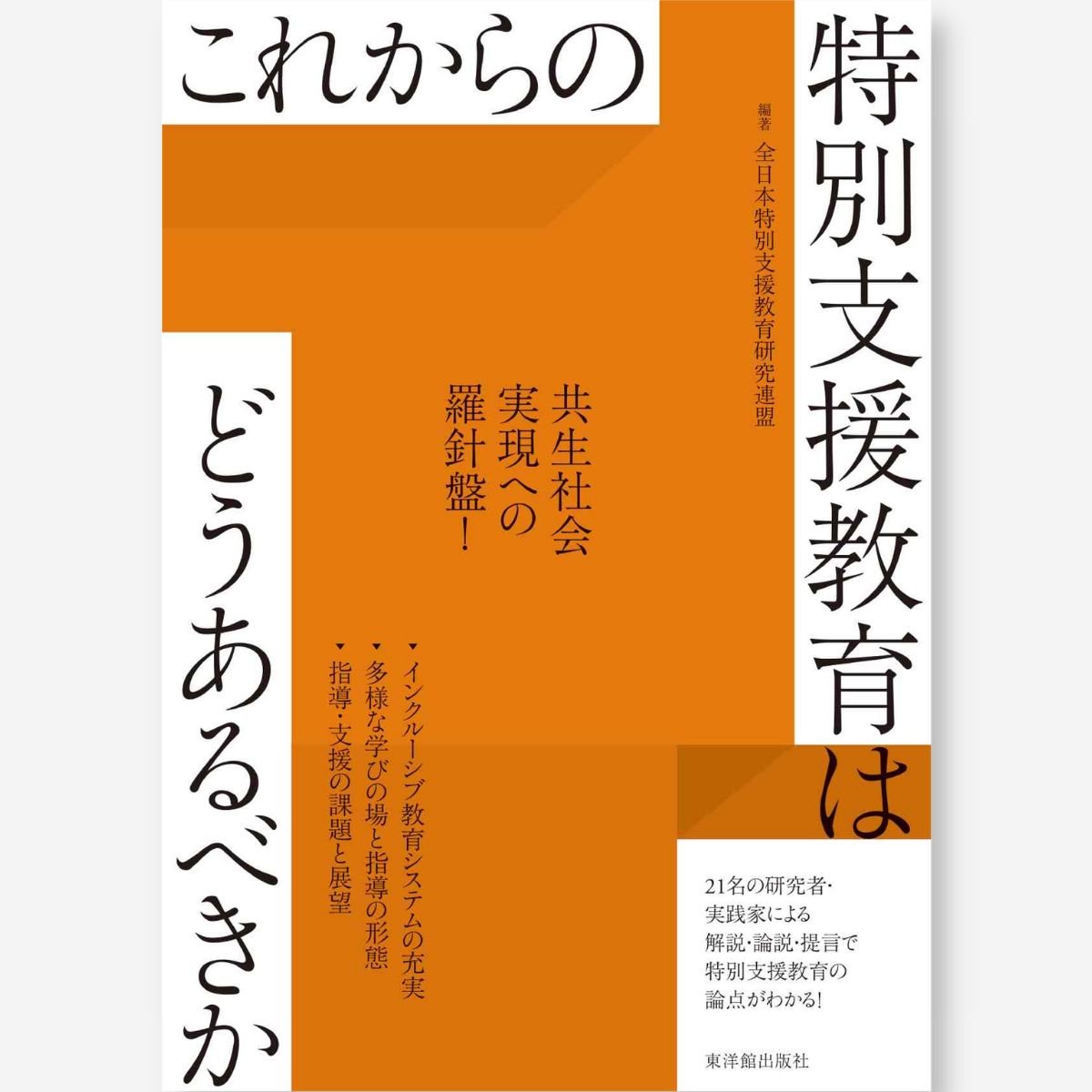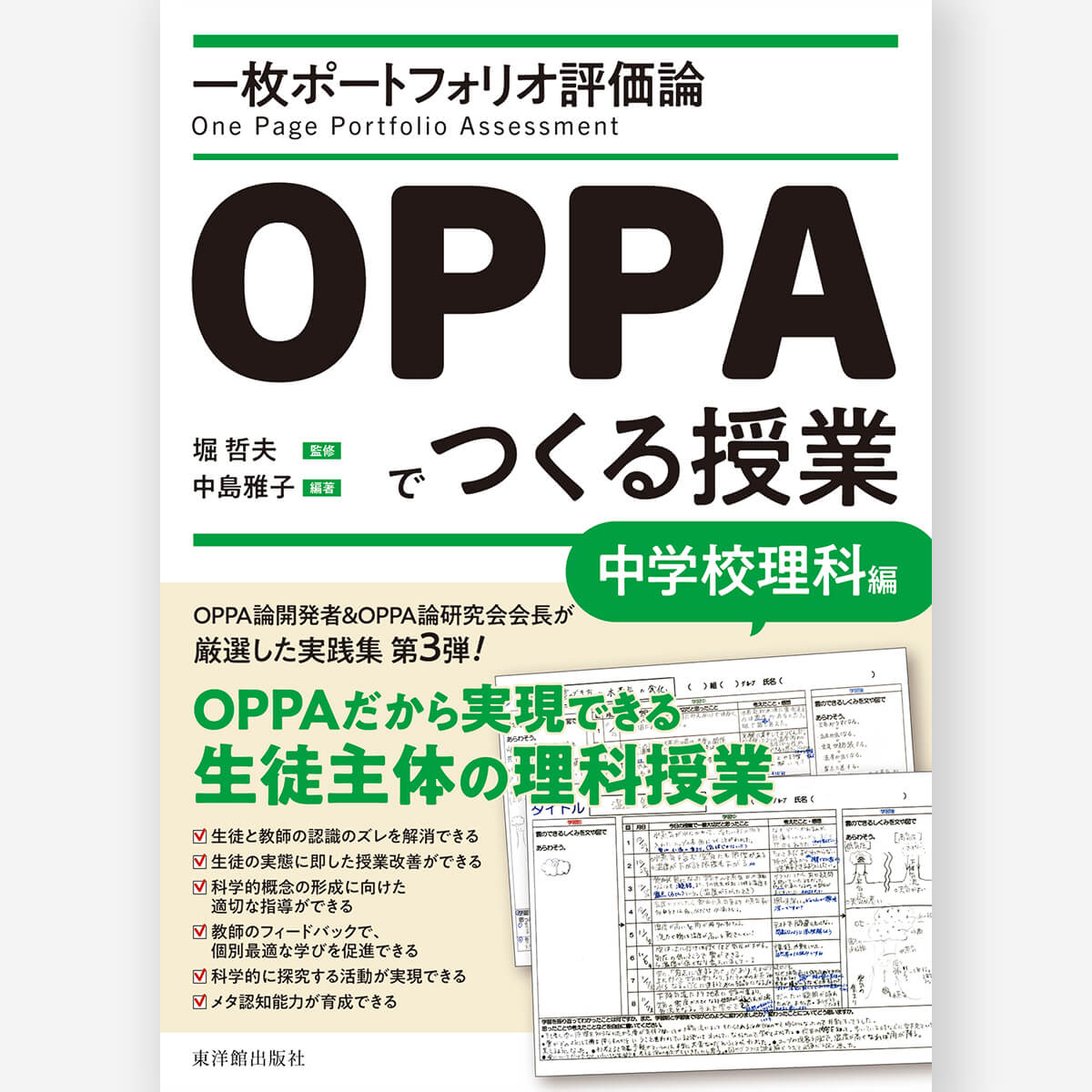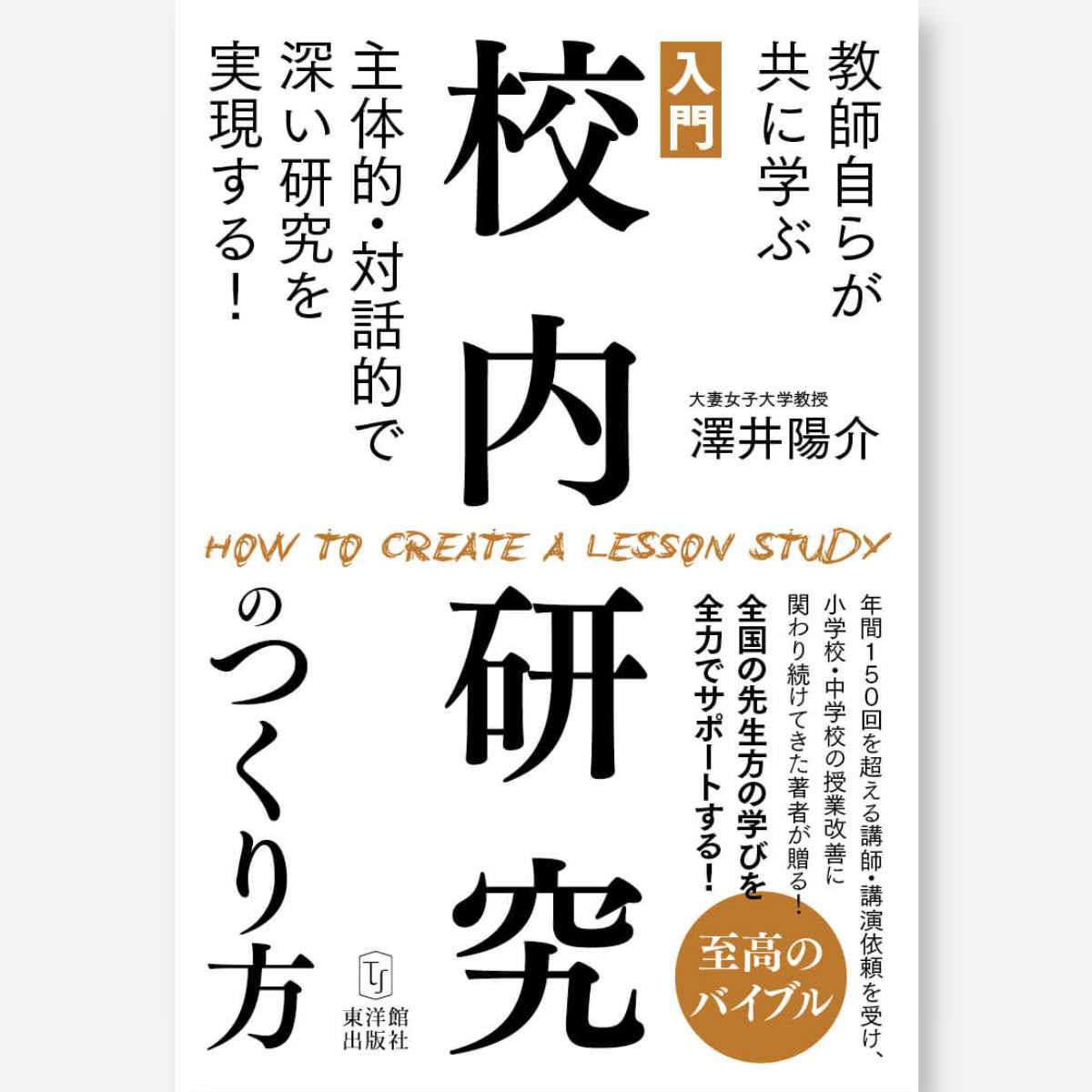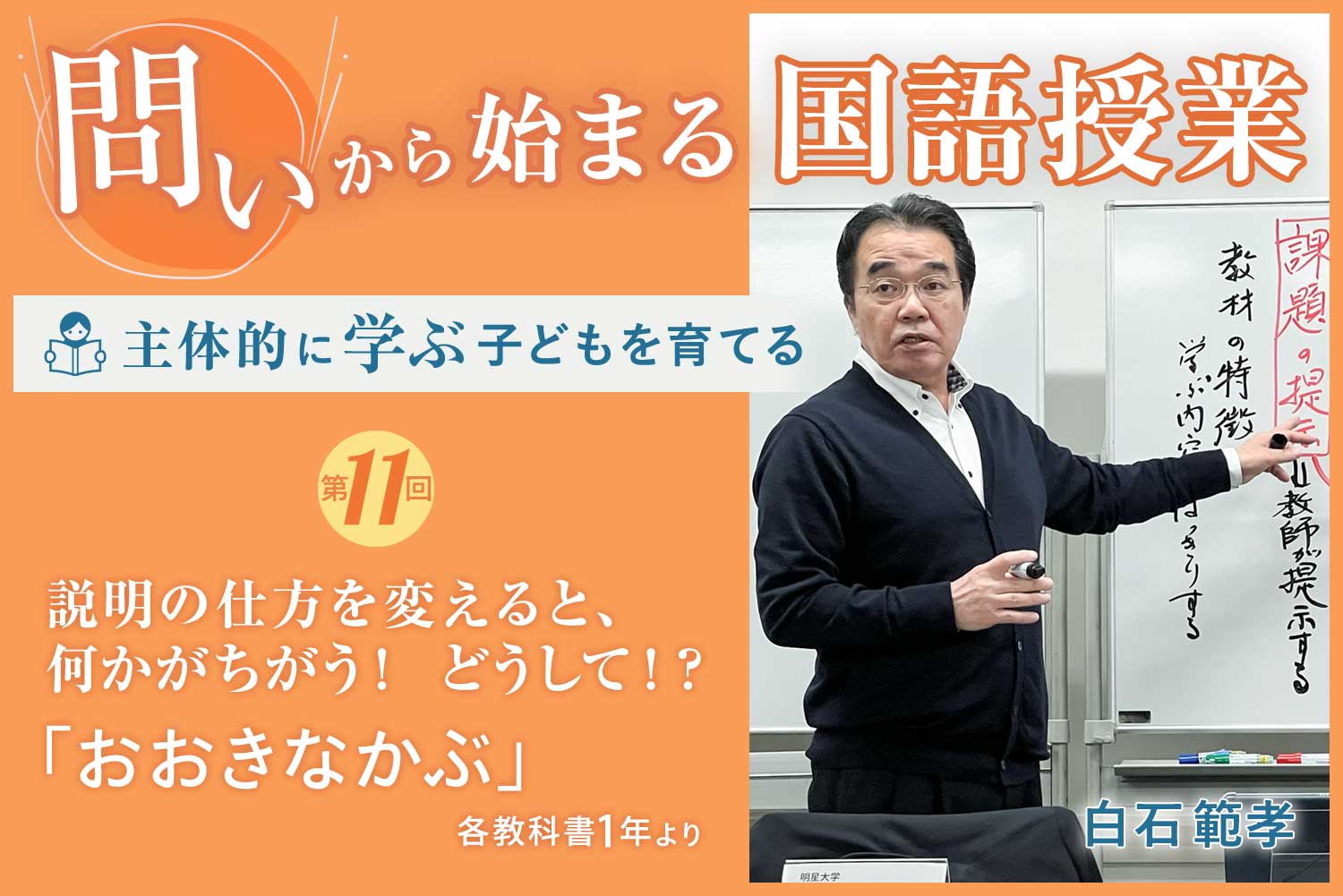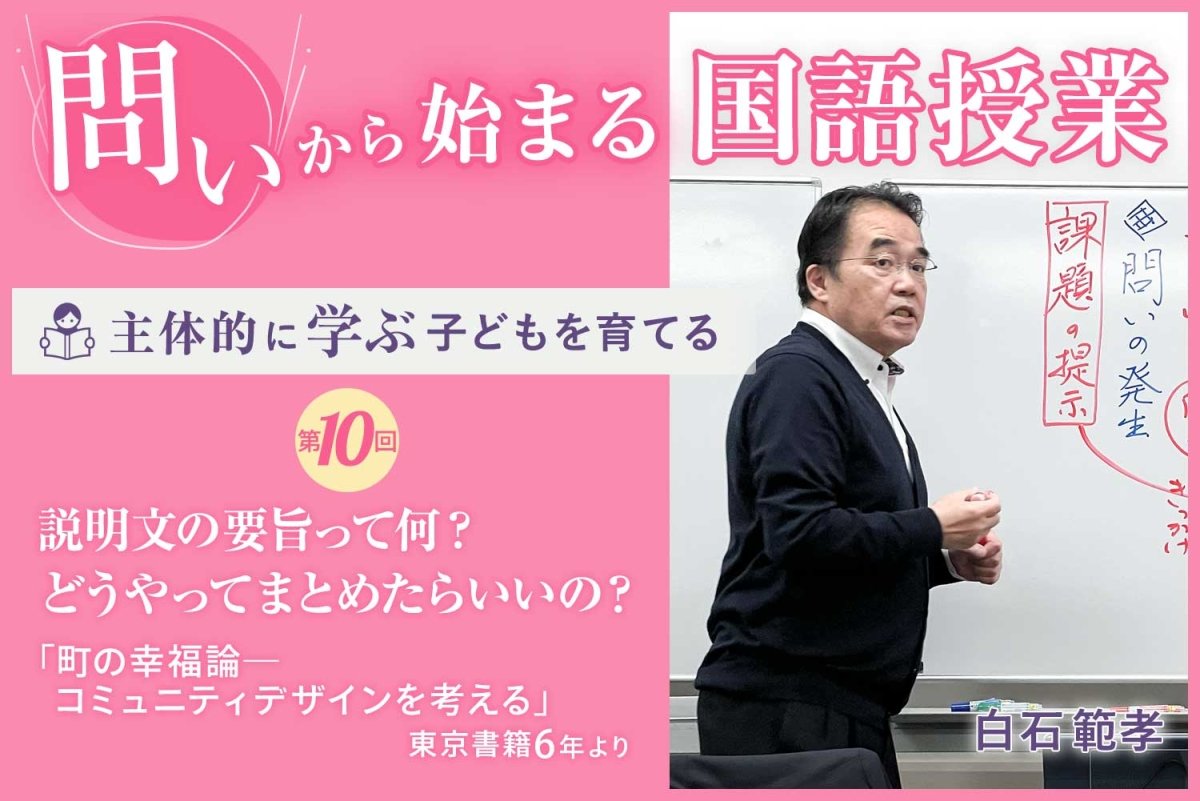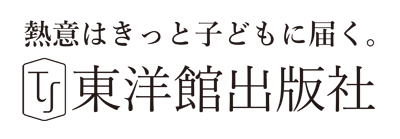母語は時空を超える
――新刊『撤退論』〔編注1〕では、人口減とどう付き合っていくかという話題がありました。人口減が進み、日本語話者が減っていく中で、国語教育はどうあるべきでしょうか。
人間は新しいアイディアを母語でしか創り出すことができない。知的なイノベーションは母語でしかできない。これが国語教育を考えるときの一番ベースに来るべき前提だと思います。
豊かな語彙を持つこと、鮮やかなレトリックを駆使できること、それは知的なイノベーションにとって不可欠です。そして、それは母語によってしかできません。僕たちは母語によってしか、複雑なニュアンスをもつ語を使い分けたり、複雑な論理階梯をもつ構文を語ったりすることはできません。
日本列島には数千年前から人が暮らしていました。そのすべての人たちが何らかの言葉を発してきたり、文字を書いたりしてきた。その全てが僕たちの「母語のアーカイブ」をかたちづくっています。僕たちが直接知っている語彙とか、使っている構文とか修辞とかは、そのごく一部に過ぎません。でも、「母語のアーカイブ」への入り口は僕たちが母語を習得してきた過程で、日本語話者全員の中に標準装備されています。国語教育というのは、子どもたち全員の中に標準装備されている、この「母語のアーカイブ」へのアクセスの仕方を教えることだと僕は思います。
日本列島で発したことのある発語や文字列のすべてがそこには集積しています。それはある種の天文学的サイズの図書館のようなものです。その図書館そのものではなく、その図書館への「入口」が僕たちの中には存在しています。国語教育というのは、この「図書館への入り口」をどうやって開き、どうやって「母語のアーカイブ」の深みに沈みこんでゆくか、それを教えることだと思うんです。
何年か前に、池澤夏樹さんの個人編の文学全集で『徒然草』の現代語をしたことがあります〔編注2〕。『徒然草』なんて、予備校時代に受験勉強で読んだのが最後だし、古語辞典たってその当時のぼろぼろのものが手元には1冊あるだけでした。果たして現代語訳なんかできるだろうかと思いましたけれど、池澤さんがわざわざご指名くださったのは「できる」という評価を下した上でのことだろうから、まあ何とかなるだろうと思って、お引き受けしました。そして、毎日一段か二段ずつちょっとずつ訳して、二年かけて全訳をしました。毎日読んでいるとだんだん慣れてくるんです。吉田兼好とだんだん呼吸が合ってくる。どういう人柄だかだんだんわかってくる。そうすると、知らない言葉でも、古語辞典を引く前に「だいたいこんな意味じゃないかな」と予測できるようになる。
訳し終えてから「『徒然草』を訳して」という演題で二度講演をしました。京都の西本願寺で講演したとき、講演が終わった後にフロアとの質疑応答の時間がありました。そのときに手を挙げた方がいて、「私は高校の国語の教師ですが、博士論文は『徒然草』で書きました」とまず自己紹介した。わあ、何を言われるのだろうとどきどきしていたら、「内田さんの訳文はたいへんよい」と言ってくれました。「とくに係り結びの訳し分けが適切だった」と言われて、こちらが驚きました。実は係り結びというのは5つぐらい意味があって、文脈に応じて、訳し変えないといけないんだそうです。そんな文法規則があることを僕は知らなかった(笑)。でも、ちゃんと訳し分けていたらしい。
こういうことができるのは、やっぱり母語だからだなと思いました。吉田兼好は800年前の人です。でも、800年前までの「母語のアーカイブ」を僕は彼と共有している。そこから湧いて出てくる表現ですから、根は一緒なんです。だから、微妙なニュアンスの違いが分かったりもする。母語だとそういうことが起きる。
生まれて初めて聞いても、意味が分かる言葉
時々、新しい日本語が生まれることがあります。「新語(neologism)」と言いますが、新語について一番面白いのは、ある人がふっと思いついてその新しい語や表現を使い出したにもかかわらず、その微妙なニュアンスが日本語話者であれば誰でもわかるということです。そして、新語の伝播はものすごく速い。たぶん数週間で日本列島を北から南まで一気に広がっているんじゃないかと思います。
そして、新語の発明は母語話者にしかできません。僕が外国語で新しい言葉を思いついても、それを口にしてみても、たぶん誰も意味がわからない。「そんな言い方はしない」と言われておしまいです。でも、母語話者だとそれまで誰も使ったことがない新語についても、意味がわかる。ニュアンスが伝わる。
印象的な新語は半疑問形です。「複雑化の教育論?」みたいに、語尾をちょっと上げる独特の言い方です。これがある時期から流行りましたね。「よく知らないんだけれども」とか「俺はあまり評価してないので、一応判断保留しとくけれども」みたいなかなり複雑なニュアンスをもっている言い回しです。
初めて聞いたのが、90年代はじめの大学の教授会でした。一人の先生がある教育プログラムについての議論の中で、半疑問形を使ったんです。でも、その微妙に語尾を上げる言い方で「そういうプログラムを企画している人が学内にいるみたいだけれど、オレはその話聞いてないし、中身知らないし、評価もしてないし、どちらかというと反対だけど」というニュアンスをみごとに伝えていて、ちょっとびっくりしました。それからしばらくしてテレビを見ていたら、出演者たちが続々と半疑問形で話していました。「伝播するの速いなあ…」と感心しました。
「真逆」とか「ほぼほぼ」とか、どれもはじめて聴いたの意味やニュアンスが理解できた。「真逆」は「正反対」よりちょっとだけ強い。「ほぼほぼ」は「ほぼ」よりもちょっとだけ確率的に低い。そういう意味の違いがわかる。いずれも日本中にあっという間に広がりました。
これが母語の生成力・伝播力というものなのだと思いました。新しい表現、新しいアイデアが出てきたとき、人々が瞬時に理解し、すぐに利用するようになる。
数学者の岡潔は「数学は情緒だ」ということを言っていました〔編注3〕。彼の言う「情緒」というのはたぶん数学的なアイデアとしてきちんとしたかたちをとる寸前の、輪郭の定かならぬ星雲状態の思念を導く力のことを指しているんだと思います。そのアモルファスな思念が形をとるには、身体的な没入が必要だ、と。星雲状態のアイデアが学的な概念にまとまるためには、「我を忘れて」没入する必要があり、そこには感情生活の豊かさの支援が要る。そういうことを岡潔は言っているんじゃないかと思います。
僕の経験ではそうです。自然科学であっても、社会科学であっても、あるいは文学であっても、ある新しいアイディアがかたちをとるときに、それはきわめて情緒的なものなんです。そして、その情緒的なもの、身体感覚的なものを言葉にするためには母語が要る。新語が湧き出てくるように、母語のアーカイブから湧き出してくる言葉でないと、この情緒をうまく掬い取ることができない。

イノベーションは、共同体のアーカイブから浮かび上がってくる
日本はノーベル賞の受賞者がアジア諸国の中では突出して多い国です。これは考えてみたら不思議なことです。日本語は国際共通語ではありません。日本語話者は世界中足しても1億人ちょっとしかいません。でも、かつて欧米の植民地であったせいで母語を奪われて、宗主国の言語が公用語になっているところでは、自然科学分野でも他の分野でも、なかなかノーベル賞の受賞者が出ません。
例えば、フィリピンはかつてアメリカの植民地、インドはイギリスの植民地でしたから、どちらでも英語は公用語です。知識人は誰でも母語同様に英語が使えます。というか使えないと政治家にも官僚にも学者にもなれません。ですから、世界標準の研究にキャッチアップしたり、国際共通語で学会発表したり、論文を書いたりする上では、日本よりむしろアドバンテージがあるはずです。でも、なぜか、どちらでも自然科学分野でのノーベル賞の受賞者が少ない。フィリピンは受賞者ゼロ、インドは5人いますが、うち外国籍が4人です。国際共通語でない言語で研究できる日本では自然科学系だけで27人(うち外国籍が3人)。この差はどう説明したらよいのでしょうか。
たしかにタガログ語やヒンドゥー語はニュアンス豊かな生活言語ですけれども、政治や経済や科学について語るのには向いていません。だから、英語を使う。みんな英語が使えるので、母語を富裕化して、母語で語れる範囲を広げるということについて、強いインセンティブがなかった。そのことがこれらの国での知的なイノベーションを妨げているのではないかと僕は思います。
フィリピンの人がこう言っていました。「英語が母語同様に使えることはたいへんpracticalであるが、母語では英語と同じ内容が話せないことはtragicである」と。これはほんとうにそうだと思います。タガログ語では、政治や経済や学術について十分に語ることができない。そのための語彙がない。そのためのレトリックや複雑な構文が洗練されていない。「言語の植民地化」というのは、そういうものだと思います。宗主国からすれば、現地住民の創発性の「芽を摘む」ことが植民地支配においては必要だったわけですから、母語を痩せ細るに任せて、宗主国の言語を学ばせた。それは日本が朝鮮や台湾でやったのと同じことです。母語を使わせず、宗主国の言語を使わせることで、彼らの「母語のアーカイブ」へのアクセスを妨害した。でも、「母語のアーカイブ」に深く沈潜することが、新しいアイディアの発生にはどうしても必要なのです。
母語で博士論文が書ける国というのは、それほど多くはありません。「日本語で書いた論文でも博士号がとれる」ということを日本のガラパゴス化の原因だとして、論文は英語で書かせろというようなことを主張する人がいますけれど、そういう人たちは「母語に世界標準の学術用語の語彙が存在する」という事実がどれほど例外的なものかを忘れていると思います。母語で国際的な研究ができるというのは、日本の数少ない知的なアドバンテージなのです。
国語教育は、母語のアーカイブにアクセスする技術を教えるための教科です。その技術に習熟することで、僕たちは自分の中にふと浮かび上がった、不定形で星雲状態のアイディアの断片に、それにふさわしい表現を与えることができる。それが知的なイノベーションをドライブする。
母語のアーカイブに深く広くアクセスできる能力を高めてゆくこと、それが言語集団の知的生命にとって死活的に重要であるということに、いま国語教育を語っている人たちはほとんど自覚的ではないと思います。だから、「古文漢文なんか教えなくていいから、英会話を教えろ」というような、言語の植民地化を歓迎するような発言をする人間が出てくるのです。

編集部注
- 内田樹編『撤退論――歴史のパラダイム転換に向けて』晶文社、2022年
https://www.shobunsha.co.jp/?p=7075 - 酒井順子・高橋源一郎・内田樹訳『枕草子/方丈記/徒然草』河出書房新社、2016年
https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309728773/ - 岡潔著・森田真生編『数学する人生』新潮文庫、2019年ほか
https://www.shinchosha.co.jp/book/101251/
教育を支える出版社として
1948年の創業以来、教育書の専門出版社として、主に学校教育に関わる出版活動を続けて参りました。学術書から実用書まで、教育書という分野において確かな地盤と実績を築いてきたという自負があります。
一方で、社会の大きな変化と、それに合わせた学校教育を含む教育情勢の変化も感じて参りました。創業前年の1947年には最初の学習指導要領が作成されました。当時はまだ「試案」という形で、戦争を省みる言葉とともに、子どもの興味や関心を大切にする児童中心主義の教育観が打ち出されました。
それから約70年が経ち、変わらない本質的な部分は現代に引き継がれつつも、全国の小中学校の9割以上に一人一台端末が配備され、授業風景が大きく変わろうとしています。学校から目を転じてみると、生産年齢人口の減少や科学技術の革新、地球規模での気候変動といった今まで人類が経験したことのない局面に直面しています。そのような変化の時代において、未来を生きる子どもたちのために、教育を支えるすべての人のために、何かまだできることがあるのではないだろうか――そのような思いから、本シリーズを新たに2022年より刊行いたします。