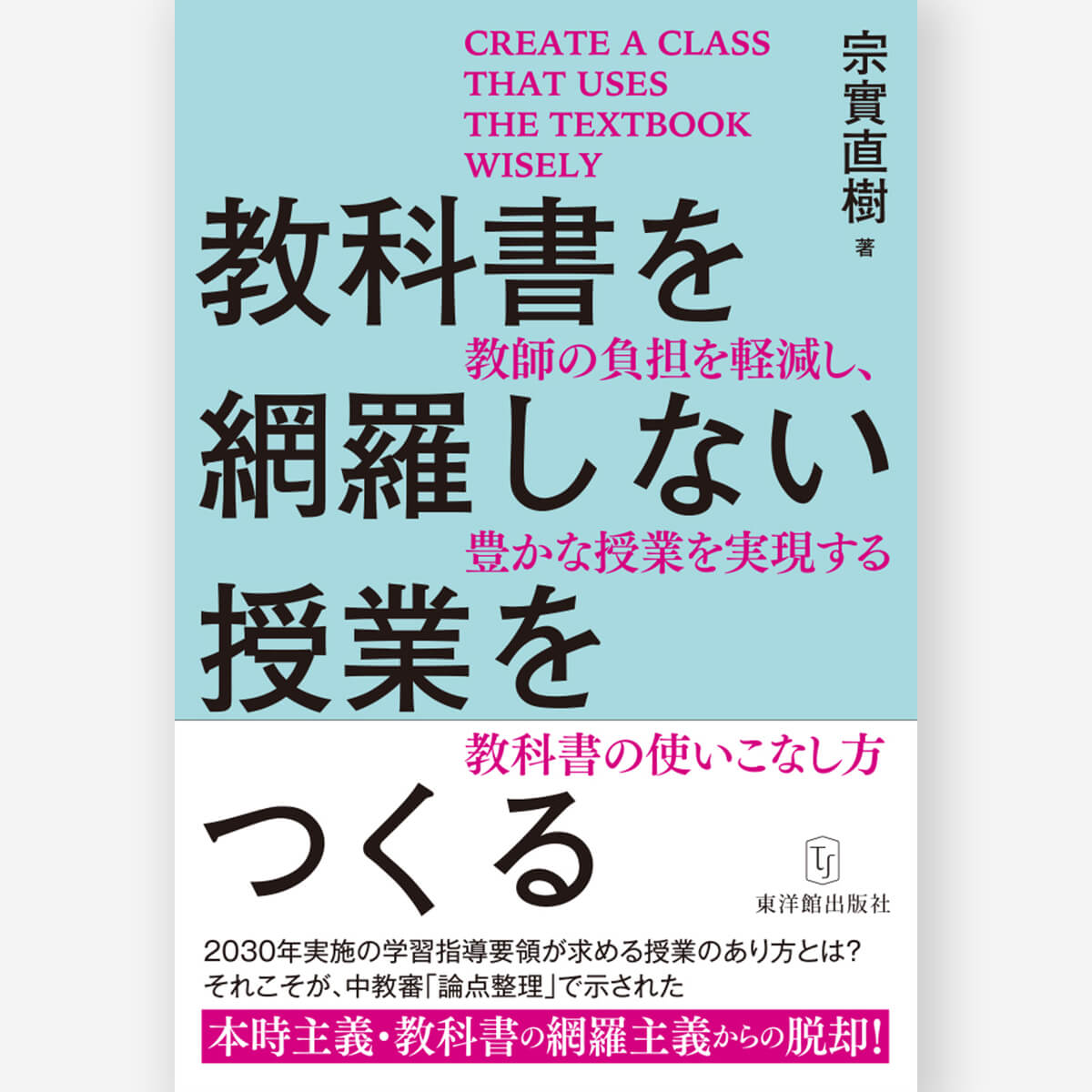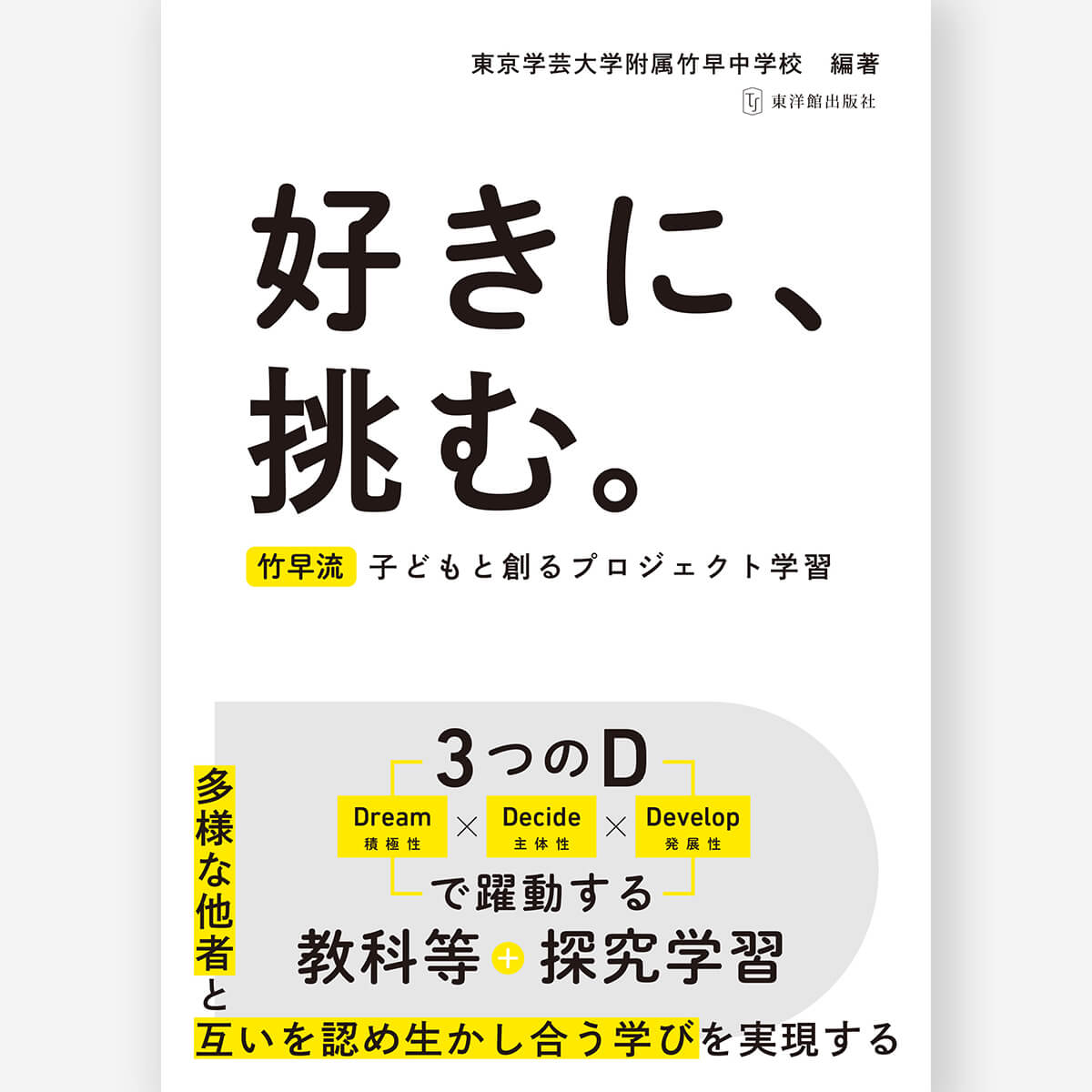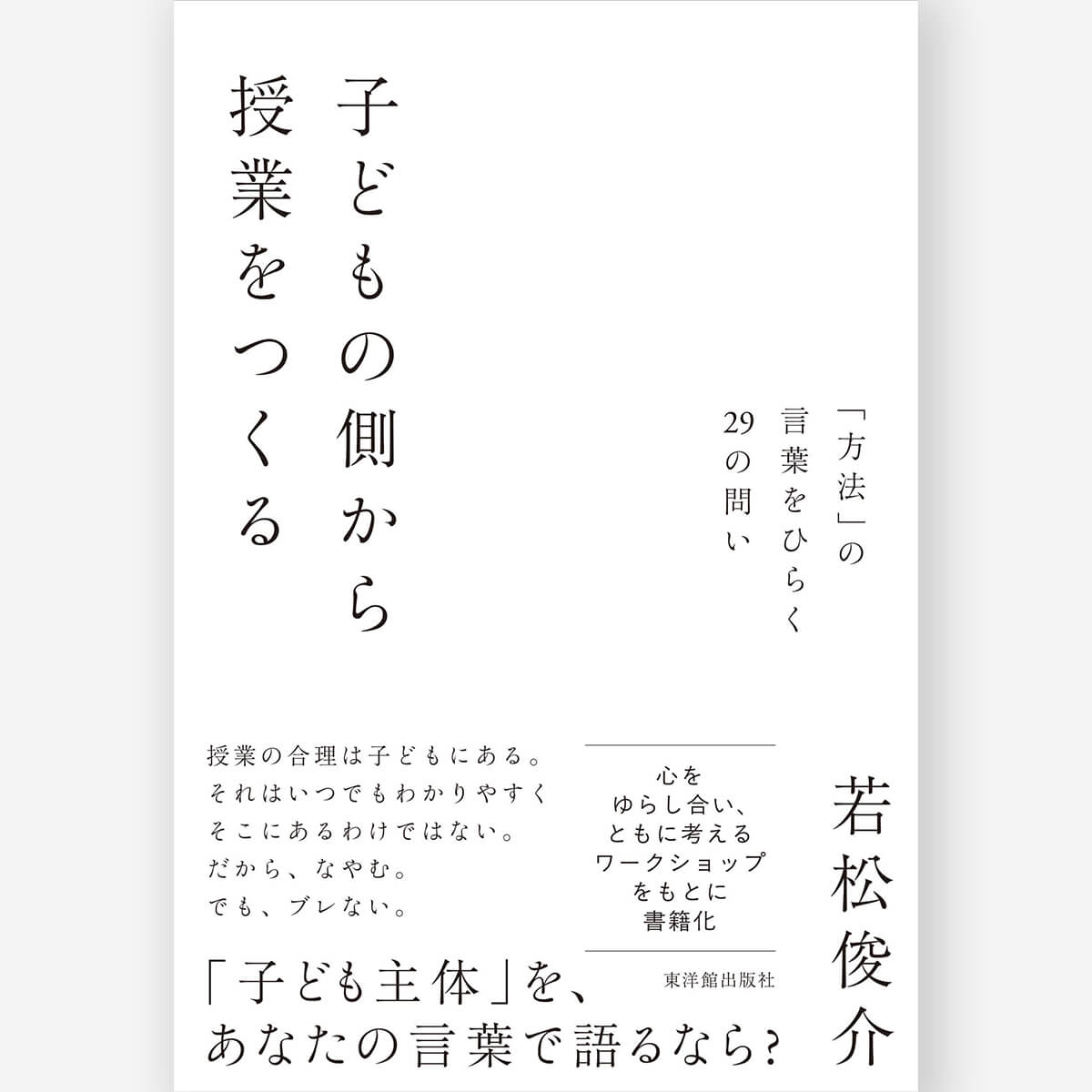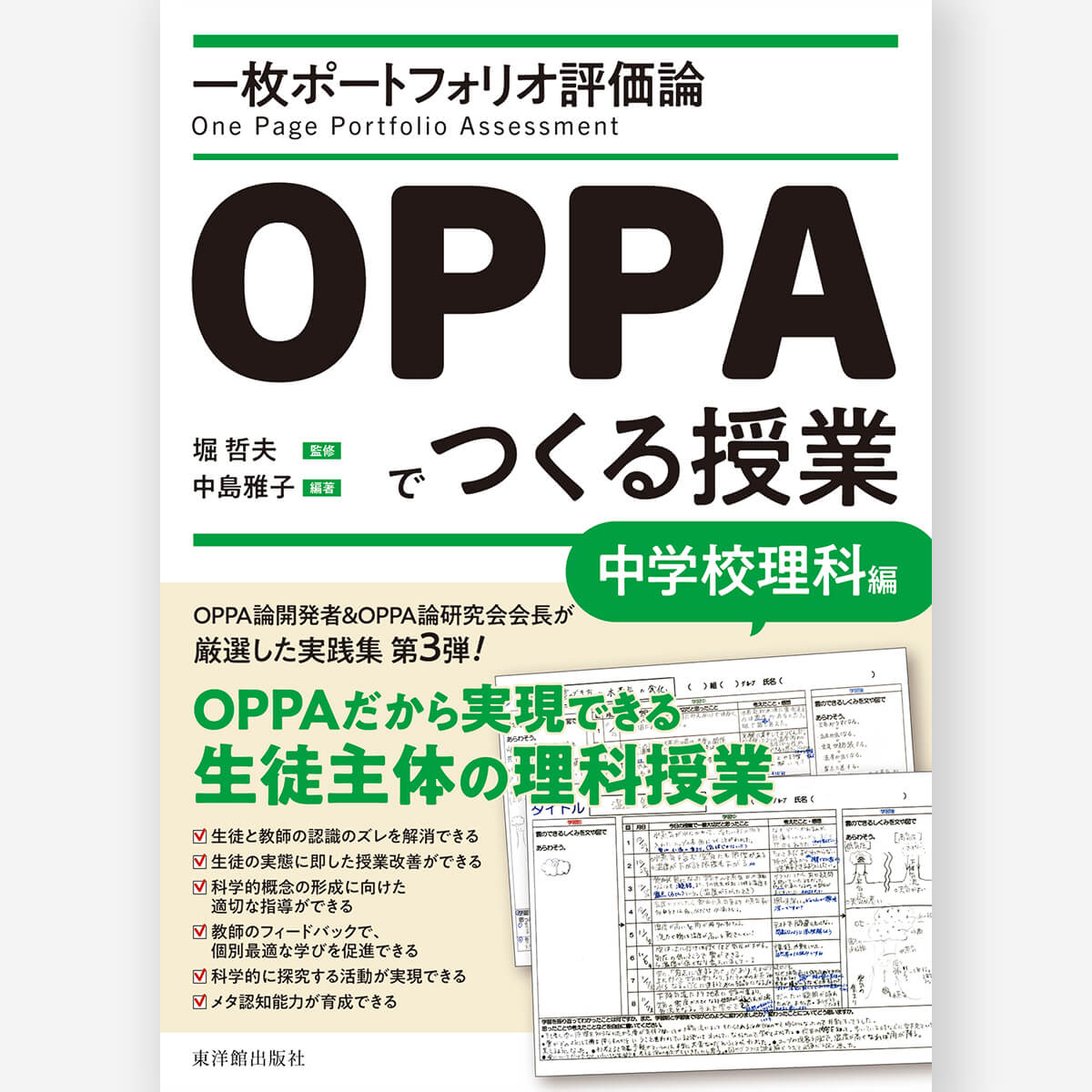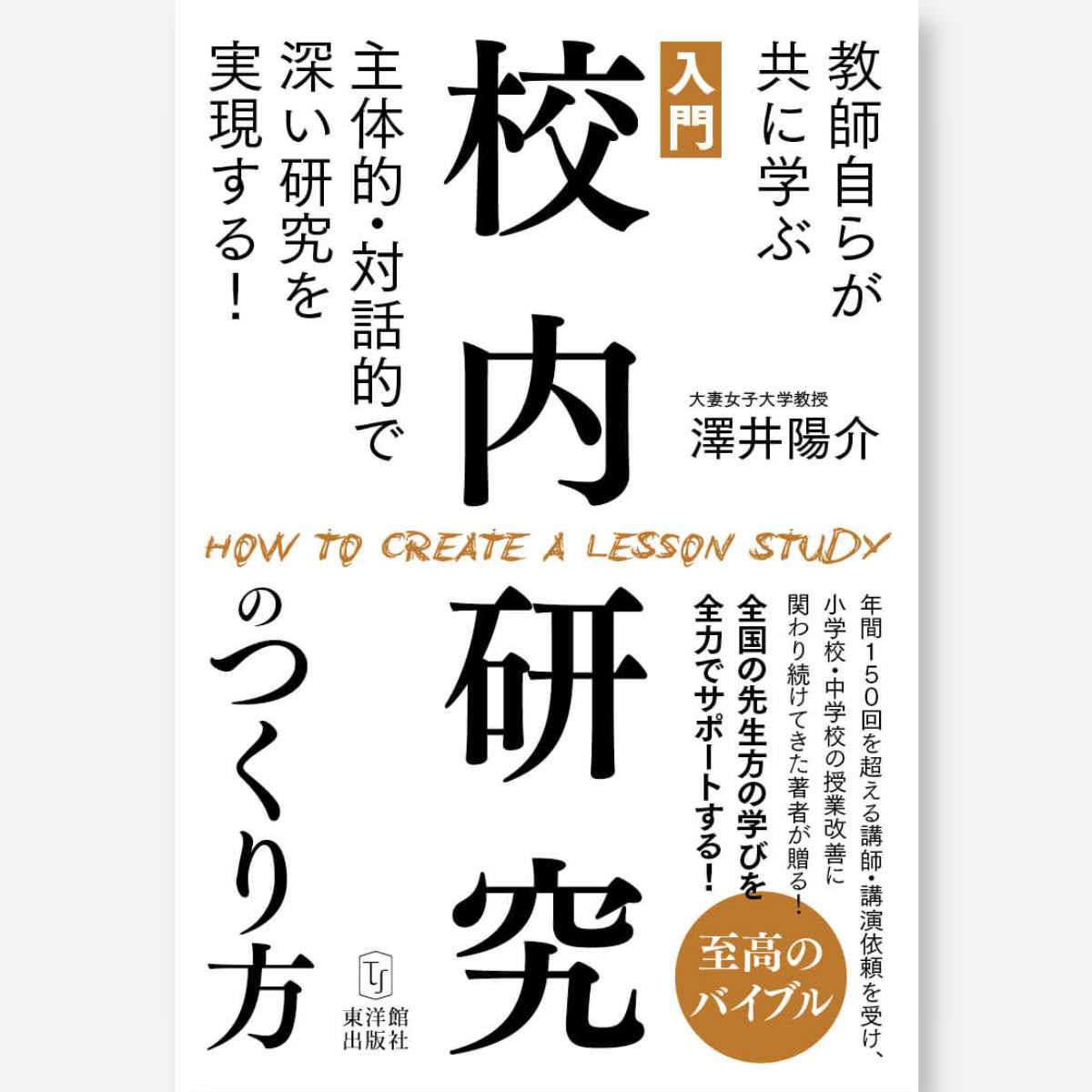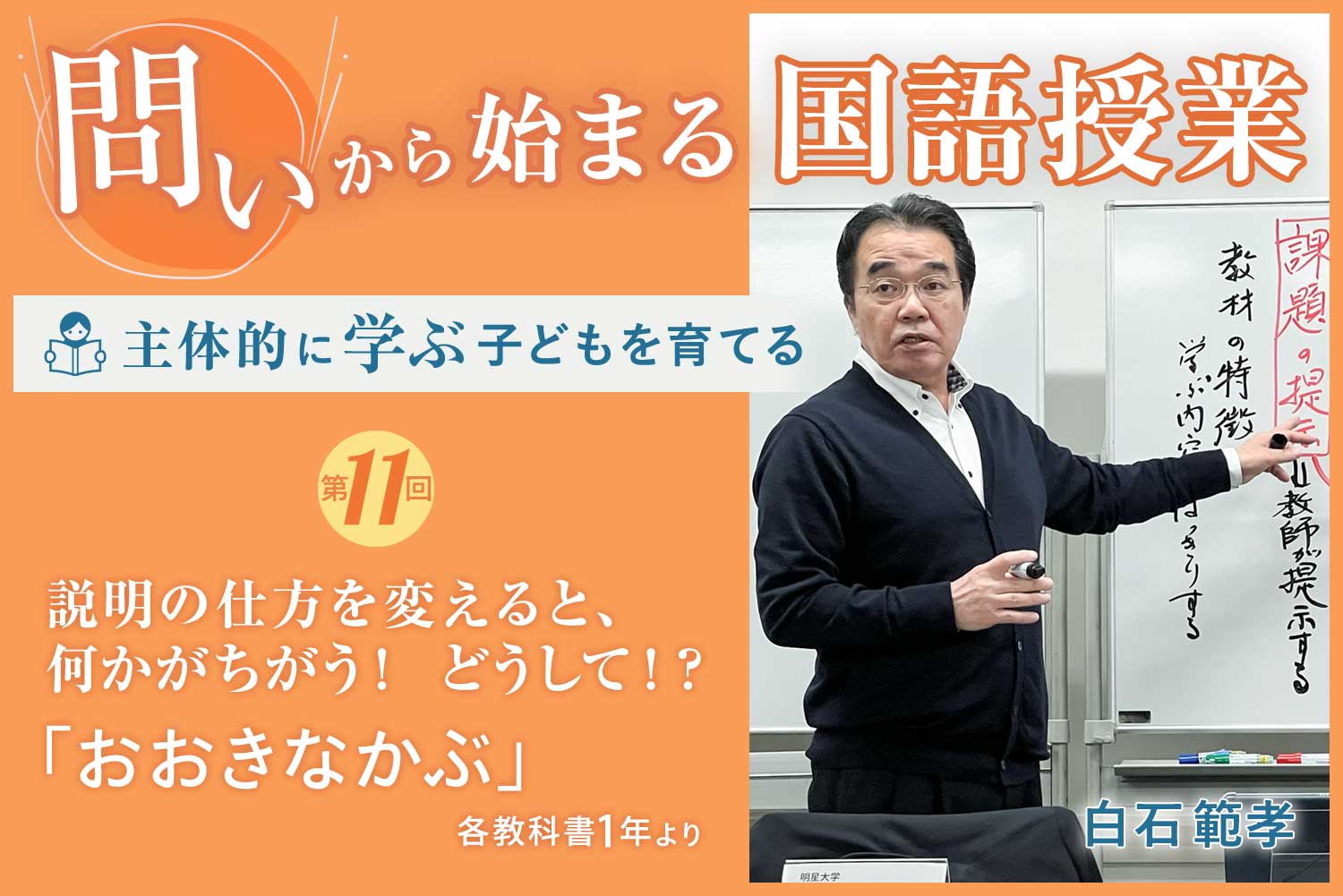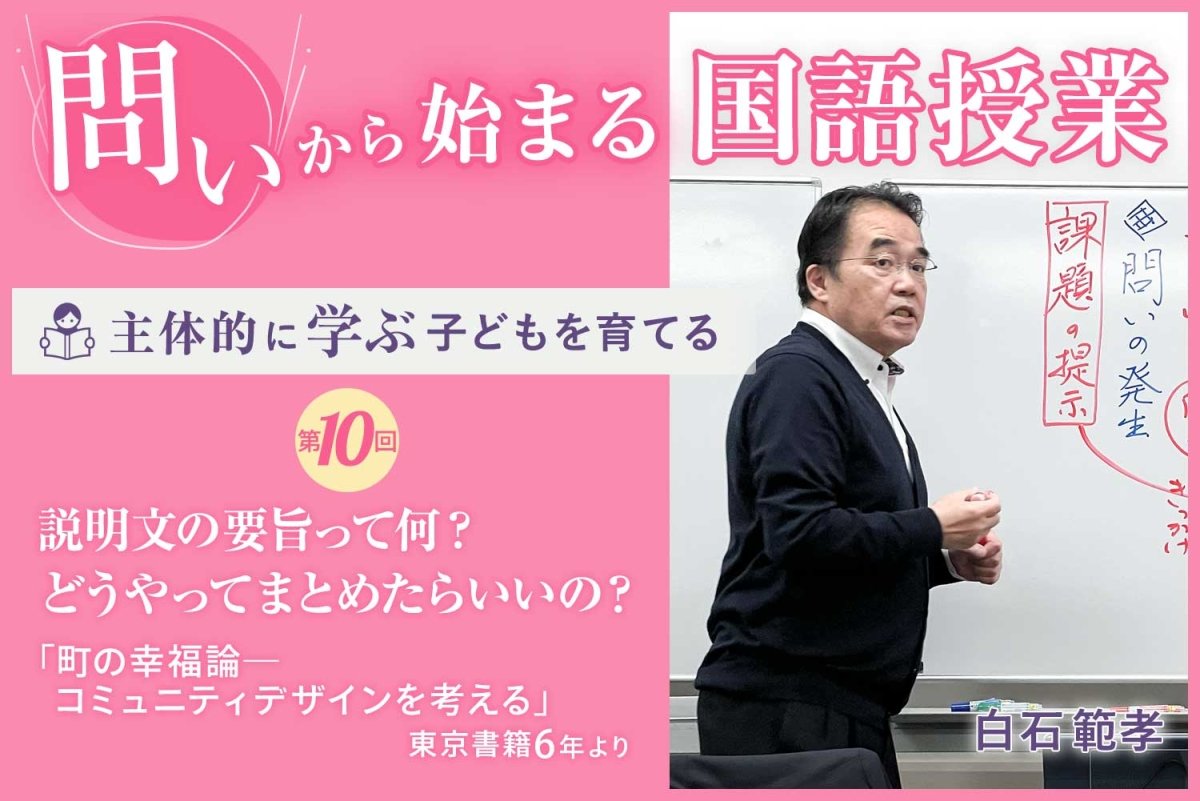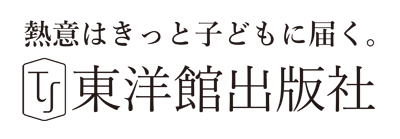フランスと日本の違い① 教育格差を広げないフランスの注力
例えば私の研究しているフランスでも、日本と同様に、一度に登校する人数を減らしたり、登校したら机を離したりして対応していました。給食でもバブル方式がとられていて、食堂で同一の学級同士での黙食などの形が取られました。
ただ、全体の指揮系統の観点で見ると、例えば感染症が少ない地域は登校自粛しないなど柔軟な対応も目立ちました。各教育委員会および校長の判断が優先されていました。人口密度や都市部と農村部の違いを配慮したためです。また何よりも、国民教育大臣(日本の文部科学大臣に当たる)が初動から大事にしたのは、学校は学力保障だけではなく、福祉も担うため、基本的には登校を継続することでした。
この根底には「子どもたちの成長において重要な運動、栄養、コミュニケーションを守る」という考えがあります。一斉休校の場合も、学童などは継続することが求められました。当初から感染率のエビデンスから特に子どもは感染率が低く、重症化しないという点が科学的に確認されたことも大きかったと感じます。あるいは、「エッセンシャルワーカー」の子ども、障がい児童生徒や家庭における生活言語が教授言語のフランス語ではない生徒などには登校の継続を推進するなど特例が認められました。教育環境格差を拡大させないためです。社会的に脆弱な立場にある家庭に手厚い支援体制を維持することが大臣の声明には意識されていたことが印象に残りました。
さらに教員は「エッセンシャルワーカー」に位置付けられ、抗ウイルスマスクの手配、PCR検査やワクチンの優先接種など社会全体で崩れないようにする対応も取られました。日本はマスクすら自前の対応もありましたよね。
フランスでは、国民教育大臣は閣僚内でもナンバースリーに入るほど影響力がある人が就くなど、「次の世代を育成するぞ!」という意識が高いです。教職員組合の影響力の強さもありますが、教育は予算も大きく、教育政策によって政治家の生命が絶たれることもあります。新型コロナウイルス感染症の発生後、学校では対策に人手が必要だということで、即座に非常勤講師が加配されるなど大胆な予算措置が行われました。また、聞いている限り、地域社会、保護者も「子どもを教えるのは先生」という意識が強く協力的という話が多いです。教える専門家という社会的評価が一定程度守られていると感じます。
同時に、フランスも中央集権的ではありますが、例えば、教科書は学校単位でそろえているなど、学校や教師個人の裁量は日本に比べて高いです。学校閉鎖なども状況に応じて柔軟に取っていました。これには、特に初等段階の学校規模が小さく、過疎地域が多いことも関係しております。市民にとって、市町村の役所の次に、正確な科学的情報を持っているのは学校であるという意識があり、教師がその情報源となることと関係しています。
フランスと日本の違い② 国立の遠隔教材の蓄積が力を発揮
フランスも北欧などのICT教育先進国よりは遅れていましたが、このコロナ禍で一気に加速し、しっかりとオンラインで学習を保障する体制をつくったと言えます。過去を振り返ってみると、海外では「電卓」が生まれたときには学校でそれを使っている姿があり、「使えるものはどんどん使っていこう」という気質があったと思います。現在ではスマートフォンも、それで調べ学習が進むのなら積極的に使います。
ただ、今回のパンデミック以前から、不登校やホームスクーラーに向けた国立の遠隔教材が豊富に用意されていたことが功を奏した点は否めません。パンデミックによって、慌てて用意したというよりは、デジタル教育への移行は数十年前から始められていたのです。その使用率は、国や学校(教師)によって違いました。パンデミックは、使用頻度を高めたと言った方がよさそうです。
日本は徹底してICT機器が個人のものとして学校に侵入してくるのを嫌っていたように感じますが、初動が遅れたことの一つの原因だと思います。GIGAスクール構想の加速化でハード面は整いましたが、ソフト面や教師の研修などに遅れが見られます。
今後は、教育のデジタル教材の貿易が激しくなることを、本書の24か国からも見て取れます。フランスのように、デジタル教材は国が中心に用意し、教科書出版等の民間企業の素材と並行して開発がなされる工夫が必要だと感じます。フランスは、国立の遠隔教育センターに加えて、国営テレビ局、ラジオ局、博物館、美術館などとも協働している点が参考になります。教材開発には国立の様々な知恵と工夫が集結するような仕組みが大事です。教育の産業化である営利目的とは異なるロジックが科学知を保障するという百科事典の国らしい教授哲学が感じられます。教師と教育学者による教材の科学的な検証を継続するためにも国による開発事業費を怠らないシステムが肝要と感じます。本書では、ほかにエストニアやシンガポールを参考に別の教育実践と哲学をうかがい知ることができます。
「先生の頑張りへの依存」がもたらす日本の国力のもろさ
改めて思うのは「日本は現場の先生の頑張りに頼りすぎているのではないか」ということです。何かが増えても、先生が頑張って何とか対応する。「できるんだったら」とさらに増える。コロナ禍でも「机の消毒作業」などを先生が行っていると報道がありましたが、これは欧州などでは考えられにくいことです。そして現状の日本では、このことが問題だとハッキリと認識されていないのです。ほかにも平時から本来福祉が担うべきことを学校が行っていることは多数あります。
こうした「先生の頑張り」でなんとか保たれている状況というのは「公教育制度としてのもろさ」です。次世代を担う子どもたちの成長に、大きな影響を与える先生方が疲弊しています。例えば、教員の精神疾患による病気休職者数が高止まりしている現状などが、国民に広くは知られていません。本務である教授に専念すべき時間が十分にさけないのはいかがなものか。
また、一斉指導からの転換期ではありますが、学習面以外でも子どもの個性が認められにくい画一性(「一斉共同体主義」「同調圧力」)が強い。パンデミック以前に海外の教育関係者からよく「日本の教育は分権化されているんですよね?」「行儀良くしすぎていて、軍隊的で怖い」「子どもらしくない」と言われます。子どもたちが似たような髪型、服装をしていて「ここって前のクラスと同じクラスじゃないよね?」と耳打ちされることもありました。
他方で、中学や高校になると授業中に寝ている生徒がいることに驚かれます。欧米のように教育課程を習得していないと原級留置というのが当たり前の国とは異なるためです。この差異は、パンデミック下の一斉休校後の授業時数確保の問題に端的に表れています。本書で取り上げた第2部の8か国では、そうした議論はみられませんでした。むしろドイツなど積極的に原級留置を活用する生徒がいるなど、就学の意味が異なることがわかります。
日本の生徒指導においてのゆとりも少なく、画一的であると、校則の意味を生徒一人一人が説明できないなど、海外から見たときに生徒や教師の説明が理解されにくい点が多いです。一斉休校における各校長、教育委員会の判断は、どの程度議論された結果なのか。基礎疾患あるいは、妊娠中の教職員に対する対応はどうだったのか。濃厚接触者の隔離による「欠席(出席停止)」の措置等についても、どの程度地域の保健所と連携が取れたのでしょう。全国で統一基準を重んじることが公平、公正なのか。ここでも一斉共同体主義や同調圧力、あるいは文部科学省や教育委員会に忖度が働かなかったのか疑問です。子どもの家庭の事情に応じて担任の判断で校長が責任をもって対処することはできなかったとしたら、それはなぜなのでしょう。本書では大阪市の久保敬校長の提言を紹介しております。
本書は、日本のこの1年半を諸外国との比較から相対化する材料を提供しています。日本の学校教育行政や学校内の教職員の努力には、どんな特徴があるのか考える材料となれば幸いです。
この危機を契機に教育を巨視的に考える
世界には、いまだに休校が長引いている国もあります。またワクチン接種・PCR検査等にみる南北格差も鮮明です。2021年末現在においても、ユネスコによれば世界には1千万人(0.7%)の児童生徒が休校によって学習の継続が保障できない状態にあります注1。ユネスコの同統計によると宣言後の2020年3月16日の時点では、6667万人(42.3%)であり、国全体の一斉休校は109カ国に及んでいました注2。その1月後には117カ国とさらに増え、1億人を超える児童生徒が登校できなくなります。この時点から編者が最も懸念したことは、アフリカ、南米、アジアと北米、オセアニア、欧州、東アジアの一部との学習権の格差拡大にありました。
マスク外交から、ワクチン外交へと格差が鮮明になることは、現在の国際情勢から予測され、デジタル教育への切り替えにも、デジタル先進国のノウハウが輸出されることになり、教育という極めて内政・文化にかかわる事項にまで踏み込んだ教育産業の貿易「新たな植民地化」が強まることに危惧したからです。本書でパンデミック宣言後の、各国の初動を明らかにすることで、そこでみられた教育課題は、近代化の象徴である公教育(学校)の長所と短所を浮き彫りにしました。その内実は、受益者側である子どもや保護者、学校に携わる教職員、教育行政官、教育研究者などの声として第1部(全26章)にまとめました。より政策動向と教育行政に焦点を当てた8か国(ドイツ、スペイン、スウェーデン、フランス、イギリス、シンガポール、ブラジル、日本)については第2部に収めました。2部構成とすることで学校現場から研究者まで読者層を広げ、パンデミックがもたらした未曾有の教育危機に世界の教育現場はどう立ち向かったのか巨視的で複眼的に考えることを試みました。
注1 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse (2021年12月30日閲覧)
注2 例えば、ユネスコのこの統計において、日本は国からの要請であったため、全国休校の国として数えられていない。