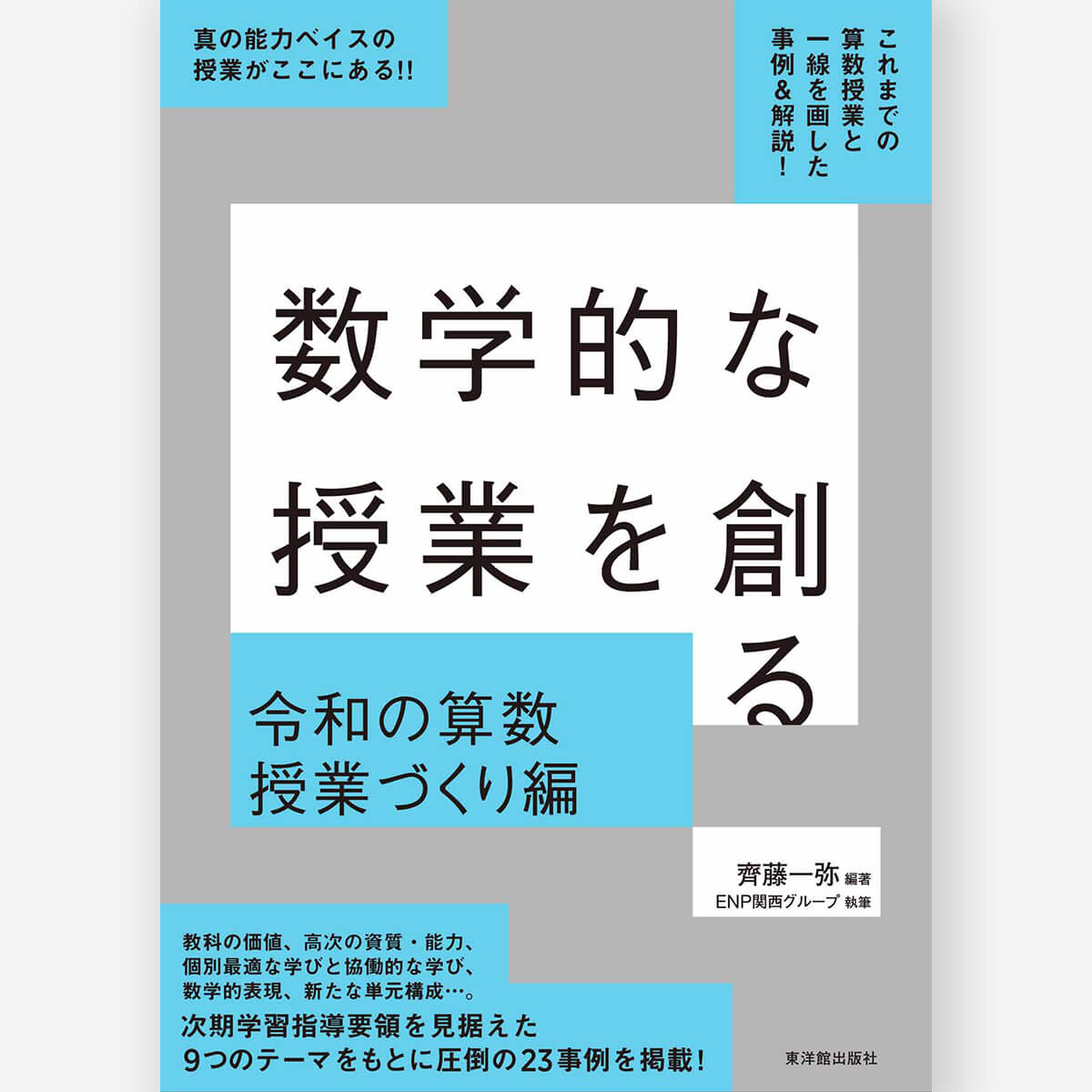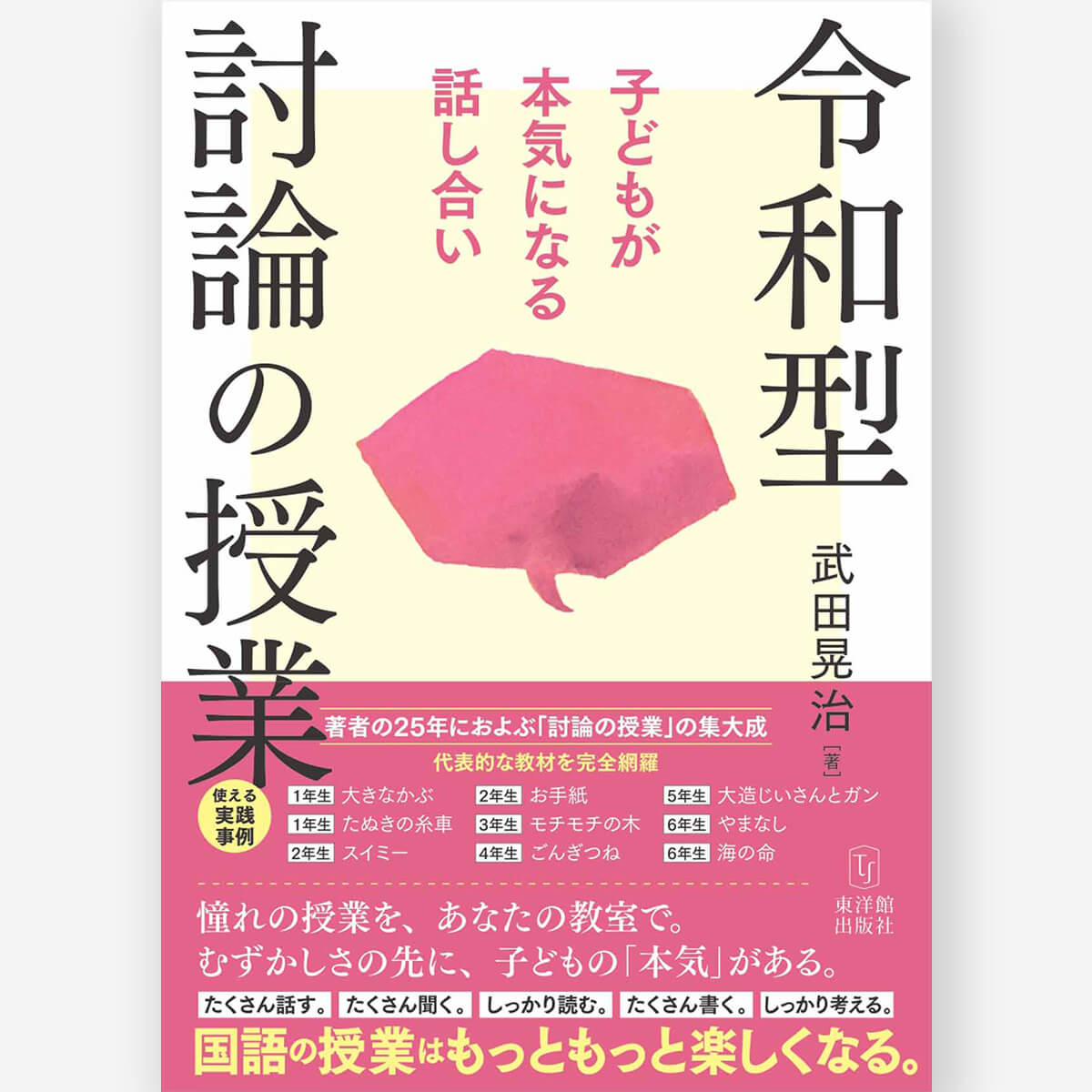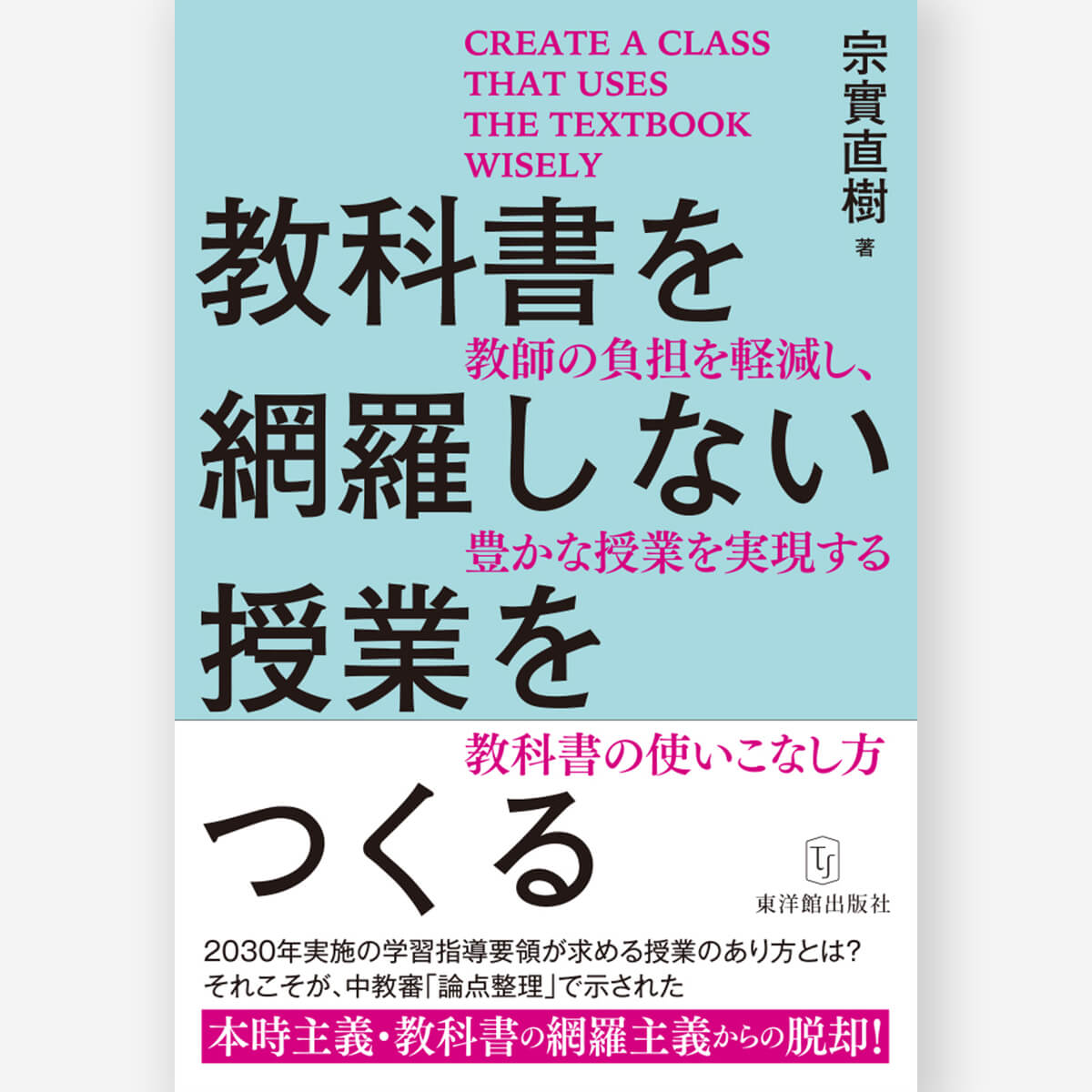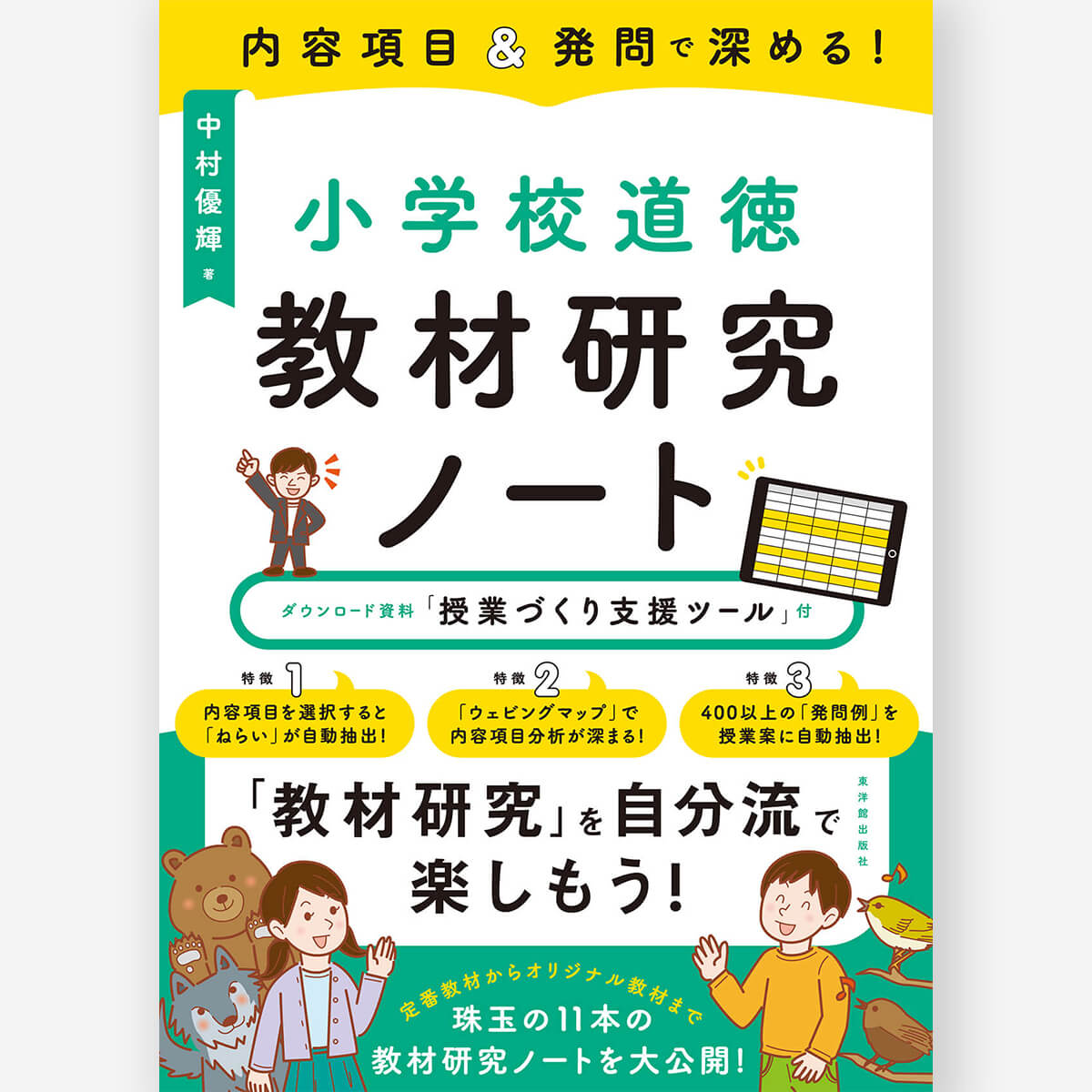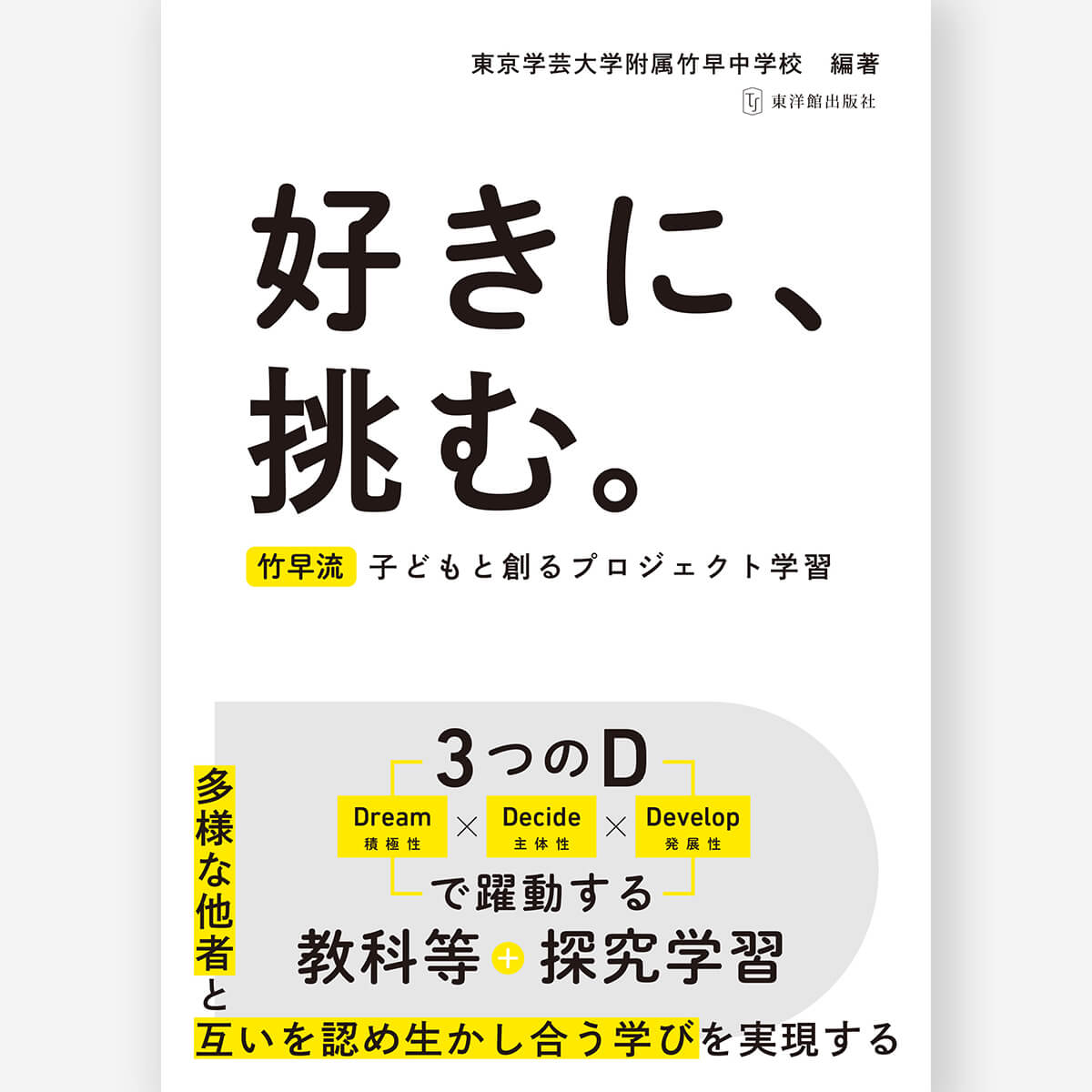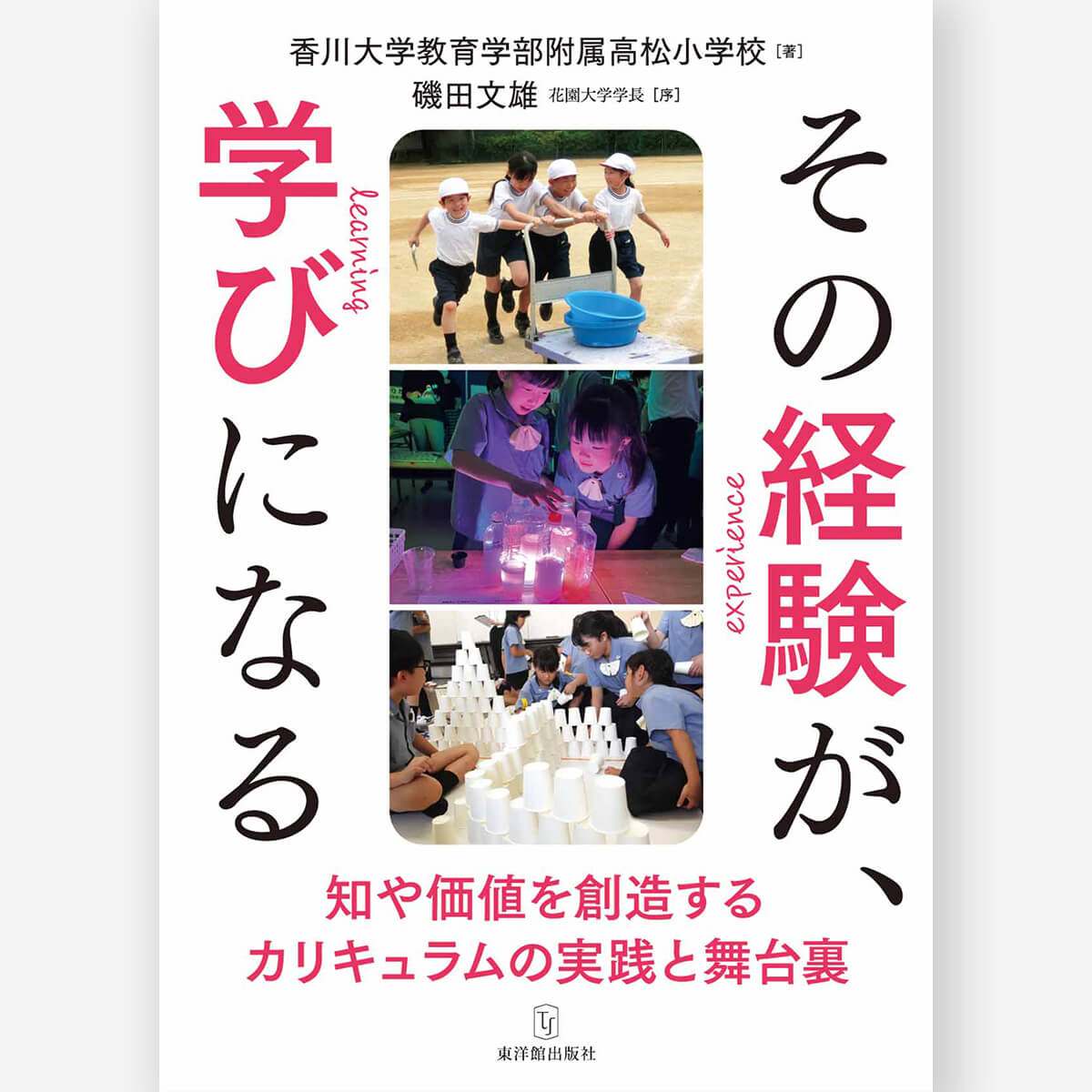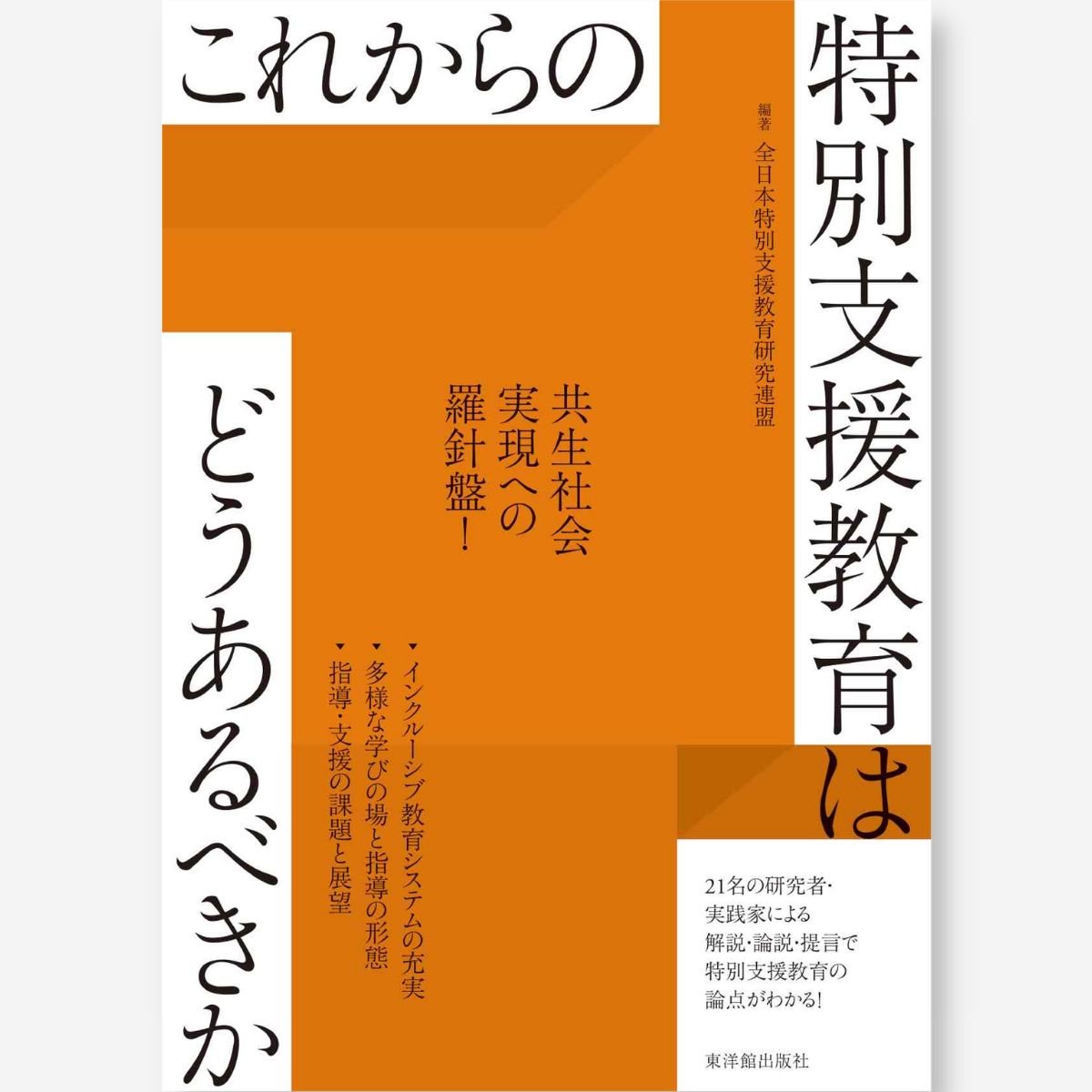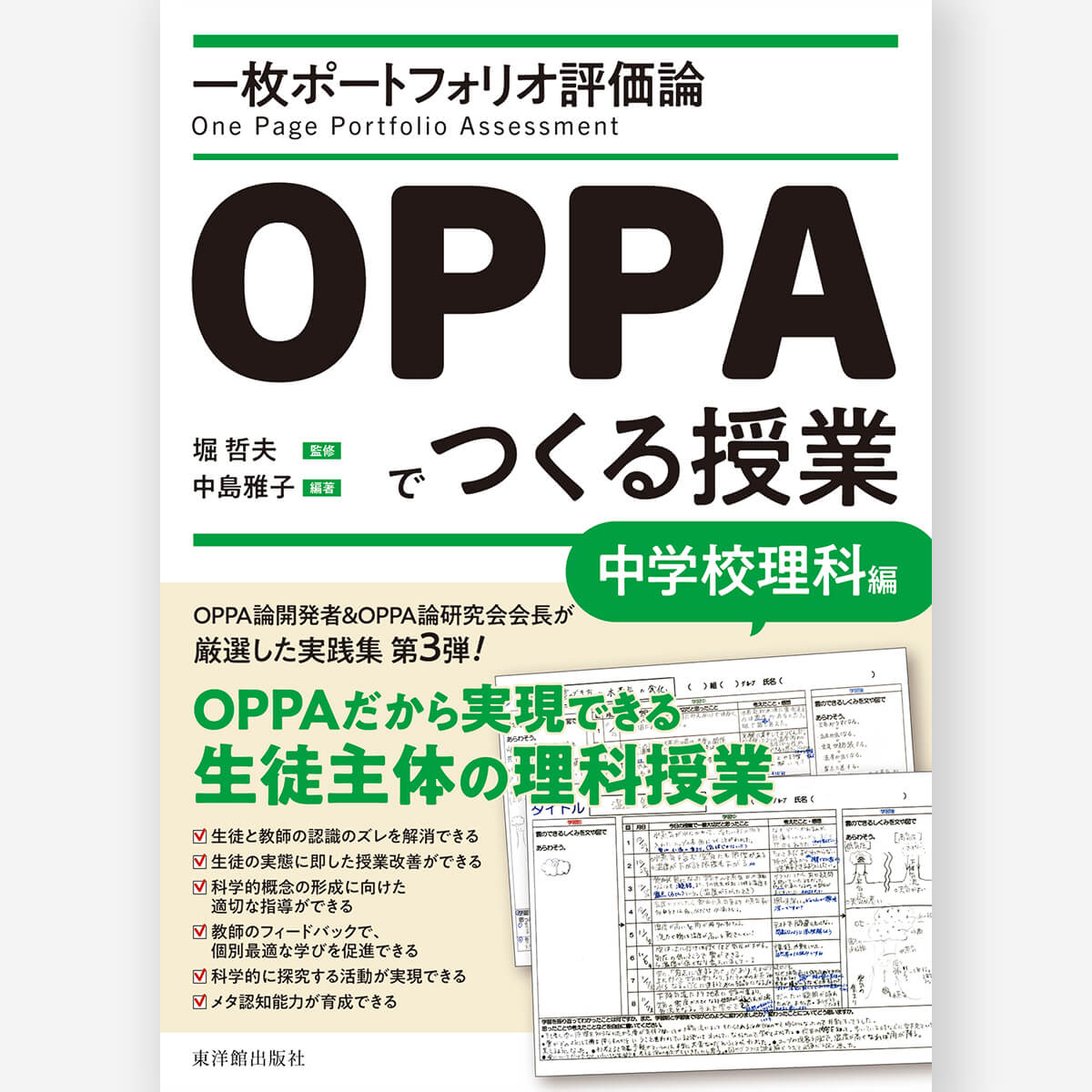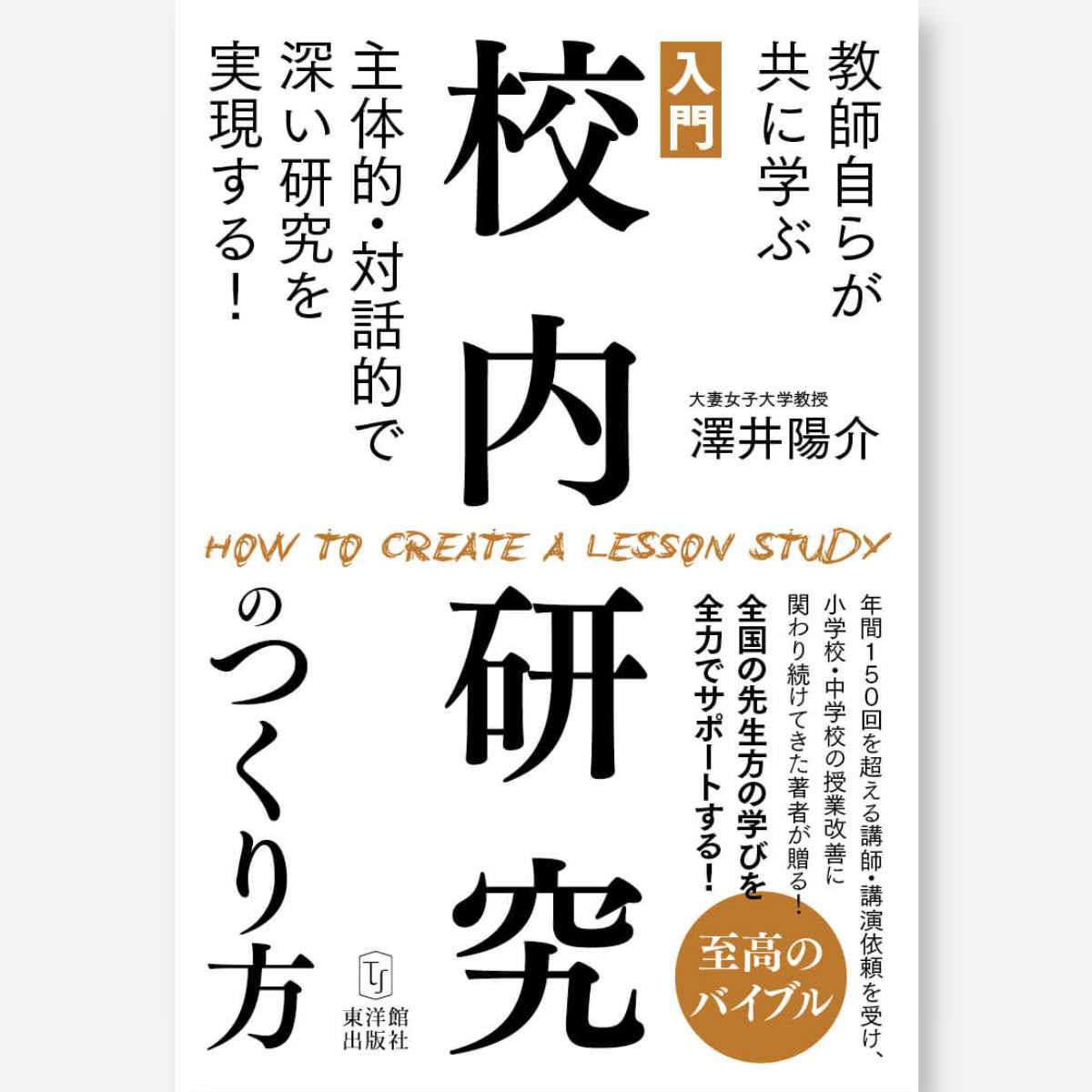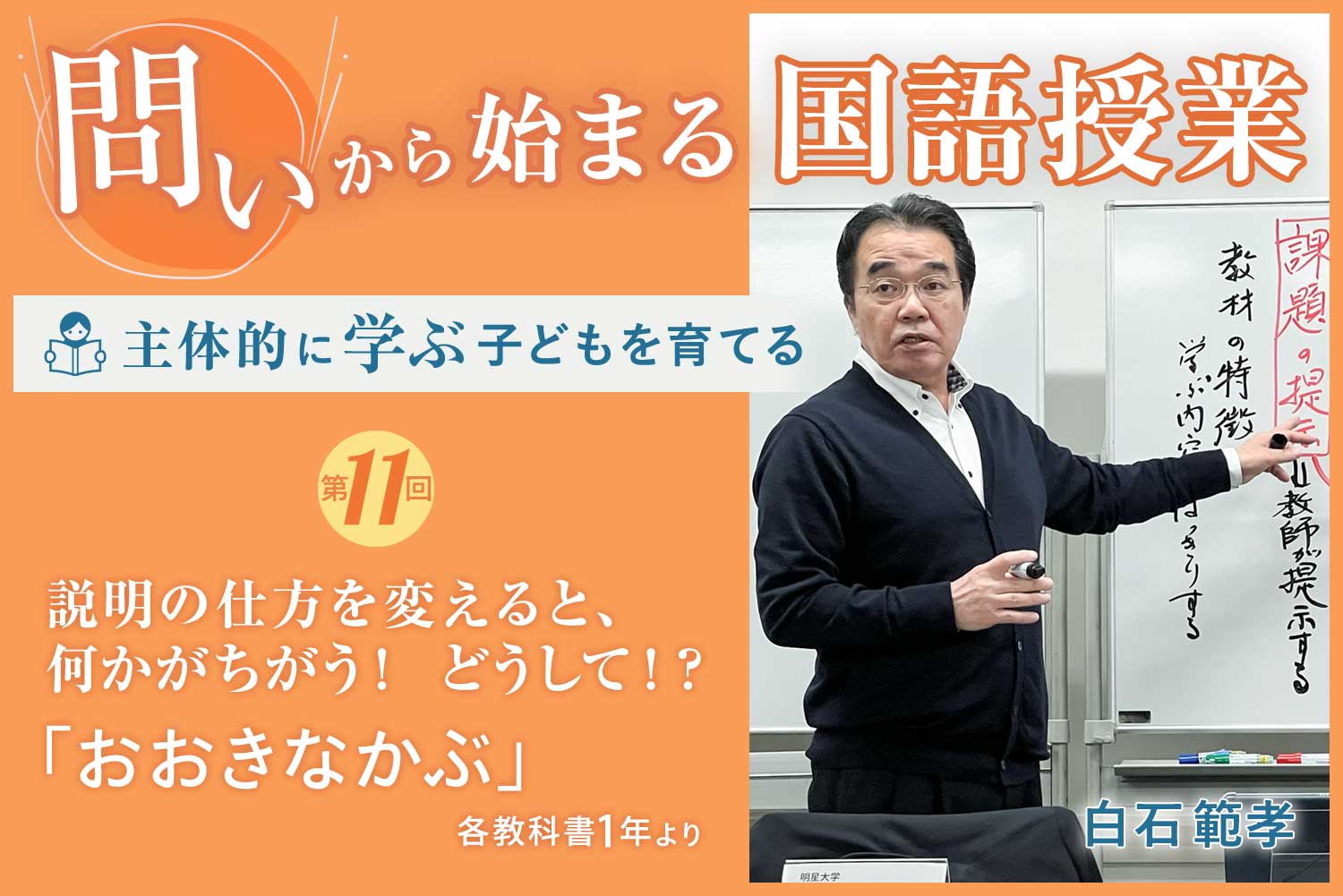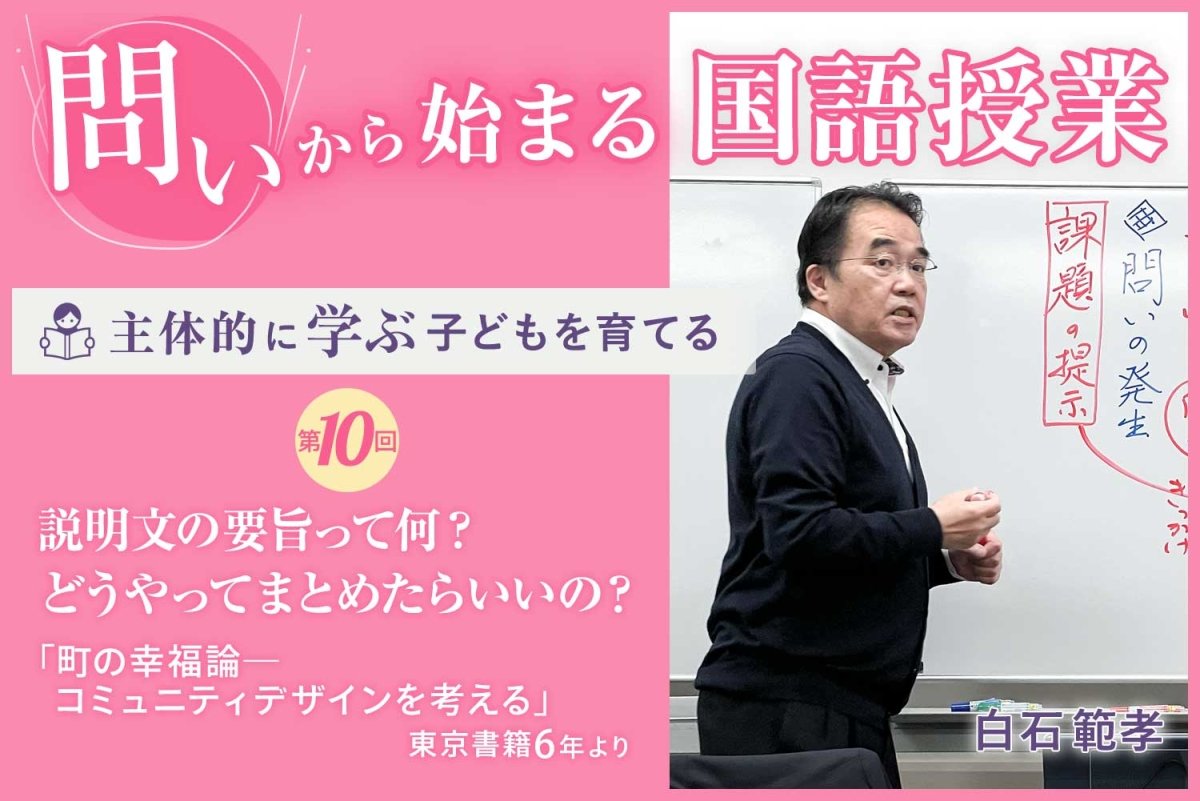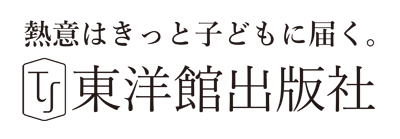はじめに
みなさん、こんにちは。内田樹です。
本書は2020年の夏から2021年の3月まで3回にわたって行った教育についての講演を書籍化したものです。
もともとは日本各地に赴いて、現地の学校の先生たちを前にして、僕が講演してから、フロアの先生方と対話をするという旅もの企画でしたが、ご承知の通りに、感染症拡大のために対面での講演が難しくなり、ツァー計画は放棄せざるを得なくなりました。代わりに神戸の凱風館(僕が主宰している道場・学塾)で行うことになりました。10人から15人ほどの聴衆においで頂き、その方たちの前で僕が2時間ほど話をして、それから質疑応答をするというやり方です。とりあえず、「人前で話す」というかたちは整えることができました。聴講者の募集・会場の設営・録音・文字起こしなどは東洋館出版社の刑部愛香さんに仕切って頂きました。お骨折りに感謝いたします。
「複雑化の教育論」というタイトルも刑部さんの提案です。どこかで僕が「教育の目的は子どもたちの成熟を支援することであり、成熟とは複雑化することだ」と話したのを聴いてくださって、「複雑化」という語が印象に残ったようです。
まえがきとして、そのタイトルの意味について少しだけ思うところを書いておきたいと思います。
成熟すると複雑になる
たしかに教育を語る人の中で「子どもたちがより複雑な生き物になることを支援するのが教育の目的だ」というようなことを主張する人はあまりいません。知識が増えるとか、感情が豊かになるとか、コミュニケーションがうまくなるというようなことを「成熟」の指標にとる人は多くいますが、「前より複雑な生き物になった」ことを成熟の徴として言祝ぐというような人はあまり見たことがありません。
「前より複雑な生き物になった」場合、子どもたちはこれまで見たことのない表情を浮かべ、聴いたことのない語彙を用いて語り始め、これまでしたことのないふるまいをするようになるわけですけれど、子どものそういう変化を見て、もろ手を挙げて喜ぶ……という親も教師も、あまりいなさそうです。たしかに、昨日までとは違う人間を相手にすることになるわけですから、当惑することはあっても、喜ぶというリアクションはあまり期待できません。でも、僕は子どもの複雑化を素直に喜ぶことは大人のたいせつな職務の一つだと思います。
別人になった子どもに向き合う大人より、別人になってしまった子どもの方がずっとたいへんだからです。一番当惑しているのは本人です。「昨日までの自分」のままではいられないというのは、自分の意志では統御できない変化なんです。生物の幼生がそれまでの殻を脱ぎ捨てて、次の段階に変態するようなものです。自分の意志でそうしているわけではありません。そうせずにはいられないのです。でも、複雑化したからと言って、子どもは「昨日より幸福になる」わけでもないし、「昨日より自由になる」わけでもないし、「昨日より強くなる」わけでもありません。長期的に見ればそうなる確率は高まるのですけれども、即席な効果は期待できません。複雑化した子どもはただ「昨日より複雑になる」だけです。
でも、そういう複雑化プロセスを連続的に繰り返す以外に子どもたちが成熟する道筋はありません。だから、教師も親も、周りの大人たちは決然として子どもの複雑化を支援するという立場を選び取る必要がある。僕はそう考えています。
計測不能な「複雑化」と向き合うこと
どうしてわざわざ「複雑化」なんていうあまり教育現場で使われない言葉を僕が持ち出してきたかというと、複雑化というのは数値的に計測することができないものだからです(まったくできないわけではありませんが)。
複雑化は計測不能である。それがとても重要なことなんだと思います。
長さも重さも大きさも、ちゃんとそれを計る「ものさし」があります。でも、複雑化を計る「ものさし」は僕たちの手元にはありません。
複雑化するときに起きているのは量的な変化ではありません。それは「表情の変化」「手触りの変化」「雰囲気の変化」というようなものです。表情が深くなる、声の厚みが変わる、身動きの分節が変わる。
変化が生じている以上、精密な計測機器があれば計測可能なんでしょうけれど、僕たちの手元には「できあいのものさし」がありません。ですから、子どもたちの複雑化を計測しようとしたら、「ものさし」はその場で手作りしなければならない。簡単な仕事ではありません。
「複雑化する子ども」に向き合い、その成熟を支援するというのは、周りの大人たちに集中力と発明の才を要求する、まことに骨の折れるプロセスなんです。
でも、それでも僕は子どもたちの成熟の指標として、「複雑化」ということをできれば最優先に掲げたいと思っています。
あらゆる社会制度について言えることだと思うのですけれど、その制度を利用する人たちの市民的成熟を要求する制度は「よい制度」です。例えば、民主制がそうです。独裁制なら「賢い独裁者」に丸投げして、市民たちは「鼓腹撃壌(こふくげきじょう)」して、わが身のことだけ考えていればよい。市民が「子ども」でも独裁制は機能する。でも、民主制ではそうはゆきません。「公共の福祉」を配慮して、そのために自分に何ができるかを考える「成熟した市民」が一定数いないと民主制は機能しません。民主制はメンバーに「大人になってくれ」と懇請する制度です。その遂行的な力ゆえに民主制は他のどの制度よりもすぐれていると僕は思っています。
教育制度も同じです。僕は社会制度をどれも同じ基準で評価します。その制度をきちんと機能させるためには、制度運用者たちの(全員とは言いませんが)一定数が「まともな大人」であることを必要とする制度は、運用者たち全員が「幼児」でも運用できる制度よりもよい制度です。僕はこの基準だけは譲りません。運用者自身に成熟を要求する制度が、子どもたちを成熟させる制度としては最も「できがよい」ものである。僕はそう信じています。
教育にかかわる「一定数のまともな大人」の頭数をひとりでも増やしたい。それが僕がこの本を書いた最大の動機です。分かりにくい話だということは分かっていますが、本書を最後までお読み下さったら、きっと僕が言いたいことはみなさんにもお分かりいただけると思います。では、また「あとがき」でお会いしましょう。
(本記事の小見出しは、編集者が追記しました。)
教育を支える出版社として
1948年の創業以来、教育書の専門出版社として、主に学校教育に関わる出版活動を続けて参りました。学術書から実用書まで、教育書という分野において確かな地盤と実績を築いてきたという自負があります。
一方で、社会の大きな変化と、それに合わせた学校教育を含む教育情勢の変化も感じて参りました。創業前年の1947年には最初の学習指導要領が作成されました。当時はまだ「試案」という形で、戦争を省みる言葉とともに、子どもの興味や関心を大切にする児童中心主義の教育観が打ち出されました。
それから約70年が経ち、変わらない本質的な部分は現代に引き継がれつつも、全国の小中学校の9割以上に一人一台端末が配備され、授業風景が大きく変わろうとしています。学校から目を転じてみると、生産年齢人口の減少や科学技術の革新、地球規模での気候変動といった今まで人類が経験したことのない局面に直面しています。そのような変化の時代において、未来を生きる子どもたちのために、教育を支えるすべての人のために、何かまだできることがあるのではないだろうか――そのような思いから、本シリーズを新たに2022年より刊行いたします。