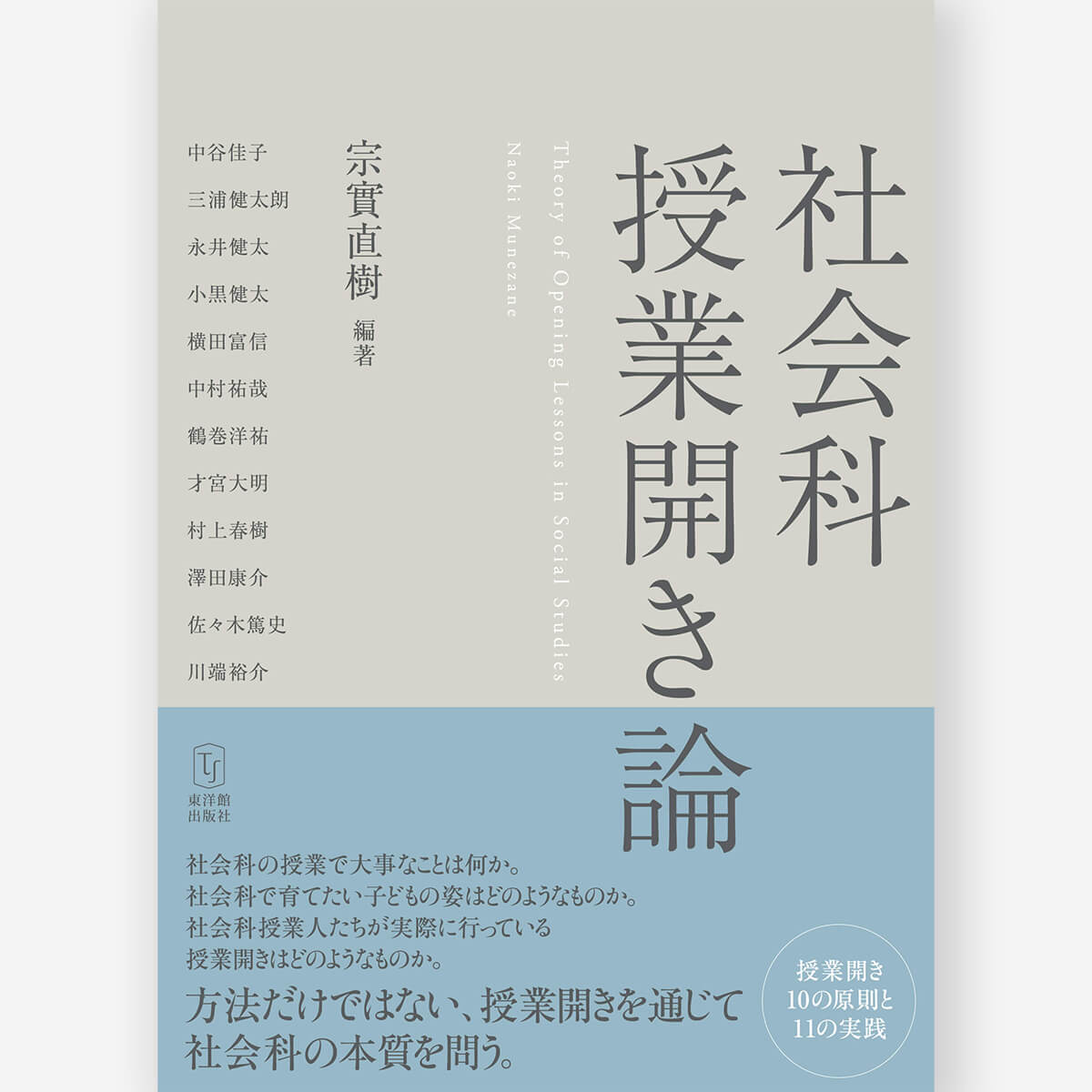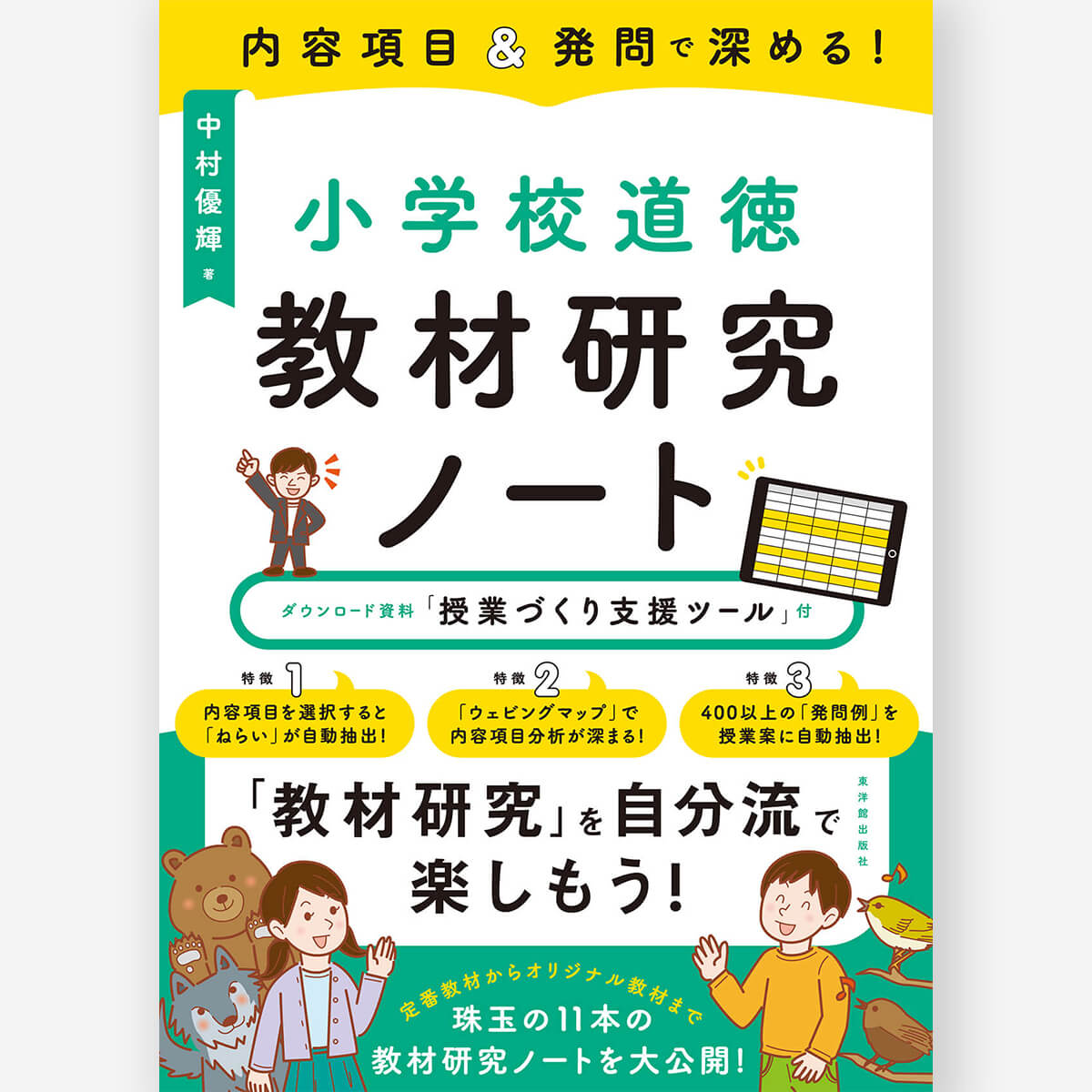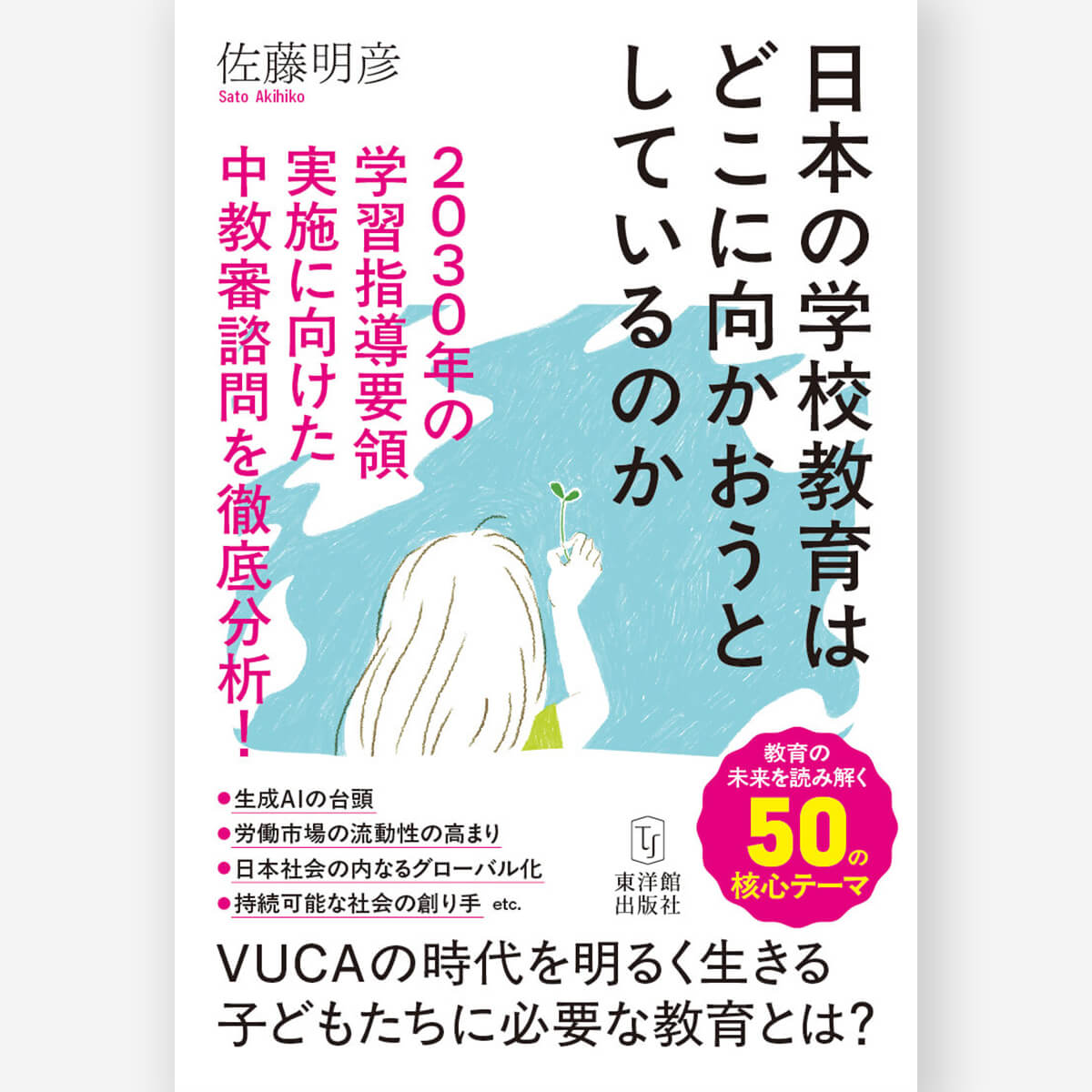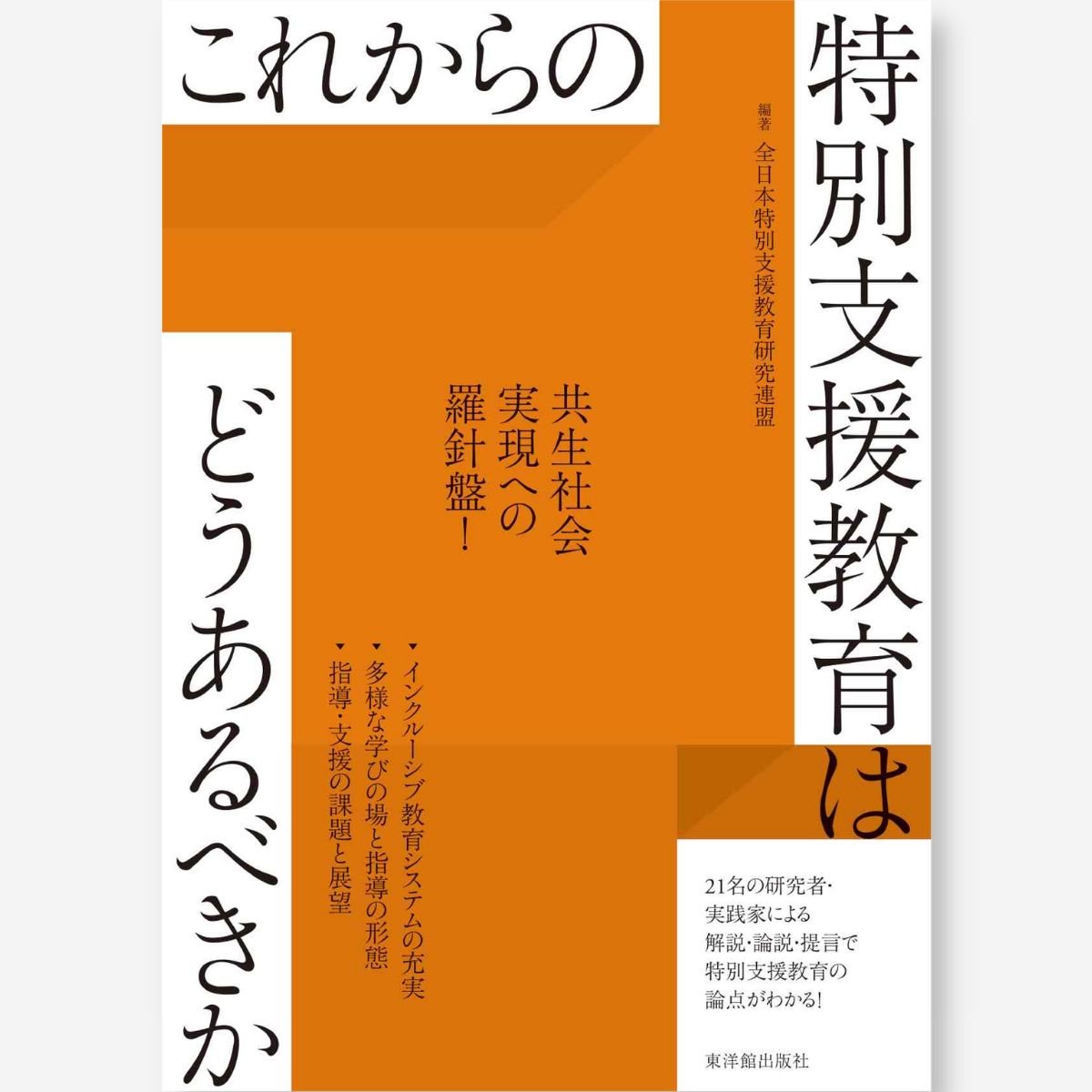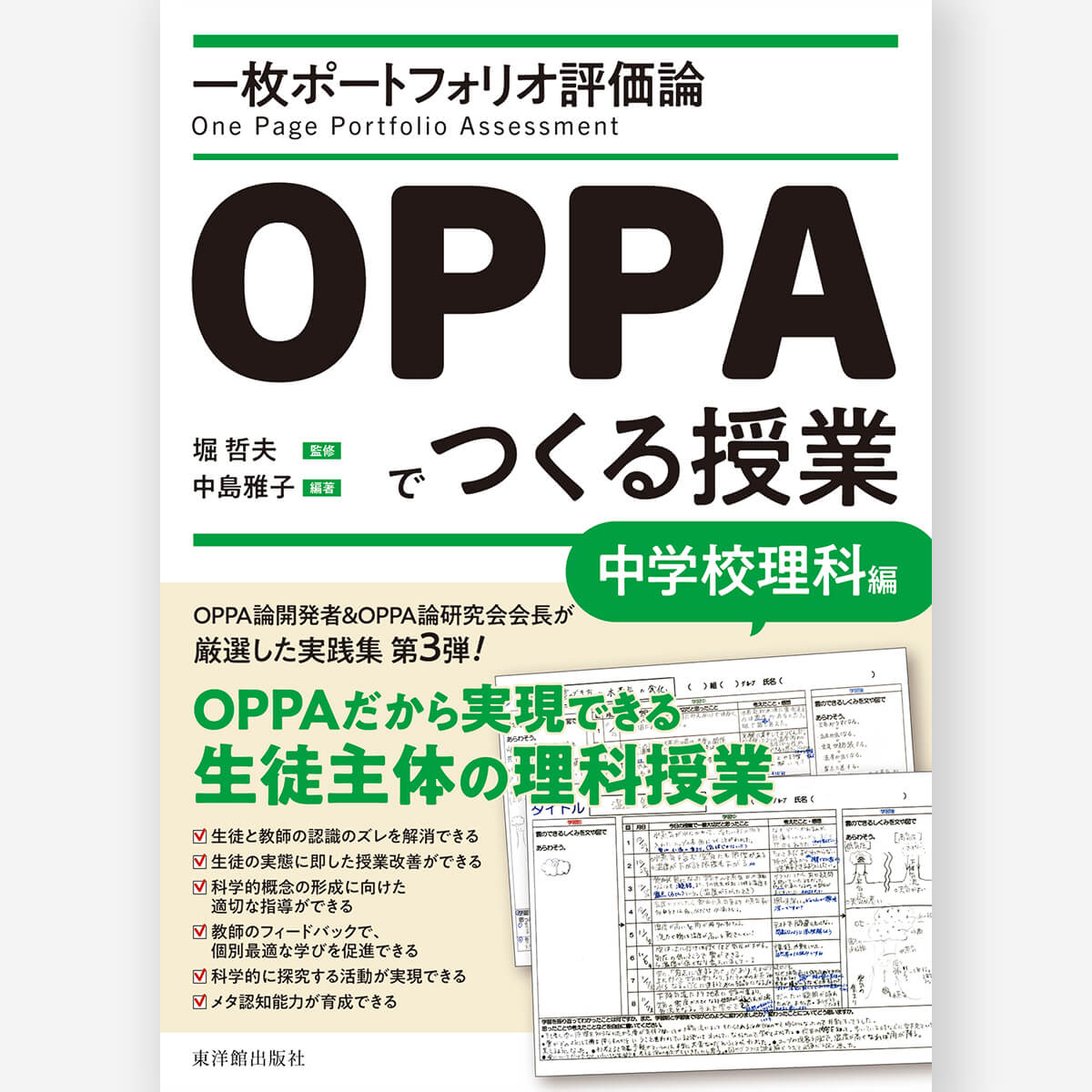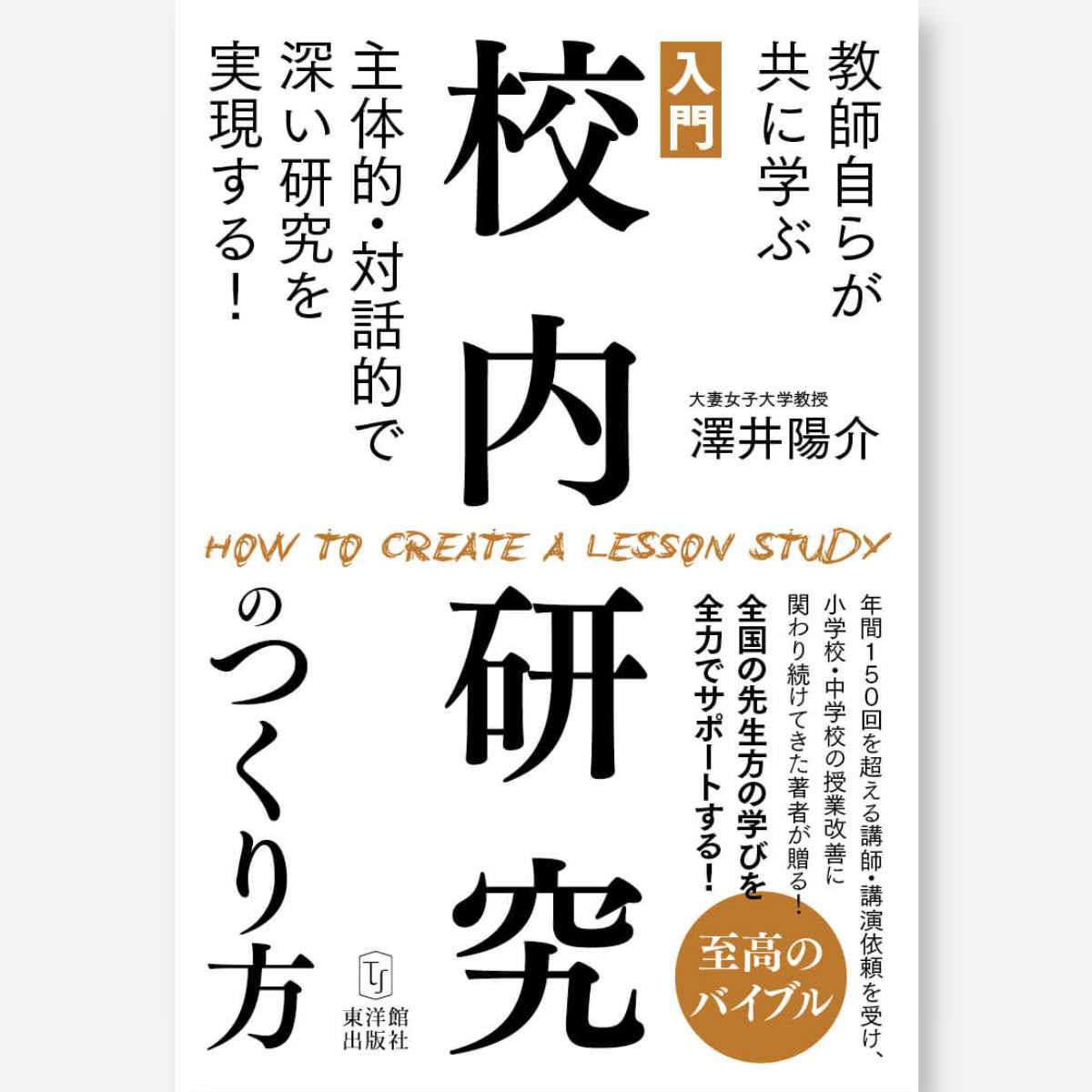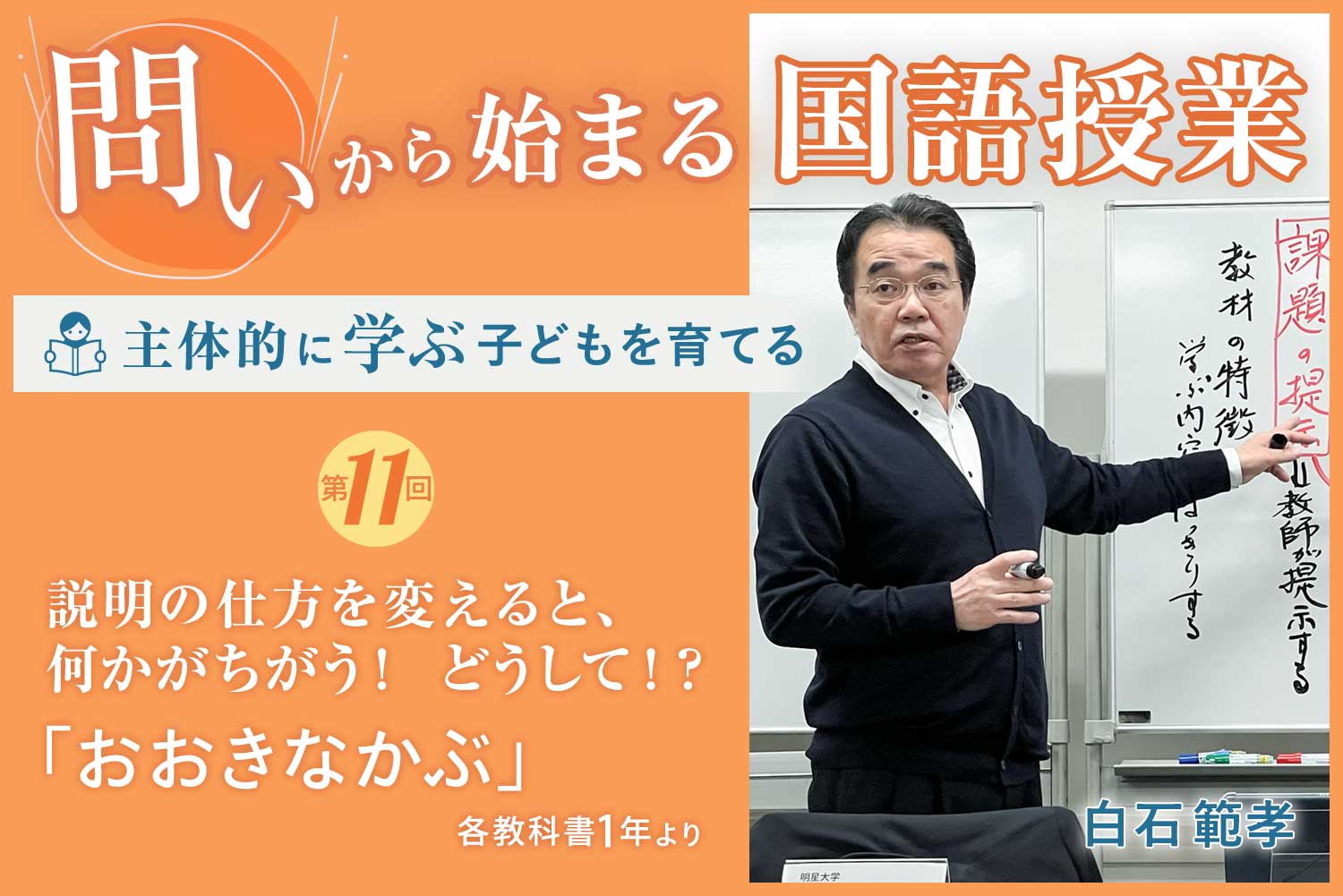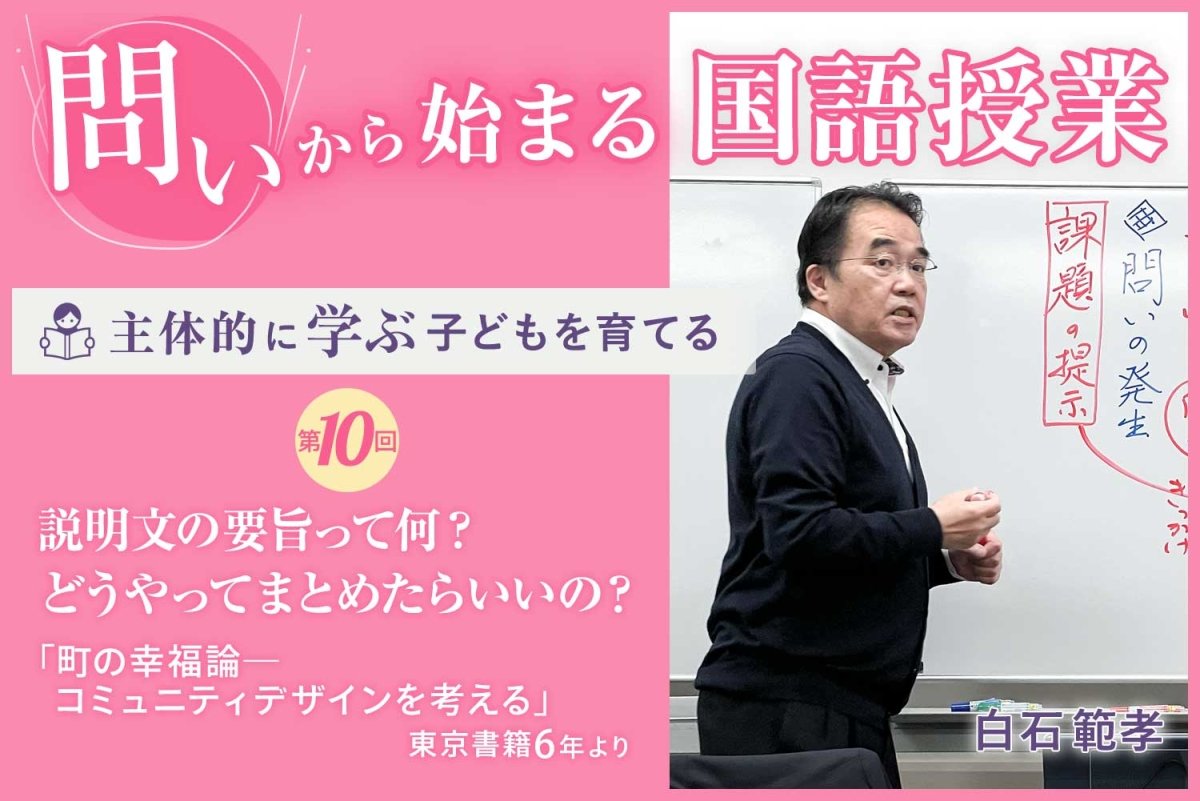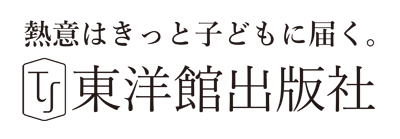休校にしたくてもできなかった国家事情
得体の知れない強毒ウイルスが世界に広がる中で、スウェーデンは特異な対応をとってきた。フランスやイタリアなどでロックダウンが始まり、おびただしい数の遺体が安置される場面や、軍隊が出動して市民の移動を規制する映像が報じられる中にありながら、スウェーデン政府はマスクの着用を推奨せず、若い人はなるべく普段通りに行動するようにアナウンスしていた。全国的な学校閉鎖も行われず、海外からは「ノーガード戦法」や「集団免疫戦略」と揶揄され、そのユニークな対応は賛否両論を呼び、大きな注目が集まっていた。
とはいえ、スウェーデンの人々がまったく楽観的だったわけではない。当初から新型ウイルスの危険性を訴える医療関係者は多かったし、自主的に感染対策をとる人もいた。スウェーデン政府も新型コロナウイルスを「社会的脅威」と位置づけ、市民の生活と健康、仕事を守ることを最上位の目標として緊急対応に取り組んできた。それでも、スウェーデンが全体的に「緩い」対応に留まっているのは、民主主義を尊重しているからに他ならない。大統領制の国では、超法規的に軍隊を動員したり、一時的に市民の自由を制限したりすることもできるだろう。しかしスウェーデンは日本と同じ議院内閣制で、首相の権限は法の支配下にある。それゆえ、多くの感染対策は強制力を持たず、「要請」や「勧告」といった「お願いベース」でしか進められない。加えて、日本のように同調圧力が強い社会ではないので、市民の一人一人が考え、バラバラに対応することになる。
スウェーデンではプリスクールや基礎学校(日本の小中学校に相当)の一斉休校は行われなかった(高校と大学、成人教育については、WHOのパンデミック宣言後すぐに全面オンラインに移行した)。このような対応も、一方では子供たちの教育を受ける権利の保障や、社会的養護のためという理由があるが、もう一方では、上記のように休校にしたくても全国一斉の措置が「できなかった」という側面もある。
「ノーガード」の学校がはじまる
コロナ禍のスウェーデンの学校は、日本から見たらほとんど感染対策がされていない、「ノーガード」の状態に見えるだろう。教職員は次々に感染したが、病み上がりで復帰した教員たちは「これで抗体ばっちり」と冗談を言い、感染済みの教職員同士で楽しそうにハグする姿も見られた。担任の欠勤が相次ぐ学校では、教室はカオスになっていたが、それでも子供たちはマスクなしで通学バスに乗り、密な教室で普段通り授業を受けていた。子供の感染が気になる親は学校を休ませたりすることもあったが、それも初期のわずかな期間だけで、ほとんどの家庭は季節性インフルエンザと同じように、罹ったら休み、治ったら戻る、というだけの対応だった。子供に消毒液を持たせようとしても、薬局では早くに売り切れていたし、マスクも手に入らなかったので、それくらいしかできないということもあった。
ただ、管理職はかなり緊張していたようだ。日本での一斉休校が報じられると、スウェーデンの新聞から筆者に取材があった。その記事を読んだ多くの管理職から、個人的に細かな質問が届いた。休校中のオンライン授業はGoogle Meetでやっているのか、Zoomでやっているのか、その時の児童生徒の個人情報の扱いにマニュアルはあるのか、といったことから、消毒液の濃度について日本には基準があるのか、足りなくなったらどうしているのか(薄めて使っているのか)、とか、休校中にも教職員は出勤しているのか、給食はどうやって提供するのか、通学バスは運休するのか、何かいいオンライン教材(プリント教材)はないか、といった、日々の具体的なことを知りたがっている様子だった。誰しも未経験のため、感染者数抑制に最も成功している日本から学びたいという意識だったと思う。
全国一斉の休校こそしなかったスウェーデンだが、実際には多くの学校や地域で学校閉鎖が起こっていた。そのほとんどは、子供たちの感染防止ということではなく、教職員の欠勤が多すぎて授業が成り立たないという事情によるものだった。ここで学校閉鎖と表記するのは、あくまでも学校施設を閉じて、授業はオンラインで提供していたためである。中には、子供たちは教室に来て、先生が自宅からオンライン授業をするという場面も見られた。また、エッセンシャルワーカーの子供や特別な対応が必要な子供などは普段通り預からないといけないので、全面的に閉鎖となるケースは限られていた。給食も工夫して提供された。
こうした混乱の中で、管理職は次第に疲弊していった。「抗体ばっちり」と快気祝いをする先生たちを横目に、欠勤者の補充(非常勤講師の手配)に追われ、消毒液などの備品をかき集め、対策会議に出席し、個別に対応が必要な家庭と連絡を取る…。感染が心配な職員や保護者からは対策が「ぬるい」と突き上げを食らい、国や自治体からは「仔細は学校で判断せよ」という通知が届く。普段でさえなり手のいない管理職だが、輪をかけて負担が増した。コロナに罹った管理職が、療養からなかなか復帰できずに、不在となる学校もあった。
国王の一声
パンデミックが長期化する中で、政府に対する批判も出始めた。マスク非推奨を貫いてきた公衆衛生庁が方針を転換し、公共の場ではマスクをつけるように「勧告」しはじめ、県域をまたいだ移動を制限するために鉄道の座席予約を絞ったり、遠距離バスを欠便させたりするようになっていった。大人数での集会も禁止された。イギリスのロックダウンのような強い制限ではなかったものの、じわじわと他国の対応に寄っていった。
大きな転機と捉えられるのは、2020年末に国王が「我々は失敗したと思う」と述べたビデオが公共放送で流れたことだった。様々な意見がある中で、国民が意思決定のよりどころにしていたのが「科学的なエビデンス」だった。政府が国民に説明する際には、必ず根拠となる学術論文や報告書を引用し、最新のデータに基づいて客観的に判断していることを強調していた。若い人は重症化リスクが少ない、国境を閉じてもいずれ感染は広がる、マスクをつけても近距離で話せば感染は起こりえる、一斉休校が感染抑止になるエビデンスはないし、子供たちにとってデメリットの方が大きい、といった判断には、すべて根拠が付されていた。
しかし、結果的に多くの犠牲者を出したことは、これまでの対策の妥当性をどれだけ説明しても覆せない事実でもある。王室でも感染者が出た経験もあり、統計的な数字を見て有効かどうかという視点ではなく、亡くなった方々とその関係者へのいたわりが求められていると感じたのだ。
「内実は日本とそれほど違わない」
2021年の秋には、スウェーデンの高校や大学は対面での授業を全面的に再開した。ワクチン接種も進み、一般的な規制も撤廃されて、もはやポスト・コロナの時代に入ったかに思われた。しかし、いま(2022年2月)はオミクロン株の広がりで、再びオンライン授業に戻っている。
スウェーデンの学校では、かねてよりICTを積極的に導入していたので、オンライン授業のハードルはそれほど高くなかった。メディアのインタビュー記事でも、「日常はそれほど大きな変化はなく、大部分は普段通りだ」と答える教員もいる。子供たちは以前から個人アカウントを持っていたし、キーボード入力に不自由はない。それでも、オンライン授業に抵抗感を持つ教員はいる。せっかく対面に戻ったところで、またすぐにオンライン授業になり、がっかりしている人は結構いるし、ICTが得意な先生とそうでない先生との温度差は日本と同じように存在する。
当初は「ノーガード戦法」と言われたスウェーデンだが、時間がたつに従って、そして、現地の事情を知るにつれて、その内実は日本とそれほど違わないのではないかと筆者は感じるようになった。考えてみれば、全世界で一斉に学校が閉鎖される、という事態は近代の学校制度が世界に広まってから初めての経験である。そして、人の移動が制限されているにもかかわらず、他国の情報がこれほど共有されるというのも初めてである。このパンデミックが始まって以来、日本を出ていない筆者が、スウェーデンの教室の様子をつぶさに「見ることができる」のは、かつてない経験だといえる。世界が共通の課題に向き合い、ともに解決策を模索するというのは、ニューノーマルの特徴的な形なのかもしれない。