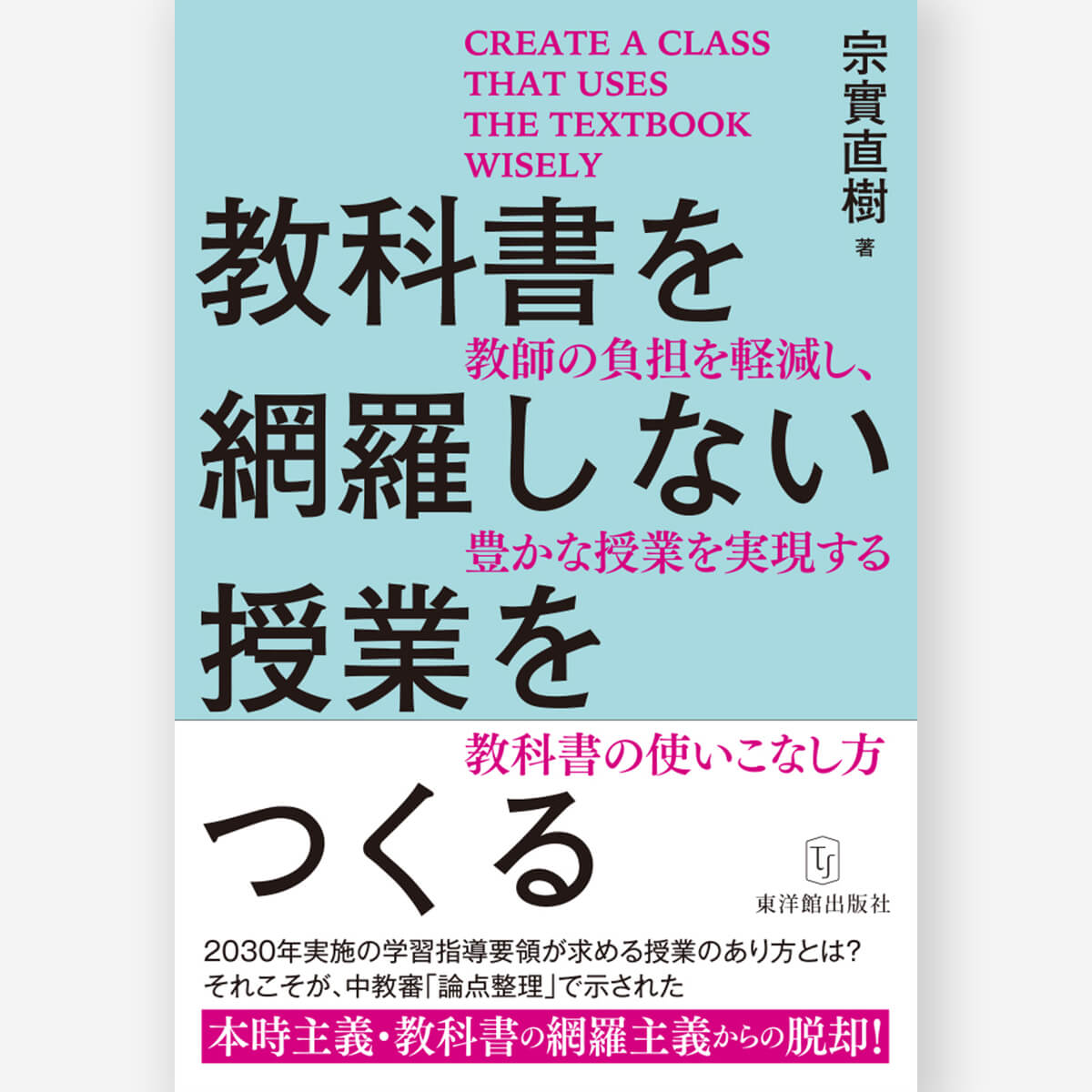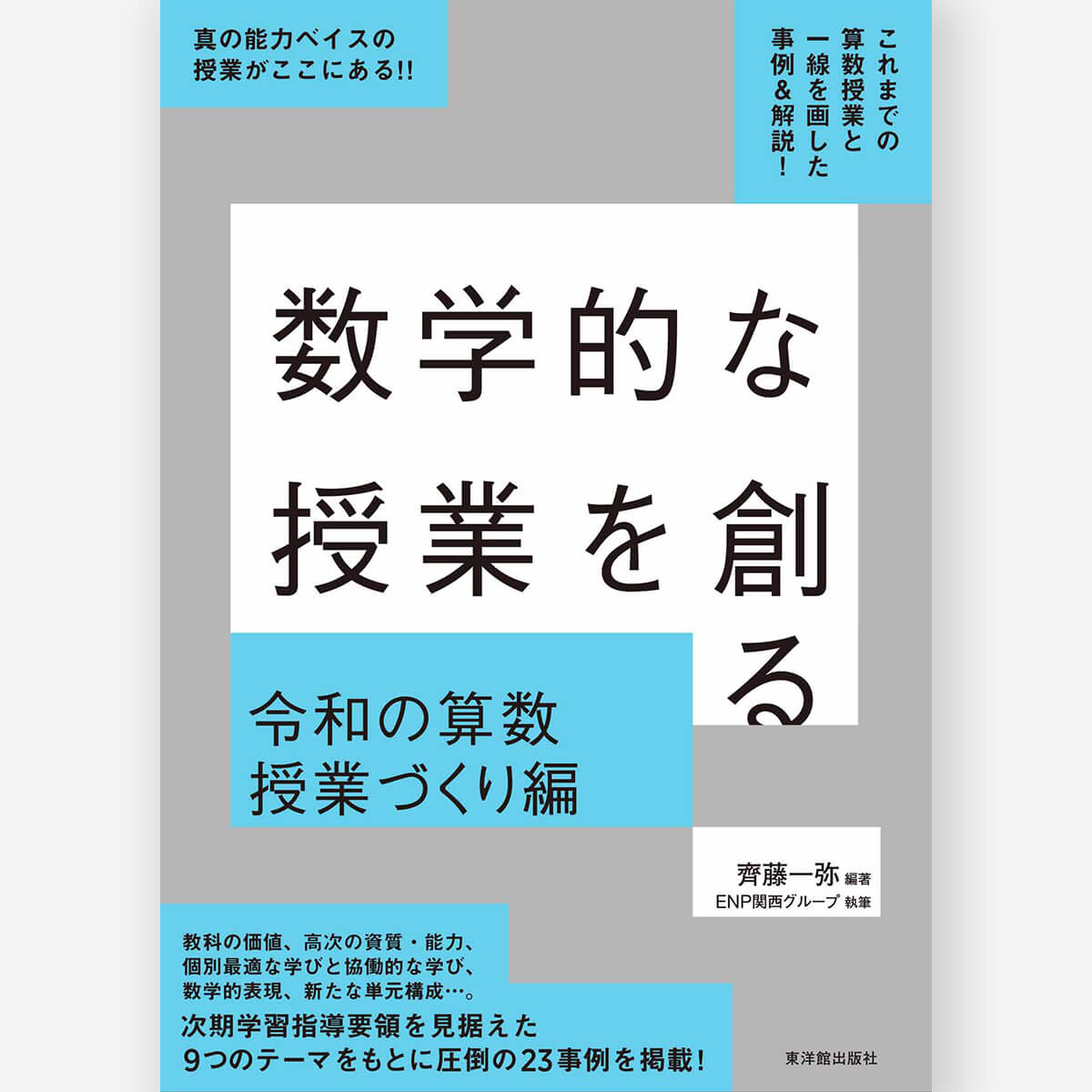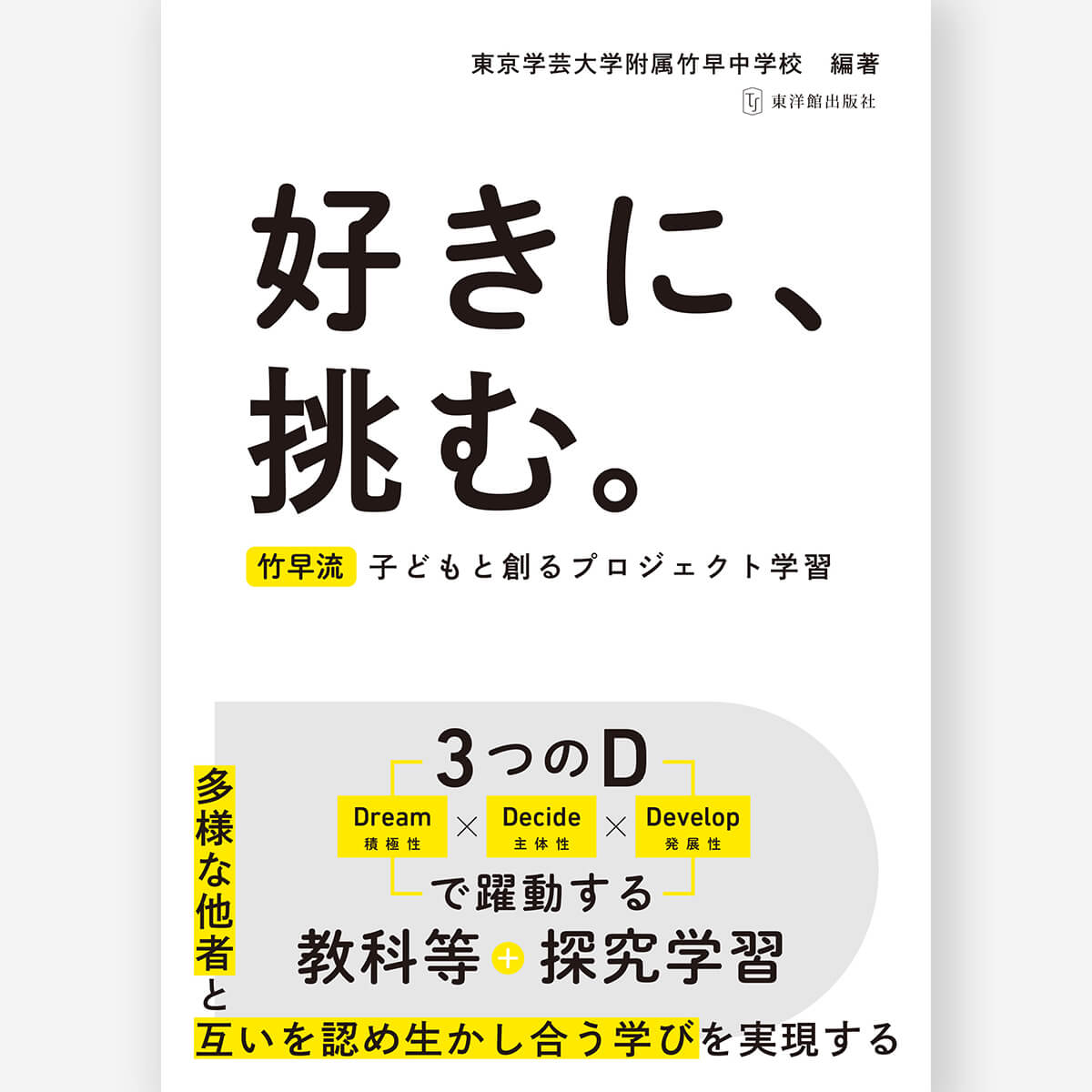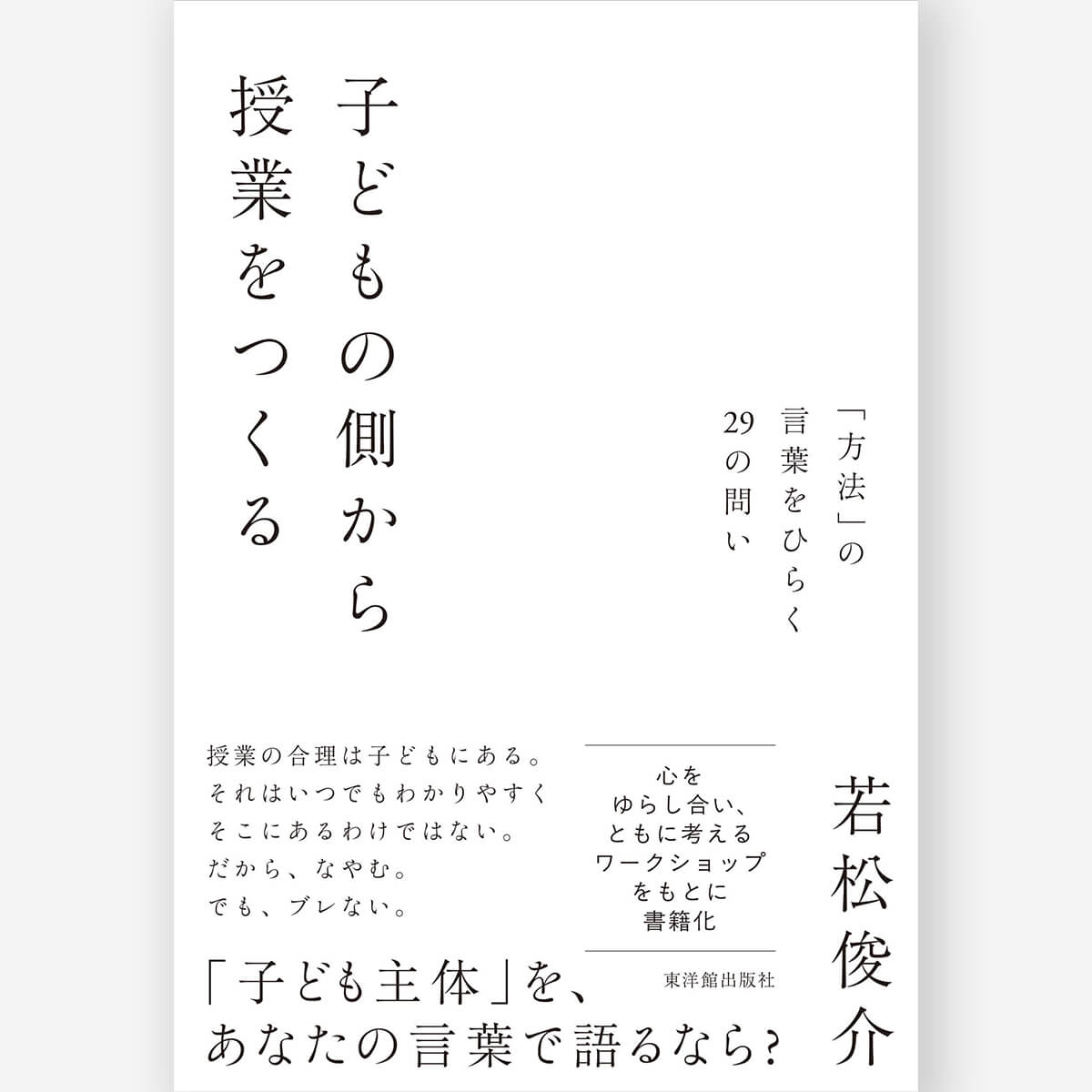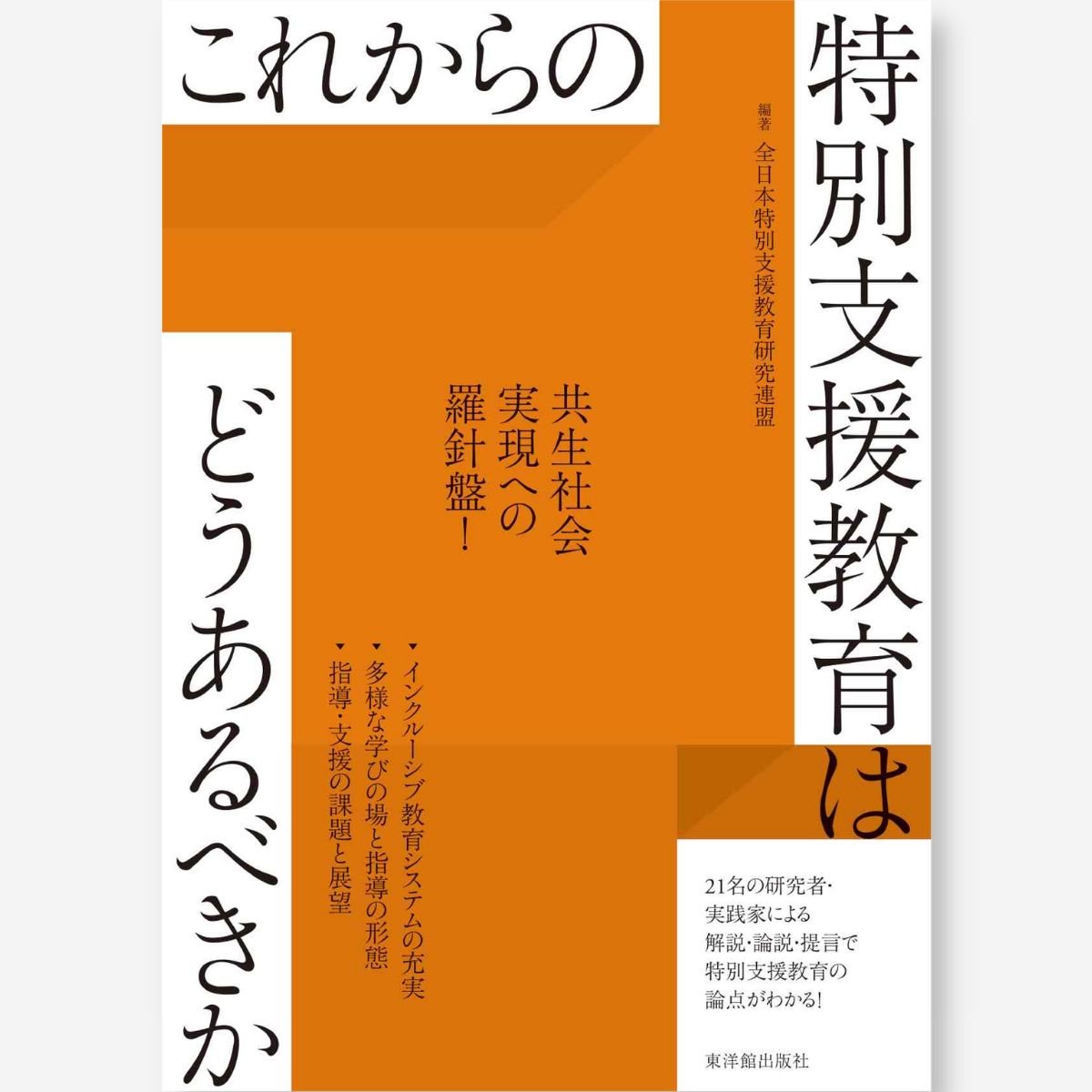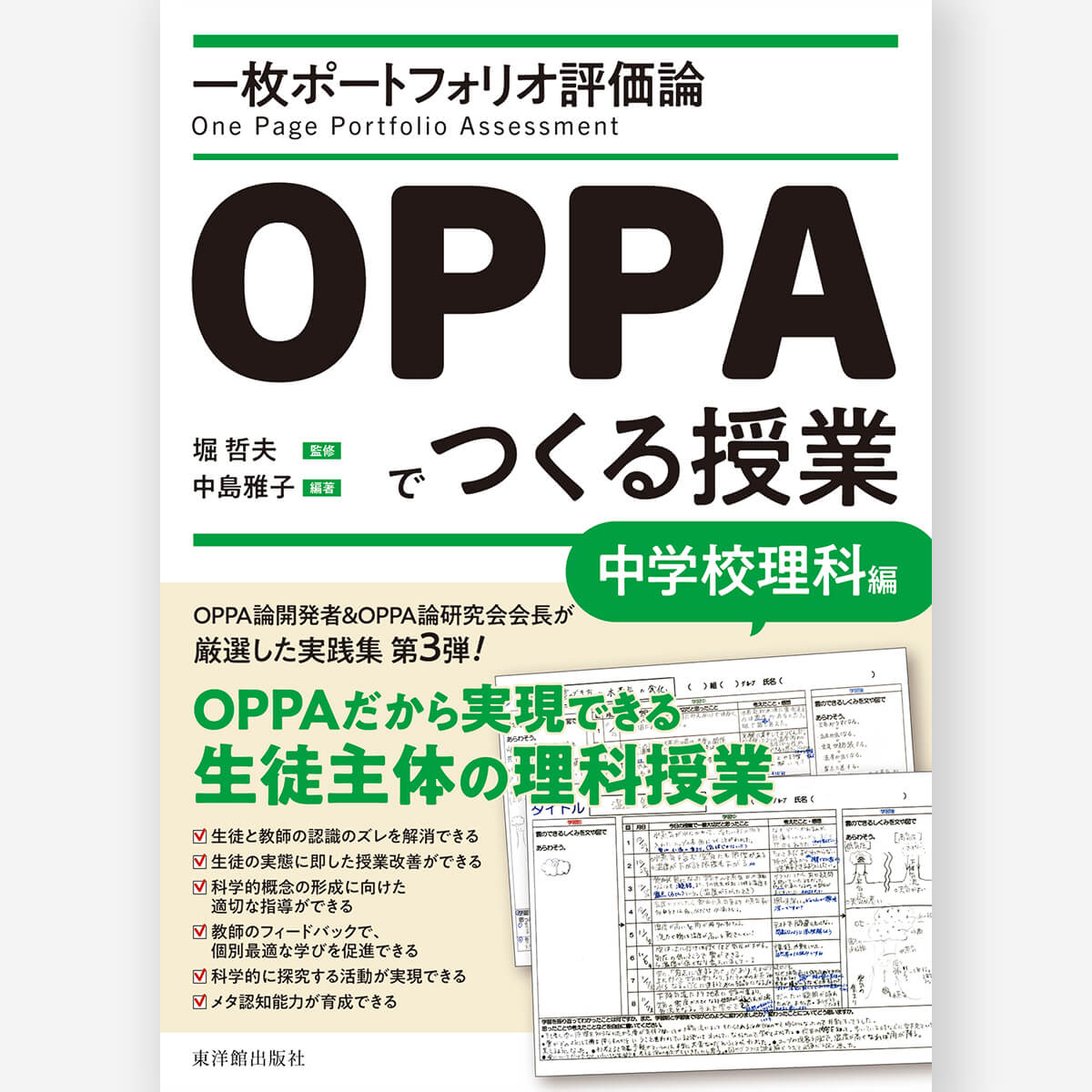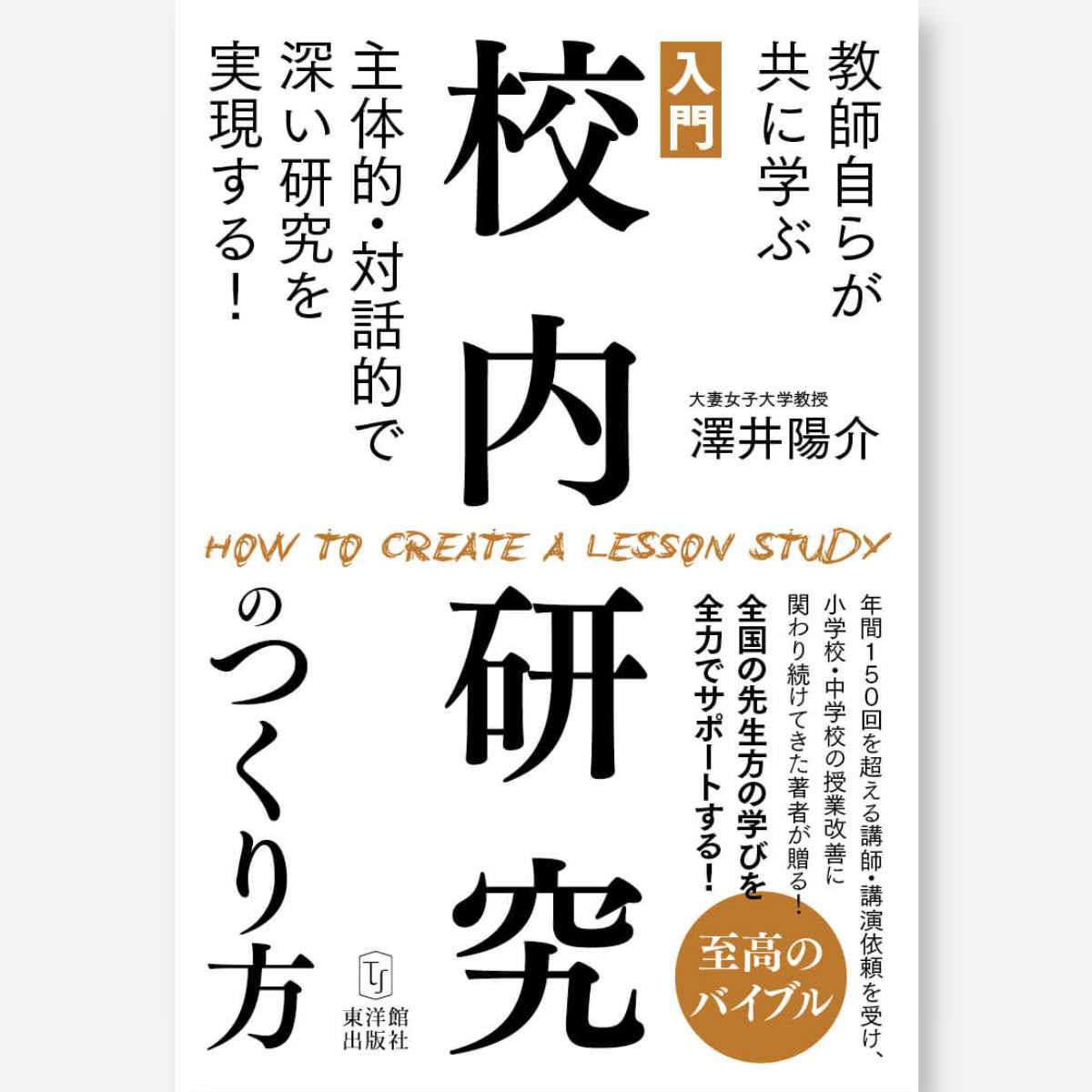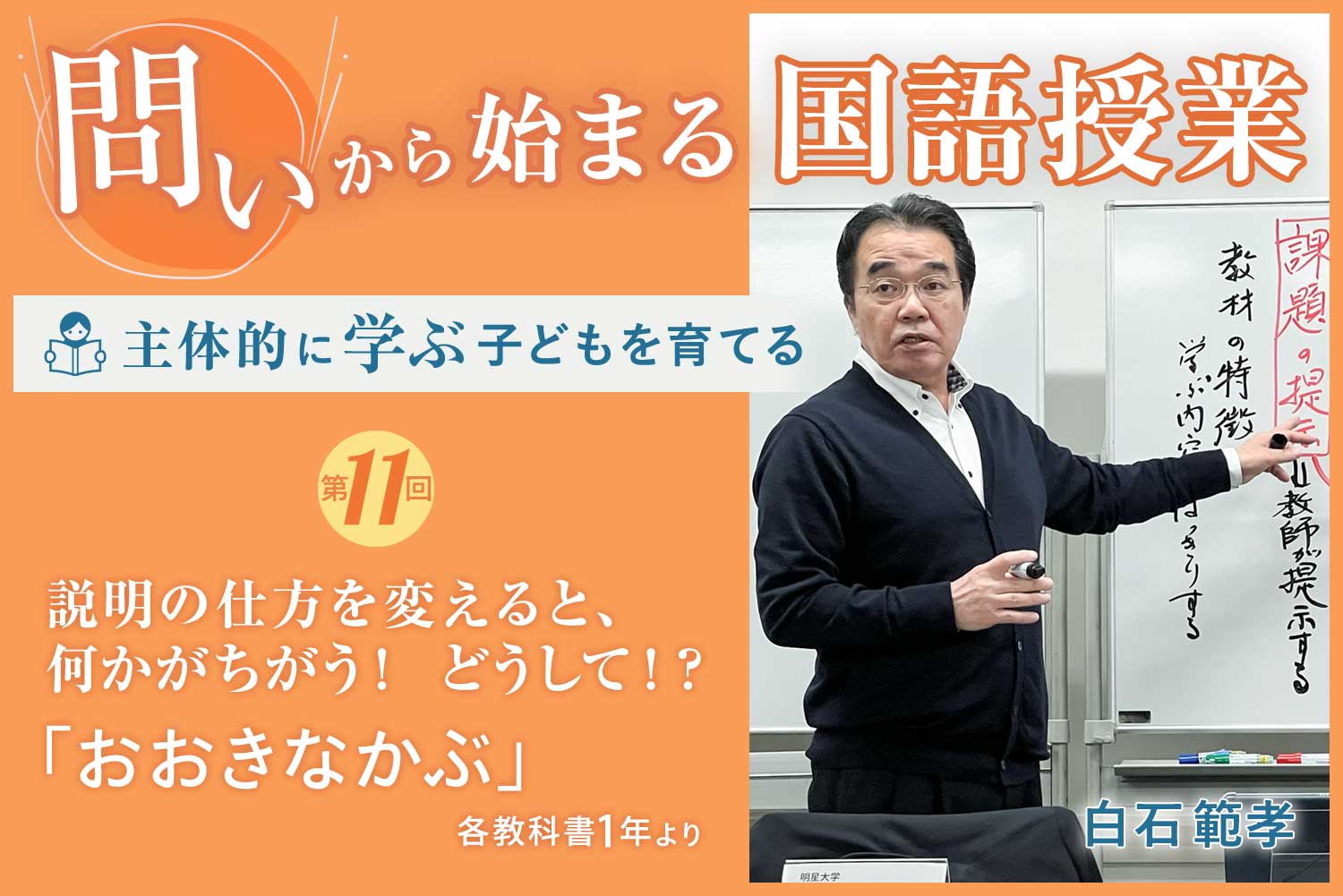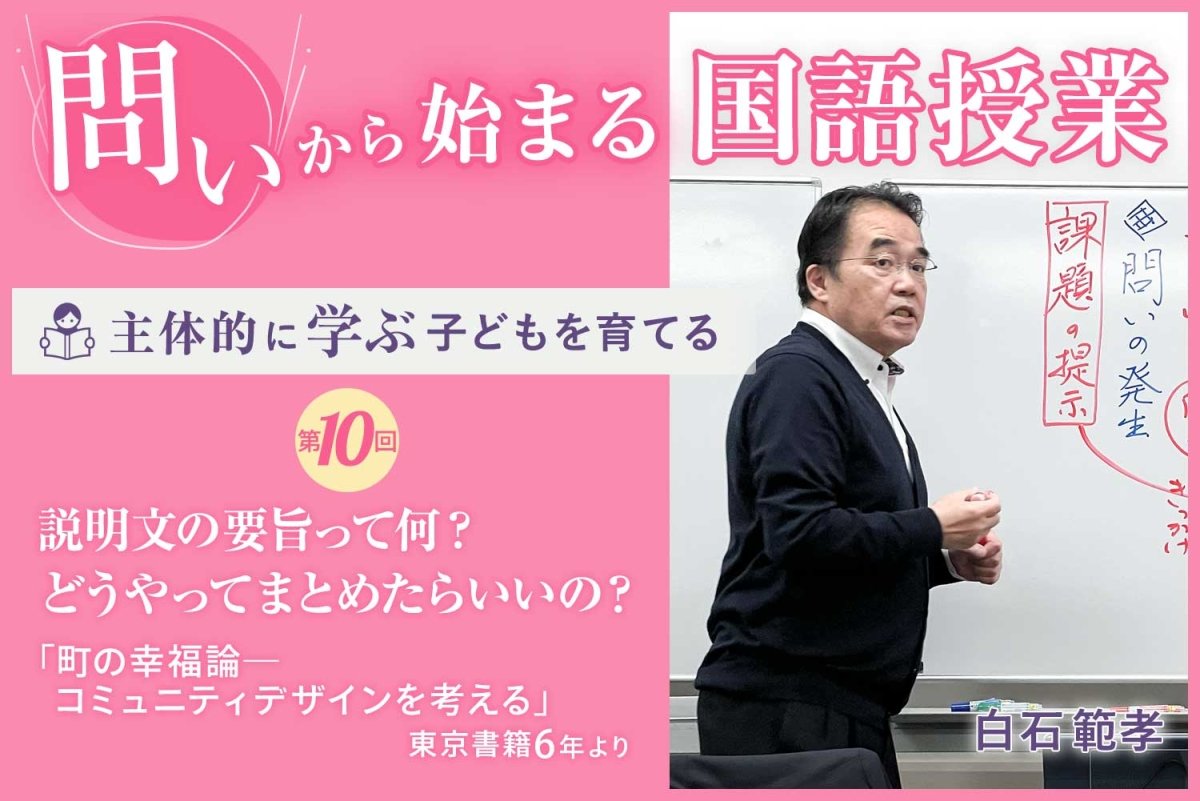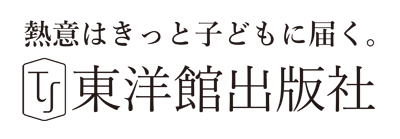〈 刊行記念イベントレポート 〉 2022年7月31日、小野健太郎著『オーセンティックな算数の学び』の刊行を記念し、オンラインイベントを開催しました。
当日はおよそ350名ものお客様にお越し頂き、ゲストの上智大学の奈須正裕先生とともに、オーセンティックな学びの奥深い世界を探りました。
連載第5回目となる今回は、イベントで行われた奈須先生と小野先生の対談の一部をお届けいたします。
「もってまわったようなこと」を丁寧にやる
小野 奈須先生が本日の講演部で「学校というものが始まる前、つまり近代以前は、実はすべての教育が、徒弟制や丁稚奉公など、常にオーセンティックであった」とご紹介しておられました。徒弟制や丁稚奉公においては、まさに「実用的文脈」で、本物の実践をすることになる(編集注:「オーセンティックな学び」には「市民、労働者や生活者の実用的文脈」と「知の発見や創造の面白さにふれる学問的・文化的文脈」の二つの分類が、石井英真先生によって整理されており、本対談でもその整理を土台として議論する。詳細は『今求められる学力と学びとは』〔石井英真、2015、日本標準、p.41〕を参照のこと。また、本連載vol.3「オーセンティックな評価」にも詳しい)。そこでは、整理された知識を順番に教え込まれるようなことはなく、実際の生活の中で学ぶからこそ、プロフェッショナルになれたのだ、と。
オーセンティックな学びの基本が、例えば靴屋さんの見習いが、現に立派な靴屋さんになるために学ぶ「徒弟制」のことだと考えると、その文脈にしっかりと乗ることが、学びのベースということになります。けれど、そうなると「そこで得た知識は『靴屋文脈』でしか使えないのではないか?」という疑問が生まれることになります。でも「靴屋文脈」だけではなくて、ある文脈で学んだことを転移させるためのコツや方略があるとするならば、何であるのか教えていただけますか。
奈須 先ほど講演で述べた「徒弟制」ということになれば何の破綻もないけれど、汎用的な「資質・能力」ということになると、未知の状況に立ち向かうことがゴールですからね。とはいえ、いくら「未知」だと言っても、膨大にあるそれぞれの「状況」を、一つ一つしらみつぶしに学んでいくというのは現実的ではないし、実際のところ無理でしょう。むしろ、自在に転移が利くよう「概念的理解」にしていく戦略が有効です。では、どうすればいいのか。
一つには、まずは思いっきりオーセンティックな文脈で学ぶということ。
おさらいすると、まずもって学習というのは、常に具体的な文脈や状況の中で生じている。
どんな状況でどんな理由でその知識が使えるのか、あるいは使えないのか、というのがわかっていないと知識なんてそもそも活用できません。いわゆる「宝の持ち腐れ型の学力」というやつですね。包丁を7本持たせている、でもそれぞれの包丁で、どんな素材をさばいてどんな料理を作れるのかということについては全く知らないという不活性な知識は学力とは呼べないのではないかと。だったら最初から「活用」の利く状況で学べばいい。自在に活用の利く知識にするためには、学びの状況を現実の社会に存在する実践に近づけようというのがオーセンティックな学びが重要である根拠でしたね。
ですからまずは、靴屋なら靴屋でいいですから、強烈なくらいに固有で特殊的な文脈で学んでいいと思います。
次に、一体それを通して何を学んだのか、一度その文脈から離れて抽象化し、自覚化・言語化・道具化する必要がある。最初はどういう視点で皆が問題解決をしていたのか、途中からの一人一人の問題解決場面ではどのように視点が移動したのか、あるいはそれに対して、算数であれば、適用された数理はそれぞれどう違うのか。例えば、同じ問題解決で使った二つの種類のわり算があったとして、それぞれ何がどう違うのかを検討する。そのことが数学的に、そして現実の文脈との関係で、整理される必要があると思うんですよ。
ある問題を「こんなふうに解いてみよう」としたときに、「こんな数学的な定式化をして処理をしたんだ」ということを言語化できる状態。
そして最後に、ここが難しいのだけれど、理想的には、その学んだ内容が、他の文脈でも存在したり機能したりしているということが、似たような文脈かつ異なる文脈で提示できるのがベストです。これは子ども自身が見つけられる場合もあるけれど、教師が提示してしまっても私はいいと思います。
昨日の授業で学んだことと類推的に同じ構造、いわば「数学的に同型」なものがあるでしょう? 数学的に同型だけれども、私たちの素朴な、あるいは日常的な実感としては全く別の文脈や別の状況、領域に属するものを一つか二つ、提示できるといいなと思います。そうすると、表面的に違うものが「同じ原理の異なる現れ」だということがわかる。つまり、これが先ほどの「概念的理解」に至るということです。
ここまで来られたら最後には、実際に、他の文脈でも学んだことを「活用」させてみる。さらに、できれば子ども一人でやらせてみる。「活用」する場合、文脈によってアレンジする必要がある場合も少なくないのですが、アレンジの方法や理由についても、子どもたちとともに考えたり学んだりする。
…と、ここまで言うとよく「こんなに、もってまわったことをしないとダメなのか」と言われるんですけど、これくらいもってまわったように丁寧にやると、もう学んだことは自在にクリアに使えるようになると思います。


「ドリル」からどこまで遠ざかるか
小野 手間はかかることなんですが、わかります。中でも、二番目の「何を学んだのか、一度その文脈から離れて抽象化し、自覚化・言語化・道具化する」というのは、「条件節をちゃんと学ぶ」という話とつながると思うんですよ。
例えば、僕は自動車の運転免許を持っているけれども、全然運転していないから運転できないんですね。奈須先生がよく例に出しておられるように、「エンジンブレーキを使う」という「行為節」は、どんな条件を満たしたときに適用されるのかという、「条件節」(※編集注:エンジンブレーキの例の場合、「もし急な下り坂や雪道ならば」が条件節となる)は、知識としては知っていて、言語化もできる。けれども、僕は実際に運転していないから、条件節が「身体化」まではしていないんです。
このことを算数・数学に引き付けて考えるならば、例えば図形で、「補助線を引く」という行為が例に挙げられます。「どんなときに」「どこに」補助線を引けばいいのか? というときに「どこに引くか」という行為節の部分は、教師側がよく「ここに引くといいよ」なんて、ヒントとして教えてしまったりするのだけれど、「なんでそこに引くのか・どんな場合に引くのか・引きたくなるのか(条件節)」「そこに補助線を引く必然性やよさって何なのか」ということについては、できる子にとっては、身体化してしまっている故にわざわざ表出されてこない。できない子にとっては、当然言語化もできない。ここで、できる子と一緒に言語化していくことも、もちろん一つには必要なことなのですが、僕らの算数授業は、ともすると言語に頼りすぎていたところはないだろうか、とも少し思うんです。もっと、図形を見た瞬間に「あ、ここに補助線を引きたい」となるような、身体に染み込んでいる状態になるには何が必要なんでしょうか。
奈須 そう考えたときに、「練習問題を繰り返しやり続ければできるようになる」と誤解する人がいるでしょう。そうではないよね。
小野 そう、それではダメなんです。ただ、難しいのは、繰り返したくさんの問題集をやり続けると、「できちゃう」子もいる。これが怖いんです。
奈須 人間は「パターン」を認識するので、「こういう問題のときはこれでできた」「似たような問題のときにこれでできたから、今回もそうなのでは」と、近年話題になっているAIの機械学習にも近いような形で、要素を抽出して帰納的に確率推論するみたいにして学び、結果的に「できちゃう」ことがある。意味や論理や筋道でやっているのではなく。
でも、それでは全く数学的ではないよね。むしろ、論理を演繹的に適用して解かなくてはならないじゃないですか。
つまり、ドリルの何がいけないかというと、やっているうちに「なぜできているのか、ルールすら説明できないにもかかわらず“できてしまう”」ところ。それをやっている限り、同じ水準の問題を解く限りにおいては正解できるのだけれど、ちょっと水準を変えられただけで、ちょっと景色が変わっただけで、もうお手上げになってしまう。以前のB問題における不振がその典型です。文脈が変わって、手がかり情報が見えなくなるから。だから、「似たような問題をたくさん解く」という戦略だけですべてを乗り越えていくのは一番やってはいけないことなんだよね。
小野 つまり、奈須先生が先ほどおっしゃった「他の文脈で機能するか確認する」ということと、「似たような問題を解き続ける」というのは、根本的に違うんですよね。前者において重要なのは「表面的には違うことに見える」というところですね。
奈須 そこが大事。表面的にはまったく違うように見えるのだけれど、実は同じ構造を持っている問題を、どれくらい持ってこられるかというのが、教師による教材的な勘・技術だと思います。つまり、数学的な構造を教師がちゃんと理解できていることが大事なんです。これは数字をちょっとずつ入れ替えた問題を何十問もやる、ということとは真逆の話でしょう。今回の学習指導要領改訂は、ドリルからどこまで遠ざかるか、ということを本気で考えているわけですから。
小野 算数・数学で言えば、今の話は「統合的に考える」という話を近いと思います。あるいは比喩的に言えば、例えば「『じゃんけん』と『三すくみ』(編集注:ここで言う「三すくみ」とは「ヘビがナメクジをおそれ、ナメクジがカエルをおそれ、カエルはヘビをおそれる、といった三者間の関係」)って一緒?」と問われたときに「一緒」と答えられるということ。要素を抜いて「構造」だけを見たときに、両者は同じことをやっていると言えるかどうか。さらには、「じゃあ、他に『三すくみ』と同じ構造になっていることってある?」と考えて、挙げられるかどうかというのが「同型な他の文脈を探せる」という状態なのですけれど、これと同じことを算数・数学の授業においてもやるのだということですね。大変なことではあるのですが、一つ一つやるしかない。

奈須 そういったことを、それぞれの教科の特質に応じて探していく、ということですよね。
例えば理科において、多様な事物現象があるけれども、化学の領域はすべて「粒子」で考えるとか、「物理」の領域ではすべて「エネルギー」で統合するとかいうふうに。
小野 今の話は、今回の本の話題でいうと「学問的にオーセンティックな文脈」の話に踏み込んでいると思うんです。要するに、一つ一つ個別な問題を解けるということではなくて、物理だったら「エネルギーで見る」というように、統合的に見られるようになっている状態で問題と向き合えているなら、それは割とアカデミックにオーセンティックになっていると言える。
ただし、ここで算数という教科が難しいのは、「物がないのに物がある」ところなんですよね。本来、算数において教師側が学ばせたいのは、抽象的な「数理の体系」である。だけれど、そのためのある種の「方便」として、子どもが考えるためのよりどころとなるような、算数の学習場面、つまり「ノンフィクション風の場面」を出さないとならない。
子どもたちはその、教師から差し出される「ノンフィクション風」の設定をよりどころとしながら数理の体系を考えるのだけれど、一方で、本書で挙げている例でいえば「2と2分の1リットルのジュース」のような「ノンフィクション風」に対して、「何それ?」とズレを感じる人もたくさんいるのだろうと思います。
加えて、単線型の学校教育を受けていくと、「実用的な目的」としては、「算数・数学を人生で最後まで使わなかった」という学び手も、多く出てきてしまうんですよね。だから、それよりも一段上の「数学的な考え方」の水準で、「あ、いいことを学んだ」という実感や「その後の人生で活きた」というレベルのことを学ばせられなければ、「算数・数学なんて学びたくない、やっても意味がない」という、“いつもの結論”に着地してしまうのではないかなと思っています。
「いつ、僕の答えを取り上げてくれるの?」
奈須 算数・数学という「学問的な文脈」でのオーセンティシティの高い事例、なにか具体的に出してみることはできます?
小野 本に載っていない事例にしましょうか。この前小学校で行った、5年生の小数のかけ算の授業です。学習の場面は、まったく「実用的文脈」のオーセンティシティについては考えていません。せいぜい、場面を想起できる程度の学習場面、「縦1.2m横2.3mのレジャーシートを持って遠足に行きます」というもの。これを、彼らには「小数のかけ算の筆算」は既習の状態で面積を解いてもらう。答えは2.76㎡になると、大半の子は答えます[図1]。

授業では、筆算での解き方だけではなく、かけ算の性質を利用して1.2と2.3それぞれ10倍して、12×23とする、ただし、積はその分100倍になるので276を100等分して2.76に直して答えるんだよ、という解き方についても、併せて押さえておきます[図2]。

ただ、その上で、授業では「答えが2.06㎡になる」という子がいたんですね。「先生、いつ僕の答えについて取り上げてくれるの?」と言ってくれた。この子が面白いのは、正解の2.76㎡には、もう納得していることなんです。2.76になること自体はわかるのだけれど、でも、僕のやり方で計算すると、2.06がでちゃうんだと。これが何故なのかを、みんなで一緒に検討してほしい、と。そう言うわけです。
さきほど、お客様からいただいた質問の中に(編集注:質疑応答タイムでの質問)「子どもとともにオーセンティックな問いをつくることは可能でしょうか?」というのがあったのですが、僕の回答としては、少なくとも「学問的な文脈」のオーセンティックな問いというのは、割とトラディショナルな、これまで私たちが大事にしてきた協働的な算数の授業をちゃんとやっていれば、子どもの側から価値のある問いが出てくるものです。それを、教師が見逃さずに取り上げるかどうかがむしろ大事、というのが一つ。二つ目は、「答えさえ出れば満足する」という学習観はもうやめようということ自体を、子どもたちと共通了解としてとれているかどうか、ということ。「2.06という答えが出ちゃう理由が知りたい」と言っている子に対して、それを取り上げると、それは必然的に、学問的に価値ある問いになってくる。そういう学習観を、そもそもみんなで共有できているかが根本的に大切です。
その子は、「小数のたし算のときには、位ごとに分けて足したから、かけ算でも位ごとに分けて考えたんだ」と説明してくれます。つまり1.2を1と0.2に分割。2.3を2と0.3に分割。それぞれの位で計算すると、1×2=2、0.2×0.3=0.06になる[図3]。両者を足すと、2.06になると。

この説明を受けて、「なるほど。これは算数のどんな考え方を使ったんだろう?」と僕が問うと、クラスのみんなは「“分ける”考え方だね」と言ってくれる。
「たし算のときの考え方を類推して使ったら、たしかに2.06になるよね、じゃあこの答えでもいい?」とその子に聞くと、「いやいや、答えが二つあるのはおかしい」と言うので、面積図で検討していくことになりました[図4]。

1×2=2の2㎡と、0.2×0.3=0.06の0.06㎡が、それぞれ、かけ算の筆算と面積図において、どこに該当しているのかを見てみると、本来の正解である2.76と比較すると2.06では足りていなかった「0.7㎡」の分がどこにあたるのか、どこの面積が漏れていたのか、というのが、図で考えることで見えてくる。また、筆算とも、面積図が対応していることにも気付ける[図5]。

この事例は、算数・数学の「縦の系統」の話にも関わります。というのは、この話はいずれ…。
奈須 因数分解の構造でしょう?
小野 そうです! 子どもたちがいずれ出会うことになる、(a+b)(c+d)という因数分解の話につながっていく学びなんです[図6]。

その算数・数学の「縦の系統」について、教師側が理解しているかどうか、つながりを見通せているかどうかで、この子の誤答の取り上げ方は変わってきてしまうんですね。
奈須先生が、Edupiaの連載(編集注:vol.1「学びの文脈を本物にする」)で書いていらした「子どもにとって最大の教材は、教師の背中だ」という話は本当にその通りで、僕が数学の文脈として一つ一つの関連性が見えている状態で子どもに話を振っているときには、数学という学問としてのオーセンティシティは比較的高い状態であると言える。子どもも、「なんで2.06になっちゃうんだろう?」という不思議さへの探究に入っていける。そのとき、「ノンフィクション風」として示されていた「レジャーシートを持って遠足に行く」という学習場面は、もはや消え去っているんです。
面積図の構造と筆算の構造がわかることで、2.06では何が足りていなかったのかが見えてきたときに、先ほどの条件節についても了解できるわけです。つまり「分割する」(行為節)という考え方が、どういう場合には適用できるのか・なんでかけ算の場合には適用できなかったのか(条件節)という話。
ただし、厳密にいえばかけ算でも分割の考え方は使えますよね。かけ算の場合にはコンビネーションとしてすべての組み合わせを尽くさないといけない[図7]。

1×0.3と0.2×2の組み合わせも計算して足せば2.76が出ます。
ですから、かけ算の場合、分割の考えは、また違う条件節が生まれる、というのが正確です。このことについても、言及している子どもも授業では存在しました。さすがにそこまでは全員が理解していたわけではなかったのですが。
…と、こんなふうな事例が、算数における学問的文脈のオーセンティシティが高まった状態かなと思っています。
曖昧なまま終わらせずに“それでも前に進む”
奈須 たし算とかけ算が原理的にどう違うか、ということ、まさに一次元と二次元の違いについて迫っているわけですね。
今の話を聞いて二つのことを思っているのですけど。一つは、教師がこのことを内容論的に見通せないことがあるじゃないですか。古典的に言えばこの話って斎藤喜博(編集注:教育学者。1911-1981年)の「◯◯ちゃん式間違い」の話ですよね。子どもが何か突飛なことを言い出したときに、算数的には間違いであったとしても、その子なりの論拠や意味合い、筋道というものがそこにはあって、僕らにとっても「ついやってしまいそうになる」その筋道が、一体どういうもので、どういう意味があって、算数的に何故間違いになるのか、ということを明らかにする。それは裏返すと、「正解となる答えが何故正解と言えるのか」もはっきりするということです。
今の事例は、たし算とかけ算の一次元の世界と二次元の世界がどう違うのかということを、筆算のレベルでも面積図のレベルでも明示的に示すことができるので、いい例だと思います。
ただね、難しいのは、小野さんのように内容研究ができている人は上手に導いてそこまで行き着けるのだけれども、内容研究がそこまでできていなくて、しかも授業中に急に言われて余計にわからないというときに、先生はどうするのか。
「それでも前に進む」というのが、私の答えですけど。もう、先生は立ち往生したっていいから、それでも前に進む。子どもがあれこれ考えて、子どもの中に気付く子が出てきたらその子にやってもらったっていいし、場合によってはチャイムが鳴ってしまったっていい。とても大事そうなことなんだけれど先生にも全貌がわからない、という不思議な状態で授業が終わる。「これを明日また考えよう」と言って子どもがそれぞれ考えてきたっていいし、先生は先生で慌てて職員室に帰って、他の詳しい先生に聞いたり自分で調べたりして答えを見つけたらいい。45分で決着をつけようとすると、そこまで子どもの問いに踏み込むことはできないのだけれど、やっぱり、どうなろうとも踏み込むことが絶対に大事なんですよね。決着がつかないなら、子どもと一緒に翌日に持ち越していいんです。
そういうことの積み重ねの中に、先ほどの小野さんの事例における男の子のような、主体的な学びの態度が出てくるんです。彼がなんで授業中に「2.06という自分の答えを取り上げて、みんなで検討してほしい」と言うことができたかというと、やはり過去にそういう経験をしてきているからなんですよね。自分であれ、友達であれ、そういう疑問を言い出して検討したときに、結果的には誤答であることがわかるんだけれども、「その誤答が、何がどう間違っていて、逆に、正解の答えが、何故正しいと言えるのか」みんなで取り組んだことによってわかったというのが、楽しかった経験として記憶に残っているから、次もまた、探究できるんですよ。
これこそが、昭和26年の学習指導要領(試案)の頃に語られた「鋭い道徳的な感情」というものでしょう。曖昧なことを曖昧なまま終わらせない。間違いならば間違いでいいのだけれど、何がどう間違っているのか数学的にはっきりさせないと気が済まないという子どもを育てる。しかもその力こそ「学力」なのだということを、今回の平成29年告示の学習指導要領は本気で示しているということを押さえておきたいですね。
小野 僕がこの子の何が面白いと思ったかというと、「正解の2.76についてはもう納得している」と言っていた点なんです。もっと言うと、そもそもみんな一人一台のタブレット端末を持っていますから、僕が言わなくたってめいめい勝手に手元の電卓で計算して、答えが2.76が正解となること自体はもう知っている。にもかかわらず、「2.06」に至る式と説明を見ると、「なんか納得できちゃう」と言っちゃう子どもたち。
いわばこれは迷路ゲームの入口と出口のようなもので、迷路の全部を飛ばして出口に行ける迷路ゲームがあったとして、そんなゲームは面白いか、と聞けば、子どもたちは「そんなの面白くない」と答えるのですよね。出口に行くことが目的なのではなくて、プロセスが楽しいということに、僕は早く子どもたちに気が付いてほしい。
“教師の掌の上”から解き放つ
奈須 二つ目に思ったことはね、今の話の裏表になるけれど、小野さんみたいに内容研究として算数的な構造が見えていると、誤答を取り上げる際にも、子どもが言っている話がどこに行き着くのかもう「見えてしまっている」がゆえに、ある意味、授業は教師の掌の上にある状態になる。そのほうが、いい学びになるはずと思いきや、案外と授業自体はつまらないものになったりするでしょう。あれが面白いものですね。
小野 いやぁ、そうですね(笑)。
奈須 先生自身が、子どもの問いがどのように数学的に意味があるのかわからなくて、授業をどこに持っていけばいいのかわからなくて、けれどその分、子どもたちがすごくがんばって、結果的に面白い発見に行き着くということがままあってね。 「いつも授業を教えてくれる先生が、わからないで、困っている」ということが伝わると、子どもにとってはそれが案外楽しい瞬間だったりする。もちろんそれは、からかうような気持ちではなくてね。大好きな先生が立ち止まっているなら、子どもたちは自分たちで一生懸命頑張って考える。そして自分たちが頑張ったことによって、先生もわかってくれたりなんかすると、さらにうれしい。
もちろん、内容研究や教材研究が隅々にまでいきわたっていて、子どもから何が出てきても、教師が教科の内容的理解ができていることが一番大事なんですが、案外それがハズれたときに、いい授業になったりする(笑)。そしてその方が、子どもにとって深い学びになったりとかね。
小野 そうですねぇ。この子が出してきた問いって、僕も正直「出るだろうな」と思って授業していました。だからおっしゃる通り、ある意味「掌の上」というか…。
小学校の教職2年目に、小数のわり算の授業をやっていた際、見通せていなかった問いが展開して、「あれぇ、想定と違うな、どうしよう。困っちゃった」と僕自身がなってしまったときがあるんですけど、子どもたちがみんなで本当によく考えてくれて、とても思い出深い学びになったんですよね。授業というのは不思議なものです。
(構成:東洋館出版社 河合麻衣)
奈須 正裕(なす まさひろ)
上智大学総合人間科学部教育学科教授。神奈川大学助教授、国立教育研究所教育方法研究室長、立教大学教授などを経て2005年より現職。2021年、『個別最適な学びと協働的な学び』を刊行。
小野 健太郎(おの けんたろう)
武蔵野大学教育学部教育学科准教授。明星学園小学校教諭、東京学芸大学附属小金井小学校教諭、東京学芸大学教育学部非常勤講師などを経て、2021年4月から現職。『オーセンティックな算数の学び』が初めての単著となる。