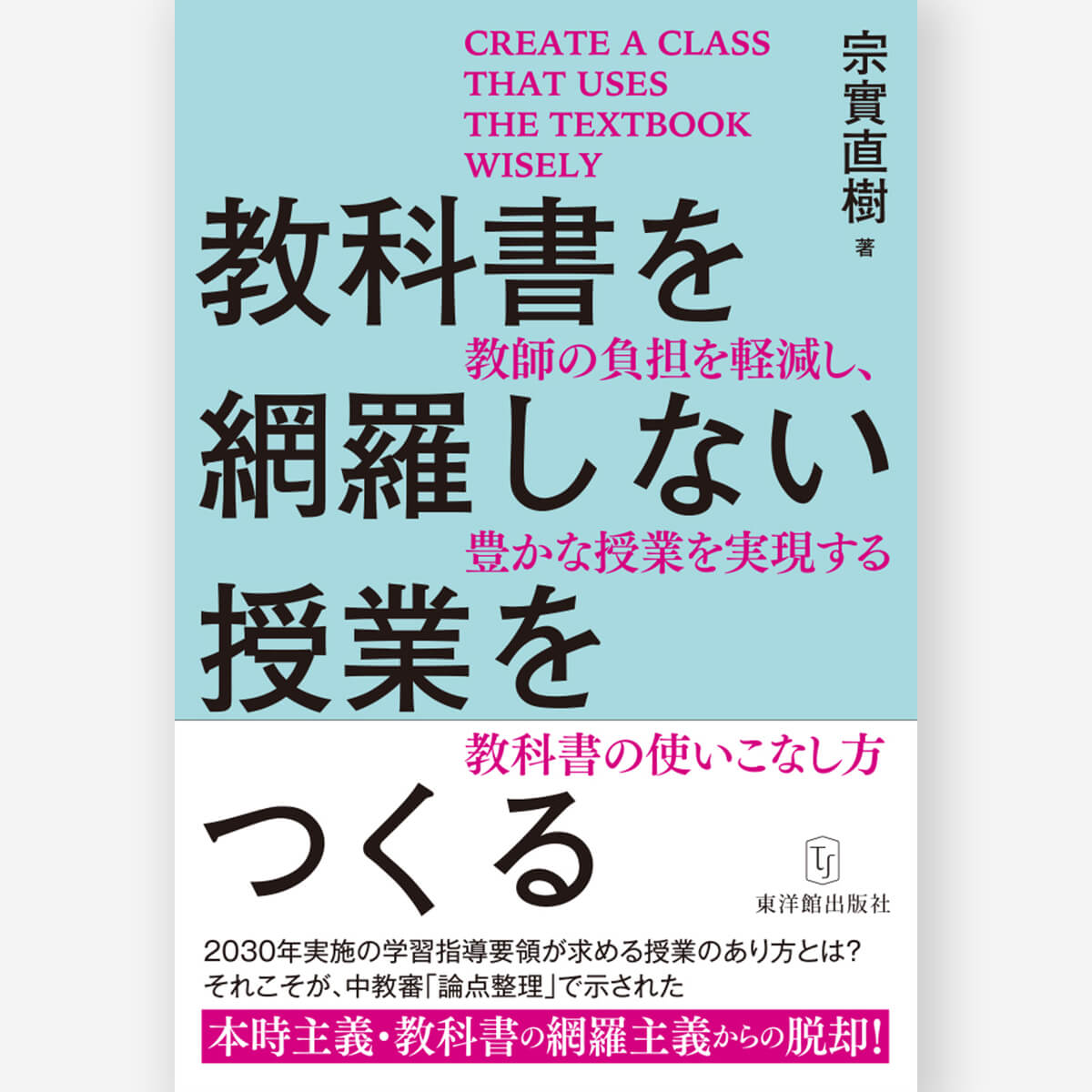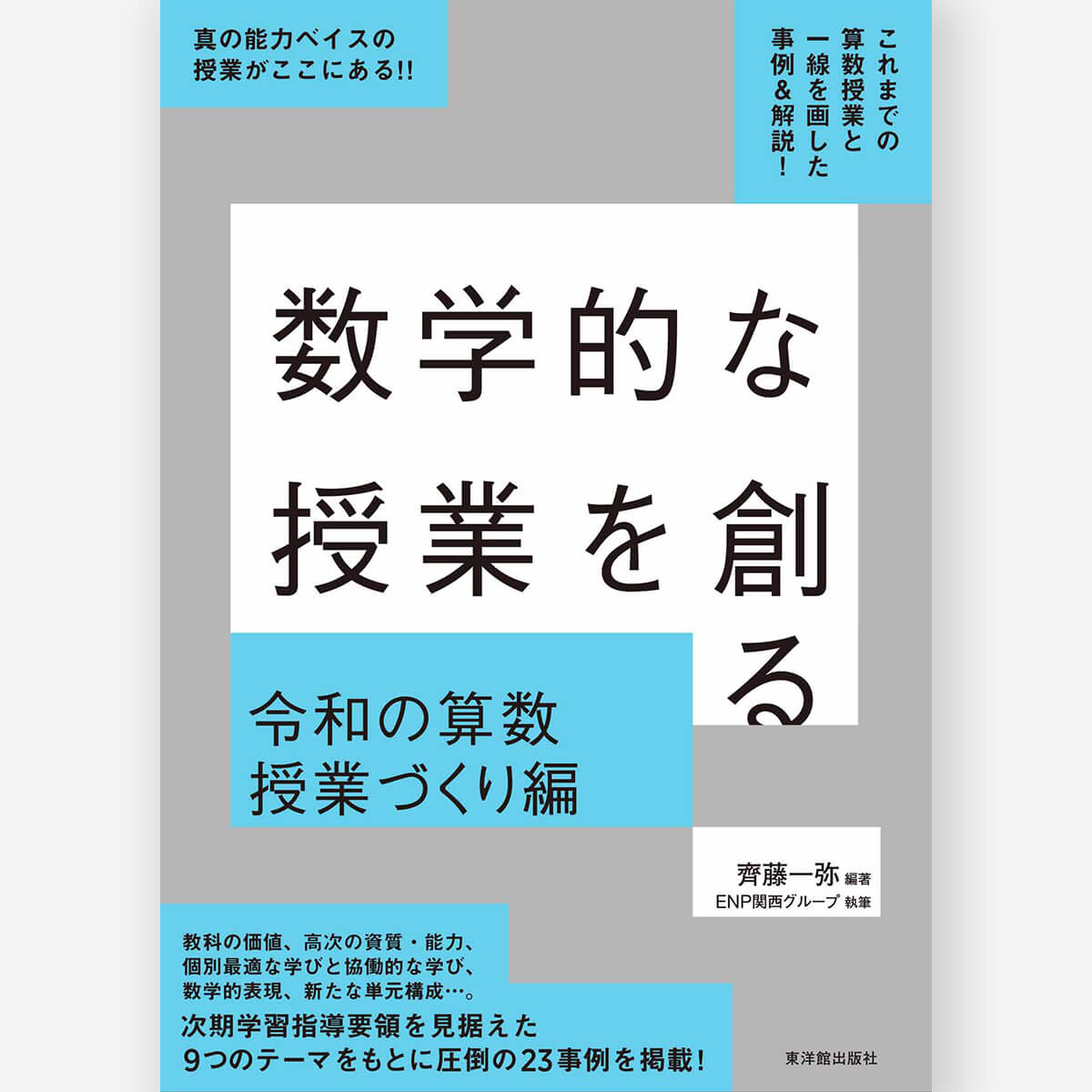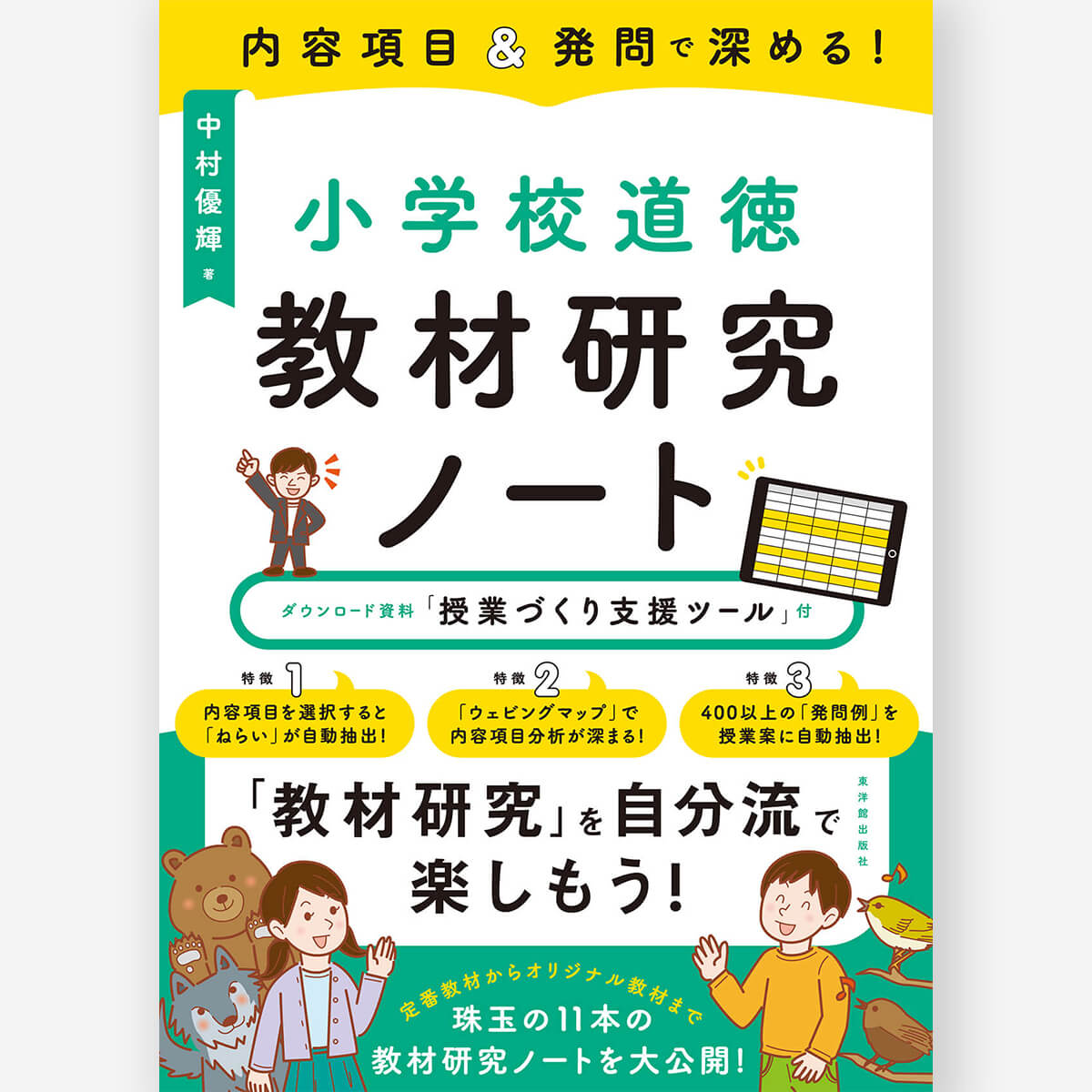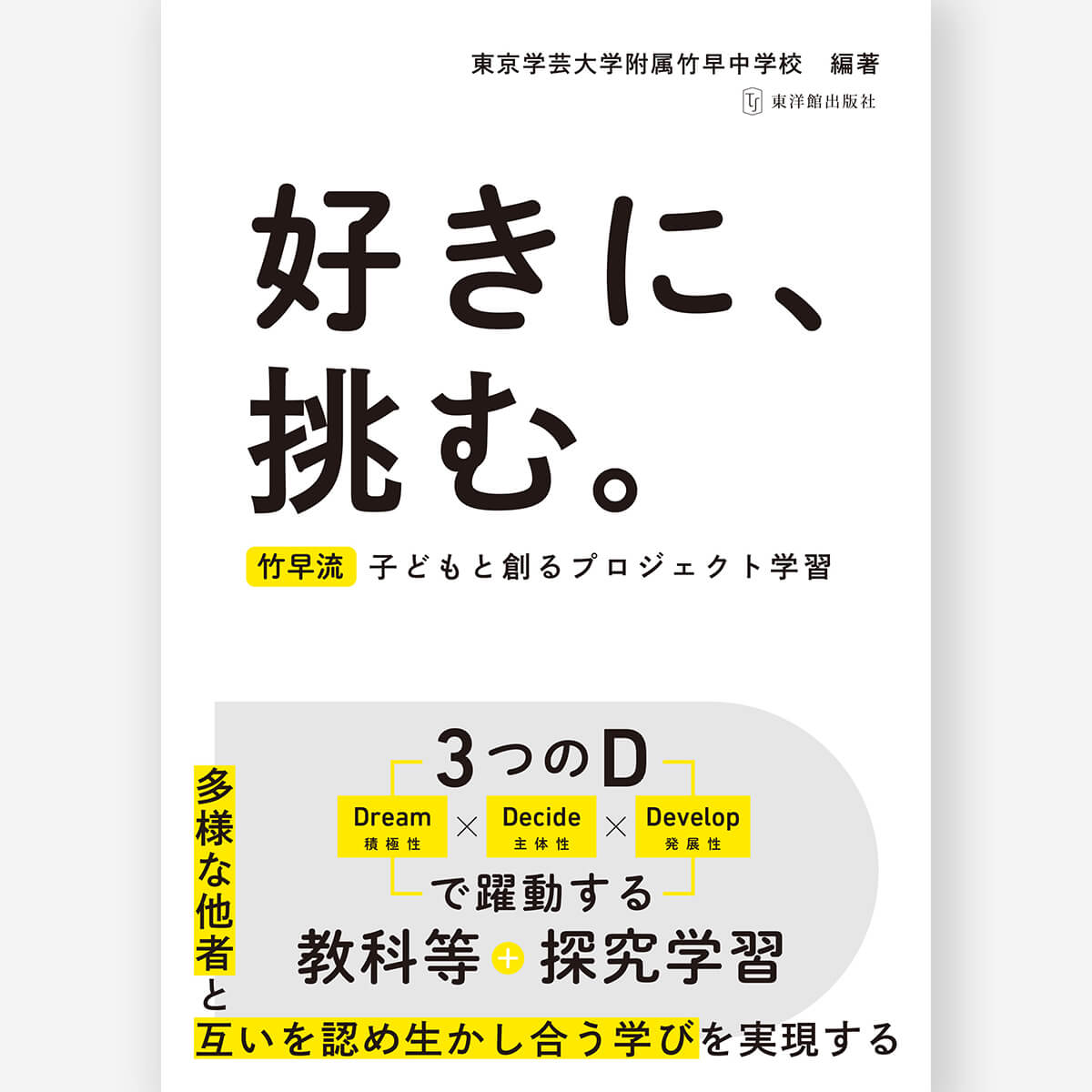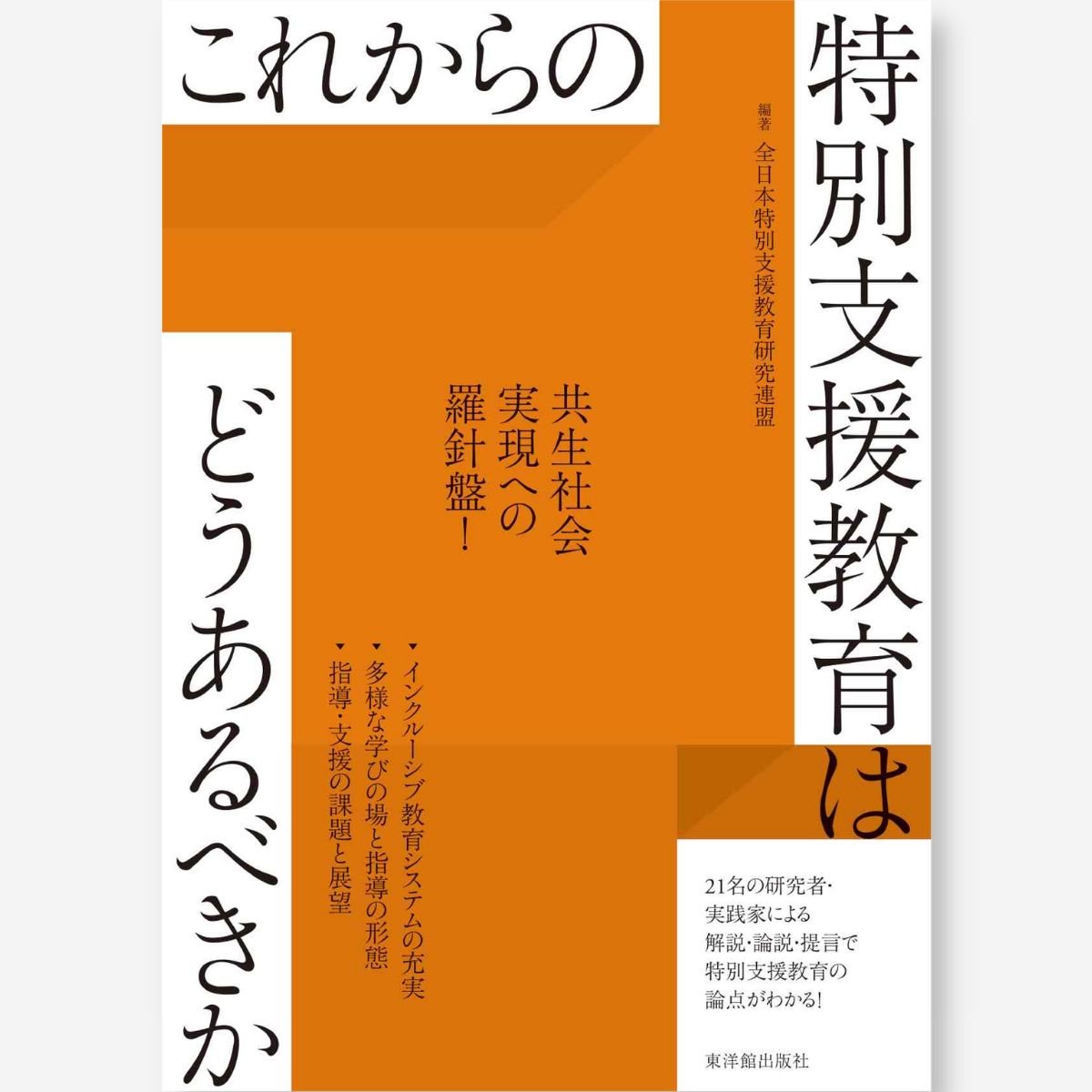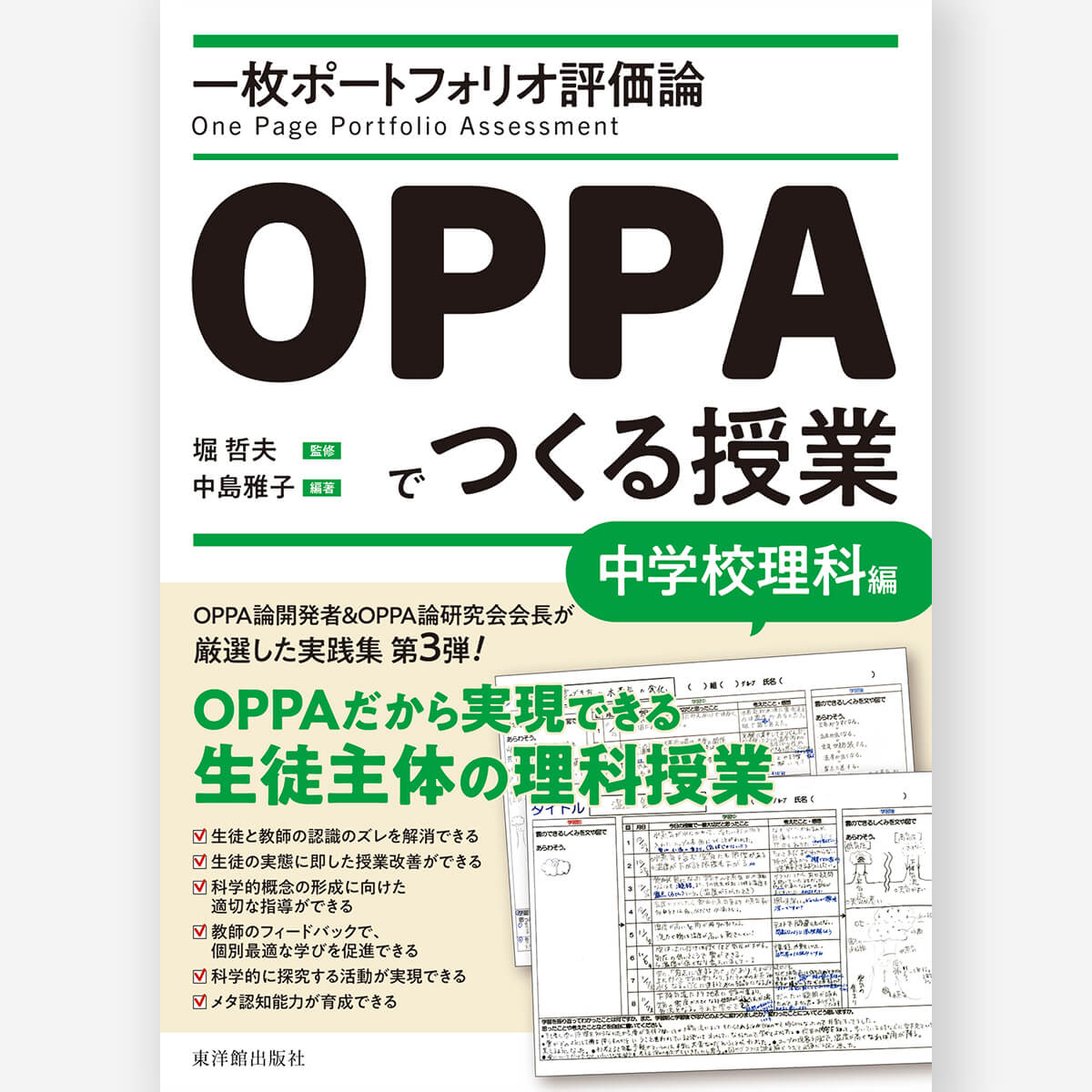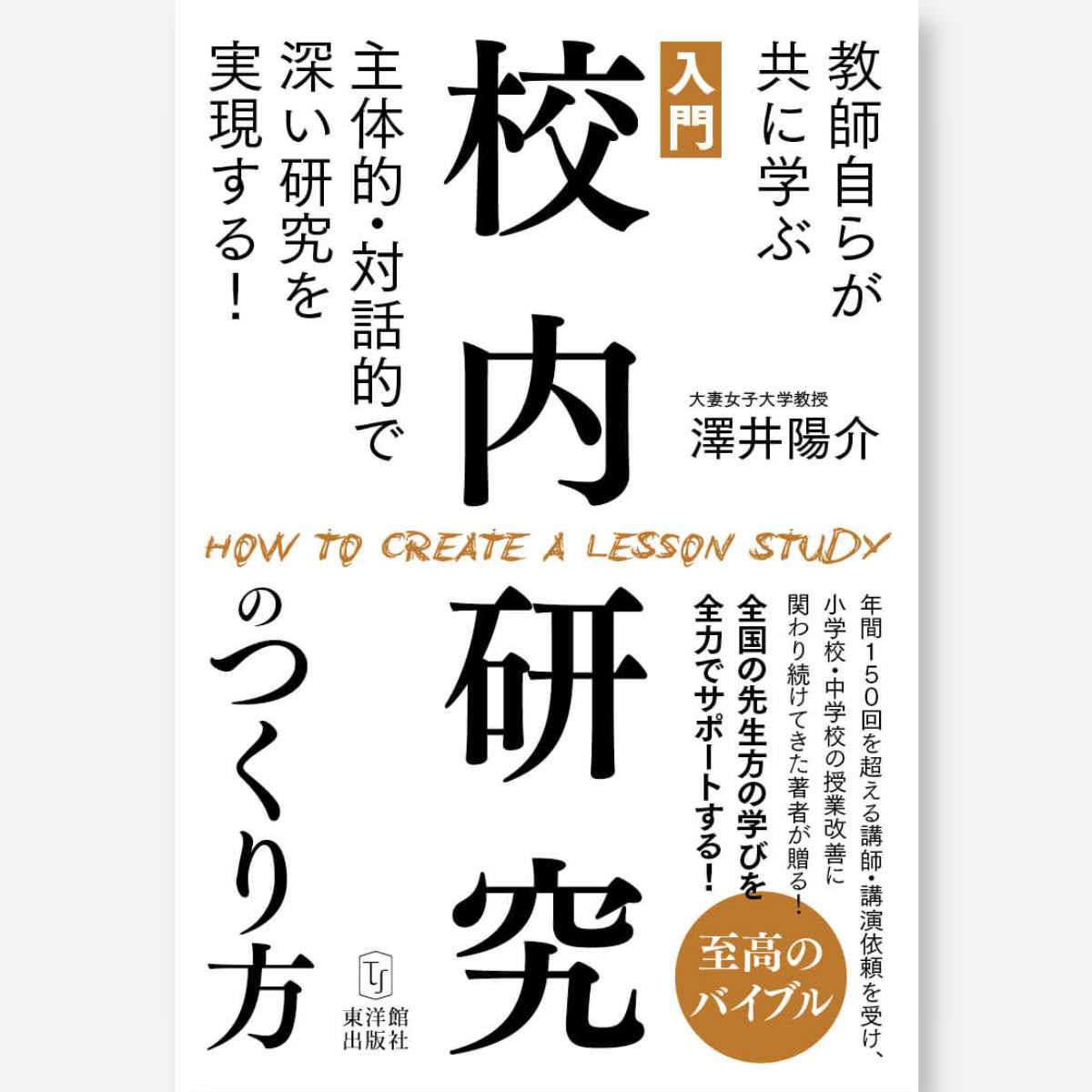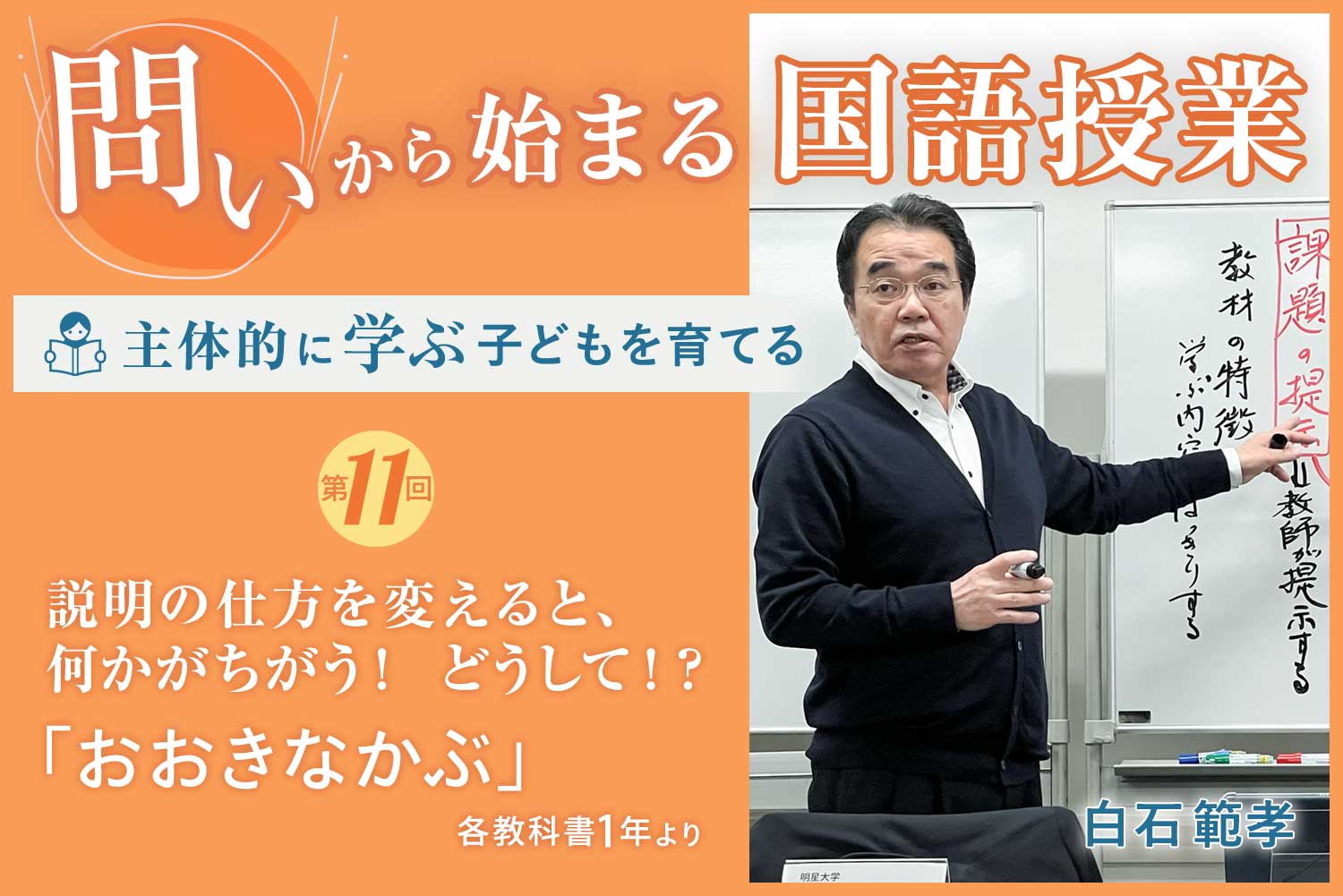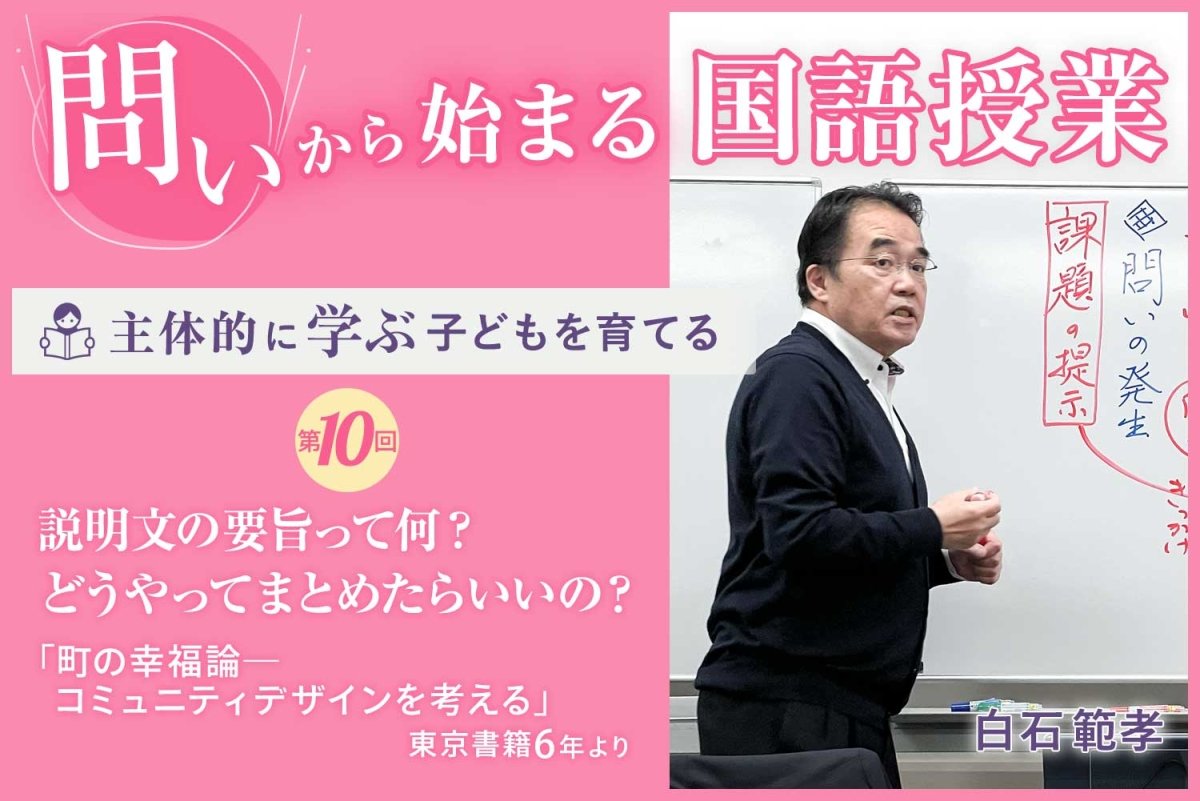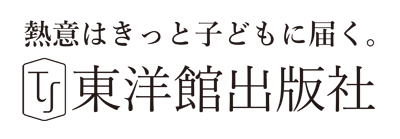コロナ禍における教育の難しさ
今回のコロナ禍は、人間の生命を脅かすリスクであると同時に、教育においては子どもの成長をいかに支えるのかをめぐる難題を突き付けるものでした。その難題とは、たとえば以下のようなものです。
- 学校を閉じるべきか、開くべきか?
- 家庭で子どもの学習を誰が支えるのか?
- ICT機器やインターネット環境が整わない家庭をどう支援すべきか?
- そもそも学校の閉鎖や再開の決定は誰がおこなうのか?
- 学校単位では対応しきれない問題を中央・地方の教育行政がどう役割分担しながら解決するのか?
これらの問題は、世界の国々が悩み試行錯誤を続けてきたものです。短期間のうちに世界数百万人の命を奪い去るという異次元のリスクの緊張感のなかで、各国は難しい判断を迫られました。
2020年3月11日のWHOによるパンデミック宣言から1年を経てもワクチンや治療薬が追いつかず、人類の科学技術の限界を目の当たりにしました。そして、パンデミックから2年を経てようやくワクチン接種が進み始めたかたと思えば、ウイルス自体が次々に変異して翻弄し続けています。
パンデミック宣言が出されたときには、すでにイタリアやアメリカをはじめ事態がすでに深刻化し始めていた国々がありました。同月内にはイギリス、ロシア、ドイツ、ブラジル、フランス、トルコ、イランなど、大陸をこえたパンデミックに突入していきました。本書では、この未曾有の事態を招いたコロナ禍に、世界の教育がどう向き合ってきたのかが示されています。共通のリスクへの各国の向き合い方には、興味深い違いも明らかになりました。
世界と日本における子どもや家庭の苦難
学校を閉鎖した場合に多くの国がとった方策は、従来の教室での授業を一定期間断念して遠隔教育へと切り替えようとするものでした。具体的には、インターネットを活用した授業が中心となりました。国のよってはラジオやテレビを活用したところもありました。第一波による学校閉鎖の際には、多くの国が遠隔教育に対応しきれず、学校も家庭も混乱に陥りました。例えば、ドイツの小学校教員が当時の子どもたちの困惑を次のように例示しています。

このような子どもの悩みは、世界の少なからぬ国々で共感されうるのではないでしょうか。他面、いくつかの国は大きな混乱を免れることができています。コロナ禍以前からICT化を国策として進めてきたエストニアや、年1回以上の全校自宅学習日を設けていたシンガポールはその代表例と言えます。
突然の休校により保護者も困惑することとなりました。家庭での子どもの学習をどう支えるかや仕事との両立、学校からの連絡などについて戸惑いの声が各地であがりました。
本Webマガジン第5回ではマダガスカルの家族の例が紹介されています。マダガスカルでは実に1年以上も学校が閉鎖され、保護者の困難もより深刻だった反面、学校を離れた家庭での教育のポジティブな面も述べられています。
次に、教員の苦難についても見てみましょう。
日本の教員はエッセンシャルワーカーではないのか
突然の休校や遠隔教育への転換は、教員をも困惑させました。一部の例外を除く多くの国でICT化への移行にハード・ソフトの両面で困難が生じました。学校再開後は、教員は感染リスクにさらされながらも勤務することとなりました。その際、少なからぬ国で教員がエッセンシャルワーカーと位置付けられ、ワクチン優先接種対象とされました。学校制度が必ずしも十分普及していないケニアでも、教員は医療関係者に次いで優先接種対象とされています。しかし、日本では残念ながら教員を手厚く保護する対応はとられませんでした。
また、諸外国ではリスク・グループの教員(高齢、基礎疾患など)や要介護家族をもつ教員などの出勤拒否が見られましたが、日本ではそうした行動をとる教員はほとんどいませんでした。日本にも当然、そうした教員が存在するにもかかわらずです。つまり、日本の教員はワクチン優先接種もない感染リスクの中で、いわば自己犠牲的に職務に邁進してきたと言えます。日本社会の中では、疑問視される向きもなく自明のことのようにやりすごされていますが、諸外国との比較からは強調しておくべき特徴と言えます。
コロナ禍の教訓
コロナ禍は世界中を混乱に陥れ、ワクチンや治療薬の開発が進んできたものの、今なお影響が続いています。諸外国における教育への対応から、私たちの社会は何を教訓とすべきでしょうか。
①教育現場のストレス対策
まず日本では、諸外国でのロックダウンのような厳しい罰則付きの強制措置はとられず、不要不急の外出を控える自主的な行動規制を基軸とした政策がとられました。実は、今回のコロナ禍で日本は、諸外国と比べて感染者数や重症化率などの被害状況は抑制的なものでした。にもかかわらず、社会の中に疲弊感やストレスが鬱積しているように感じられます。とりわけ学校の閉鎖と再開に翻弄された教職員や家族、そして何よりも子どもたちは、極めて大きなストレスに晒されてきたと言えるでしょう。
②感染対策物資の迅速な至急
コロナ禍における混乱やストレスは世界中で見られますが、日本の場合、マスク配布(さらには遅配や欠陥品などの問題)や、首相の全国一斉休校要請(2020年2月)、経済的支援策の遅れ・錯綜など、市民感覚として納得がえられにくい政策がまかり通っている点が気になります。もちろん、未曾有の危機の中で市民も政治家もともに試行錯誤し、奮闘してきたことは間違いありません。ただ、諸外国では意思決定の際に政府首脳が説明を尽くしていたり、政策判断の根拠として専門機関の科学的知見がふまえられているため(第2部の各章に詳しい)、理屈のとおらない政策が次々にとられる状況はありません。
③感染対策におけるリーダーシップ
たとえば、コロナ第1波の際のドイツのメルケル首相(当時)のテレビ演説は、民主主義国家が国民の自由を制約するという苦渋の判断をしなければならないことを真摯にうったえ、多くの人びとの共感を呼びました。
感染症対策全般において専門機関の知見は、ヨーロッパ諸国では極めて重視されています。たとえば、ドイツのロベルト・コッホ研究所やフランスのパスツール研究所、スペインの疫学国立センターなどは、コロナ禍の政策判断において大きな存在感を示しました。ところが日本では、専門家会議が設置されているものの補助的であり、常設の専門機関は政治の陰に隠れて市民からは見えにい、という政治主導が際立っています。
海外にも波紋を広げている校長の「提言書」
2020年2月の首相の休校要請に99%もの自治体が従ったことは、日本の統治構造の問題を象徴する出来事でした。各自治体は首相からの要請に「納得・賛同」して休校決定したのではなく、「従わなければ後で不利益が生じる」といった消極的な判断となりました。地方自治体においても政治的な意思決定の弊害があらわれています。たとえば、コロナ禍を契機として教育政策に学校現場から苦言を呈する「提言書」(大阪市立木川南小学校・久保校長)は、「教育委員会の対応に懸念を生じさせ」た等として訓告に処されました。
この教育行政の対応と逆行するかのように、この「提言書」は教職員からも保護者や市民からも共感を集めています。また、「提言書」を自動翻訳で読んだ世界の教育学者らがメッセージ動画をYoutubeで公開しています(https://www.youtube.com/watch?v=KbdefwHnzso&t=8s)。
書籍では、末尾の資料として、コロナ禍で顕在化した各国の教育の特質を一覧化しました。休校決定の機関や政策の主要アクター、中央―地方関係、教育行政の自律性、学校の自律性、教員の位置づけ、学校外の教育機会、社会的弱者への政策対応、ICT化の課題など、平時には見えにくい9か国の教育行政のガバナンスが比較しています。

持続可能な教育現場の実現に向けて
日本では学校再開後に長期休暇を短縮したり休日を授業日に変更したりする政策がとられましたが、諸外国ではそうした政策はとられず休日の確保が政策課題とされました。日本では、「子どもの学びを止めない」というスローガンの下で、授業時数の「回復」が図られ、学校行事等は中止となり、いわゆる受験教科に重点を置いた対応が広くとられました。休校期間中の在宅学習も時数に算入されなかったために、再開後の学校生活は授業で埋め尽くされてしまいました。そのような学校の姿は、子どもも保護者も教員も全く望まないものでしたが、日本の教育課程行政のしくみ上この問題を解決しうるのは文部科学省をおいて他にありませんでした。にもかからず、この権限をもつ当局は英断を避けたために、学校現場や教育委員会は授業時数の「回復」に振り回されることになったと言わざるをえません。
日本社会は、2003年のSARS(重症急性呼吸器症候群)や2012年のMERS(中東呼吸器症候群)から今回のCOVID-19まで、諸外国と比べると相対的に被害が抑えられてきました。しかし、ガバナンスの構造において非常に大きな問題があると言わざるを得ず、今後さらなる未知のリスクが直面した際に、対応が可能なのか大きな懸念が残ります。折しもの、ロシアによるウクライナ侵攻が新たなグローバル・リスクとなりつつある中で、未知のリスクに対して政治的な意思決定が機能するのかが切実な問題となっています。
これまでの日本のリスクへの向き合い方は、市民的な努力や忍耐に多くが委ねられているのが現状であり、政策判断の決定的な権限をもつ主体がそこでしかなしえない英断を回避する傾向があります。難しい判断ほどに「地方ごとの判断の尊重」や「学校ごとに適切な対応」が持ち出され、英断が回避されてはならないでしょう。コロナ禍において家庭や学校だけが奮闘したのではなく、中央や地方の政治レベルでも必死の努力が続けられてきたことは確かです。しかし、仮に「法的根拠はないが休校の要請をします」という判断がなされたとしても、科学的知見を尊重する努力や関係機関との合意をつくる努力などが軽視されているとすれば、政治の「英断」とは到底言えません。現実の世界には「やって悪くなる努力」というものがあることも、教訓とすべきではないでしょうか。
【参考文献】
・園山大祐・辻野けんま編著(2022)『コロナ禍に世界の学校はどう向き合ったのか―子ども・保護者・学校・教育行政に迫る―』東洋館出版社
・園山大祐・辻野けんま・有江ディアナ・中丸和(2021)「国際比較に見るCOVID-19対策が浮き彫りにした教育行政の特質と課題――フランス、スペイン、ドイツ、日本の義務教育に焦点をあてて――」『日本教育行政学会年報』47号、25~45頁。