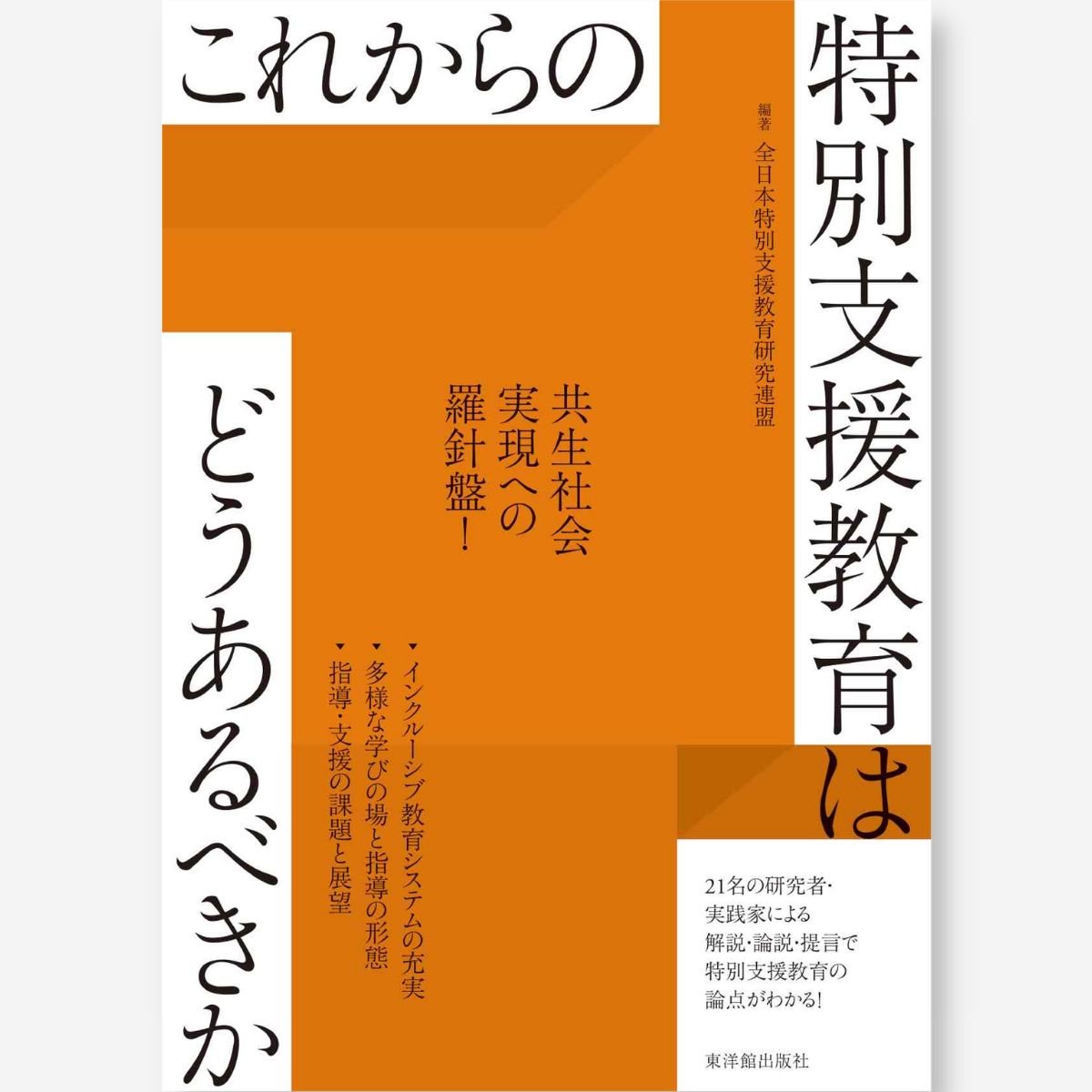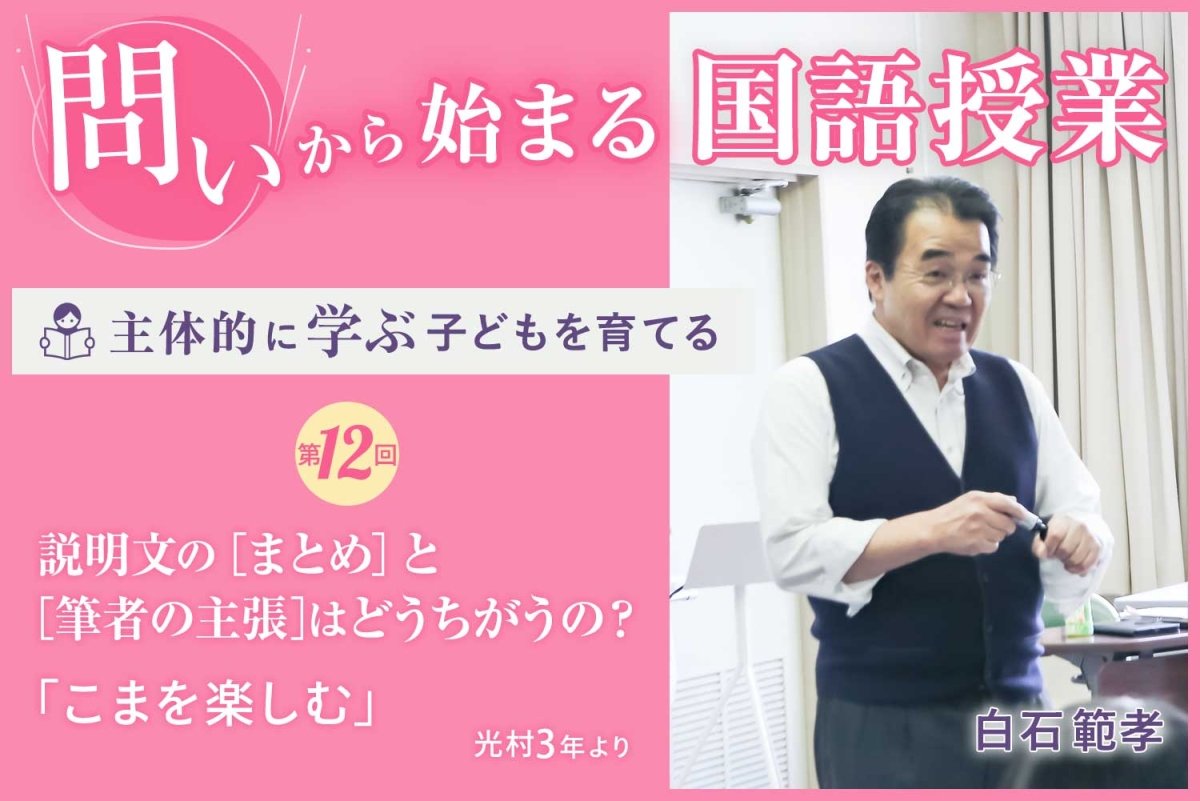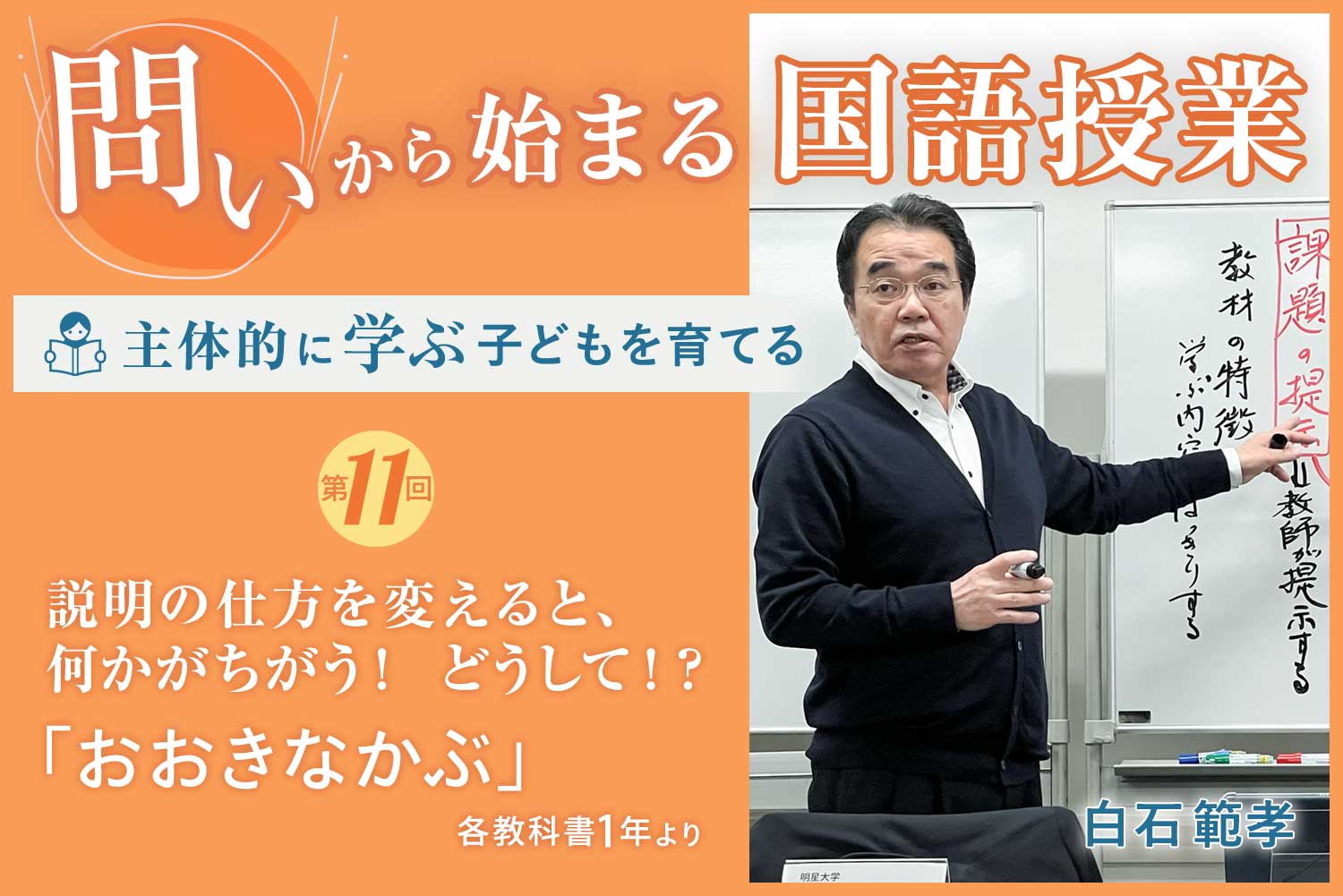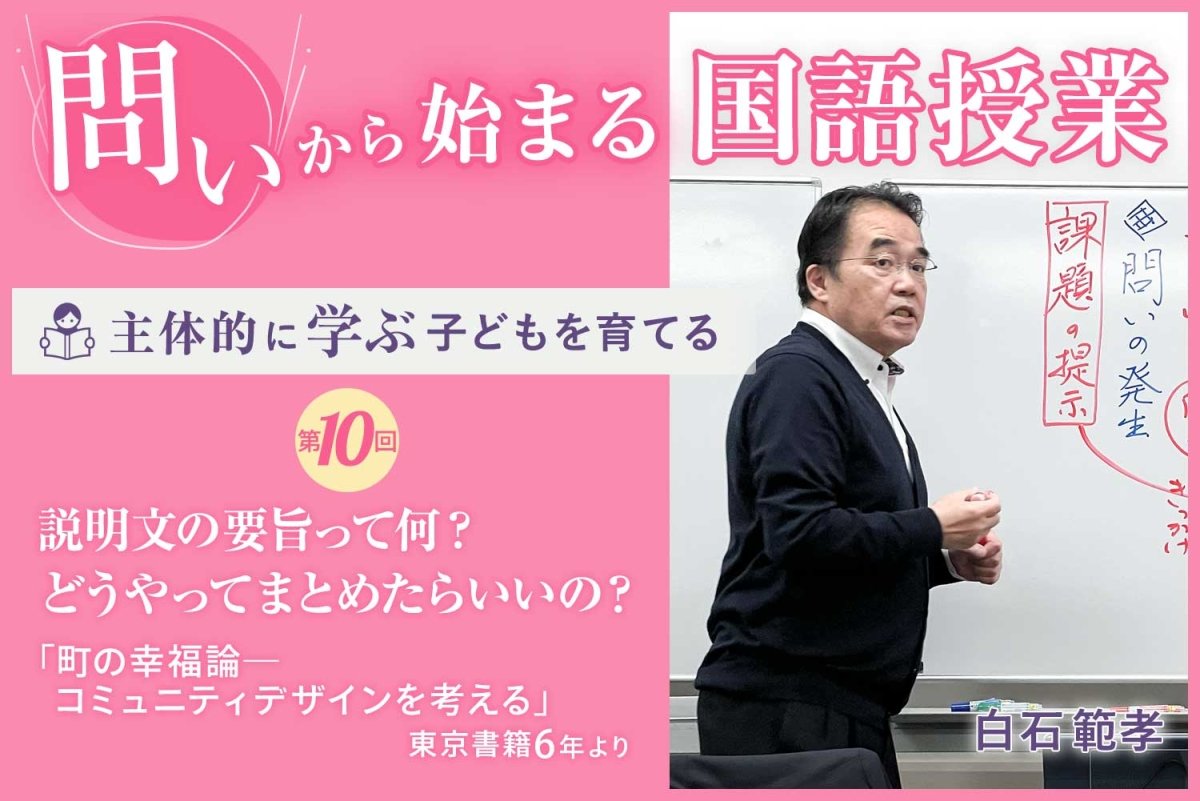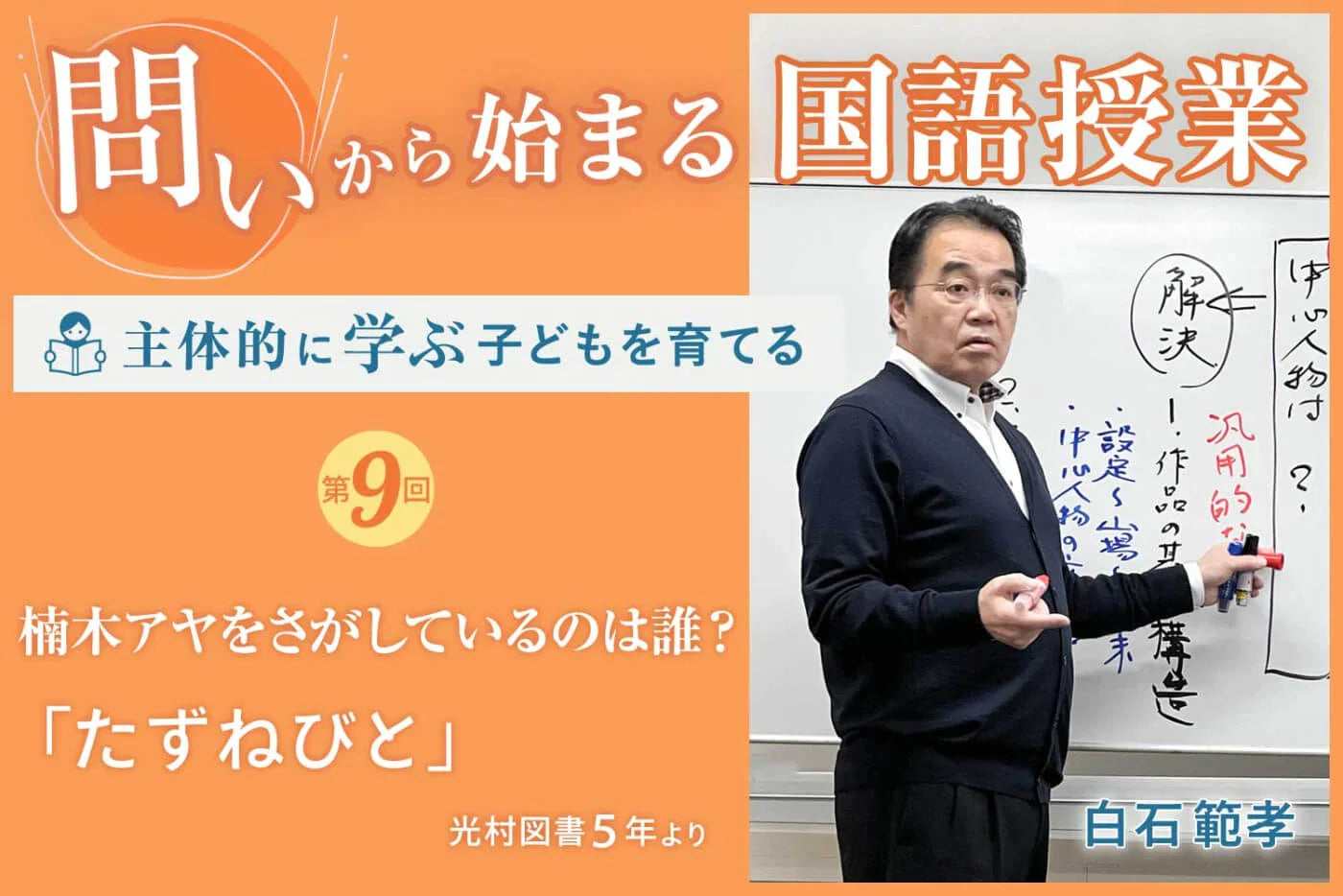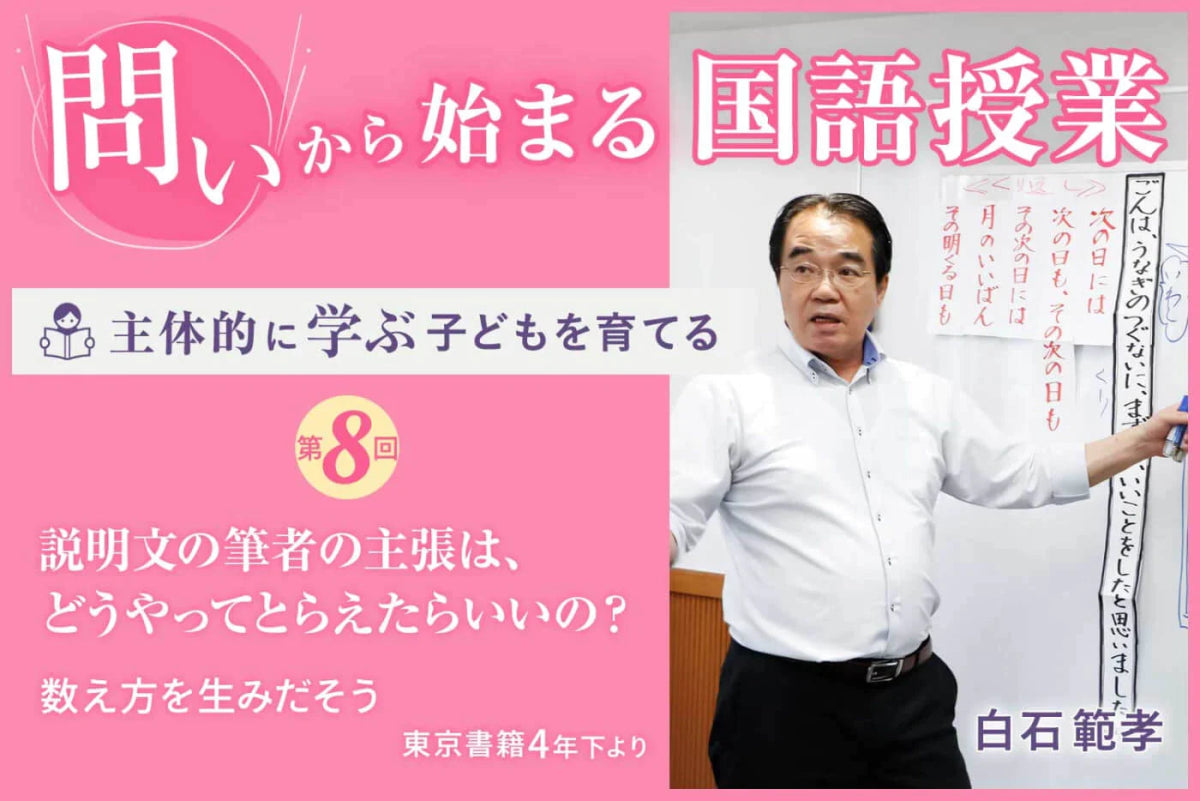不登校を経て世界を飛び回るフォトジャーナリストとなった佐藤慧さんが多感な子どもたちに綴った読み物、10分後に世界が広がる手紙シリーズ全3巻(小社刊)。ここでは、学校という場のかけがえのなさや、不安・窮屈さを感じている思春期の心に向き合う5話を、Edupia連載として再編集しました。
第3回は『毎日がつまらない君へ』収録の「かべをこえる凧」。移動の自由のないイスラエルのガザ地区の子どもたちが、遠く離れた日本に目を向けていました。
世界は味わいきれないもの
世界のあちこちを旅していると、今まで知らなかった文化や、すてきな人々との出会いが、なによりも楽しみになってきます。今度はどんな出会いがあるだろう、この地方ではどんな食事を食べているのかな、聞いたこともないこの音色は、いったいどんな楽器でかなでられているの?
そんなわくわくと、刺激に満ちた出会いが、人生のすべての時間を使っても味わいきれないほどに、この地球にはあふれています。
自然のえがきだす絶景もまた、そんな旅の宝物です。どこまでも続く砂丘のえがく幾何学模様や、風にゆれる草花でいっぱいの平原、視界におさまらないほどの大きな滝や、まるで火星のように岩だけがえんえんと続いている荒野。自分の知っている世界なんて、ほんのちっぽけなものにすぎないのだと、そんな景色たちが教えてくれます。
このように、自分の住みなれた場所をはなれて、見たこともない世界へ出かけていくことは、君の感性をゆたかにする、大切な学びをあたえてくれることでしょう。
けれど、もし、そんな移動の自由がなかったら?
2019年の終わりごろから、世界中で新型コロナウイルスの感染がひろがりました。日本でも、なるべく外を出歩くことはしないようにと、日常が大きく変わりました。 きっと君も、学校がいつもとちがったり、自由に遊びに行けなかったりしたことが、あったのではないでしょうか。 家や、自分の住んでいる地域にばかりとじこもっていると、なんだかきゅうくつな感じがしてきませんか?
でもこの世界には、もう何十年も、移動の自由をはばまれている地域もあるのです。今回は、そんな地域のひとつ、パレスチナの「ガザ地区」というところのお話をします。
移動の自由がない暮らし
パレスチナとは、国の名前ではありません。正確にいうと、国としてみとめている国々もあるのですが、日本は国としてみとめていないのです。なぜそんなことが起きているのかというと、ひとつの土地をめぐって、イスラエルという国ともめているからです。
その土地は、はるか昔、ユダヤ人とよばれる人々のくらす土地でした。その後、ほかの国々の侵略などによって、かれらは国を追われ、世界中にちらばっていくことになります。大勢のユダヤ人がいなくなったその土地には、今のパレスチナの人々の、先祖たちがくらし始めました。
ところが、第二次世界大戦で、多くの命がうばわれたユダヤ人たちの一部が、「わたしたちも安心してくらせる国がほしい」「そうだ、もともとあの土地は、わたしたちのものじゃないか」と、その土地に自分たちの国、イスラエルをつくってしまったのです。
パレスチナの人々は、「ヨルダン川西岸地区」と「ガザ地区」という、ふたつの地域にとじこめられてしまいました。どちらとも、3階建てのビルくらいの高さの、コンクリートのかべやフェンスにかこまれていて、人々は自由に出入りすることができません。
ガザ地区には海もありますが、ちょっとでも沖に船を出すと、イスラエルの軍隊にうたれてしまいます。出入り口も限られているガザ地区は、「天井のない監獄」ともよばれています。かべの外からミサイルが飛んできて、いきなり街中で爆発することも、めずらしくありません。
そんなガザ地区にくらす友人は、「わたしたちはふつうの日常がほしいだけなの」と、ぼくに言いました。
ふつうに学校に行って、仕事をして、ミサイルがふってくる心配をせずにぐっすりねむって、大切な人たちと笑ってすごす。そんな日常を夢見ているといいます。
でも空だけはつながっている
ガザ地区の中学校で、毎年3月、あるもよおしがおこなわれていると聞き、おとずれました。学校に着くと、生徒たちが、思い思いに絵をかいています。
なにをしているのかと聞くと、「凧」をつくっているのだそうです。日本でもお正月に飛ばす、あの凧です。
実はこの凧は、東日本大震災で亡くなった方々の、追悼のためにあげる凧だというのです。あの日、遠くはなれた日本をおそった津波の映像は、ガザ地区の人々にも、大きなしょうげきをあたえました。
「故郷を失うこと、大切な人を失うことのつらさを、わたしたちはだれよりもよく知っています」と、ハニーちゃんというあだ名の女の子が教えてくれました。「わたしたちはここから出ることができないけれど、空はどこまでもつながっているから、きっと凧を通じて、日本にも想いがとどくと思います」

ハニーちゃんの瞳には、大つぶのなみだがうかんでいました。もっともっと、広い世界を見たいのに。いろんな人に会いたいのに。たくさんの夢を、かなえたいのに……。
目の前だけが世界のすべてではない
こうした可能性をはばむかべは、じっさいにそびえ立つものばかりではありません。「本当におそろしいのは、心の中のかべなのよ」と、ハニーちゃんがつぶやきました。「なんだかこわいな」「めんどうだな」「どうせ自分には、なにもできないよ……」。そんな心の中のかべが、世界を小さく、息苦しいものにしてしまうのだというのです。
走る子どもたちの手をはなれた凧は、空に吸いこまれるように、高く、高く、かべよりも高く、まい上がっていきました。その凧にみちびかれるように見上げた空は、今まで世界中のどこで見た景色よりも、温かな想いに満ちていました。
いつか君が、まい上がる凧のような心を持った大人になって、もっともっと楽しく、たくさんの人々とふれ合える世界をつくっていくことを、ぼくも楽しみにしています。

もし君が、学校でなかなか「種」を見つけられなくても、大丈夫。「種」は学校の中だけにあるわけではないのです。世界は、学校の何千倍も、何万倍もひろいのですから。学校ですごす時間というのは、そんな、もっともっと広い世界の中で「種」を見つける、練習のようなものかもしれません。
「もう種をみつけたよ!」という君は、さらにたくさんの種を見つけられるかもしれません。「種」はいくつ持っていても、いいのです。ポケットいっぱいにつめこんだ「種」が、大人になってから、とつぜん芽を出し、花ひらくこともあるでしょう。その「種」を友達に分けることで、その友達にとっての大切な「種」になるかもしれません。
今日君は、どんな「種」を見つけられるかな? 君の見つけたその「種」は、どんな花をさかすのでしょう?