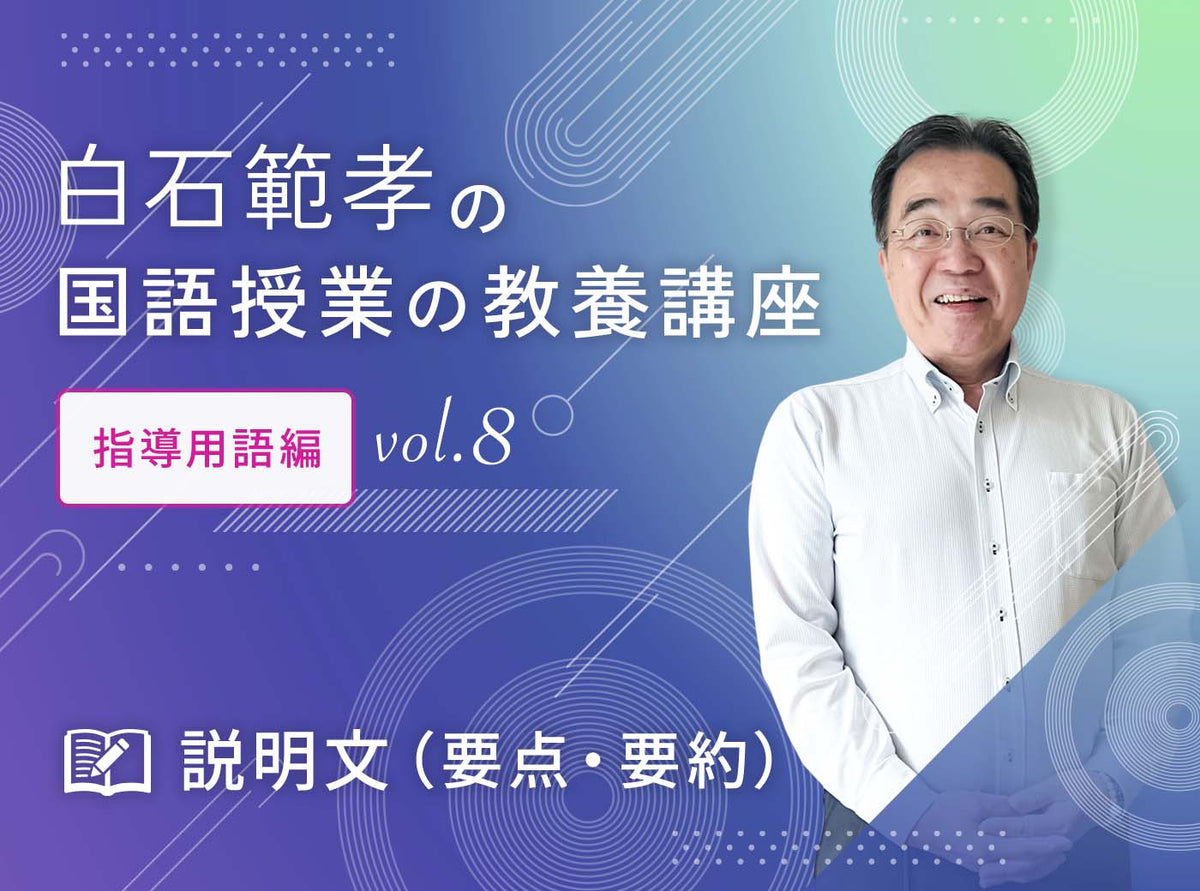
説明文(要点・要約)
|
|
この連載の本年度のVol.6で、「要旨」について説明しました。
「要旨」によく似た言葉に「要点」「要約」があります。
いずれも説明文の指導でよく使われる用語ですが、これらをきちんと区別して使えているかというと疑問が残ります。
これまでも繰り返しお伝えしていますが、国語の学習において大切なことは、「用語」「方法」「原理・原則」を学ぶことによって、汎用的な読みの力を身に付けることです。
「要点」「要約」「要旨」についても、それぞれが何を示しているのか、それぞれをどうやってまとめるのか、何のためにまとめるのか――などを、違いを明確にしたうえでとらえておくことが大切です。
まず、「要点」「要約」とは何なのかをおさえておきましょう。
「要旨」についてはVol.6でも説明していますが、「要点」「要約」との違いを明確にするために、改めて確認します。
実際の文章を使って、「要点」をまとめてみましょう。
次の文章は、「すがたを変える大豆』(光村図書3年)の①段落です。
わたしたちの毎日の食事には、肉・やさいなど、さまざまなざいりょうが調理されて出てきます。その中で、ごはんになる米、パンやめん類になる麦の他にも、多くの人がほとんど毎日口にしているものがあります。なんだか分かりますか。それは、大豆です。大豆がそれほど食べられていることは、意外と知られていません。大豆は、いろいろな食品にすがたをかえていることが多いので気づかれないのです。
この段落の「要点」をまとめます。
| 方法 | 「すがたを変える大豆」の場合 |
| ⑴ 形式段落を、構成している文に分ける。 |
|
| ⑵ 形式段落の「まとめになっている一文」または「大切な一文」をとらえる。 | 大豆は、いろいろな食品にすがたをかえていることが多いので気づかれないのです。 |
| ⑶ ⑵でとらえた一文の主語をおさえる。 | 大豆は |
| ⑷ ⑵でとらえた一文を、⑶でとらえた主語が文末で体言止めになるように書き換える。 書き換えた文が、この形式段落の「要点」となる。 |
いろいろな食品にすがたをかえていることが多いので気づかれない大豆。(①段落の要点) |
このような手順で、この形式段落の要点は「いろいろな食品にすがたをかえていることが多いので気づかれない大豆。」であることがわかります。
続いて「要約」の方法を説明する前に、「要点」から意味段落をとらえる方法をおさえておきましょう。
《「すがたを変える大豆」の意味段落をとらえる》
| 意味段落をとらえる方法 | 「すがたを変える大豆」の場合 |
| ⑴ 各形式段落の「要点」をまとめる。 |
|
| ⑵ 各形式段落の主語をとらえる。 |
|
| ⑶ 同じ主語の連続したまとまり(主語連鎖)をとらえる。このまとまりが、意味段落となる。 |
|
このように、「要点」から意味段落をとらえることができます。
先ほども述べたように、「要約」とは、文章全体を短くまとめたものです。
「要約」した文を「要約文」といいます。
実際の授業でも「この文章を要約しましょう」といった活動がよく行われています。
しかし、「要約」の方法を具体的に指導できているでしょうか?
「子どもたちの感覚まかせ」になっていないでしょうか。
「要点」をまとめるために明確な方法があったように、「要約」するためにも明確な方法があります。
《「要約」する方法 》
では、「すがたを変える大豆」を、実際に「要約」してみましょう。
先ほどまとめた意味段落をもとに「すがたを変える大豆」の文章構成をとらえると、次のようになります。
昔から大豆にいろいろ手を加えて美味しく食べてきた。(①、②段落)
|
くふうの例(③~⑦段落)
|
「昔の人のちえにおどろかされる」という筆者の主張(⑧段落)
これらをもとに「要約文」をまとめると、次のようになります。
《「すがたを変える大豆」の要約文(例)》
筆者は、大豆にいろいろな手をくわえて、おいしく食べるくふうを「すがたをかえる大豆」として、説明している。
そして、「大豆をその形のまま調理するくふう」や「ちがう食品にするくふう」さらに、「取り入れる時期や育て方のくふう」を、具体例としてあげている。 これらのくふうは、大豆のよいところに気づき食事に取り入れてきた昔の人々のちえであり、このちえにおどろかされると主張している。
※「要約文」は、どの程度の長さにまとめるかによって、文章が変わります。上記の「要約文」は一例ととらえてください。
*
今月は「要点」「要約」についてお話ししました。
これらの意味や、まとめるための方法を知ることは大切なことです。
しかし、それ以上に重要なのは、「要点をまとめる」「要約する」といった読みの力を、様々な読みの場面に活かしていくということです。
国語の学習内容が子どもたちの「汎用的な読みの力」となるようにすることを、意識していただければと思います。
次回は、「文学(変容)」についてご説明する予定です。
また、一緒に学びましょう。